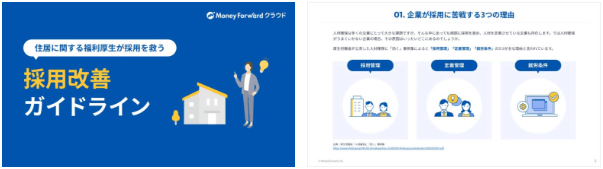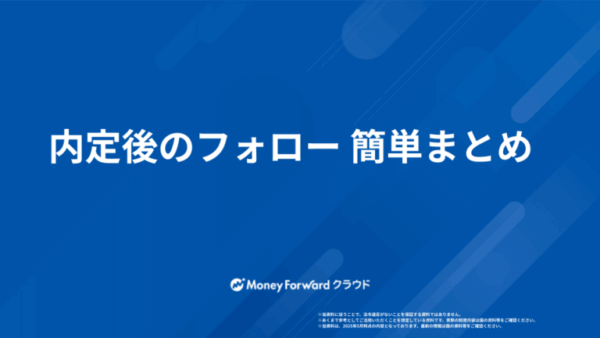- 更新日 : 2025年12月8日
縁故採用とリファラル採用の違いは?メリット・デメリットをもとに解説
従業員など関係者の紹介による採用方法に、縁故採用とリファラル採用があります。両者とも信頼できる人のコネクションを利用して採用する方法ですが、同じように見えて違いがあります。
近年、採用難から紹介により従業員を採用する企業が増えています。縁故採用やリファラル採用の違い、縁故採用のメリット・デメリットについて解説します。
目次
縁故採用とは?
縁故採用というと、「コネ入社」などと揶揄され、マイナスのイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。縁故採用とは、血縁・地縁、友人・知人、従業員や業務上の関係者などの個人的なつながりを利用して企業が従業員を採用することを指します。
近年、中途採用の枠を増やす大企業も出てきており、中途採用でも従業員の採用が難しいのが現状です。候補者の素性がよく知れていて、採用にかかるコストも少なく、採用をした際に辞退されるリスクが低いこともあって、縁故採用を一つの手段として取り入れ、人材を確保をする企業が増えています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
縁故採用が生まれた背景
縁故とは、血縁や姻戚によるつながりを意味します。つまり、縁故採用とは、親類・縁者を頼って就職することを指します。縁故採用がいつごろから行われていたのかは明確ではありません。
しかし、日本の歴史的な観点から見れば、力を持っていた武士や貴族などの権力者に頼って血縁関係や婚姻関係により重要な地位や職を与えられていた時代があり、古い歴史があります。
昭和の時代に入ってからも一般的な採用手段として行われていた時代があり、珍しい採用方法ではありませんでした。現在は国家公務員や地方公務員などでは禁止されていますが、民間企業では法的に禁止されているわけではありません。
縁故採用とリファラル採用の違い
縁故採用とリファラル採用に明確な定義はありませんが、両者には違いがあります。縁故採用は経営者や取引先とのコネクション重視の採用方法で、候補者の能力が採用基準を満たさず、実力が伴わなくても採用するイメージになります。ただし、必ずしも無審査で採用しなければならないというわけではありません。候補者の素性がよく知れていて、信用できる人からの紹介なので辞退されるリスクが低く、入社の手続きを簡素化しても問題ない採用方法と考えるのがよいでしょう。
一方、リファラル採用は、その企業の従業員や関係者が声をかけて候補者を企業へ紹介するものの、候補者の能力や適性などを考慮して選考し、採用を決定します。そのため、採用に至らないケースも多くあります。リファラル採用の詳細については、以下の記事でも説明していますので参考にしてください。
縁故採用とアルムナイ採用の違い
縁故採用とアルムナイ採用にも違いがあります。アルムナイという言葉は卒業生や同窓生を意味し、退職した人材と考えればよいでしょう。アルムナイ採用は、退職した人材とコミュニケーションを取りながら、自社で勤務経験があり、他社でキャリアを積んだ人材を再雇用する採用方法です。結婚や育児・介護、配偶者の転職などで退職した従業員を再雇用する制度が代表例として挙げられます。アルムナイ採用について詳しく知りたい方は、以下記事もご覧ください。
縁故採用のメリット
縁故採用は「コネ入社」などと呼ばれることもあって、ネガティブなイメージを持つかもしれません。しかし、近年、人手不足解消のための採用方法として縁故採用を取り入れる企業が増えているのには理由があります。縁故採用のメリットを6つ紹介します。
採用コストの削減につながる
求人広告を出せば、応募の有無にかかわらず広告料がかかります。人材紹介会社に依頼して採用すれば、多額の手数料がかかることも珍しくありません。縁故採用は人のつながりにより候補者を紹介してもらうため、人材紹介会社への紹介手数料や求人サイトへの広告料などを支払う必要がなく、採用コストの削減につながります。
選考辞退等のリスクが低い
従業員や業務上の関係者などの個人的なつながりにより紹介してもらうため、面談できる確率が高く、マッチング制度が高いといわれています。また、採用される側としても、信頼できる人から紹介された仕事で安心感があり、採用をした際に辞退されるリスクが低く、企業としては採用率が高まるメリットがあります。
早期退職のリスクが低い
入社後に業務上の悩みが生じた場合には紹介者が相談役となるケースが多く、職場に問題があれば企業に情報が入ることも多いでしょう。候補者の経歴や性格は紹介者から事前に聞くことができるため、入社後のフォローもしやすいこともあり、早期退職のリスクが低いといえます。
職場とのミスマッチが少ない
新卒入社でも中途採用による入社でも、入社直後に退職してしまうケースが発生することがあります。これは候補者の業務の内容や労働条件、職場の雰囲気などが、実際に仕事を始めたら「イメージと違う」とギャップを感じてしまうために起こることです。しかし、縁故採用では、候補者は紹介者から自社の業務内容や職場の雰囲気などを事前に聞いているため、入社後の職場や業務内容とのミスマッチが起こりにくい特徴があります。
候補者の素性がよく知れている
紹介者が自社の従業員や関係者であるため、候補者の素性はよく知れていて、安心して採用することができるでしょう。そのため、経歴詐称のリスクなどもほとんどありません。人とのつながりから採用をすることは、企業にとっても応募者にとってもコミュニケーションを取りやすいというメリットもあります。
一般的な募集で採用が進まない場合に活用できる
近年、人手不足に悩む経営者は多く、求人広告を出しても誰からも応募が来ないということが珍しくありません。縁故採用は、候補者の情報収集のルートも一般的な募集方法とは異なります。募集の時期を問わず必要な時期に声をかけることができるため、一般的な募集で採用が進まない場合に活用できる点もメリットといえるでしょう。
縁故採用のデメリット
縁故採用は、通常の選考を経て入社した従業員と比べて公平性・透明性の点で問題があり、実施していない企業もあります。縁故採用のデメリットについても紹介します。
他の社員から「コネ入社」として認識される可能性
縁故採用は、通常の選考を経て採用された従業員から「コネ入社」とのレッテルを張られ、能力やスキルを十分に有していても職場で疎外感を覚え、職場になじみにくくなるケースがあります。職場全体のモチベーションの低下や人間関係のトラブルが発生することなどが考えられるため、特別扱いをして不公平感から誤解されることがないよう、企業としても配慮が必要です。
縁故採用で紹介された人材が採用基準に満たない場合も
紹介された候補者が必ずしも自社の採用基準を満たしているとはかぎりません。能力やスキルを十分に有していない人材を採用すれば、かえって企業にとってマイナスになってしまいます。
不採用の判断が難しい
縁故採用では、紹介者の顔を立てなければならず、断りにくいということがあるでしょう。しかし、入社後に能力不足やスキル不足が発覚すれば、かえって周囲の従業員の負担が大きくなり、職場を混乱させることになります。また、取引先や有力者から紹介された人材の採用を断ると、紹介者との関係性が悪くなり、トラブルになる可能性があるため注意しなければなりません。
採用計画・予定を立てにくい
縁故採用は、多人数の採用には不向きで、通常の選考を経て採用するケースと比べて応募人数の見通しがつきにくい採用方法です。欠員募集など少人数を時間をかけて探す余裕があるときには問題ありませんが、紹介者が現れる確証はなく、採用までに時間がかかることもあります。企業に必要な人員数を確保できるとはかぎらないため、採用計画を立てにくいデメリットがあります。
同質的な人が集まる可能性
紹介者と似た同質の人材が集まりやすく、多様性を持った組織を構成するのが難しくなります。企業の競争力の強化やイノベーションの創出には、多様性を持った組織づくりが必要です。同質の人材ばかり採用をしていると多様性が失われる可能性があるため、自社にとって必要な人材を明確にして紹介者を募ることが必要になります。
縁故採用を導入する際の注意点
縁故採用のメリットとデメリットを理解した上で、導入する際の注意点について解説します。
コネ入社と認識されないように採用基準を厳守する
地位や権力がある人物から紹介された候補者を優遇して採用することは、不公平感から社内の反発や不信感を生み出す原因になることがあります。「あの人はコネ入社だから仕事ができない」などと誤解を生まないように、採用基準は厳守する必要があります。縁故採用であっても、あらかじめ採用基準を明確にして、必ず採用するとは限らないことを紹介者や候補者に説明しておきましょう。
採用した場合の社員への説明を用意しておく
入社後も、採用した従業員に対して「紹介者が誰であろうと特別扱いはしない」「仕事内容や待遇に差をつけるようなことはない」とよく説明しておく必要があります。そのためには、採用基準や選考基準を明確化し、紹介者がいたとしても選考時に採用基準をクリアしたことが説明できるように準備しておくのがよいでしょう。
入社後の状況を定期的に確認する
入社後の状況を確認し、定期的にフォローすることが大切です。「コネ入社」とのレッテルを張られて人間関係のトラブルが発生することがあるため、採用した従業員が相談しやすいようにコミュニケーションをよく取るようにしましょう。
縁故採用は法律から見たとき合法?
縁故採用は、国家公務員や地方公務員などでは禁止されているものの、民間企業では法的に禁止されているわけではありません。ただし、職業紹介事業に該当すれば厚生労働大臣の許可が必要となるため、紹介することが事業となれば職業安定法に抵触する可能性があります。紹介した従業員などに過度の報酬を支払うことは避け、就業規則にルールを設けて給与としてお礼程度の金額を支払うことは問題ないと考えられます。
職業安定法
(報酬の供与の禁止)
第四十条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
一般的な採用活動に縁故採用やリファラル採用を組み合わせるのが効果的
縁故採用には、候補者の能力が採用基準を満たさず、実力が伴わなくても採用するイメージがありますが、必ずしも無審査で採用しなければならないというわけではありません。しかし、従業員から誤解されやすい採用方法でもあるため、目的や理由、経営者の考えをよく周知・説明し、社内の理解を得ることが大切です。
近年の人手不足感から、通常の採用方法に加えて縁故採用やリファラル採用を取り入れる企業が増えています。一般的な募集で採用が進まない場合には、縁故採用やリファラル採用など複数の採用方法を組み合わせて募集することも検討してはいかがでしょうか。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
バーンアウトからの立ち直り方7ステップ!原因や予防策を解説
ストレスとうまく付き合えずに、心身ともに疲れ果ててしまう「バーンアウト」は、現代社会の深刻な問題の一つです。仕事へのモチベーションの低下や情緒的な枯渇、同僚への無関心などの症状が現…
詳しくみるメタ認知とは?高い人・低い人の特徴や高める方法を簡単に解説
メタ認知とは、自分の考え方や学び方を俯瞰し、計画・監視・調整で成果につなげる力です。成果が伸び悩むときこそ、自分やチームメンバーのメタ認知を高め、改善につなげる考え方が重要だといわ…
詳しくみるオンライン適性検査とは?やり方や適性検査の種類・対策方法をわかりやすく解説
オンライン適性検査は、多くの企業で採用選考の初期段階にとり入れられており、その実施形態も多様化しています。初めてオンラインで適性検査を受ける方にとっては、「どんな内容なのか」「どう…
詳しくみるエニアグラムとは?性格診断をタイ プ別に解説、ビジネスへの応用や導入企業の事例
エニアグラムとは、人の思考や行動パターンを診断し9つのタイプに分類する性格類型です。従来、哲学・人間学・心理学などで研究が行われてきましたが、近年ではビジネスシーンでも積極的に活用…
詳しくみるチームビルディングとは?意味や目的、具体例を紹介!
現代のように競争が激しいビジネス環境では、優れた個人の力だけで成功することは難しいでしょう。多くの企業はチームビルディングの重要性に気付き、組織内の人材が円滑に協力し合えるようなチ…
詳しくみるメンバーシップとは?意味や使い方・雇用形態を解説!
メンバーシップとは、各メンバーが役割を果たすことで組織全体に貢献することを意味する用語です。例えば、看護の分野ではチームで目標を共有しメンバーが協力して患者に最善の看護を提供するこ…
詳しくみる