- 更新日 : 2025年8月25日
残業時間の平均はどれくらい?2024年4月からの上限規制についても解説!
日本の全産業の残業時間の平均は、厚生労働省の調査で月10時間と言われています。近年、残業時間は減少傾向にありますが、その大きな理由の一つが働き方改革です。
この記事では日本の残業時間の概況、残業時間の上限規制や残業時間の削減方法について解説します。自社の競争力を高める働き方改革のための一助としていただければ幸いです。
目次
日本における残業時間の平均は?
日本における残業時間の平均は、厚生労働省の毎月勤労統計調査により明らかにされています。残業時間は、毎月勤労統計調査の中では「所定外労働時間」として報告されています。所定外労働時間とは、企業が定める所定労働時間を超えた労働時間のことです。
毎月勤労統計調査(令和5(2023)年確報値)によると、調査対象の全産業の残業時間の平均は10.0時間/月となっています。この統計における1か月あたりの平均出勤日数が17.6日であることから、1日あたりでは約34分の残業時間ということになります。
また、労働者の種別で区分すると、一般労働者は13.8時間/月、パートタイム労働者は2.2時間/月で、一般労働者の残業時間が多い状況です。
なお、前年比では全産業で0.9%減となっており、総じて残業時間は減少傾向にあります。
参考:毎月勤労統計調査 令和5年12月分結果確報|厚生労働省
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
36協定の締結・更新ガイド
時間外労働や休日労働がある企業は、毎年36協定を締結して労働基準監督署に届出をしなければなりません。
本資料では、36協定の役割や違反した場合の罰則、締結・更新の手順などを社労士がわかりやすく解説します。
割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)
割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。
本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。
2024年4月から適用!残業時間の上限規制について
残業時間は労働基準法により上限が規制されています。正確には「時間外労働」の上限規制です。
一般的な残業時間は企業ごとに定められた所定労働時間を超えて働いた時間ですが、労働基準法における時間外労働とは、法定労働時間である8時間/日、40時間/週を超えて働いた時間のことです。
2019年4月に労働基準法が改正され、時間外労働の上限が罰則付きで規定されました。中小企業については1年遅れの2020年4月より適用されています。また、中小企業以外でも以下の業種については上限規制の適用が猶予されていましたが、2024年4月より適用されることになります。
- 建設業
- 自動車運転の業務
- 医師
- 砂糖製造業(鹿児島県、沖縄県)
以下では2024年4月より時間外労働の上限規制が適用される各業種について、その内容を解説します。
違反になる残業時間
2019年4月より時間外労働の上限について以下の通り規定されました。この規定を超えた時間外労働や休日労働をさせた場合には、労働基準法違反になります。なお、「休日労働」とは労働基準法が定める休日(法定休日)に働くことです。法定休日以外の会社が定める休日に、法定労働時間を超えて働く場合は時間外労働となります。
原則
時間外労働:45時間/月 360時間/年
特別条項付き36協定を締結する場合
①時間外労働:720時間/年
②時間外労働+休日労働:100時間未満/月
③時間外労働+休日労働の2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均の全て:80時間/月
④時間外労働が45時間/月を超えられるのは年間に6か月以内
なお、要件②③は特別条項付き36協定を締結していない場合であっても適用されます。
例えば、時間外労働が40時間/月で特別条項に該当しない場合でも、休日労働が60時間/月となる場合は、時間外労働+休日労働が100時間/月となり、②の要件に抵触します。
2024年4月より適用される各業種については、以下の通り規定されます。2019年4月の規定内容と一部異なる点があります。
建設業
災害復旧・復興事業を除き、上記の①~④の全てが適用される。
災害復旧・復興事業については、上記の②③は適用されない。
自動車運転の業務
上記①(特別条項付き36協定締結時の時間外労働の上限)は960時間/年となる。
上記②③④は適用されない。
※労働基準法とは別に厚生労働大臣の改善基準告示の改正により、拘束時間や休息時間、運転時間などの上限も改定されて従来より短くなります。(時間外労働の上限規制と同じく2024年4月より)
参考:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示) |厚生労働省
医師
一般労働者と同程度:時間外労働 960時間/年
医師を派遣する病院、救急医療等、臨床・専門研修等:1,860時間/年
砂糖製造業(鹿児島県、沖縄県)
1〜④全てが適用される。
その他、時間外労働の上限規制の詳細は以下のリンクも参考にして下さい。
上限は月100時間未満になる
時間外労働の上限は、特別条項付き36協定を締結する場合に月100時間未満となります。厳密に言えば、時間外労働と休日労働を合計した時間の上限が月100時間未満ということになります。
上限規制の例外
時間外労働の上限規制には例外があります。労働基準法36条11項の規定により、新たな技術、商品または役務の研究開発業務については上限規制が適用されません。
「新たな技術、商品または役務の研究開発業務」とは、専門的、科学的な知識等を持つ従業員による新技術、新商品等の研究開発業務のことです。
長時間労働者への医師による面接指導
労働基準法による残業時間の上限規制とあわせて、2019年4月より労働安全衛生法も改正されました。
長時間労働者への医師による面接指導の要件が以下のように変更されました。
・時間外労働と休日労働の時間が80時間/月を超え、疲労の蓄積が認められる者
なお、この場合の「時間外労働」は40時間/週を超えて働いた時間です。
2019年の改正前の要件は100時間/月超であったため、面接指導の対象が拡大しました。
参考:働き方改革関連法で、労働安全衛生法も改正されたと聞きました。具体的な改正内容を教えてください。|厚生労働省
上限規制に違反した場合の罰則
労働基準法により残業時間の上限規制に違反した場合の罰則も定められています。労働基準法119条により、以下の規定に違反した場合には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 時間外労働+休日労働:100時間未満/月
- 時間外労働+休日労働の2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均の全て:80時間/月
この罰則は、上記の基準を超えて働くことを指示した管理監督者等だけでなく、違法状態の是正措置を行わなかった事業主にも適用される両罰規定とされています。
残業時間を減らすためには?対処方法
労働基準法の改正への対応や働き方改革を進める意味で、残業時間を減らす取り組みが求められています。以下では残業時間を減らすための対処方法について、4点紹介します。
業務体制の改善・業務の効率化
まずは、残業の発生原因を十分に分析することが重要です。特に業務体制と業務の進め方について、改善や効率化を進める必要があります。
例えば、業務が特定の従業員に集中している場合、その従業員の業務量が増えがちになります。そのような従業員は主要な業務を担当していることが多いため、その従業員との調整や内容確認が必要になる場合には、他の従業員の業務が止まり、効率が落ちてしまいます。
業務の属人化を防ぐためには、業務分担の見直しを行ったり、業務のマニュアル化を行ったりするなどの対応が必要です。また、業務分担の見直しにあたっては、業務の棚卸しを行い、不必要な業務がないかの確認やルーティンワークを効率化するなどの取り組みも重要です。
チームで仕事を進める形式の場合には個人での対応には限界があるため、チーム全体で業務の進め方を整理する必要があります。効率的に業務を進めるために、チーム内でクラウドサービス等を利用して業務に関する情報共有を進め、業務連絡の時間を短縮するなどの取り組みが求められます。
残業を許容する文化・体質の改善
これまで、日本企業では長時間労働が評価される風潮がありました。しかし最近では、少子高齢化による生産年齢人口の減少で人材確保がより難しくなっています。限られた人員で効率的に業務を進めることが求められているため、残業を許容する文化や体質の改善が急務です。
残業を許容する文化や体質の改善のためには、成果を重視した評価への移行が重要です。新たな評価制度の導入にあたっては、評価対象者のみならず評価者である管理監督者の意識改革を行う必要があります。
また、度々問題となっているサービス残業をやめさせる取り組みも必要です。そのために2017年に厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づく取扱いを経営陣や管理監督者に改めて徹底することが求められます。労働時間の適正把握を行わず、上限規制を超えた時間外労働等が発生すると、労働基準監督署による行政指導の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
参考:労働時間の適正な把握のために – 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
勤怠管理システムの導入
タイムカードや出勤簿、パソコンのログアウト時間等で職場の退出時刻を把握する場合、残業時間の実績の確認は可能です。一方で残業中にリアルタイムに残業時間を確認できないため、長時間労働を防ぐ効果は期待できません。
そのような場合、勤怠管理システムを導入により残業時間を可視化すると、管理監督者、従業員本人ともにリアルタイムに残業時間を意識しながら業務を行え、長時間労働の抑制につながります。
あわせて、従業員から管理監督者への残業時間の事前申請を行うようにすると、効果をより高めることができるでしょう。
残業の上限規制について周知 – 残業を出来る限り削減するように呼びかけ
残業の上限規制が新たに設けられる業種においては、法改正の概要に関して社内周知を行い、残業時間削減のための機運を作る必要があります。
特に残業を指示する側にあたる経営陣や管理監督者に対しては、業務の進め方や評価制度の改善等の残業時間削減の取り組みを率先して進められるよう重点的に働きかけを行う必要があります。
建設業や自動車運転の業務では、2024年問題への対応として政府が法改正を含む様々な取り組みを進めているため、その内容も理解した上で業務改善を進めるとよいでしょう。
残業時間の多い業種・職種
残業時間が多い業種や職種について、厚生労働省の毎月勤労統計調査の令和5(2023)年分の結果によると、上位5業種は以下の通りです。
1位:運輸業・郵便業 22.7時間/月
2位:情報通信業 15.5時間/月
3位:電気・ガス業 14.8時間/月
4位:学術研究等 13.8時間/月
5位:建設業 13.7時間/月
※調査産業計 10.0時間/月
最上位の運輸業・郵便業(自動車運転の業務)や、5位の建設業は、2024年4月まで時間外労働の上限規制の適用が猶予されていることに加えて慢性的な人手不足もあり、残業時間が多い状況です。また、企業におけるDX化のニーズが増す中、人手不足が顕著なIT系の企業が含まれる3位の情報通信業も同様に残業時間が多くなっています。
働き方改革で自社の競争力を高めよう
労働基準法改正による残業時間の上限規制を受けて残業時間は全体として減少傾向にあるとは言え、人手不足とされる業種では依然として残業時間が多い状況です。
一方、昨今ではワークライフバランスを志向し、育児等と仕事の両立を考える従業員も増えていることから、人材確保のためには残業時間の削減などの働き方改革が急務と言えます。残業時間の削減に取り組むと、自社の生産性向上にもつながるため、結果として業績が上がる可能性があります。
この記事を参考に、働き方改革を通じた優秀な人材の確保と生産性の向上を進め、自社の競争力をより高めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
シフトや勤務変更の進め方とは?拒否できるケースやトラブルを防ぐコツを解説
勤務時間や業務内容、勤務地が変更される「勤務変更」は、企業が柔軟に運営を進めるうえで欠かせない対応です。一方で、こうした変更は従業員の生活や働き方に直結するため、不安や疑問を抱かれ…
詳しくみるコワーキングとは?働き方の特徴やコワーキングスペースについても解説!
現在では、テレワークなどの多様な働き方が普及し、これまでとは異なった方法で業務を行うことも珍しくありません。多様な働き方は、業務の無駄を省き、効率化の効果も期待できます。 当記事で…
詳しくみる運送業の労働時間のルールとは?労働基準法の上限規制と改善基準告示について解説
2024年4月の法改正、いわゆる「2024年問題」が適用されてから1年以上が経過しました。運送業界では、トラックドライバーの労働時間管理がこれまで以上に厳格化され、「自社の対応は十…
詳しくみる労働時間が月200時間とは?手取りの目安や残業の上限を解説
厚生労働省では、時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら医師による面接指導が必要なレベルであると言及しています。では、労働時間が月200時間の場合、見直すべき状況かどうかは内容次…
詳しくみる有給もらってすぐ辞めてもよい?退職直前の有給は使える?メリット・デメリットを解説
年次有給休暇を取得した直後に退職することは、「非常識では?」「会社に迷惑がかからないか?」と不安に感じる人も多いでしょう。この記事では、有給休暇を取得してすぐ退職することの法的な位…
詳しくみる100連勤は違法である理由|労働基準法に基づき分かりやすく解説!
100連勤は、肉体的疲労と精神的なストレス、そしてプライベートの喪失が重なり、働く人にとって大きな負担となります。表面的には仕事をこなせているように見えても、休息が取れないまま働き…
詳しくみる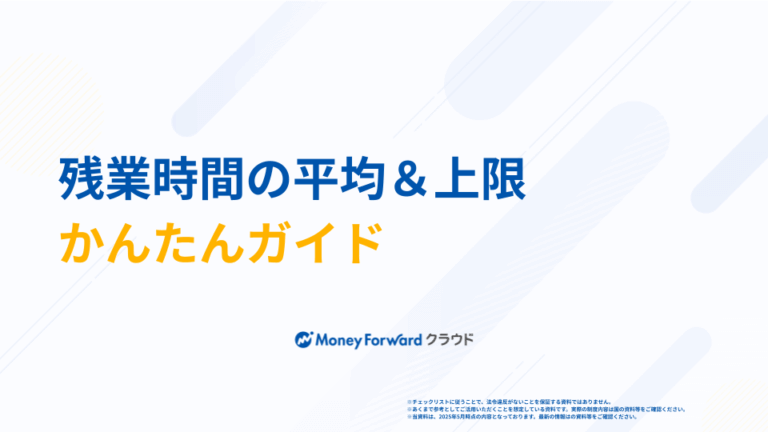



.png)