- 更新日 : 2026年1月9日
転籍とは?出向との違いやメリット・デメリットを解説!【テンプレート付き】
新卒採用であれ中途採用であれ、退職などの特別な事情がなければ通常は採用先の企業で勤務を続けることになります。しかし、人事異動の一環として他企業に籍を移す場合もあるでしょう。
当記事では、転籍について解説を行っています。出向との違いや転籍のポイント、メリット・デメリットなどについて解説しているため、ぜひ参考にしてください
目次
転籍とは?
「転籍」とは、現在籍を置いている企業との労働契約を終了させ、他企業との労働契約を締結することを意味します。「移籍」と呼ばれる場合もありますが、意味として異なることはありません。
転籍は人事異動の一環として行われます。しかし、出向など他の人事異動とはどのように異なっているのでしょうか。
転籍と転職に違いはある?
転籍は、企業による人事異動制度のひとつです。企業が持つ人事権に基づいて、社員に転籍を命じることになります。一方の転職は社員が自発的に退職し、他の企業と労働契約を締結することになります。転職が企業による人事異動として行われることはありません。
転籍と出向の違い
転籍は、それまで勤めていた企業との労働契約を終了させます。つまり、在籍していた企業の籍は、転籍により消滅することになります。一方の出向は、通常勤務先である企業に籍を残したまま他企業で業務に従事する点で転籍と異なった制度です。
転籍と左遷の違い
企業は、評価の低い社員を閑職などに異動させる「左遷」を行うこともあります。企業によっては、左遷の目的で転籍を行う場合もあるでしょう。しかし、転籍はキャリアアップを目的とする「栄転」の場合もあり、一概に左遷であると決めつけることはできません。
会社における転籍の意味
企業が転籍という言葉を用いる場合は、人事異動を指します。人材育成や雇用調整など、企業の目的に応じた形で、社員に対して転籍を命じることが一般的でしょう。転籍した社員は、それまで勤務していた企業の籍を失い、転籍先企業の社員として扱われます。
日常生活における転籍の意味
転籍は企業の人事制度としてだけでなく、日常生活でも使用されています。代表的な例として、戸籍の本籍地を移すために行う「転籍手続」が挙げられます。市区町村役所の戸籍課などで、転籍届を提出したことのある方も多いのではないでしょうか。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
従業員情報の一元管理を実現する方法
従業員情報の収集や転記、複数システムの情報更新など「従業員情報の管理」が複雑になっていませんか?
この資料では、従業員情報の管理でよくあるお悩みとマネーフォワード クラウド人事管理を活用した業務改善方法を紹介します。
労務管理業務のミス・トラブル防止ガイド~身上変更編~
本資料では、身上変更手続きの流れや、よくあるミス・トラブル事例を防ぐためのポイントを紹介します。
ぜひダウンロードのうえ、業務にお役立てください。
社員情報管理シート(ワード)
社員情報の管理にご利用いただける、ワード形式の管理シートです。ダウンロード後、直接入力や編集が可能です。
ぜひ、社内の社員情報管理や整理にお役立てください。
労働者名簿(ワード)
労働者情報の管理にご利用いただける、ワード形式の労働者名簿です。
直接入力や編集が可能になっておりますので、名簿の作成や管理にご活用ください。
転籍をより深く理解するために:出向の種類
転籍と出向は共通点も多く、時には混同して使用されているケースも見られます。しかし、両者は根本的に異なった制度です。出向の種類を解説するため、しっかりと理解し、混同しないようにしてください。
転籍出向
「転籍出向」では、出向元企業との労働契約を解消し、出向先企業と新たに労働契約を締結します。企業によっては別の定義をしている場合もありますが、当記事で解説する転籍は、この転籍出向を指しています。「移籍出向」と呼ぶ場合もありますが、意味合いに違いはなく、同様の人事異動と考えて問題ありません。
転籍出向(転籍)では、出向期間が経過しても出向元に復帰する可能性はほとんどありません。人事戦略の一環として行われるような場合には、出向元に復帰することもあり得ます。しかし、その場合でも復帰時には新たな労働契約の締結が必要となります。出向元との労働契約は、すでに解消されているためです。
在籍出向
通常企業が出向という言葉を使う場合には、転籍出向ではなく「在籍出向」を意味しています。単純に出向といった場合には、在籍出向を指す場合が多いでしょう。
在籍出向は、転籍出向と異なり、出向元企業との労働契約は解消されません。そのため、出向元企業に籍を残したまま、出向先企業で業務を行うことになります。この点が転籍出向(転籍)との根本的な違いです。また、在籍出向は出向元企業と雇用関係が継続したままであり、出向期間が経過した後は出向元へ復帰することが一般的であることも特徴となります。
転籍におけるポイント – 子会社や関連会社に行く場合
転籍は、グループ内の子会社や関連会社に対して行われることが多くなっています。転籍では、それまでの勤務先企業との雇用関係を終了させるため、押さえておくべきポイントが存在します。
労働条件の変更 – 福利厚生や給与・休日など
転籍では、それまでの労働契約を解消し、転籍先企業との間で新たな労働契約を締結します。その際には、労働条件が変更されることもあり、転籍の対象となる社員への十分な説明が必要となるでしょう。グループ内であっても別企業での勤務となるため、給与はもちろんのこと、休日や福利厚生などにも変更が生じることが予想されます。
転籍の場合も退職金は出る?
退職金は、法律で支給が義務付けられているわけではありません。そのため、支給の有無や内容についても企業によって異なることが通常です。これは、転籍の場合における退職金の扱いについても同様で、どのように規定しているかは企業によって異なります。しかし、労働契約が終了することになるため、一般的には転籍時に一旦退職金を清算する企業が多いでしょう。
転籍時に退職金を支給せずに、転籍先企業での勤務年数を通算し、転籍先企業の退職時に支払われる場合もあります。退職金は勤続年数が大きく関わることが多く、しっかりと扱いを定めておく必要があるでしょう。
転籍先で退職した場合
通常転籍先企業を退職した場合であっても、元の企業に復帰することはありません。在籍出向などとは異なり、元の企業との雇用関係はすでに終了しているためです。そのため、転籍先企業を退職した場合は、転籍先企業の就業規則等の定めに基づいて退職処理がされることになるでしょう。
転籍は拒否できる?手続きなど
企業は、社員に対して人事権や指揮命令権を有しています。そのため、就業規則等に根拠規定があり、必要性があれば転籍や出向などの人事異動を命じることが可能です。
しかし、労働契約の終了と新たな締結を伴う転籍は、社員の個別的同意がなければ行えません。一方的に労働契約を終了させたり、新たに締結させたりすることはできないからです。企業にとって人事戦略上の必要性があるだけでは足りません。そのため、就業規則等に「転籍を命じることができる」と規定されていても、合意しない(拒否する)ことは可能です。
社内において、転籍拒否の手続きが定められている場合は、その定めに従って手続きを行うことが望ましいでしょう。しかし、仮に所定の手続きを経なくとも、社員が転籍に対して拒否の意思表示を行えば、転籍は不可能となります。ただ、この場合であっても後に、「言った」「言わない」の争いが起きる可能性があります。そのため、可能であれば書面で拒否の意思表示を行うべきでしょう。
転籍を従業員にさせる企業側のメリット
それまでの勤務先企業との労働契約を終了させる転籍は、社員にとって大きな影響があります。ときには拒否されることもあり得る転籍を、企業が行うメリットはどのようなものなのでしょうか。
人材の育成・キャリアップに繋がる
転籍は、企業の人事戦略に基づいて実行される場合もあります。それまでと異なった環境である転籍先での業務は、新たな気付きにつながることも多く、社員の成長を促す効果も期待できます。そのため、転籍は企業の人材育成にとってメリットのある制度だといえるでしょう。
グループや関連会社へのノウハウ伝達・ナレッジの蓄積
グループ内の子会社や関連会社に社員を転籍させることは、親企業などが持つ業務ノウハウの伝達効果が期待できます。また、転籍はグループ内でのナレッジシェアの効果もあり、組織全体の知識やスキルの向上が見込めるでしょう。
雇用調整
労働契約を終了させる転籍は、雇用調整の手段としても活用可能です。雇用調整の手段として整理解雇などを行えば、その有効性を巡って後の訴訟問題にも発展しかねません。しかし、再就職先ともいえる転籍先が用意されている転籍であれば、トラブルに発展することも少ないでしょう。
転籍をする従業員側のメリット
転籍は、企業だけでなく社員にとってもメリットのある制度です。項目ごとにメリットを見ていきましょう。
人材の育成・キャリアップに繋がる
すでに述べた通り、転籍は企業にとって、人材育成の面でメリットのある制度です。そして、これは転籍をする側にとっても変わることのないメリットになります。これまでと異なった環境での業務は、新たな知識やスキルの習得を促し、キャリアアップにつながります。
出世などのチャンスが広がる
転籍によってキャリアアップができれば、昇進のチャンスも多くなるでしょう。また、元の企業では評価されなかった人材でも、異なった環境である転籍先では高い評価を受ける場合もあります。転籍先という新しい環境へ飛び込むことは、チャンスの拡大につながるといえるでしょう。
転籍を従業員にさせる企業側のデメリット
転籍はメリットばかりではなく、デメリットも存在します。企業側にとってのデメリットを見ていきましょう。
話し合いによる同意が必要
転籍は、対象者となる社員の同意がなければ行えません。就業環境や労働条件が大きく変わる可能性もある転籍について、同意を得ることは容易ではないでしょう。必要性を十分に説明し、場合によっては転籍によるインセンティブの付与も考えなくてはなりません。
転籍元の部署について新しく人員を割り当てる必要がある場合も
転籍を行えば、当然、元の部署の人員は減少します。代替人員がすぐに確保できれば良いですが、人材獲得競争が激化している昨今では、それも容易ではないでしょう。転籍の際には業務効率化も併せて検討する必要があります。
転籍する従業員側のデメリット
転籍は、社員のキャリアップにつながる制度です。しかし、メリットばかりではなく、デメリットも存在するため注意しましょう。
新しいルール・規則を学ぶ必要がある
転籍をした社員は、転籍先の就業規則等の適用を受けることになります。これまでとは違った職場のルールが存在する場合もあり、新しいルールや規則を学ぶためには、十分な時間が必要となります。
勤務先・居住地が変わる可能性も
同じオフィスビル内にグループ会社を設けている場合もあります。しかし、転籍先が同じ所在地であることは少ないでしょう。転籍による勤務先の変更は、通勤時間の増加につながる場合もあり、場合によっては引っ越しまで必要となります。
転籍における注意点
転籍は、労働契約の解除と締結が必要となります。そのため、通常の人事異動とは異なった注意点も存在します。
労働者本人の同意が必要
これまでも解説してきた通り、転籍には対象者本人の同意が必要です。どれだけ企業にとって必要性の高い転籍であっても、本人の同意がなければ行えないことに注意しましょう。なし崩し的に行ってしまえば、後の訴訟問題にも発展しかねません。
労働条件などの明示が必要
転籍では、それまでの雇用関係を終了させ、あらたな労働契約を締結する関係上、改めて労働条件について明示が必要となります。グループ内での異動のため、明示は不要であるなどと安易に考えないようにしましょう。
退職金の取扱や支払い時期の合意が必要
転籍によって、退職金の取扱いが変更される場合もあり得ます。支給額が低下したり、支払時期が変更されたりする場合もあるため、しっかりと説明し合意しましょう。一方的に退職金を減額させることはできないため、合意が得られなかった場合には代替措置を講じるなどの努力を行うことが必要です。
転籍辞令・転籍同意書の無料テンプレート
転籍の同意をえる場合には、転籍辞令を提出しておくことでトラブルが防げます。以下から無料でテンプレートをダウンロードいただけます。
転籍辞令のテンプレート・ひな形
転籍同意書のテンプレート・ひな形
転籍を活用した企業の成長を
転籍は、就業環境や待遇が大きく変化する可能性があり、社員にとっても負担の大きい制度といえます。しかし、有効に活用すればグループ全体の成長にもつながり、競争力強化も図れます。当記事の解説を参考に適切な転籍を実施してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
報酬制度の設計方法は?税金の扱いや役員報酬の場合などを解説
報酬制度は、社員のやる気を引き出し、企業の成長を後押しする重要な仕組みです。しかし設計は複雑で、目的や種類、税務の扱いまで幅広い知識が必要です。不公平な制度はモチベーション低下や離…
詳しくみる労働基準法第106条とは?就業規則の周知義務や注意点をわかりやすく解説
労働基準法第106条は、就業規則など会社のルールを従業員に周知する義務を規定した重要な条文です。企業の人事・法務担当者にとって、従業員へのルール周知は法令遵守の基本であり、怠れば労…
詳しくみる退職勧奨と諭旨解雇の違いとは?条件や正しい手続きの流れを解説
退職勧奨と諭旨解雇の違いについて、理解できていないと感じる方もいるのではないでしょうか。 本記事では、退職勧奨と諭旨解雇の基本的な違いや特徴を整理し、それぞれの概要をわかりやすく解…
詳しくみる【条件チェック付】育休の延長はできる?給付金の申請方法や会社への伝え方
現在育児休業を取得中なものの、保育園が決まらない、子どもを養育予定者だった配偶者自身が病気で養育の期間を伸ばしたいといった場合には、申請すれば育児休業の延長を行えます。 本記事では…
詳しくみる就業規則の相談窓口の記載例・サンプル|パワハラ防止措置の義務化についても解説
企業の健全な発展と、従業員が安心して働ける環境の構築において、ハラスメント等の相談窓口の設置は極めて重要です。特に、2022年4月から中小企業を含む全企業にパワーハラスメント(パワ…
詳しくみる人事管理システムのメリット・デメリットを解説!選び方や注意点も紹介
「人事業務が煩雑で時間がかかる」「人材データをうまく活用できていない」。こうした課題を解決するのが人事管理システムです。システムの導入は、業務効率化と戦略的な人材活用の両面でメリッ…
詳しくみる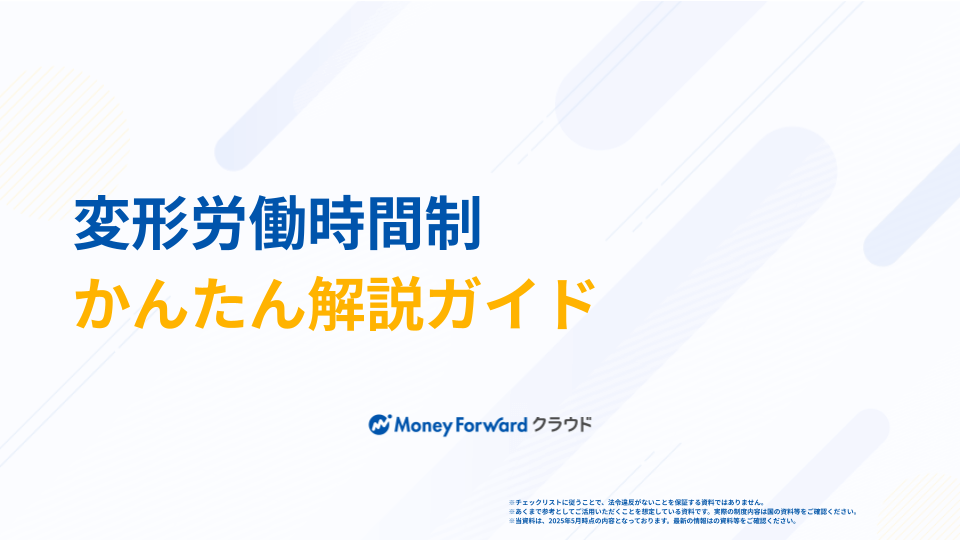


-e1763456976307.jpg)
-e1763457332633.jpg)