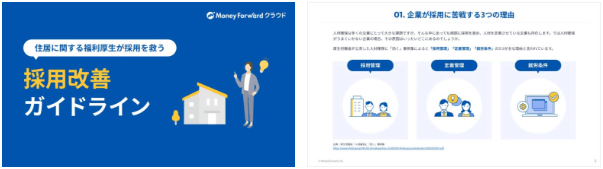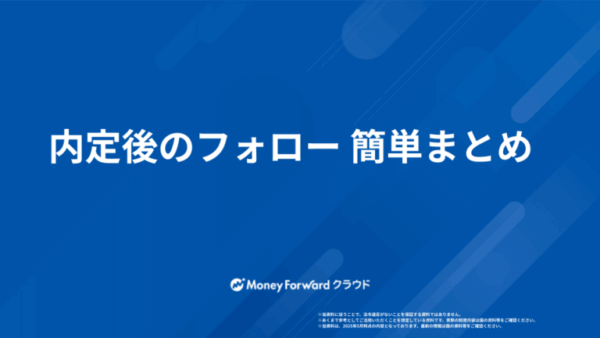- 更新日 : 2025年11月11日
有効求人倍率とは?計算方法や最新情報を紹介!
有効求人倍率とは求職者数と求人数の割合を示す数値です。求職者に対して求人がどのぐらいあるかを表し、求人数を求職者数で割って計算されます。求職者数と求人数が同じである場合に1になり、求人が多いと1より大きくなり、求人が不足していると1より小さくなります。雇用状況を表す重要な指標であり、推移は景気動向の判断に用いられます。
目次
有効求人倍率とは?
有効求人倍率とは、有効求職者数に対する有効求人数の割合の数値です。求職者が求人数に対してどれだけ存在しているかを表し、労働市場の需給バランスを示します。推移からは経済の動向が判断でき、重要な経済指標として用いられます。
厚生労働省によりハローワークにおける求人・求職の状況から算出し、一般職業紹介状況(職業安定業務統計)で毎月公表されています。
有効求人倍率における「有効」とは?
有効求人倍率の「有効」とは、求職者が求人に応募できる状態であることを意味します。申込みのあった日を含めて3ヵ月の求職・求人から計算される指数が有効求人倍率です。求人倍率を示す指標には有効求人倍率の他に、新規求人倍率と月間有効求人倍率があります。
- 有効求人倍率申込みのあった日を含めて3ヵ月間の求職者数に対する求人数の割合
- 新規求人倍率申込みのあった日を含める各月の求職者数に対する求人数の割合
- 月間有効求人倍率前月から繰り越された求職者数・求人数と新規求職者数・求人数の合計から求める求人倍率
有効求人倍率が高い・低い場合はどう考えればよい?
有効求人倍率は求職者1人に対して何件の求人があるかを示す指標です。有効求人倍率が高い場合、求職者にとって競争は少なくなり、優位に立つことができます。逆に有効求人倍率が低い場合は、求職者の競争は激しくなると考えられます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
最新の有効求人倍率データ
2022年平均の有効求人倍率は1.28で、前年の1.13に比べて0.15上昇しました。平均の有効求人は前年に比べて12.7%増え、平均の有効求職者は前年に比べて0.7%減っています。
【有効求人倍率の推移】
| 2018年 | 1.61 |
|---|---|
| 2019年 | 1.60 |
| 2020年 | 1.18 |
| 2021年 | 1.13 |
| 2022年 | 1.28 |
有効求人倍率の計算方法
有効求人倍率は過去3ヵ月間の申込みされた求人数を、同じく過去3ヵ月間に申込みされた求職者数で割って求めます。計算式は以下の通りで、求職者数と求人数が同じである場合に1倍となります。
・有効求人倍率を求める計算式
例えば過去3ヵ月間の申込みされた求人数が100人、求職者数が110人の場合は次のように計算します。
100/110=0.91
過去3ヵ月間の申込みされた求人数が100人、求職者数が90人の場合は次のように計算します。
100/90=1.11
有効求人倍率を参考にするうえでの注意点
有効求人倍率は雇用状況を示す指標で、職業への就きやすさを表しています。就職・転職活動で有利か不利かの基準にできますが、以下に説明するような注意点もあります。
ハローワーク以外の求人・求職は含まない
有効求人倍率はハローワークに申込みがあった求人・求職の情報に基づいて計算されます。ハローワークに申し込まれていない求人・求職は計算に含まれないため、実態とは差が生じます。求職活動では民間の就職・転職情報で、求人に対する求職者の割合などをチェックする必要があります。
正規・非正規雇用の区別はない
有効求人倍率は正規・非正規雇用を区別していないため、正規雇用で求職をしている場合は参考になりにくい点にも注意しなければなりません。正規雇用と非正規雇用で求人・求職数に大きな差がある場合に、とくに気をつける必要があるでしょう。
有効求人倍率を人材の流出防止に役立てよう
有効求人倍率とは求職者数と求人数の割合を示す数値です。1人の求職者に対して何人の求人があるかを表し、数値が大きい場合は求人が多くあり、数値が小さい場合は求人が少ないことを表します。
求人数を求職者数で割って計算され、求職者数と求人数が同じ場合は1になります。1より大きいと求職者より求人数が多いため売り手市場、1より小さいと求人数より求職者数が多いため買い手市場であることを示します。
有効求人倍率は雇用状況を示し、求職・転職活動において求職者が有利か不利かの把握に用いられます。数値が大きい場合は求職者優位であるため、転職も求職者にとって有利に働きます。そして有効求人倍率の動向は、自社内で転職・退職を考えている人を後押しする可能性もあるため、人材の流出防止のためにも注視し続ける必要があるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
エンパシーとは何か?ビジネスにおける重要性や具体例、高め方を解説
ビジネスシーンにおいて「エンパシー」という言葉を耳にする機会もあるでしょう。多様な価値観を持つ人々がともに働く現代において、他者を理解する力は組織運営においても重要な能力です。 エ…
詳しくみるダイアローグとは?意味や実施方法を解説!
ダイアローグとは、単なる情報交換にとどまらずに相互理解を通じて意識や行動の変化を引き出し合う創造的コミュニケーション手法です。チーム内のコミュニケーションの質を高め、パフォーマンス…
詳しくみるPM理論とは?PとMの違い・4つのリーダータイプ・育成方法まで解説
PM理論は、リーダーシップを 目標達成機能(P) と 集団維持機能(M) の2軸で捉える行動理論で、チームが成果を出し続けるためのリーダー行動の状態を客観的に把握できるのが最大の特…
詳しくみるバックグラウンドチェックとは?目的や調査項目、実施する流れを解説
企業が採用時に、候補者の信頼性や適性を確認する手段として、バックグラウンドチェックがあります。では、バックグラウンドチェックは、どのように実施されるのでしょうか? 本記事では、バッ…
詳しくみるチームワークを高めるには?リーダーの役割や失敗例、企業事例
ビジネスシーンにおいては、他のメンバーと共同して業務を進めることも少なくありません。このようにひとりではなく、複数人のチームによる場合には、チームワークが非常に重要です。 当記事で…
詳しくみる5月病とは?症状や対策、治し方を解説
5月病とは、新年度になり環境が変わったことにより、環境に適応しきれないなどの原因で、心身の不調に悩まされる症状です。5月病を抑制するためには、日常生活における心がけや工夫が大切です…
詳しくみる