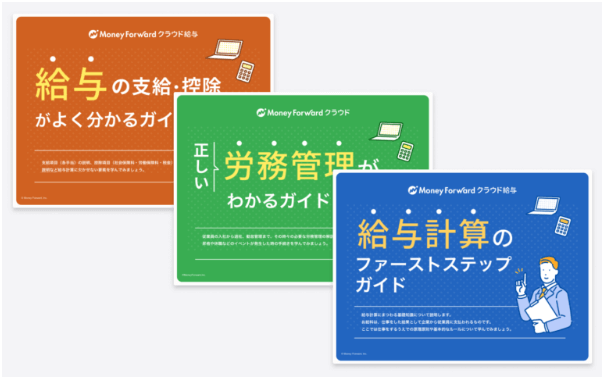- 更新日 : 2026年1月30日
ボーナス(賞与)とは?支給日や手取り計算方法など解説
ボーナス(賞与)とは、毎月の給与とは別に支払われる特別な賃金であり、一般的には夏と冬の年2回支給されます。所得税法では「給与、賃金、賞与、手当などの名称に関わらず、労働の対価として支払われるもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの」と定義されています。
本記事では、ボーナスの定義から、公務員と民間企業での支給時期の違い、手取り額の計算シミュレーション、さらには損をしないための「支給日在籍要件」まで、人事労務の視点で詳しく解説します。
目次
ボーナス(賞与)とは?
ボーナスとは、毎月の定額給与とは別に、会社の業績や個人の査定に応じて支払われる臨時賃金です。
英語の「Bonus」と日本語の「賞与」は言葉が違うだけで、実務上は同じ意味を指します。
法律上の支払い義務はない
ボーナスには、労働基準法などの法律による一律の支給義務はありません。
給与とは異なり、ボーナスを「支給するかどうか」「いくら支払うか」は各企業の就業規則や労働契約の定めに委ねられています。そのため、業績悪化を理由に「賞与なし」としても、規定に「業績により支給しないことがある」旨の記載があれば法的に問題はありません。
所得税法における賞与の定義
税法上、ボーナスは「3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの」と定義されています。
毎月支払われる通常の給与に対し、賞与は支払い間隔が3ヶ月を超えるため、所得税の計算方法(源泉徴収税率)が通常の給与とは異なる仕組みになっています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
賞与計算規程(エクセル)
賞与計算に関する取り決めを整備するための、エクセル形式の規程テンプレートです。貴社の規定や運用に合わせて手軽に内容を修正・カスタマイズいただけます。
スムーズな運用開始をサポートする実用的な資料としてご活用ください。
賞与計算(社会保険料計算)シート
賞与支給額の算出および、社会保険料の計算に対応した実務用シートです。
計算業務の効率化と円滑な事務処理をサポートする資料として、ぜひダウンロードしてご活用ください。
給与計算ミスを防ぐ60のチェックリスト<完全版>
給与計算ミスの発生を防ぐため、雇入れ直後・異動直後などのシーン別に確認すべきポイントを完全保存版・チェックリストとしてまとめました。
起こりやすいミスの傾向についても解説していますので、ぜひ業務にお役立てください。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
ボーナスの支給日はいつ?
一般的に夏は6月下旬から7月上旬、冬は12月中旬から下旬に支給されるのが通例です。
ただし、具体的な日付については公務員と民間企業で決まり方が異なります。
【公務員】法律・条例で固定された支給日と運用ルール
公務員のボーナス支給日は、法律や条例によって日付が厳格に特定されています。
- 具体的な日付: 国家公務員の場合、夏は6月30日、冬は12月10日と定められています。
- 休日の扱い: 支給日が土曜日や日曜日に重なる場合は、直前の平日に繰り上げて支払われるのが通例です。
- 指標としての役割: この固定された支給日は、民間企業が自社の賞与支給日を検討する際の有力な指標(ベンチマーク)としても活用されています。
【民間企業】各社の裁量による支給時期と決算賞与の有無
民間企業のボーナス支給日は、各社の就業規則や資金繰り、給与支払日の慣習に合わせて柔軟に設定されます。
- 一般的な傾向: 夏は6月下旬〜7月上旬、冬は12月中旬〜下旬に設定する企業が多いですが、必ずしも公務員と同じ日にする必要はありません。
- 第3のボーナス「決算賞与」: 定期賞与(夏・冬)とは別に、企業の決算月(例:3月)に合わせて利益を還元する仕組みです。この制度がある企業では、年3回の支給タイミングが存在することになります。
- 実務上の注意: 支給日をいつにするかは自由ですが、一度規則に定めた場合は、その日に支払う法的義務が生じる点に留意が必要です。
ボーナスの支給回数や支払いに関するルールは?
ボーナスの支給回数や日程に法律上の制限はなく、年1回から3回、あるいは「なし」とするのも企業の自由です。
ただし、就業規則に支給回数や日程を明記している場合は、企業はその定めに従う法的義務が生じます。
民間企業のボーナス支給日の決まり方
民間企業のボーナス支給日は、各社の就業規則や資金繰り、給与支払日の慣習に合わせて自由に設定されます。
法律による縛りがないため、多くの企業では公務員の支給日に合わせたり、月々の給与支給日と同じ日に設定したりすることで、振込実務の効率化を図っています。
ただし、一度規則に定めた日付は「労働契約」として法的拘束力を持つため、正当な理由なく遅延させることはできません。
決算賞与を損金算入するための支払い期限
決算賞与をその年度の損金(経費)として計上するには、「事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内」に支払う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、その年度の経費として認められず、節税効果が得られなくなる可能性があるため、労務担当者は財務部門と連携して厳格にスケジュールを管理しなければなりません。
税務上で必須となる従業員への通知
決算賞与を未払金として計上する場合、「全従業員に対して、あらかじめ個別の支給額を通知していること」が税務上の必須要件です。
単に「ボーナスを出す」と伝えるだけでなく、各人にいくら支払うかを具体的に確定させ、通知した事実を残しておく必要があります。これにより、法的に「債務が確定している」とみなされ、当期の損金として処理することが可能になります。
ボーナスの種類は何がある?
ボーナスは主に基本給連動型・業績連動型・決算賞与の3種類に分けられます。
多くの企業ではこれらを単独、あるいは組み合わせて支給額を決定しています。それぞれの性質を理解することで、自社の評価制度がどのタイプに該当するかを把握できます。
基本給連動型の特徴
「基本給の〇ヶ月分」のように、月々の基本給をベースに支給額を決定する方式です。
日本の伝統的な企業に多く、支給額の予測が立てやすいため従業員の生活設計が安定するというメリットがあります。一方で、会社や個人の最新の業績が金額に反映されにくいという側面も持っています。
業績連動型の特徴
会社全体の利益や部門・個人の目標達成度(査定)に応じて、支給額が変動する方式です。
成果がダイレクトにボーナス額へ反映されるため、従業員のモチベーションアップにつながりやすいのが特長です。外資系企業や成果主義を導入している企業で広く採用されていますが、業績が悪化すると支給額が大きく下がるリスクもあります。
決算賞与の特徴
企業の決算期において、予想以上の利益が出た際に特別に分配される臨時ボーナスです。
夏や冬の定期賞与とは別に支給されるもので、その年度の利益を従業員に還元する性質があります。会社にとっては節税効果があり、従業員にとっては「会社の成功を分かち合う」という結束力を高める効果が期待できます。
ボーナス支給の有無や金額はどう決まる?
ボーナスの有無や金額は、就業規則の規定と会社業績・個人査定の組み合わせによって決定されます。
法律による強制がないからこそ、会社ごとに定められたルール(賃金規定)がすべての判断基準となります。
ボーナス支給をなしにできる条件
就業規則に「業績により支給しないことがある」旨の条項(エスケープクローズ)があれば、不支給にすることが可能です。
もし規則に「年2回、各2ヶ月分を支給する」と断定的に記載されている場合は、業績に関わらず支払う義務が生じます。そのため、リスク管理の観点からも、多くの企業では業績に応じた変動の余地を残す規定を設けています。
ボーナスの支払金額の算出方法
一般的には「基本給 × 支給倍率(月数) × 人事評価係数」などの計算式を用いて算出されます。
支給額の決定プロセスは企業規模によって異なります。大企業ではあらかじめ定められた算定式に基づき機械的に計算されることが多い一方、小規模企業では社長の裁量によって額が決定されるケースも見られます。
計算ルールを明確化・透明化するメリット
ボーナスの計算方法をオープンにすることは、従業員の納得感を高め、モチベーション向上に直結します。
「なぜこの金額なのか」という根拠が明確であれば、従業員は次の支給に向けた目標を立てやすくなります。また、労務担当者にとっても、計算ルールが定まっていることで支給時期の事務作業を大幅に効率化できるという実務上の利点があります。
ボーナスの手取りはどう計算する?
額面の約8割が手取りの目安です。ボーナスの支給額(額面)からは、社会保険料と所得税が天引きされます。月々の給与計算とは異なり、原則として住民税が引かれないことが大きな特徴です。
天引きされる社会保険料の算出
ボーナス額面(1,000円未満切り捨て)に、会社と折半する保険料率を乗じて算出します。
退職時の社会保険料免除ルール
退職する月(資格喪失月)に支払われたボーナスからは、健康保険と厚生年金の保険料は徴収されません。
- 保険料がかからない例: 12月20日に退職し、12月25日にボーナスを受け取った場合、月をまたぐ在籍ではないため免除されます。
- 保険料がかかる例: 12月31日(月末)に退職した場合。翌年1月1日が資格喪失日となるため、12月のボーナスからも保険料が引かれます。
所得税の計算と住民税の扱い
ボーナスの所得税は、「前月の給与額」に基づいた専用の税率を使用して計算します。
- 所得税: 前月の給与(社会保険料控除後)と扶養家族数から決まる「算出率」を、ボーナス額面から社会保険料を引いた額に乗じます。
- 住民税: 前年の年収を12分割して毎月の給与から徴収する仕組みのため、ボーナス時に別途天引きされることは原則ありません。
ボーナス受給で損をしないための注意点は?
「支給日に在籍しているか」と「査定期間(評価対象期間)」の2点を正確に把握することが不可欠です。
特に退職や転職を控えている時期は、これらの仕組みを誤解すると支給対象から外れたり、想定より大幅に減額されたりするリスクがあります。
知らないと危険な「支給日在籍要件」
就業規則に「支給日に在籍していること」という規定がある場合、支給日より前に退職するとボーナスの受給権利が消滅します。
たとえば、査定期間中にフルタイムで働き高い成果を出していたとしても、支給日の前日に辞めてしまえば1円ももらえない可能性があります。このルールは「将来の貢献への期待」という性質も含むため、法的に有効と認められるのが一般的です。退職日を決める際は、必ず自社の就業規則を確認しましょう。
ボーナス評価の対象となる「査定期間」の把握
一般的に夏は「前年10月〜3月」、冬は「当年4月〜9月」の成果が評価対象となります。
この期間の途中で入社・復職・休職をした場合、支給額が日割り計算になったり、「寸志(すんし)」として少額の支給に留まったりすることがあります。「今の頑張りがいつのボーナスに反映されるのか」というサイクルを知ることで、支給額の妥当性を冷静に判断できるようになります。
ボーナスを満額受け取って辞めるためのスケジュール
ボーナスを確実に、かつ満額受け取ってから辞めるには、「支給日を過ぎてから退職願を提出する」のが最も安全なスケジュールです。
支給日直前に退職意思を伝えると、会社によっては情意評価(今後の期待値)が下がり、査定額が減額されるケースも稀にあります。円満に、かつ権利を最大限に活かして受給するためには、賞与が手元に入った後に退職アクションを起こすことを推奨します。
【人事労務向け】ボーナス支給後の必要手続きは?
支給日から5日以内に年金事務所等へ「賞与支払届」を提出する義務があります。
正確な届出は従業員の将来の年金額に直結するため、事務担当者は漏れのない対応が求められます。
年金事務所への「賞与支払届」の提出
社会保険加入者全員の賞与額を報告します。
正式名称は「被保険者賞与支払届」で、紙のほか電子申請も可能です。もし事前に賞与支払予定月を登録していながら、業績不振等で支給しなかった場合でも、「賞与不支給報告書」の提出が必要になる点に注意してください。
70歳以上の従業員への対応
厚生年金保険料の徴収義務はなくても、「70歳以上被用者賞与支払届」の提出が必要です。
70歳を過ぎても働く従業員に賞与を支払った場合、その額は「在職老齢年金」の計算(年金カットの判定)に使用されます。保険料は発生しませんが、届出を怠ると年金支払額の過不足に繋がります。
育休者や産休者への対応
社会保険料が免除されている休業者に賞与を支払った場合も、賞与支払届の提出は必須です。
育児休業等で保険料が免除されていても、賞与額を報告することで、休んでいた期間も「標準的な賞与があった」ものとして将来の年金額が計算されます。従業員への不利益を避けるため、忘れずに処理を行いましょう。
適切なボーナス運用が会社の信頼を築く
ボーナスは従業員のモチベーションを左右する重要な賃金であり、正確な計算と透明性の高い運用が求められます。
労働者にとっては自身の貢献が反映される大切な機会ですが、会社側にとっては社会保険料の算出や所得税の源泉徴収、さらには「賞与支払届」の提出といった煩雑な実務が発生するタイミングでもあります。
人事労務担当者は、自社の就業規則に基づいた適正な支給を行い、従業員に対して「なぜその金額なのか」を説明できる体制を整えておくことが重要です。ミスなく迅速な事務処理を行うことは、従業員との信頼関係を深めるだけでなく、企業全体のコンプライアンス遵守にも直結します。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
給与計算はAIで自動化できる?RPAとの違いや仕事がなくなるのかも解説
近年、AIを活用した給与計算が注目されています。AIは、勤怠データの取り込みや給与計算、社会保険料の算出、給与明細の作成までを自動化し、業務の効率化と正確性の向上に貢献します。しか…
詳しくみる長野県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
長野県は農業や製造業が活発で、特に精密機器や自動車部品の生産が盛んです。また、豊かな自然を活かした観光業も地域経済を支えています。こうした多様なビジネス環境では、給与計算の正確性と…
詳しくみる役員報酬の決め方ガイド!具体的な流れや注意点、金額の相場・変更ルールまで徹底解説
会社経営において、役員報酬の決め方は、手元に残るキャッシュと納税額を左右する最も重要な経営判断の一つです。社長や取締役の給与額を適切に設定することで、法人税と個人の所得税・住民税・…
詳しくみるエクセルを使用した給与計算の方法とは?メリットや関数を紹介
エクセルでの給与計算は、コストを安く抑えられ手軽に使えるメリットがある一方で、法律の改正を随時手動で反映しなければならないといった作業が必要です。ここでは、エクセルを使用した給与計…
詳しくみる秋田県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
秋田県は農業や林業、漁業が盛んで、特に米や日本酒の生産が有名です。また、観光業も成長しており、多様なビジネスが展開されています。こうした地域特有の業種では、給与計算の正確さと効率化…
詳しくみる給与計算の流れと業務を自動化するメリット
給与計算の一連の流れは、RPAや給与計算ソフトを用いることで、自動化できます。人の感覚的なチェックができない、イレギュラーに対応できないといった難しい課題があるものの、給与計算を自…
詳しくみる
-e1763462562443.jpg)
シート-1.png)