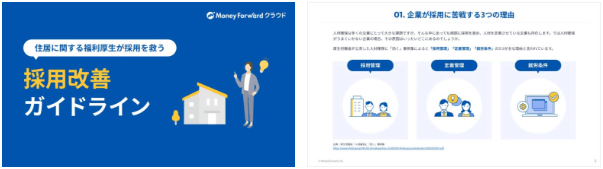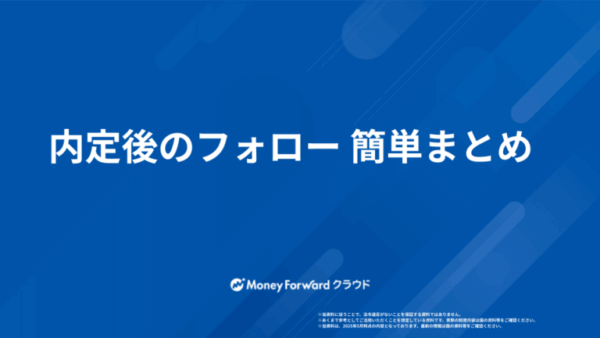- 更新日 : 2025年12月17日
第二新卒とは?意味や企業の採用において見るべきポイントを解説
第二新卒とは、明確な定義はありませんが、一般的に「卒業後就職し、その後離職した人(卒業後3年以内)」を意味する言葉です。この記事では、第二新卒の定義や第二新卒の募集が注目される背景、第二新卒を採用するメリット、採用手順について解説します。
目次
第二新卒とは?
厚生労働省「若年者雇用を取り巻く現状」によると、第二新卒は、各企業の中で定義がある場合はその定義によるものとし、特に定義がない場合は学校卒業後おおむね3年以内の者とされています。学校卒業後すぐに就職する人は除き、職務経験の有無は関係ありません。
新卒との違い
新卒とは、「新規卒業」や「新規卒業者」の略で、「その年の3月に卒業する見込みのある学生」を指すことが一般的です。学校卒業後にすぐ新入社員として働く人も新卒と呼ばれます。第二新卒は、学校を卒業して新卒として就職したものの、事情により退職をして3年以内の人を指すことが一般的です。
既卒との違い
既卒とは、学校卒業後一度も就職したことがない人を指す言葉です。第二新卒は就職したことがある人を指しますが、既卒は社会人経験のない人を指します。第二新卒と同様に卒業後3年以内までが既卒と扱われることが多く、アルバイトの有無にかかわらず既卒と呼ぶ傾向が多いようです。
フリーターとの違い
フリーターとは、アルバイトで生計を立てている人を指します。第二新卒と比較する場合、主に正社員経験がない人をフリーターと呼ぶことが一般的です。
第二新卒に年齢は関係ある?
第二新卒とひと口に言っても年齢はさまざまです。中卒や高卒は20歳前後、4年制の大学を卒業している場合は25歳前後、大学院を卒業している場合は26歳前後となります。明確な定義はないため、学校卒業後おおむね3年以内の年齢と考えるとわかりやすいでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
第二新卒は中途採用?新卒採用?
第二新卒を中途採用とするか、新卒採用とするかは企業によって異なります。中途採用は、社会人経験を3年以上積んでいる人を採用することが一般的です。しかし、第二新卒は3年以内に退職してしまっています。
中途採用はある程度キャリアを積みスキルやノウハウを身に付けた状態であるのに対し、第二新卒は実務経験が豊富とは言えません。とはいえ、その分どのような職種や社風にもなじみやすいことが期待ができます。
即戦力であれば「中途採用」、即戦力というより新卒に近い人材を求める企業であれば、「新卒採用」として第二新卒を採用応募することになるでしょう。
第二新卒の募集が注目される背景
従来は、第二新卒はマイナスなイメージが強くありました。しかし、現在はイメージが変わりつつあります。ここでは、第二新卒の募集が注目されるようになった背景を見ていきましょう。
終身雇用制度の希薄化
従来は、企業が正社員を定年まで雇用する制度である終身雇用制度が当たり前のものとされていました。しかし、経済成長が低迷したことで人件費の負担が重くなり、現在はこの制度は希薄化しつつあります。その結果、「転職」に対するハードルが下がりました。「早期離職→転職」というようなマイナスイメージが強かった第二新卒に対しても肯定的な意見が増えてきたことが注目され始めた背景と言えるでしょう。
新卒一括採用制度の問題点
新卒一括採用制度は終身雇用制度や年功序列の一部として機能する制度でした。しかし、終身雇用制度が希薄化した現在では、「定年まで雇うかわりに若いうちは給料が安い」「何年もかけて会社への忠誠心を育てる」といった新卒一括採用制度の在り方が機能しなくなりつつあります。
新卒一括採用制度における企業にとっての最大の問題点は、新卒一括採用への依存度が大きすぎて転職市場が発達せず、中途採用で優秀な人材を採用できないことです。そこで、新卒に近い存在で、可能性や伸びしろがある第二新卒が注目されるようになったと考えられます。
新卒に比べ教育コストがかからない
新卒の場合はビジネスマナーを基礎から教えなければならないため、研修期間が長く、それに伴い教育コストがかかります。第二新卒は、短期間とはいえ社会人経験があり、以前の勤務先で新入社員研修を終えていることがほとんどです。ビジネスマナーやビジネスの基礎が既に身に付いているため、新卒ほどの教育コストがかからないとされています。
第二新卒を採用するメリット
ここでは、第二新卒を採用するメリットを3つ紹介します。
基本的なマナーやスキルを身に付けている
先ほども触れましたが、第二新卒は社会人経験があることから、基本的なビジネスマナーやある程度のスキル、ネットリテラシーなどを身に付けている傾向にあります。研修のコストや手間がかからず、業務内容によっては即戦力となる可能性もあるでしょう。
新しい挑戦など意欲が高い
第二新卒は会社選びのミスマッチを経験しているからこそ、改めて自分の適性を認識し「新しく挑戦しよう」といった意欲が高くなりやすい傾向があります。社会人としての基本的なマナーやスキルを身に付けていて、なおかつ転職への本気度が高い第二新卒は、アグレッシブな若手人材を求める企業に適した人材と言えるでしょう。
新卒に比べ目的が明確な人材が多い
新卒一括採用による就職は、「大企業だから」「とりあえず受かったから」など漠然とした理由で会社選びをする人も少なくありません。卒業と同時に一斉に就職を求められるため無理もないでしょう。
しかし、第二新卒は会社選びの失敗経験があるため、目的が明確化された状態で就活をしています。失敗によって明らかになった目的に基づいて会社選びをしているため、入社後のミスマッチも起こりづらいと言えるでしょう。
第二新卒を採用するデメリット
第二新卒の採用はメリットが数多くある一方でデメリットも存在します。
新卒に比べ採用コストが高い
中途採用は新卒採用と比較して採用コストが高くなる傾向にあります。ただし、第二新卒やポテンシャルのある未経験採用を実施する場合は、中途採用のなかでも低予算で抑えることも可能です。第二新卒に経験やスキルを求め、即戦力として採用したい場合は予算が100万円を超える可能性も出てきます。
早期離職のリスク
前職で早期離職していることから「またすぐに辞めてしまうのではないか」と不安を感じる点はデメリットとなるでしょう。入社後のスキルマッチとカルチャーマッチに着目して、採用担当者だけでなく現場社員も積極的に採用活動に参加することが大切です。採用コストを無駄にしないためにも「前職の退職理由」「前職における不満」などを質問し、長く働けるかどうか見極めなければなりません。
組織へのフィット感
第二新卒は、一度、別の会社での価値観や文化を経験していることから、新しい環境に適応できないかもしれない懸念があるのです。採用活動においては企業文化への適応性という意味で「カルチャーフィット」という言葉が使われます。前述のように、現場社員も採用活動に参加して、実際の職場の雰囲気や業務内容を応募者に伝えたり見せたりする必要も出てくるでしょう。
第二新卒を採用する流れ
ここでは、第二新卒を採用する一連の流れを紹介します。
あえて第二新卒を採用する目標を設定
現社員の中には、第二新卒に対して良いイメージを持っていない人もいるかもしれません。なぜ新卒ではなくて第二新卒を採用するのか疑問を抱く人も出てくるでしょう。そこで「事業拡大に伴い迅速に若手人材を獲得するため」「新卒と異なり通年採用活動ができ、どの会社にも染まっていない第二新卒にフォーカスするため」など、あえて第二新卒を採用する目標を設定しましょう。現社員からの理解を得られるうえ、採用活動の方針も定まります。
採用コストやポジションを決定
リクルートの「就職白書」などを参考に、中途採用の平均コストを調べて採用予算を策定しましょう。平均コストはあくまでも参考にとどめ、自社に合った予算を立てることが大切です。ダイレクトリクルーティングやソーシャルリクルーティング、リファラル採用などを活用すれば採用コストを抑えられます。
採用コストと合わせてポジション決めも行いましょう。実際に応募者と面接をしてから決定できるように、複数の職種を用意してオープンポジションで選考するとスキルのミスマッチを防げます。
募集を行う
採用方法やポジションが決まったら、実際に広報・募集活動を行います。自社のホームページや求人サイトなどで募集要項を発信しましょう。募集要項には「事業拡大に伴い人員が必要なので、未経験者でも丁寧にフォローします」というような採用の目的と待遇を記載します。第二新卒のなかには社会人経験の浅さから応募をためらう人もいるためです。多くの人に安心して応募をしてもらえるように業務内容や求める人物像についても詳しく記載しましょう。
選考を行う
募集後、求職者から応募が来たら採用選考を行います。書類審査や筆記試験、面接などを通じて応募者のスキルや価値観、人間性などを確認しましょう。選考時は、スキルや経験だけでなく、人間性が自社にフィットするかどうかも確認することが重要です。選考前に求職者のことをより詳しく知りたい場合は、求職者と企業がお互いの知りたい情報を気軽に交換できる「カジュアル面談」を実施すると良いでしょう。
内定通知を出す
最終面接に合格した求職者に内定通知を出します。面接結果の最終的な内定通知は郵送が一般的ですが、入社の意思確認をしたい場合は電話で知らせることもあるようです。この場合、企業に直接来るように伝え、入社の意思を確認したあとに内容通知や重要書類を渡すことになります。
入社前と後のフォローを行う
内定辞退を防ぐために、入社前のフォローも必須です。内定者の疑問や不安を解消する機会や、求めている情報を提供できる場を設けましょう。例えば、「内定者同士の交流会」「現社員との交流会」「不安や疑問を解消する相談会」などが挙げられます。第二新卒は就職した経験があるとはいえ、転職には不安や疑問が付きまとうものです。入社後の教育はもちろん、入社前のフォローも行うようにしましょう。
第二新卒の採用で自社にマッチした人材を獲得しよう
ここまで、第二新卒の概要や第二新卒を採用するメリットについて解説しました。第二新卒と聞くと「早期離職」というイメージが強いかもしれませんが、基本的なビジネスマナーやパソコンスキルを身に付けているメリットがあります。「新卒一括採用シーズンに人が集まらなかった」「即戦力でなくてもいいから若手人材を求めている」という企業の人事労務担当者の方は、この機会に第二新卒の採用を検討してみてはいかがでしょうか。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
自己啓発とは?目的やメリット・デメリットを解説!
自己啓発とは自分のスキル・能力を向上させるための取り組みを指します。従業員が自己啓発を行うと効率的に業務ができたり高い技術を要する作業ができたりと、仕事にも良い影響を与えます。企業…
詳しくみる休職者が多い職場の特徴とは?人事が知るべき職場改善ポイントを紹介
「職場で休職者が増えている」、「一人が休むと次々に休職者が出る」そんな悩みを抱える人事担当者は少なくありません。 休職者が多い職場には、長時間労働や人間関係の悪化など複数の特徴があ…
詳しくみる短期離職とは?一般的な期間や短期離職が転職活動に与える影響を解説
短期離職とは、就職してから短期間のうちに退職することです。一般的には、3年以内に退職すると短期離職と判断されるケースが大半です。 短期離職をした人の中には「短期離職をしたらどのよう…
詳しくみる従業員エンゲージメント向上施策7選!向上のメリットや導入ステップを解説
企業と従業員の結びつきを強めることは、組織の成長において欠かせない要素です。しかし、「従業員エンゲージメント」という言葉を聞いたことはあっても、向上させる方法や導入時のポイントなど…
詳しくみるCAB適性検査とは?IT人材の採用で活かす目的やGAB・SPIとの違いを解説
企業のIT人材獲得競争が激化する中、候補者の潜在能力を客観的に評価する手法として「CAB適性検査」が注目されています。特にプログラマーやSEといった専門職の採用において、その効果を…
詳しくみる人材育成の課題とは?企業が直面する問題と解決策を解説
企業にとって、人材は最も重要な資源の一つであり、その育成は持続的成長につながる戦略課題です。しかし現実には、指導者不足や離職、時間や予算の制約など、多くの企業が人材育成に課題を抱え…
詳しくみる