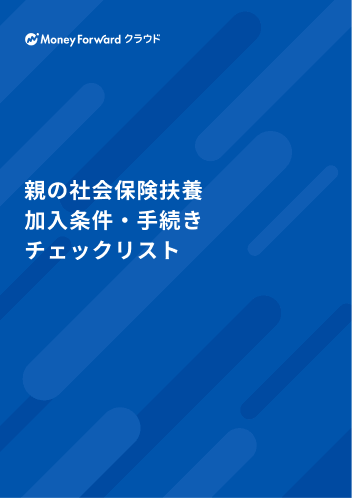- 更新日 : 2025年11月14日
親を社会保険の扶養に入れることはできる?条件や保険料を解説!
社会保険には扶養という家族の生計を支援する大事な制度があります。そんな扶養制度ですが、親と同居していなくても親を扶養に入れることはできるのか、親を扶養に入れる際の条件は、など親を扶養に入れる際のルールはご存知でしょうか。当記事では親を扶養に入れる際にまつわるさまざまな疑問点を解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
親を社会保険の扶養に入れることはできる?
社会保険の扶養対象者は、配偶者と三親等内の血縁者および事実婚関係にある配偶者とその両親・子・孫のため、その他複数の条件を満たせば親を扶養に入れることが可能です。
なお、社会保険とは「健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険」の5つの保険の総称ですが、会社員の場合狭義の意味で「健康保険・介護保険・厚生年金保険」の3つを表す際に「社会保険」という言葉が使われることが多いため、当記事では「健康保険・介護保険・厚生年金保険」を指して解説します。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
親を社会保険の扶養に入れる条件
続いて、親を社会保険の扶養に入れる条件について説明します。まずは被扶養者である親の住所および住民票が日本国内にあること、被扶養者が被保険者である自身より主として生計を維持されていることが条件になります。以下その他の条件を順に解説します。
自分が社会保険に加入している
扶養に入れる人自身が社会保険に加入している必要があります。扶養は、あくまで経済的に自立している人が経済的に自立していない人を支援する制度ですので、扶養をする人自身が社会保険に加入していて対象者を支援できる体制である必要があります。
親がバイト先などで社会保険に加入していない
社会保険の二重加入はできないため、被扶養者である親がバイト先などの就業先で社会保険に加入していない必要があります。2022年10月より社会保険の加入条件が緩和されたため、親の就業先で加入を勧められる可能性もあるので注意が必要です。社会保険加入の条件は厚生労働省のWebサイトなどで確認しておきましょう。
被保険者の収入もしくは仕送りで生活している
被保険者より主として生計を維持されていることが条件にあるため、同居している場合は被保険者の収入が主で生活をしている必要が、別居している場合には仕送りが主で生活をしている必要があります。親が自分の収入で生活をしている場合は扶養の対象にはならないので注意しましょう。
親の収入が扶養者の半分未満
上記収入要件の補足として、被扶養者である親の収入は親と同居している場合には扶養者の収入の半分未満、別居している場合には仕送り額未満である必要があります。
親の1年間の収入が130万円未満もしくは180万円未満
親の収入が扶養者の半分未満であることもしくは仕送り額未満であることに併せて、親の年間収入が130万円未満、60歳以上または障害者の場合は年間収入が180万円未満である必要があります。この時「年間収入」とは過去1年間を遡った実際の収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間収入見込み額のことを指します。例えば、被扶養者に該当する時点で1ヶ月で5万円の収入があった場合、1年間で60万円の収入が見込めるため年間収入は60万円と言ったように概算で算出します。
親を社会保険に入れることで変わる保険料
複数の条件を満たせば親を扶養に入れることができることがわかりました。続いて、親を扶養に入れた場合親の各保険料はどうなるのか解説します。
親の健康保険料
親を扶養に入れると親が支払う社会保険料は0円になりますが、親には健康保険証の被扶養者用が配布されます。一方親が社会保険の扶養に入らなかった場合には、親自身で国民健康保険に加入し保険料を支払って国民健康保険証が配布ことになるので、少なからず親の生計の負担になります。親を自身の社会保険の扶養に入れることで、親は国民健康保険料を支払わずに保険証を取得することができるため負担軽減に繋がります。
親の介護保険料
介護保険料は、健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が保険料を支払う義務が生じるというものです。ですが、親を自身の社会保険の扶養に入れた場合、親が支払うべき介護保険料は健康保険が負担してくれるため支払い額は0円になります。そのため、親を自身の社会保険の扶養に入れることで親の介護保険料の負担も軽減されます。
しかし、健康保険組合によっては規約により40歳未満の被保険者に40歳以上の被扶養者の介護保険料の納付を求めている場合もあるため、各健康保険組合のWebサイトなどで確認するようにしましょう。
親を社会保険の扶養に入れる手続きや書類
親を社会保険の扶養に入れる際には、被扶養者の条件に該当するかを事前に確認し、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」と必要な添付書類を所轄の年金事務所か事務センターに提出します。「被扶養者(異動)届」と添付書類は以下です。
被扶養者(異動)届

出典:第3号被保険者関係届
必要な添付書類
- 被扶養者の戸籍謄本か戸籍抄本
- 住民票の写し(被保険者が世帯主で被扶養者と同一世帯である場合に限る)
- 振込の場合:預金通帳の写し、振込明細書
- 送金の場合:現金書留の控え(写し)
親を社会保険の扶養に入れるうえでの注意点
75歳以上の親の場合
75歳になると後期高齢者医療制度に加入することとなり後期高齢者医療制度の保険料の支払いが発生するため、社会保険の扶養から外れることになります。そのため社会保険の扶養対象に年齢制限はないものの、親が75歳になった時点で社会保険の扶養対象ではなくなってしまうので注意しましょう。また、親が75歳に到達した時点で扶養から外す手続きが必要になるので併せて注意が必要です。
片方の親だけ社会保険の扶養に入れる場合
加入している健康保険組合の規約によっては、両親のいずれもが亡くなっていない場合、社会保険の扶養に両親のうちどちらかだけを入れるということができない場合があります。例えば、父親の年収が300万円、母親の年収が100万円という状態で母親だけ加入条件を満たしていたとしても、母親だけを自身の社会保険の扶養に入れることができない場合があるのです。健康保険組合の規約によるもののため、自身が加入している健康保険組合のWebサイトで確認するようにしましょう。
条件を満たせば親を扶養に入れることができる
複数の条件さえ満たせば親を扶養に入れることができること、理解いただけたかと思います。収入要件は一見複雑そうですが、一つずつ確認すれば扶養に入れる条件を満たしているか否か確認いただけます。また、今現在は親が国民健康保険や国民年金保険に入っている場合は、自身の社会保険の扶養に入れることで節約にも繋がります。ぜひ一度条件を確認してみてはいかがでしょうか。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
会社の代表者変更で必要な社会保険手続きは?事業所関係変更届の書き方も解説
会社の代表者や名称の変更、所在地の移転などが発生した際は、社会保険の変更手続きを行う必要があります。特に年金事務所の管轄が変わる都道府県をまたぐような移転の場合には、保険料率が変更…
詳しくみる社会保険(公的保険)と民間保険の違いとは?
保険には、国などが運営する社会保険と民間保険があります。いずれも保険事故が発生したときに備え、多くの人が集団を作り、個人経済のリスクを分散しようとする保険方式による点は共通していま…
詳しくみる労働保険の一般拠出金の申告とは?書き方や計算方法を解説
労働保険の年度更新の時期になると、事業主や労務担当者の方は「労働保険料・一般拠出金申告書」の作成に取り組みます。この申告書には労働保険料だけでなく、「一般拠出金」という項目もありま…
詳しくみる労災保険の休業補償給付を請求する際に医師の証明は必要?請求時に必要な書類も解説
休業補償給付とは、業務上のケガや病気が原因で休業する場合に、休業日の収入の一部を補填するための給付です。休業補償給付をスムーズに受け取るには、医師の証明が必要かどうかを含め、手続き…
詳しくみる社会保険は勤務期間の2ヵ月後から適用?令和4年10月の変更点
有期契約社員は、正社員とは社会保険の加入条件が異なります。旧制度では、契約期間が2ヵ月未満の方はその間の加入は不要でした。令和4年10月以降は更新の可能性がある場合、2ヵ月後からで…
詳しくみる雇用保険被保険者転勤届受理通知書とは?保管方法や転勤の手続きも解説
従業員が転勤する際、「雇用保険被保険者転勤届」の提出が必要ですが、その手続きが無事に完了したことを証明するのが「雇用保険被保険者転勤届受理通知書」です。この通知書は、手続きが正常に…
詳しくみる