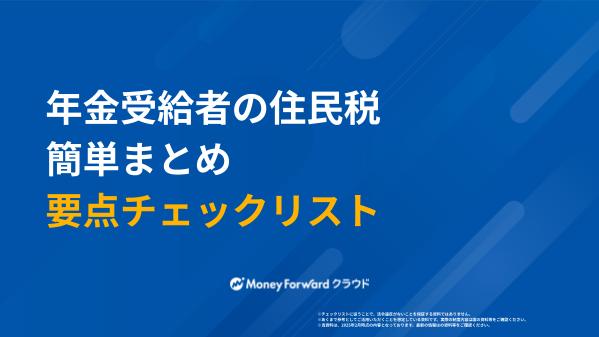- 更新日 : 2025年10月31日
年金から住民税は引かれる?課税・非課税の条件や金額を解説
2009年10月から、公的年金から住民税が引かれる特別徴収が行われるようになりました。特別徴収の対象は、4月1日時点で65歳以上の公的年金受給者のうち、住民税を納税する義務がある人です。
特別徴収対象年金額や特別徴収される住民税額は、毎年6月に市区町村から送付される税額決定・納税通知書に記載され、通知されます。
目次
年金から住民税は引かれる?
会社員の給与所得や個人事業主の事業所得には、税金がかかります。では、高齢者が受け取る老齢年金や、障がい者・遺族に対して支払われる障害年金・遺族年金に税金はかかるのでしょうか? ここでは、「年金から住民税が引かれるか」について解説します。
厚生年金の場合
会社員や公務員など、厚生年金の加入期間がある人には老齢厚生年金が支払われます。老齢厚生年金は課税されるため、老齢基礎年金と合わせて一定額以上になると住民税を支払う必要があります。
国民年金の場合
国民年金から高齢者に支払われる年金を老齢基礎年金といいます。一定の保険料納付済期間に、65歳以上の高齢者に支払われる年金です。老齢基礎年金も課税されるため、老齢厚生年金と合わせて一定額以上になると住民税がかかります。
遺族年金・障害年金の場合
遺族年金は生計維持者を失った一定の遺族を対象に支払われる年金で、国民年金から支払われる遺族基礎年金と、厚生年金から支払われる遺族厚生年金があります。
障害年金は一定の障害を持つ者に対して支払われる年金で、国民年金から支払われる障害基礎年金と、厚生年金から支払われる障害厚生年金があります。
遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)と障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金)に住民税はかかりません。金額に関係なく、非課税とされています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
年金から住民税が引かれる条件
年金から住民税が引かれることを、特別徴収といいます。以下の条件に該当する場合、年金から住民税が特別徴収されます。
- その年の4月1日時点で65歳以上であること
- 年金額が18万円以上であること
ただし以下の場合、特別徴収は行われません。
- その年の1月2日以降、他の市町村に転出した場合
- 年度の途中で介護保険料額や税額に変更があった場合
- その年の4月1日時点で年金の支払いを受けていなかった場合
- 特別徴収額が年金支給額を超える場合
年金から住民税を支払う方法
2009年10月支給分から、年金から住民税が引かれる特別徴収が行われるようになりました。年金受給者の納税の手間を省くとともに、市町村における事務の効率化を図るために導入された制度です。住民税の支払方法や注意点を解説します。
特別徴収で支払う
住民税の支払方法には年金からの特別徴収の他に、市役所や金融機関などで納付書によって納める普通徴収があります。しかし、年金からの住民税の特別徴収は地方税法第321条7の2に基づく制度で、個人が徴収方法を選択することはできません。条件に該当する場合、住民税は年金から特別徴収されます。
普通徴収の支払いで二重課税にならない?
年金から特別徴収される住民税は、支払われる年金にかかる分のみです。他に所得がある場合はその所得から引かれたり、普通徴収で納めたりする必要があります。普通徴収が行われる場合でも、年金からの特別徴収による二重課税にはなりません。
年金からの控除額一覧
年金に対してかかる税金は、受取年金額から公的年金等控除額を差し引いて計算されます。公的年金等控除額は年齢と年金額、年金以外の所得金額によって決まります。
・年金以外の所得がないか、1,000万円以下の場合
| 年齢 | 年金額 | 公的年金等控除額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 |
| 130万円超410万円以下 | 年金額×25%+27.5万円 | |
| 410万円超770万円以下 | 年金額×15%+68.5万円 | |
| 770万円超1,000万円以下 | 年金額×5%+145.5万円 | |
| 1,000万円超 | 195.5万円 | |
| 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
| 330万円超410万円以下 | 年金額×25%+27.5万円 | |
| 410万円超770万円以下 | 年金額×15%+68.5万円 | |
| 770万円超1,000万円以下 | 年金額×5%+145.5万円 | |
| 1,000万円超 | 195.5万円 |
・年金以外の所得が1000万円超2,000万円以下の場合
| 年齢 | 年金額 | 公的年金等控除額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円以下 | 50万円 |
| 130万円超410万円以下 | 年金額×25%+17.5万円 | |
| 410万円超770万円以下 | 年金額×15%+58.5万円 | |
| 770万円超1,000万円以下 | 年金額×5%+135.5万円 | |
| 1,000万円超 | 185.5万円 | |
| 65歳以上 | 330万円以下 | 100万円 |
| 330万円超410万円以下 | 年金額×25%+17.5万円 | |
| 410万円超770万円以下 | 年金額×15%+58.5万円 | |
| 770万円超1,000万円以下 | 年金額×5%+135.5万円 | |
| 1,000万円超 | 185.5万円 |
・年金以外の所得が2,000万円超の場合
| 年齢 | 年金額 | 公的年金等控除額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円以下 | 40万円 |
| 130万円超410万円以下 | 年金額×25%+7.5万円 | |
| 410万円超770万円以下 | 年金額×15%+48.5万円 | |
| 770万円超1,000万円以下 | 年金額×5%+125.5万円 | |
| 1,000万円超 | 175.5万円 | |
| 65歳以上 | 330万円以下 | 90万円 |
| 330万円超410万円以下 | 年金額×25%+7.5万円 | |
| 410万円超770万円以下 | 年金額×15%+48.5万円 | |
| 770万円超1,000万円以下 | 年金額×5%+125.5万円 | |
| 1,000万円超 | 175.5万円 |
2009年10月に始まった住民税の特別徴収を正しく理解しよう
2009年10月に、年金から住民税が引かれる特別徴収制度が導入されました。その年の4月1日時点で65歳以上、18万円以上の老齢年金受給者が対象です。条件に該当する場合に特別徴収が行われ、普通徴収を選択することはできません。
老齢年金にかかる税金は、受け取る年金額から公的年金等控除額を差し引いた金額をもとに計算されます。年金や税金に対する理解を深めるために、住民税の特別徴収の仕組みや税額の計算方法の知識を身につけましょう。
よくある質問
年金から住民税は引かれますか?
老齢年金からは住民税が引かれますが、遺族年金や障害年金からは引かれません。詳しくはこちらをご覧ください。
年金から住民税はどのようにして支払われますか?
基本的に、年金から天引きされて支払われます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
失業手当の受給条件は?対象期間や申請手続きを解説!
雇用保険は、受給資格を満たした方が退職した場合一定期間失業手当を受給できる制度です。いつからもらえるかは退職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。もらうには毎月認定を受ける…
詳しくみるパートが社会保険に加入したくないときの働き方は?年収の壁についても解説
パートタイムで働く方が、配偶者の扶養を維持したまま、ご自身の社会保険への加入を避けたいと考えるケースは少なくありません。ただし、2024年10月以降、社会保険の適用範囲は段階的に拡…
詳しくみる労働保険確定保険料申告書とは?書き方や記入例、事業廃止の場合を解説
労働保険の確定保険料申告書は、労働保険料の計算や納付時には欠かせません。本記事では労働保険の確定保険料申告書について、書き方や記入例、事業廃止の場合の手続きなどをわかりやすく解説し…
詳しくみる源泉徴収の計算方法と対象となる所得
わたしたちが払っている税金は、1年間の総収入から基礎控除や社会保険料などを差し引きした後、その残額に税率を掛けることにより計算されます。 一般的なサラリーマンの場合、勤め先の会社側…
詳しくみる配偶者や親族の扶養に入るためには?手続きや条件を解説!
夫婦で働いている人は、それぞれが社会保険に加入して働くか、それとも、夫か妻の扶養に入って働くかの選択によって、それぞれの働き方が違ってきます。被保険者の扶養に入ることで、保険料が免…
詳しくみる週20時間で社会保険加入になる?条件やシミュレーション、手順など解説
「パートのシフトを週20時間以内に抑えるべきか?」「社会保険料はいくらか?」 2024年10月の法改正で51人以上の企業まで適用が拡大され、2025年以降は全企業への導入も議論され…
詳しくみる