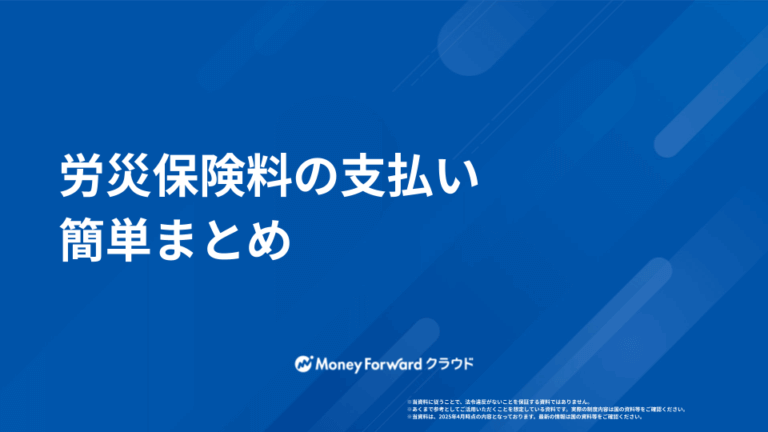- 更新日 : 2025年9月9日
【社労士監修】労災保険料の支払い手続きや計算方法についてわかりやすく解説
労災保険は、労働者保護を目的とした強制保険で、労働者が1人でもいる事業は労災保険に加入しなければなりません。保険給付の対象となるのは労働者で、労災保険料は全額を事業主側が負担します。労災保険料は賃金の総額に労災保険料率をかけて計算され、概算で支払ったものを翌年に精算する形で納付します。この手続きを年度更新といいます。
労災保険とは
労災保険とは、労働者が業務中にケガを負った場合などを対象にした給付を行う保険制度です。正式名称を「労働者災害補償保険」といい、労働者災害補償保険法に基づく制度です。労災に遭った場合、業務によって疾患を発症した場合、そして通勤中に事故に遭った場合などに、療養の給付や年金・一時金の支給を行います。具体的には、療養(補償)給付や傷病(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付などの給付を行います。
労災保険について詳しくは、こちらの記事で説明しています。
労災保険の負担は誰がするか
労災保険の加入で必要となる労災保険料は、事業主が負担しなければなりません。労災保険料と同じ労働保険料である雇用保険料、社会保険料である健康保険料や厚生年金保険料が事業主と労働者の折半で負担するのに対し、労災保険料は労働者との折半とはならず、全額を事業主が負担します。本来、事業主は労働基準法の第8章「災害補償」の規定に基づき、労働者が業務上、負傷などをした場合、無過失の補償責任があるからです。事業主に労災保険を強制的に加入させることで迅速・確実な被災労働者への補償を可能にする仕組みになっています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労災対応がよくわかるガイド
前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。
一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
年度更新の手続きガイドブック
年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。
本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
労災保険料の申告・支払い
労災保険料は多くの事業では、雇用保険料と一緒に労働保険料として申告・支払の手続きを行います。労働保険料はあらかじめ概算で申告・支払をしておき、年度が終了してから確定・精算を行う方法で手続きします。
年度終了後の確定・精算を行う際は、同時に新しい年度の概算での申告・支払を行い、この手続きを「年度更新」といいます。毎年6月1日から7月10日まで(6月1日や7月10日が土曜日・日曜日にあたる場合は翌日や翌々日の月曜日)の期間に年度更新を行い、労災保険料の申告・納付をしなければなりません。
差額の納付
労働保険料の年度更新で必要になるのは、前年度に概算で申告・支払を行った手続きに対する差額の納付です。同時に新年度の概算での申告・支払も必要になります。
また事業拡大により年度の途中で労働者が増え、賃金総額が大幅に増加した場合には、年度途中でも増加分の概算保険料の申告・納付が必要になります。以下の条件に2つとも該当する場合は、増加概算保険料の申告・納付を行わなければなりません。
- 賃金総額の見込み金額が当初の予定の2倍を超えて増加したこと
- 増加した賃金総額による概算保険料の金額が申告済の保険料より13万円以上増加すること
延納・分割納付
延納・分割納付は、労働保険料が一定額以上の場合に認められる制度です。次の条件のいずれかを満たす場合に、原則として労働保険料を3回に分けて支払うことができます。
- 概算保険料が40万円以上であること(労災保険料のみの場合は20万円以上であること)
- 労働保険事務を労働保険事務組合に委託していること
| 第1期の納付期限 | 第2期の納付期限 | 第3期の納付期限 | |
|---|---|---|---|
| 原則 | 7月10日 | 10月31日 (労働保険事務組合による場合は11月14日) | 翌年1月31日 (労働保険事務組合による場合は翌年2月14日) |
| 4月1日から5月31日までの間に保険関係が成立した場合 | 保険関係成立の日の翌日から50日以内 | 10月31日 (労働保険事務組合による場合は11月14日) | 翌年1月31日 (労働保険事務組合による場合は翌年2月14日) |
| 6月1日から9月30日までの間に保険関係が成立した場合 | 保険関係成立の日の翌日から50日以内 | 10月31日 (労働保険事務組合による場合は11月14日) | 翌年1月31日 (労働保険事務組合による場合は翌年2月14日) |
労働保険関係が、9月30日までに成立していない場合、延納・分割納付はできません。
労災保険の加入条件と加入対象
労災保険には、事業単位で加入します。労働者が1人でもいれば、強制的に加入しなければなりません。労災保険の対象となるのは労働者で、事業主は対象外です。労働者は正社員・パート・アルバイトといった身分に関係なく、全員が労災保険の対象になります。
労災保険料の計算方法
労災保険料は次の計算式で計算します。
賃金の総額とは労働者に労働の報酬として支払う、全ての賃金の合計額です。賃金・給料・給与・手当・賞与など、名称にかかわらず、労働者に支払うもの全てが賃金の総額には含まれます。
基本的には就業規則や賃金規則に支払うことが定められているものは全て、賃金の総額として労災保険料計算の算定基礎になります。ただし退職金や慶弔見舞金などは、賃金の総額には含まれません。労災保険料率は、労災保険率表の該当する業種の率を用います。

計算は以下のように行います。
- 賃金の総額が1億2千万円の建設業の場合
1億2千万円×15/1000=180万円
- 賃金の総額が1億2千万円の建設業の場合
- 賃金の総額が1億円の食料品製造業の場合
1億円×6/1000=60万円
- 賃金の総額が1億円の食料品製造業の場合
- 賃金総額が8千万円の印刷業の場合
8千万円×3.5/1000=28万円
- 賃金総額が8千万円の印刷業の場合
- 賃金の総額が3千万円の小売業の場合
3千万円×3/1000=9万円
労災保険料の申告・納付の手続きは経営者として確実に行おう
労災保険は、万が一の労災事故発生への備えとなる、大切な制度です。労働者保護のために設けられた公的保険制度で、従業員が1人でもいる事業は必ず労災保険に加入しなければなりません。労災保険の加入対象となるのは労働者に限られ、事業主は対象外です。
労災保険料は、賃金の総額に労災保険料をかけて求められます。労災保険料は事業の危険度によって、業種ごとに率が設定されています。労災保険料は一元適用事業の場合は雇用保険と一緒に、概算で申告・納付します。年度更新によって精算し、毎年この手続きを繰り返します。
年度更新は、毎年この手続きから7月10日までと期限が決まっているので、しっかりと準備しておきましょう。
よくある質問
労災保険料は誰が支払いますか?
労災保険料は全額を事業主が負担し、従業員に負担義務はありません。詳しくはこちらをご覧ください。
労災保険料はどのように計算されますか?
賃金の総額に労災保険料をかけて求めます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労災保険の特別加入制度とは?対象者や申請についても解説
労災保険制度は、労働によるケガ・病気などから労働者の生活を守るためのものです。 しかし、労災保険は基本的に日本国内で雇用されている労働者のみが対象となるため、労働災害が発生しても労…
詳しくみる労災で医療費が10割負担?払えないときの対応や返金手続きを解説
労災(労働災害)によるけがや病気で病院を受診したにもかかわらず、医療費を全額(10割)請求されることがあります。受診した医療機関が労災指定病院でない医療機関を受診した場合や、必要書…
詳しくみる求職者支援制度とは? 給付金の条件や職業訓練の内容、手続きを解説
求職者支援制度とは、再就職や転職などに役立つ知識やスキルを身につけるため、給付金をもらいながら職業訓練を受講できる国の支援制度です。失業保険を受けられない人が対象者に該当します。 …
詳しくみる引越し時のマイナ保険証の住所変更はどうする?手続きの流れや必要書類を解説
マイナ保険証とは、「マイナンバーカードの健康保険証利用」の略称です。マイナンバーカードを事前に登録することで、健康保険証として病院受付で利用できます。 政府はマイナ保険証への移行を…
詳しくみる厚生年金の44年特例とは?特例の対象者にメリット・デメリットはある?
会社員が加入する厚生年金保険には、44年特例という優遇措置があります。 年金制度自体が非常に複雑であるため、44年特例もあまり知られていないのが実情です。 本稿では、44年特例の優…
詳しくみる厚生年金における32等級とは?改定や保険料を解説
厚生年金保険料は毎月の給与によって納める金額が異なり、わかりやすいように等級で区分されています。2020年9月1日より、厚生年金保険の等級の上限が「第32等級」に引き上げられました…
詳しくみる