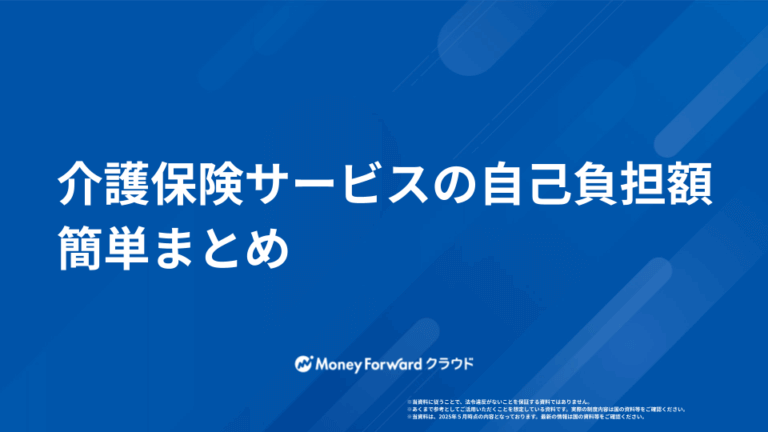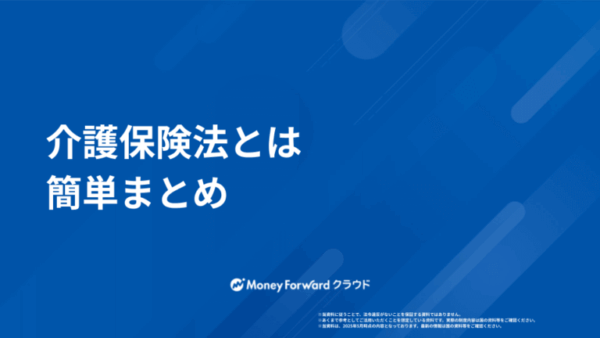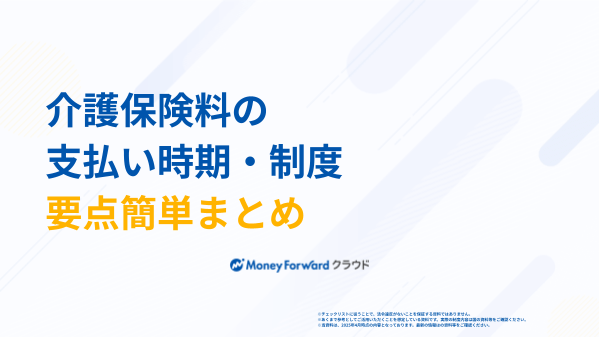- 更新日 : 2025年7月3日
介護保険サービスの自己負担額は?負担割合や計算方法も解説
介護保険サービスを利用することになった際に、気になる点の一つとして「いくらかかるのか?」ということがあります。サービスを安心して受けられるようにするためにも、かかる費用についての目安を知っておくことが必要でしょう。
今回は、介護保険サービス提供を受けるにあたっての自己負担割合や自己負担額について見ていきます。
目次
介護保険の自己負担額は?

引用:利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレットの送付について|厚生労働省
介護保険サービスを利用する場合、利用金額の一部は介護保険でカバーしてもらえます。そのため、利用者はサービス利用料の全額を負担する必要はありませんが、利用料の一部は負担することになります。
現在は、所得金額等によって上記のような利用者の自己負担割合になっていますが、いつから変更になっているのでしょうか?
自己負担割合は基本は1割
介護保険の介護サービスを利用するとき、利用者には一部の自己負担額が発生します。この自己負担の割合は1割・2割・3割の間で変わりますが、通常は1割負担でサービスの利用ができます。
例えば、自己負担の割合が1割負担の利用者は、毎月2万円の介護保険サービスを利用しても、自分が支払う金額は2,000円になります。
収入などの条件によって、2~3割の場合もある
自己負担の割合は、本人や世帯の所得などに応じて変わります。法改正もあり、平成27年から一定以上の所得者は2割負担に、平成30年からは現役並みの所得者は3割負担に変更になっています。
基本的に、所得が高くなっていくほど自己負担の割合は大きくなっていきます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐
妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。
仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
介護保険法とは かんたん解説ガイド
介護保険法の概要や仕組みについて、わかりやすく解説したガイド資料です。
制度への理解を深めるための学習用資料や、社内研修の参考情報としてご活用ください。
介護保険料の支払い時期・制度 要点簡単まとめ
介護保険料の支払い時期や制度の仕組みについて、要点を簡潔にまとめた資料です。
実務における確認用や、制度理解を深めるための参考資料としてご活用ください。
自己負担割合の決定要因
介護保険サービスの利用に関する自己負担割合は「本人の合計所得金額」と「65歳以上の人の世帯の人数」で決まります。
「本人の合計所得金額」と「65歳以上の人の世帯の人数」から、1割・2割・3割のどの自己負担割合が決定されるのかは、前段落の「利用者負担の判定の流れ」を参照してご確認ください。
自己負担額の計算方法
介護保険料の計算方法については、下記の記事を参考にしてください。
自己負担額の計算方法についてですが、介護保険サービスには多くの種類があり、一般的にはそれを組み合わせて利用します。
利用する介護保険サービスの種類によって利用金額が変わり、所得によって決まる利用者の自己負担割合もさまざまです。
実際に介護保険サービスを利用することになった際に、お住まいの市区町村の市(区)役所や役場、地域包括支援センターなどに相談し、支給限度額や軽減制度などの説明も受けながら負担の少ない方法を検討していきましょう。
介護保険には支給限度額がある
介護保険には要介護度の区分別に、1か月に介護保険サービスを利用できる支給限度基準額である上限額が決められています。この上限額を超える部分は全額自己負担となります。
介護保険サービスの支給限度基準額については、下記の記事で確認してください。
介護保険が使えるサービスの種類と自己負担割合
介護保険が使えるサービスには、在宅介護サービス、施設入居サービス、地域密着型サービスなどがあります。
それぞれの介護サービスでかかる自己負担割合が1割・2割・3割のどれにあたるかは、介護サービス利用者が所持している「介護保険負担割合証」を確認するか、前述の「利用者負担の判定の流れ」を参照して確認してください。
在宅介護サービス
在宅介護サービスには、自宅で利用できる介護サービスや施設に通って受けることができる介護サービスがあります。
- 訪問型サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護 など
- 通所型サービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア) など
施設入居サービス
施設入居サービスは、特別養護老人ホームなど、施設に入居して利用する介護サービスです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老健) など
地域密着型サービス
地域密着型介護サービスは、高齢者が施設の立地場所と同じ地域に住んでいる人が利用できる介護サービスです。
- 訪問・通所型サービス
- 小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護 など
- 認知症対応型サービス
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) など
- 施設・特定施設型サービス
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 など
自己負担額を正しく把握して、適切に介護保険サービスを利用しましょう!
今回は、介護保険サービスの利用を受ける際の自己負担額やその計算方法、サービスの種類などについて見てきました。
要介護度の区分に応じた介護保険サービスの支給限度基準額を正確に把握して、利用する介護保険サービスを適切に選択して利用していきましょう。
よくある質問
介護保険の自己負担額はいくらですか?
介護保険の自己負担額は、年金収入+その他の合計所得金額による「合計所得金額」に応じた自己負担割合によって変わります。自己負担割合は原則1割ですが、所得によって2割負担、3割負担になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
自己負担額の計算方法について教えてください。
1か月に利用した介護保険サービスの利用額に対して、要介護度に応じた支給限度基準額までは自己負担割合で計算し、限度額を超えた部分や介護サービスの範囲外のサービス利用分は全額自己負担となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
個人事業主は厚生年金に加入できる?
個人事業主は国民年金に加入するのが一般的です。一方、会社員や公務員などは所属している会社や組織で厚生年金保険に加入します。国民年金よりも手厚い保障を受けられるので、厚生年金保険に加…
詳しくみる【記入例付き】通勤災害用の様式第16号の5(1)の書き方は?提出方法まで解説
通勤中の事故で怪我を負った場合、治療費や薬代などを立て替えることになり、経済的な不安が生じることがあります。こうした費用を労災保険に請求する際に必要となるのが「様式第16号の5(1…
詳しくみる退職手続きでミスする原因は?よくあるケースや対策を解説
退職手続きのミスによるトラブルを防ぐために、よくあるミスや現場で発生しがちなトラブル、注意すべきポイントなどをわかりやすく解説。法的観点からの留意点、再発防止に役立つ体制づくりまで…
詳しくみる雇用保険被保険者離職証明書の離職理由|自己都合・会社都合の書き方やコードを解説
雇用保険被保険者離職証明書および離職票に記載される離職理由は、退職後の失業保険(基本手当)の受給内容を左右する重要な項目です。離職理由の書き方や、ハローワークが判断する離職区分コー…
詳しくみるアルバイトをする学生は社会保険に加入するべき?条件を解説
事業者に雇用されて働いている人は社会保険に加入していますが、同じように雇用されていても学生のアルバイトはあまり加入していません。アルバイトとして働く学生は基本的に社会保険への加入義…
詳しくみる社会保険の出産手当金とは – 条件や期間も解説!
出産手当金とは、被保険者が出産により休職し給与の支払いを受けられない場合、休職期間の生活保障のために、社会保険の一つである健康保険から支給される手当のことです。今回は出産手当金の概…
詳しくみる