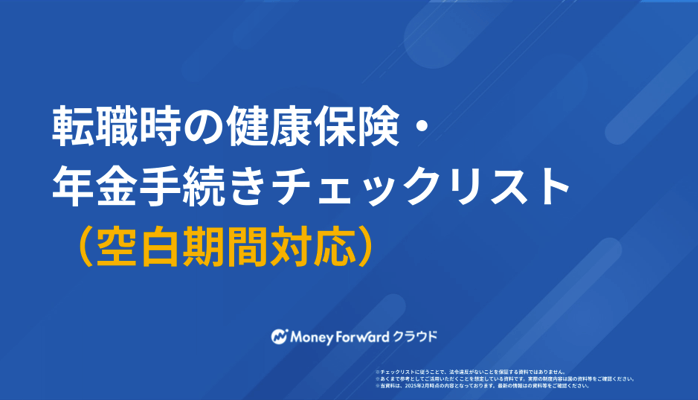- 更新日 : 2025年12月15日
転職・退職で健康保険の切り替えに空白ができたら?14日過ぎた場合も解説
退職してから転職まで期間が空く場合、任意継続や家族の扶養に入ることを選択しない場合は、一度国民健康保険に切り替える必要があります。国民健康保険加入の手続きは、退職日の翌日から14日以内に行うことが原則です。14日を過ぎても行えますが、退職日翌日までさかのぼって保険料を徴収されます。
手続きを遅らせると医療費が全額自己負担になるなどのリスクがあるので注意しましょう。
今回は、転職、退職時の空白期間における健康保険や年金の切り替え手続き、注意点について、解説します。
目次
転職で空白期間ができる場合の健康保険の手続きは?
就職して健康保険に加入していた場合、退職することでその被保険者資格を失います。
新しい会社で働き始めるまでの期間における選択肢としては、以下の3つがあげられます。
- ケース1. 国民健康保険に加入する
- ケース2. 任意継続を選択する
- ケース3. 家族の扶養に入る
日本はすべての国民が何らかの公的医療保険に加入する、「国民皆保険」制度が導入されているため、必ずいずれかの手続きが必要です。 まずは、退職時の健康保険証やマイナ保険証の取り扱いや注意点から見ていきましょう。
前提として退職時に健康保険証・マイナ保険の機能は停止する
2024年12月以降、従来の健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への一本化が進みました。経過措置として使えていた従来の健康保険証(プラスチックや紙のもの)も、2025年12月1日をもって有効期限切れとなり、12月2日以降は使用できなくなります。
これに伴い、退職時のルールも以前とは変わっています。
■ 従来の保険証は「会社へ返却」が基本
退職時には、手元にある従来の健康保険証は会社へ返却するのが原則ですが、2025年12月2日以降はカード自体が無効となるため、自分で廃棄する必要があります。
自分で処分する場合は、個人情報保護のため、裁断機を使うか、ハサミで細かく切ってから破棄してください。
■ マイナンバーカード自体は会社へ返却しない
マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合でも、マイナンバーカード自体を会社へ返却する必要はありません。マイナンバーカードは身分証明書や行政手続き用として引き続きご自身で使用・保管するものです。
■ 「資格確認書」を持っている場合
マイナンバーカードを発行しておらず、従来の保険証の代わりに「資格確認書」で受診していた場合は、その資格確認書を退職日までに会社へ返却する必要があります。資格確認書の有効期限が過ぎた後に退職した場合は、返却は不要です。この場合は、ご自身で廃棄してください。
■ 退職日の翌日から保険証機能は「無効」になる
カードは手元に残りますが、退職日の翌日(資格喪失日)以降、そのマイナンバーカードに紐付いていた「会社の健康保険の資格情報」は自動的に無効(資格喪失)となります。 カード自体は有効でも、医療機関のカードリーダーに通すと「資格なし」等のエラーが出て使用できません。
■ 資格喪失後に使ってしまった場合のリスク
万が一、データの反映ラグなどがあって医療機関で使えてしまった場合でも、後日、健康保険組合や協会けんぽから医療費(本来の負担割以外の7〜8割分)の返還請求を受けます。 返還請求を受けた場合、一時的に医療費を全額自己負担で立替えたり、新しい保険者へ療養費の申請を行ったりと、非常に煩雑な手続きが発生します。
また、無効と知りながら使用した場合は詐欺罪に問われる可能性もあるため、新しい保険への切り替えが完了するまでは絶対に使用しないよう注意してください。
ケース1. 国民健康保険に加入する
任意継続への加入を選択しない場合や、家族への扶養に入らない場合には、国民健康保険に切り替えて加入しなければなりません。国民健康保険への加入の手続きは、退職日の翌日から14日以内に、居住地を管轄する役所の窓口(郵送・オンライン対応)で手続きを行う必要があります。
手続きが完了すれば、データが更新され、お持ちのマイナンバーカードをそのまま「国民健康保険証」として利用できるようになります(※マイナ保険証を利用しない方には「資格確認書」が交付されます)。
国民健康保険とは、地方自治体が運営する、自営業者や無職の方など健康保険に加入していない方が加入する保険のことです。国民健康保険には扶養の概念がないため、たとえば自営業を営む夫婦は、夫も妻も国民年金の保険料を支払う必要があります。
国民健康保険への加入手続きは14日を過ぎても行えますが、退職日の翌日までさかのぼって保険料を支払う必要があることを覚えておきましょう。
手続きの際、加入していた健康保険の資格喪失日がわかる書類や、本人確認書類(マイナンバーカード)などが必要です。それ以外に退職証明書や離職票などの提示が求められることがあるため、事前に役所の担当窓口に問い合わせをしておくと安心です。
データ反映前に通院の予定がある場合
国民健康保険の手続きをしても、マイナ保険証として医療機関で使えるようになるまで数日〜程度のタイムラグが発生する場合があります。直近で医療機関にかかる予定があるときは、窓口でその旨を伝えましょう。加入者情報を証明する「資格情報」などを発行してもらえる場合があります。
転職先で新しい保険証が発行されたら
転職先で社会保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。マイナ保険証のデータ上は新しい保険が有効になりますが、国民健康保険料の「徴収」を止めるための脱退手続きは自動では行われないため、忘れずに役所へ届け出てください。
ケース2. 任意継続を選択する
転職によって空白期間が発生する場合、それまでの健康保険の任意継続を選択するという選択肢もあります。任意保険で継続できるのは、最長2年間です。任意継続のためには以下の2つの要件を満たしている必要があります。
- 資格喪失の前日まで継続して2ヶ月以上、被保険者であった
- 退職日の翌日から20日以内に手続きを行う
会社員として加入していた健康保険の保険料は基本的に会社と個人で折半していたのに対し、任意継続ではすべて自分で負担しなければなりません。それでも、所得によっては国民健康保険よりも安いケースがあるでしょう。
また原則、任意継続の途中で国民健康保険に切り替えたり、家族の扶養に入ったりすることはできない点もおさえておきましょう。
ケース3. 家族の扶養に入る
転職先での勤務まで期間が空いてしまう場合、条件をクリアしていれば、親や配偶者が加入している健康保険に被扶養者として加入することもできます。
健康保険によって「年収130万円以下、かつ被保険者の年収の2分の1以下」など条件が決められているため、自分が条件を満たすかどうかを確認する必要があります。
失業給付を受給している期間は収入があるとみなされ、被扶養者に切り替えできない場合があるため、事前に確認することが大切です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
入社や退職に伴う社会保険の手続きは多岐にわたり、ミスが許されません。特に厚生年金や健康保険は従業員の将来の給付や医療に直結するため、正確な処理が求められます。
手続きの不備でトラブルになる前に、本資料で社会保険・労働保険の正しい手順や必要書類を確認しておきませんか?
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険加入条件 簡単図解 ミニブック
パートやアルバイトの社会保険加入条件を、最新の法令に基づいて正しく判断できていますか?要件の確認漏れは、未加入によるトラブルや遡及徴収のリスクにつながりかねません。
本資料では、複雑な加入条件を視覚的にわかりやすく図解しています。自社の現状チェックや従業員への説明にご活用ください。
転職で空白期間が1日だけでも健康保険の加入は必要?
「次の入社まで数日しかないから、手続きしなくても良いのでは?」と考えるかもしれませんが、たとえ1日であっても健康保険の加入手続きは必要です。
健康保険の加入手続きは、変更があった日から14日以内に役所に届け出る事務的な締切のことですので、「14日間は保険に入らなくていい期間」ではありません。
法律上、退職日の翌日から次の入社日の前日までは、自動的に「国民健康保険」などの被保険者期間となります。空白が1日だけであっても、その1日は「国民健康保険に加入している状態」でなければなりません。
健康保険料は「月末時点」の加入先で決まる
健康保険料は日割り計算されず、原則として「月末時点で加入している保険」に対して1ヶ月分が発生します。
同月内に退職と再就職が完了する場合
3月10日退職、3月25日再就職の場合、3月31日の月末時点では新しい会社の保険に加入しているため、国民健康保険料は発生しないケースが一般的です。
月をまたいで空白期間がある場合
3月20日退職、4月5日再就職の場合、3月31日の月末時点では国保に加入しているため、3月分の国民健康保険料の支払いが必要です。
保険証がないと一時的にでも10割負担になる
健康保険に加入していない大きなリスクは、その数日間の空白期間に予期せぬ病気やケガをした場合です。手続きをしていない間に病院に行くと、手元に有効な保険証がないため、医療費はその場で全額(10割)自己負担となります。
後から手続きをすれば、本来の自己負担分(3割など)を除いた7割分は返金されます(療養費支給申請)。しかし、返金を受けるためには、結局「国民健康保険への加入手続き」を行い、その期間の保険料を支払う必要があります。
転職で健康保険の手続きが14日を過ぎた場合はどうなる?
引越しや書類の遅れなどで、国民健康保険の加入手続きが「14日以内」を過ぎてしまうこともあるでしょう。期限を過ぎた場合でも手続き自体は可能です。保険料は退職翌日までさかのぼって請求されます。
保険料は退職翌日までさかのぼって請求される
手続きが遅れたからといって、保険料の支払いが免除されるわけではありません。 国民健康保険の資格取得日は「届出をした日」ではなく、「退職日の翌日(資格喪失日)」となります。そのため、手続きをした時点で、未加入期間だった過去の分までさかのぼって保険料をまとめて請求されます(最大2年度分)。
医療費がいったん全額自己負担になる
手続きが完了するまでの間に病院にかかった場合、マイナ保険証は無効となっているため、窓口での支払いは10割負担となります。 後日、加入手続きを済ませてから「療養費支給申請」を行えば、自己負担分(3割など)を除いた差額が払い戻されますが、申請の手間と一時的な金銭負担がかかります。
また、やむを得ない理由がなく届出が遅れた場合、給付が制限されるケースもあるため注意が必要です。
離職票が届かなくて14日を過ぎそうなときは?
「会社から離職票や資格喪失証明書が届かない」ために手続きに行けないというケースはよくあります。 この場合、14日を待たずに、まずは居住地の市区町村役場の窓口へ相談に行きましょう。
身分証明書(マイナンバーカード等)や年金手帳があれば、役所から会社へ資格喪失日の照会を行ってくれたり、仮の手続きを進めてくれたりする場合があります。書類が揃ってから行くのではなく、事情を伝えに行くことが大切です。
転職で空白期間ができる場合の年金の手続きは?
転職で空白期間ができる場合、年金の手続きも必要です。会社員時代は「厚生年金」に加入していましたが、退職して次の会社に入社するまでの間は、国民年金(第1号被保険者)への種別変更手続きが必要です(20歳以上60歳未満の方)。
国民年金の切り替え手続きも、退職日の翌日から14日以内に市区町村役場で行います。健康保険の手続きと同じ窓口や隣接する窓口で扱っていることが多いため、マイナンバーカードや年金手帳(基礎年金番号通知書)を持参し、まとめて手続きを済ませると効率的です。
14日を過ぎてしまったとしても手続きは可能です。手続きを忘れてしまった場合、退職後しばらくすると自宅に「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」が届くため、期限内に支払うようにしましょう。
国民年金の保険料未払いに注意する
厚生年金は保険料を会社と本人が折半し、本人負担分も給料天引きをして会社が負担してくれますが、国民年金は自分で保険料を支払います。未払いがあると老後に受け取る年金額に影響があるだけでなく、重い障害を負ったときに支給される障害年金や、遺族に支給される遺族年金が受け取れなくなる可能性があります。
経済的に苦しい場合は「免除・猶予」を申請する
経済的な事情で年金の保険料を支払えないという方に対しては、納付の「猶予」や「免除」といった制度があるため、役所の年金窓口で相談してみましょう。退職(失業)を理由とする特例免除などの制度があります。
免除や猶予が承認された期間は、将来の年金受給資格期間としてカウントされ、万が一の事故などで障害を負った際の「障害年金」の対象にもなります。未納のままにするとこれらの権利を失う可能性があるため、まずは相談しましょう。
転職中の保険料は年末調整や確定申告で控除できる?
転職活動中の空白期間に、ご自身で支払った「国民健康保険料」や「国民年金保険料」、あるいは「任意継続の保険料」は、全額が「社会保険料控除」の対象になります。税金の負担を軽減できるため、忘れずに申告しましょう。
再就職先での年末調整で申告する
年内に新しい会社へ入社した場合は、年末調整で申告できます。 「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に、支払った保険料の合計額と名称(国民健康保険、国民年金など)を記入します。
必要な証明書について
- 国民年金:日本年金機構から送られてくる「控除証明書」の添付が必須です。
- 国民健康保険:原則として証明書の添付は不要ですが、支払った金額を正確に記入する必要があります。領収書や、役所から送られる納付額のお知らせを保管しておきましょう。
年末調整に間に合わなかった場合や申告を忘れた場合は、翌年にご自身で確定申告を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けられます。
転職による空白期間も健康保険への加入を忘れずに
転職による空白期間が生じる場合、次の会社に入社することが決まっていたとしても、国民健康保険に切り替える、家族の扶養に入るなど何らかの手続きが必要です。
国民健康保険には14日以内に加入の手続きを行うことになっています。14日を過ぎても加入手続きはできますが、さかのぼって保険料を支払わなければならないため、早めに手続きをしましょう。
よくある質問
転職で空白期間ができる場合の健康保険の手続きは?
退職後の空白期間が15日以上になるケースで、任意継続や家族の扶養に入ることを選択しない場合は、一度国民健康保険に切り替える必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
転職で空白期間ができる場合の年金の手続きは?
次の会社の入社日が退職日の翌月以降になるケースでは、一時的に国民年金に切り替えなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労災保険の時効は2年?5年?申請期限と延長ができるケースを解説
労災保険の申請には期限があります。申請が遅れると、受け取れるはずの給付金が受け取れなくなることもあります。この記事では、労災保険の時効について、具体的な期限や起算日の数え方、時…
詳しくみる社会保険料計算にマクロ作成は有効?手順と注意点を解説
社会保険料の計算は、エクセル(Excel)のマクロ機能を利用することで、迅速な計算や自動化も可能です。そのため、毎月の給与計算における標準報酬月額の算定から保険料の算出まで、一連の…
詳しくみる社会保険の扶養とは?年収の壁についても解説
配偶者の収入で生活している専業主婦などは、自分では社会保険に加入しなくてもよい場合があります。社会保険被保険者である配偶者の扶養に入ることで、自分自身は社会保険料を納付しなくても健…
詳しくみる介護保険サービスの自己負担額は?負担割合や計算方法も解説
介護保険サービスを利用することになった際に、気になる点の一つとして「いくらかかるのか?」ということがあります。サービスを安心して受けられるようにするためにも、かかる費用についての目…
詳しくみる労働保険の年度更新とは?時期や電子申請・申告書の作成方法、効率化を解説
労災保険や雇用保険の年度更新は、電子申請の導入により、効率的な申告が可能となっています。これにより、平日の日中に労働局や労働基準監督署に出向く必要がなく、休日や夜間でも自宅から申告…
詳しくみる高年齢雇用継続給付とは?制度の変更点と計算方法を紹介
従業員が60歳で定年を迎えても、企業は65歳まで継続して雇用する義務があります。企業は非正規雇用に切り替え、給与を減額するのが一般的です。これを補填するのが雇用保険から支給される …
詳しくみる