- 更新日 : 2025年11月21日
時短勤務における給与計算のやり方は?給与は減るの?
働き方改革が叫ばれるなか、法律も整備され、多くの企業で働き方の多様化が進められています。時短勤務もそのひとつです。育児時短勤務、介護時短勤務は育児・介護休業法で義務づけられましたが、それ以外の事由でもワークライフバランスの観点から時短勤務を導入する企業の割合が増えています。
その一方、労務の提供がなければ、使用者は賃金の支払い義務はありません。基本給、手当、ボーナス等、給与計算はどうなるのでしょうか。今回は、時短勤務に関わる種々の疑問に答えてします。
目次
時短勤務すると給与はいくら減額される?
一般的に時短勤務にすると、給与はどの程度、減額されるのか、ざっくりとシミュレーションしてみます。次のような事例を想定します。
従業員Bさん:
・8時間労働のときの給与
基本給:200,000円+時間外手当
・6時間労働の時短勤務を選択
Aさんの労働時間は、8時間から6時間に減少しました。割合としては25%減となっています。基本給も25%減、つまり、15万円になります。5万円減ったことになり、さらに時短勤務前は時間外労働による手当がありましたが、こちらもなくなることになります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント
給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。
この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。
給与規程(ワード)
こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
時短勤務における給与計算の方法
時短勤務とした場合に、給与がどの程度の減額となるかはイメージしていただけたのではないでしょうか。実際の給与は、基本給のほかにも諸手当やボーナスもあります。それぞれについて、計算式を示して説明してきます。
時短勤務について一般的な給与計算
まず、基本給の場合、労働時間比例で考えることになります。仕事の内容や責任の程度が同じであれば、時間当たりの賃金は変わらず、労働時間に比例して減額するというのが基本的な扱いです。つまり、前述の事例のように所定労働時間に対する時短勤務による労働時間の割合を計算します。
次の事例で考えてみましょう。
基本給:250,000円
時短による労働時間:6時間
所定労働時間に対する時短労働時間の割合=6÷8=0.75(75%)
時短による基本給は次のようになります。
計算式は次のように示すことができます。
手当の計算はどうなる?
諸手当については、企業によって支給されるものが異なってきます。就業規則あるいは、それに準じるもので各手当の支給の趣旨、支給要件、支給額等については定めているのが一般的です。各企業では、そのうえで諸手当を次のように3つに分けてルールを決めています。
- 労働日数や労働時間を基準とする手当
通勤手当、食事手当、宿直手当等のように労働日数や労働時間に応じて支給する者が該当します。これらについては、時短勤務とした場合、実際の労働日数と労働時間によって支給額を算出することになります。
- 職務を基準とする手当
役職手当や資格手当等、職務によって支給するものが該当します。これらの手当については、実際の労働日数と労働時間での計算は馴染みません。企業側は、あらかじめ就業規則等でルール化しておくことが大切です。
- 家庭関連の手当
従業員の家庭に関連した住宅手当、扶養手当等が該当します。これらの手当は、時短勤務にしても支給額を変えることは適切ではありません。
ボーナス(賞与)の計算はどうなる?
賞与については、基本給と異なり、法律で支給が義務づけられているわけではありません。支給する場合も就業規則に「会社の業績等を勘案して定める」としているケースが一般的ですが、時短勤務にするに際し、やはりルールを明確化しておくべきでしょう。
基本的な考え方としては、賞与を何を基準として算定するのかによって、次のように分けることができます。
- 基本給を基準にする場合
短時間勤務になった従業員の基本給を基準に賞与を算定することになります。前述の事例のように基本給250,000円の従業員が6時間勤務で基本給が187,500円となった場合、賞与の支給基準が基本給の2カ月分であれば、「187,500円×2=375,000円」ということになります。
- 企業業績・個人業績を基準とする場合
この場合は、フルタイムの従業員と短時間勤務となった従業員の賞与の支給額に労働時間によって差を設けることは適切ではありません。両者に同じ基準を用いることが必要です。
目標管理によって個人業績を評価する場合は、短時間勤務に変更するに際し、達成不能な目標を設定しない等の配慮が求められます。
- 基本給、企業業績・個人業績の複合的に基準とする場合
基本給基準による賞与額と、企業業績・個人業績基準による賞与額を上記で説明したそれぞれの基準によって別々に算定したうえで、合算して全体の賞与支給額が算出されます。
時短勤務の給与計算において悩みやすいポイント
時短勤務の場合の基本給、諸手当、賞与の給与計算について解説してきました。時短勤務になる人は、就業規則でそれぞれの給与の支払基準を確認しておくことが大切です。
ここではあらためて重要なポイントを確認するとともに、特に法律で義務化されている育児・介護のための時短勤務で注意すべき点についてみていきます。
時短勤務でも給料が変わらないときは?
時短勤務では、基本的に給与が減額されることはすでに説明した通りであり、常識的にも多くの方はそうした認識かと思われます。しかし、前述の諸手当のうちで職務を基準とするもの、家庭関連を基準とするもの、また企業業績・個人業績の賞与では、支給額に差を設けることが適切でない場合があります。時短勤務になるに際しては、この点をよく理解しておくことが大切です。
育児時短勤務の場合の給与計算対象期間は?
育児・介護休業法では、育児・介護については時短勤務を導入することを義務づけており、一定の要件を満たした従業員から申し出があれば、事業主は労働時間を短縮しなければなりません。
一定の要件とは、次の5点です。
- 3歳未満の子どもを養育する労働者であること
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日雇い労働等、日々雇用される労働者でないこと
- 短時間勤務制度の適用期間に育児休業をしていないこと
- 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
ただし、育児・介護休業法による時短勤務は、利用できる期間が限定されています。育児のための時短勤務には、上記のように「3歳未満の子どもを養育する労働者」という要件があります。正確に言えば、「3歳の誕生日の前日」までが、時短勤務の対象期間ということになります。
介護のための時短勤務の場合の給与計算対象期間は?
家族の介護のための時短勤務については、介護休業とは別に連続する3年以上の期間内で2回以上利用することができます。
連続する3年以上の期間は、従業員が短時間勤務を利用すると申し出た日から起算します。
2回以上とされる各々の時短勤務の対象期間については、法的にルールがないため、事業所では従業員の介護事情に配慮して決めることが望ましいでしょう。
時短勤務者の退勤が「早退」扱いになる会社は?
時短勤務の場合の給与計算については、基本給の場合、すでに述べた労働時間比例が一般的な方法です。この方法では、給与における基本給を改定することが必要になります。
基本給を改定しない方法として、所定労働時間である8時間に対し、時短した部分を遅刻・早退扱いすることも考えられるでしょう。この場合、遅刻・早退による労務の提供のない時間分の賃金は控除して減額します。
ただし、遅刻・早退による賃金控除によって結果的に月額給与は減額になりますが、固定的賃金の減額には該当しません。これは社会保険の随時改定(月変)において注意する必要があります。
つまり、随時改定の要件である被保険者の報酬が、固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったことにならないということです。
時短勤務に移る前に給与計算の方法について確認しておこう!
時短勤務した場合の給与計算について詳しく解説してきました。もしも時短勤務に移る場合、基本給、諸手当、賞与のそれぞれについて計算方法がどのようになるのか、自分のケースを想定してシミュレーションしておくことが大切です。その際、会社の就業規則の賃金規程もしっかり確認しておきましょう。
よくある質問
時短勤務の給与計算について教えてください。
基本給の場合、所定労働時間と時短した労働時間で、労働時間比例で算定するのが一般的です。詳しくはこちらをご覧ください。
各種手当の計算はどうなるか解説してください。
諸手当を性質によって3つ類型化し、各々の計算方法によります。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
裁量労働制の疑問を解決!休日出勤や深夜業、休憩時間はどう考える?
裁量労働制と休日出勤・深夜業 裁量労働制においては、「業務遂行の方法や時間配分を大幅に労働者に委ねている」ため、いつ、どのくらいの時間労働するかは、基本的に労働者の裁量に委ねられて…
詳しくみる月平均所定労働時間160時間は適正?計算方法や残業代の仕組みを解説
「自分の会社の月平均所定労働時間は160時間だけど、これって普通なの?」「もしかして、他の会社より多く働かされているのでは?」 ご自身の労働時間について、このような疑問や不安を感じ…
詳しくみる年間労働日数の平均は?年間休日との関係や日数の決め方を解説
従業員は、年間で何日程度働くべきなのでしょうか。また、その日数はどのように決めればよいのでしょうか。平均して、どの程度の日数働いているのかも気になるところです。 当記事では年間労働…
詳しくみる勤怠管理システムのメリット・デメリットを徹底解説!選び方のポイントも紹介
勤怠管理システムの導入を検討していませんか?勤怠管理システムは、業務効率化やコスト削減はもちろん、コンプライアンス強化にもつながる多くのメリットがあります。しかし、知っておくべきデ…
詳しくみるインフルエンザで休養を取る場合、有給は使えない?会社としての対応を解説
インフルエンザで仕事を休む場合、有給休暇を取得することは可能です。ただし、有給休暇の消化を従業員に強制してはいけません。 労働基準法では、有給休暇の取得は従業員の自由な意思に委ねら…
詳しくみるエクセル(Excel)の勤怠管理のメリットとデメリット
エクセルの勤怠管理で何ができる? 従業員の勤怠管理に紙のタイムカードを使用していませんか?勤怠管理はエクセル(EXCEL)を使うと非常に便利です。エクセルを使用することで ・出社・…
詳しくみる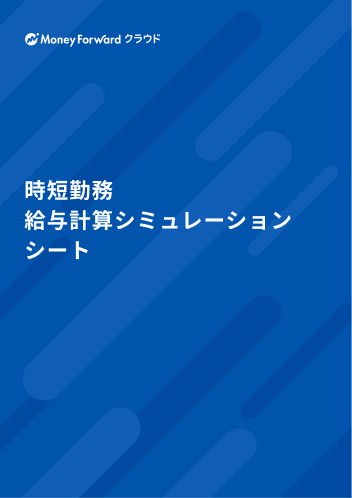

-e1762740828456.png)

