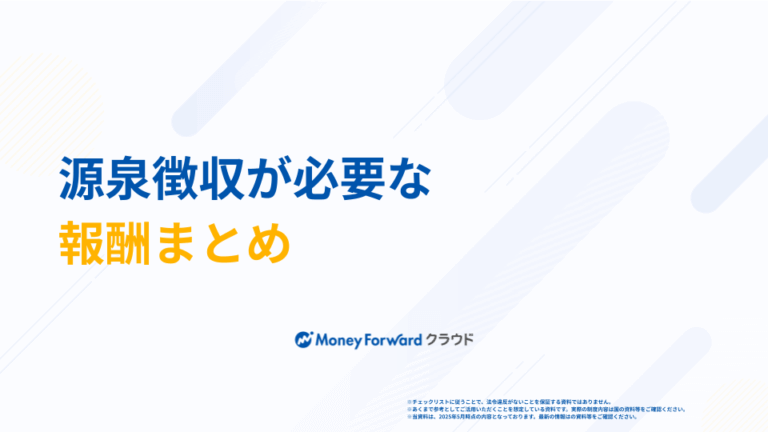- 更新日 : 2025年7月24日
源泉徴収が必要な報酬と注意事項を徹底解説!
事業を行っていると、個人事業主でも報酬を支払う機会があります。身近なところでは、税理士や社会保険労務士に報酬を支払っている方もいるでしょう。これらの報酬を支払う場合も、条件を充たせば源泉徴収をしなければなりません。では、源泉徴収が必要な報酬とは具体的にはどのようなものでしょうか。ここでは、源泉徴収が必要な報酬・料金の事例と源泉徴収を行う際の注意点について説明します。
源泉徴収が必要な報酬・料金
報酬を支払う相手は、個人である場合と、法人である場合があります。いくつか代表的なケースをご紹介します。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
個人に報酬・料金を支払う場合
(1).作家や大学教授などに原稿や講演を依頼した場合の原稿料や講演料は、源泉徴収が必要な報酬・料金
原稿料や講演料などを報酬・料金として支払う場合、下記に注意が必要です。
(1)-a調査費、取材費、車代といった名目で支払っても、実態が原稿料や講演料と同じならば、源泉徴収の対象です。
(1)-b.旅費や宿泊費は報酬・料金に含みます。ただし、支払い者が直接ホテルや旅行会社へ支払い、その料金が通常の範囲内ならば、報酬・料金等に含めなくても大丈夫です。
(1)-c.懸賞小説・文学賞の応募作品の入選者への支払いや新聞、雑誌の投稿の謝礼金は、5万円以下であれば源泉徴収をする必要はありません。
(1)-d.試験問題の出題料や答案の採点料は、原稿料になりません。
(2).弁護士、税理士、司法書士など、特定の資格を持つ人への報酬・料金
(3).社会保険診療報酬支払基金が、個人経営の診療所などに支払う診療報酬
(4).プロ野球選手などのプロのスポーツ選手、モデル、保険外交員、集金人などに支払う報酬・料金
(5).個人で経営する芸能プロダクションや芸能人に支払う報酬・料金
(6).バーやキャバレーのホステス、パーティコンパニオンなどに支払う報酬・料金
(7).ホステスやコンパニオンに支払う報奨金、衣装代、深夜帰宅のタクシー代は、報酬・料金に含まれます。
(8).プロのスポーツ選手などと専属契約を結ぶ際に支払う契約金
(9).クイズ番組の獲得賞金など広告宣伝が目的の賞金や賞品、および個人の馬主に支払う賞金(広告宣伝を目的とした賞金等の額が50万円以下の場合、源泉徴収の対象になりません)
法人に報酬・料金を支払う場合
競馬で賞金を受ける馬主が法人の場合、その賞金は源泉徴収の対象となる報酬・料金です。
源泉徴収をする場合に注意する事項
前項を踏まえた上で、報酬・料金の源泉徴収について、間違えやすい注意すべきことを下記に列挙します。
1.実際の内容が報酬・料金であるものを、取材費、車代、謝礼の名目で支払ったとしても、それは源泉徴収の対象となります。ただし、報酬を支払う人が、直接交通機関やホテルなどに支払ったものは報酬・料金に含めなくても大丈夫です。この場合の交通費、ホテル代は、あくまでも常識の範囲の料金となります。
2.金銭の代わりに物品で支払っても、報酬・料金とみなされます。
3.報酬・料金に消費税が含まれている場合、請求書上で報酬・料金額と消費税額が明確ならば、その報酬・料金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。報酬・料金額と消費税額が明確でない場合には、消費税を含めた金額が源泉徴収の対象となる報酬・料金となります。 顧問税理士に、源泉徴収後の手取り金額で月々の報酬を支払っている事業者も多いでしょう。手取り契約とは、報酬の支払額を税引き後の手取り額で契約をしている場合です。手取り契約の場合は、特別な計算方法で源泉徴収を行う必要があります。
4.手取り額が89万7,900円以下(支払報酬額100万円以下)の場合は、税率10.21%で計算 支払報酬金額の計算
手取り額÷0.8979となり、源泉徴収税額は、上記の支払報酬金額×10.21%です。
例:手取り額50万円の場合
支払報酬金額:500,000÷0.8979=55万6,854円
源泉徴収額:56,854円
5.手取り額が89万7,900円超(支払報酬額100万円超)の場合は、二段階税率を適用
手取り額が89万円7,900円(支払報酬額100万円)までは10.21%で計算し、100万円を超えた部分について20.42%で計算します。
源泉徴収税額は、(上記の支払い報酬金額 - 1,000,000)×20.42%+102,100です。
例:手取り額150万円の場合
支払報酬額 :(1,500,000-897,900)÷0.7958+897,900÷0.8979=756,597+1000,000=1,756,597円
源泉徴収額:256,597円
まとめ
源泉徴収の対象となる報酬・料金の範囲は多岐にわたっているため、なかなか把握しにくいものです。すべてを把握する必要はありませんが、自分の事業に関する支払い報酬・料金については、きちんと理解することが大切です。また、支払いの際には、報酬の内容が適切かどうか確認し、正しく計算しましょう。特に、手取り契約の場合は、源泉徴収金額の計算は注意が必要です。
参考:
国税局ホームページ「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
国税局ホームページ「原稿料や講演料等を支払ったとき」
国税局ホームページ「手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法」
源泉徴収の計算
源泉徴収票の見方を理解しよう!
よくある質問
源泉徴収が必要な報酬を支払う相手が法人である場合の代表的なケースは?
競馬で賞金を受ける馬主が法人の場合、その賞金は源泉徴収の対象となる報酬・料金です。詳しくはこちらをご覧ください。
源泉徴収をする場合に注意することは?
実際の内容が報酬・料金であるものを取材費、車代、謝礼の名目で支払ったとしてもそれは源泉徴収の対象となること、金銭の代わりに物品で支払っても報酬・料金とみなされること、などが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
定額減税の給与計算やシミュレーション例をわかりやすく解説
政府の経済政策の一環として、定額減税が導入されることになりました。この制度は、従業員の税負担を軽減し、経済活性化を図るための取り組みです。給与計算の現場では、この定額減税の適用に際…
詳しくみる有休はいつ増える?増え方の条件や日数、パートアルバイトの場合も解説
有休(年次有給休暇)は、入社後6ヶ月継続勤務し、出勤率が8割以上であれば付与されます。 その後は勤続年数に応じて増えていき、最大で年間20日付与されます。 パートやアルバイトの方も…
詳しくみる所得税の税率について|税金の計算方法や法律改定など
所得税は個人の所得に課税される税金で、通常給与や賞与から源泉徴収され会社が代理納付します。年間の収入から経費や所得控除を差し引いた課税所得に税率を掛け合わせることで税額を算出するこ…
詳しくみる西宮市の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
西宮市は、阪神間に位置し、洗練された住宅地と商業エリアが調和する魅力的な都市です。多くの企業が集まるこの地域では、給与計算の正確性と効率性がビジネス成功の鍵を握っています。 本記事…
詳しくみる役員報酬の給与明細は必要?テンプレートをもとに書き方を解説
役員報酬は給与明細の発行が必要です。役員は労働者ではありませんが、役員報酬は所得税法上の給与所得に該当するため、明細の発行が義務付けられています。従業員を雇わない一人社長であっても…
詳しくみる有給休暇の給料はいくら支払う?賃金3つの計算方法と買取できる例外を解説
有給休暇は給与が発生する休暇のため、正確に給与計算を行い、支給しなくてはいけません。有給休暇の給与の計算方法や付与要件、パートやアルバイトの有給休暇の条件などについてまとめました。…
詳しくみる