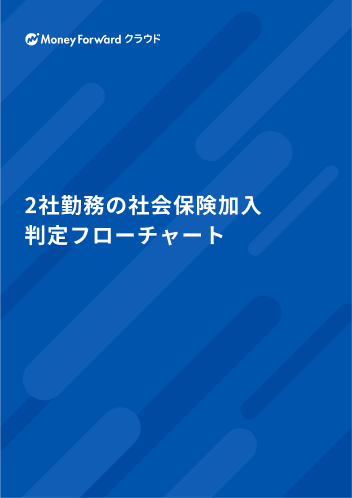- 更新日 : 2026年1月6日
2カ所以上の会社で雇用されるようになった場合の社会保険の取り扱いについて
一般に、会社勤めの方は勤め先の会社(適用事業所)で社会保険に加入します(※1)。
社会保険には「健康保険」(※2)と「厚生年金保険」があり、従業員のみならず会社の社長や役員の方でも加入できます。
通常、社会保険の加入手続きは、入社と同時に会社が行います。
しかし、すでに会社勤めをしていながら、新たに別の会社に勤める(別の仕事を始める)という例も少なくありません。
例えば、本業の傍ら副業でアルバイトをすることなどが挙げられます。
また、会社の代表者が新たに別の会社を設立して、両方から報酬を受ける場合もこれに該当します。
今回は、このように2カ所以上の会社で雇用されるようになった場合の社会保険の加入について解説します。
※1 なかには、社会保険が適用されない会社もあります。法人ではない個人経営で、従業員が常時5人未満の場合、または農林水産業、サービス業など特定の業種に属する会社については、社会保険の適用が任意とされています。
※2 健康保険加入者のうち、40歳以上の方は介護保険にも加入することになります。
社会保険の加入要件
まず、社会保険の加入要件について見ていきましょう。
そもそも社会保険は「国民皆保険・国民皆年金」という日本の社会保障制度を成り立たせるために、強制加入を原則としています。
そして、社会保険が適用されている会社(適用事業所)と使用関係にあり、労働の対価として賃金を得ている人なら、国籍、年齢、賃金の多寡などに関係なく被保険者となります。
主な例外には「短時間労働者」があげられます。これはいわゆるパートタイマーやアルバイトとして働く人々のことです。
ただし、短時間労働者が一定の条件を満たす場合は、社会保険加入の対象となります。
- 1週間の所定労働時間…同一の事業所に使用される通常の労働者の3/4以上
- 1カ月の所定労働日数…同一の事業所に使用される通常の労働者の3/4以上
1週間の所定労働時間や1カ月の所定労働日数が3/4未満であっても、以下の場合にすべて該当する人は、短時間労働者になります(被保険者が常時501人以上の企業や、500人以下でも労使合意に基づき申出をしている企業や個人事務所の場合)。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
出典:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
「通常の労働者」とは、一般的にフルタイムの正社員を指します。フルタイムの目安は、その会社の就業規則などに定められた勤務時間に基づいて考えます。
一般的には「1日8時間、1週40時間」が基準となっていることが多く、この原則は労働基準法のなかで定められている法定労働時間に基づいたものです。
パートやアルバイト社員の場合、この労働時間が保険加入の可否を左右します。
例えば、1週間の平均労働時間を40時間として、40×3/4=30、つまりその人の労働時間が週30時間以上か否か、これがひとつの基準となります。
「有期契約の従業員は社会保険に加入する必要がない」と考えている人が居るかもしれません。
しかし、契約期間の定めの有無は、社会保険の加入に直接影響しません。
例えば、無期契約の従業員であっても、1日4時間で週5日勤務なら計20時間で加入要件を満たしません。これとは逆に、有期契約の場合でも、1日8時間で週4日勤務なら、計32時間となるため社会保険に加入する必要があります。
では、2カ所以上の会社で雇用される場合、どのように社会保険加入の要件が該当するかを見ていきましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
2カ所とも要件を満たさない場合
勤め先が2カ所とも短時間勤務で、週30時間以上の要件を満たさない場合には、原則どちらの会社の社会保険も加入対象外です※。
つまり、短時間勤務の職場をいくつ掛け持ちしようと、社会保険には原則加入対象外となります。その場合は、従業員が個人で国民健康保険に加入する必要があります。
健康保険はサラリーマンとその家族を対象とする医療保険ですが、国民健康保険は、健康保険加入者以外の人(すでに退職した75歳までの高齢者や無職者、自営業者など)を対象としています。このため、社会保険の加入要件を満たさない従業員も、国民健康保険の加入者には該当します。
運営する保険者が市町村(または同業の自営業者による国保組合)ということになるため、加入者自らが加入手続きをする必要があるのです。
なお、年金は自動的に国民年金となり、被保険者自身が毎月月末に前月分の保険料を納付します(口座振替も可能)。
1カ所で要件を満たす場合
複数の会社で働いていて、どちらか1つの会社で社会保険の加入要件を満たす場合は、その会社で社会保険に加入します。
この場合、社会保険加入などの手続きや支払う保険料、受け取る保険金などについては1社のみで働いている場合と同じです。
2カ所とも要件を満たす場合
所属している2カ所以上の会社がいずれも社会保険の加入要件を満たす場合、会社と本人それぞれで、社会保険の手続きを行う必要があります。それぞれの手続について見ていきましょう。
本人
2カ所以上の会社で社会保険の加入要件を満たした場合は、被保険者本人が主たる事務所を選択する必要があります。具体的には、2カ所以上の会社で社会保険の加入要件を満たした事実の発生から10日以内に「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
提出先は、選択する事業所の所在地を管轄する年金事務所です。
保険料の支払い
年金事務所では、すべての会社の給料を合算し、給料額に応じた各会社や被保険者本人の社会保険料を算定します。会社や本人は、年金事務所の計算した金額を納めます。
例えばA社から30万円、B社から10万円の給料を受け取っていたとします。また、この給料(標準報酬月額)に対応する保険料は4万円でした。
この場合、A社とB社の賃金は3:1であるため、社会保険料もこの割合で按分します。按分後の保険料はA社分3万円、B社分1万円となります。
2カ所以上の会社に雇用される場合は社会保険料に注意
以上のように、2カ所以上の会社に雇用される場合でいずれも社会保険の加入要件を満たす場合は、それぞれの会社で資格取得届を提出する必要があります。この場合いずれか一つの会社を選択事業所として届出を提出し、選択する会社の管轄する保険者によって一括して業務が取り扱われます。
多様な働き方に合わせた適切な社会保険の取り扱いについて理解を深めておきましょう。
よくある質問
正社員の社会保険の加入条件は?
正社員は原則、社会保険に加入しないといけません。パート・アルバイトの場合は一定の条件を満たせば加入できます。詳しくはこちらをご覧ください。
パート・アルバイトの場合の社会保険の加入条件は?
1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働日数が3/4以上の場合などでは社会保険に加入します。 詳しくはこちらをご覧ください。
2か所で社会保険に加入している場合の手続きは?
詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
従業員に住所変更があった場合の社会保険の手続きについて解説
社会保険に加入している従業員が転居等した場合、届け出済みの住所も変更する必要があります。住所変更は「健康保険・厚生年金被保険者住所変更届」で行います。住所変更があった後、窓口持参・…
詳しくみる健康保険とは?被用者保険と国民健康保険の違い
健康保険は、日本の医療制度を支える重要な保険制度です。会社員や公務員が加入する政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合のほかに、個人事業主や自営業者が加入する国民健康保険があります…
詳しくみる介護保険で医療費控除の対象になるものとは?
介護保険制度では、訪問介護や訪問入浴介護など、さまざまなサービスを受けることができます。利用できるサービスのなかには、自己負担分を医療費控除として申告できるものがあり、医療費控除を…
詳しくみる労働保険の年度更新申告書を間違えたら?訂正方法を解説
労働保険の年度更新(毎年6月1日~7月10日)の申告書を提出してから、間違いに気づいたという方もいらっしゃるでしょう。 賃金総額の計算などで、「通勤手当を入れ忘れた」「役員報酬を誤…
詳しくみる【テンプレ付】労災事故報告書とは?提出義務がある事故や記入例を解説
労災事故報告書は、一定の労災事故があったことを届け出る際に用いる書類です。事業場内で火災などが発生した場合は、労働安全衛生規則第96条の規定により、様式第22号を用いて報告しなけれ…
詳しくみる医療費の限度額とは
重症の病気やけがによる長期入院や療養が必要となった場合、自己負担すべき医療費が高額になってしまいます。そのため、個人の負担を軽くできるように、健康保険には「高額療養費制度」が設けら…
詳しくみる