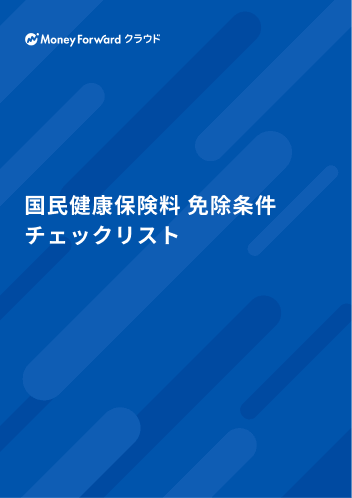- 更新日 : 2025年11月18日
国民健康保険の免除について
国民健康保険は、病気やけがになったときに、相互に助け合い、経済的な負担を分かち合う制度です。
加入者がそれぞれ保険料を出し合い、さらに国や自治体が税等を出して医療費を負担するもので、社会保険などに加入していない方が必ず入る必要があります。無職であっても加入し
なければならず、収入がある・なしに関わらず保険料を納めなければいけないわけです。
国民健康保険の保険料は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」の3つから成り、年度(4月から翌年の3月)を単位として計算します。
保険料は各区分において、平等割額や均等割額などのように均等に負担する部分と、所得に応じて負担額が異なる所得割額の部分などの合計から成り、世帯で合算します。そのため、事情によっては保険料の支払いが大きな負担となり、支払いが滞ったり、困難だったりという場合もあると思います。
財産や遊ぶお金はあるのに保険料は払えない、というような理屈は通りませんが、病気や震災などにより所得が大幅に減った場合や、前年度よりも所得が減少して、やむを得ず支払いに困っている方には、救済の措置として保険料の減額や減免などの免除制度が設けられています。
今回は、国民健康保険料の減免などの免除制度について解説します。
減免等の免除制度の概要
災害や所得が減少したなどの理由で、国民健康保険料を納めるのが難しい、困っているという方は、場合によっては、保険料の免除や、一部負担にすることができます。
国民健康保険の免除・減額の条件については各市町村によって異なりますが、減額および免除等は世帯全員の所得を合計したうえで決定され、7割、5割、2割のなかから減免率が選ばれます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
保険料均等割軽減
国民健康保険の軽減制度における、それぞれの軽減率に対応する軽減基準所得は以下の通りです。
令和3年度以降の国民健康保険料の軽減基準額は変更されました。
基準となる所得金額適用についての留意点
自分の収入に対して何割減になるのか、自分で計算して申請する必要はありあません。申請されている所得に基づいて、しかるべき割合を適用したうえで軽減されます。
留意すべきは、減免を受けたい月の保険料の納期限までに申請する必要があるということです。また、所得が未申告の方が世帯にいる場合には、適用されないので注意が必要です。
ただし、独自の自治体で設定されている減額および免除の制度等、申請が必要な場合もありますので、各市区町村にお問い合わせください。
保険料の減免
国民健康保険料については、震災・風水害・火災などの災害にかかる減免のほか、退職・倒産・休廃業や営業不振等により、所得が大幅に減少した世帯への減免制度があります。
また、コロナウイルス感染症に係る減免措置もあります。
非自発的失業者に係る保険料の軽減
65歳未満で会社の倒産や会社の都合で退職した人で、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である方は、国民健康保険料が軽減される場合があります。
国民相互の助け合いである国民健康保険制度
国民健康保険は、都道府県や市町村が運営する公的な医療保険制度です。
病気やケガなどに備えて、加入者が互いに医療費の負担を支えあう助け合いの制度です。
万が一、保険料が不足すると、加入者への給付が十分に行えず、加入者の医療費負担が大きくなってしまいます。
しかし、経済的にどうしても支払が困難な状態になった場合は、減免など対応策があります。細かな条件は地方自治体によっても異なることもありますので、自治体の窓口に問い合わせましょう。
支払が困難だからといって、未払いの状態にしておくことのないよう、必ず相談することが大切です。
よくある質問
国民健康保険制度とはどのような制度ですか?
病気やけがになったときに、経済的な負担を分かち合うため、加入者が保険料を出し合い、さらに国や自治体が税等を出して医療費を負担する制度です。詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険に加入するのはどのような人ですか?
社会保険などに加入していない方が必ず入る必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険料が支払えない場合の対応策はありますか?
災害や所得が減少したなどの理由で保険料の支払が困難な場合には、保険料の免除や、一部負担とすることができます詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
従業員が退職したら何をすべき?社会保険手続きや必要書類の書き方まとめ
従業員の退職が決まったら、人事がするべき手続きが数多くあります。なかでも健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険は、手続きの期限が決まっているため、迅速に必要書類を提出しなけ…
詳しくみる社会保険料のダブルチェック方法は?計算ミスを防ぐダブルワーク時の注意点
社会保険料の計算ミスを防ぐには、複数担当者によるダブルチェックが大切です。特に、従業員がダブルワーク(副業・兼業)を行っている場合、各事業所の給与を合算して保険料を決定するため手続…
詳しくみる休職のまま退職した時の失業保険について!金額はどれくらい?【退職届テンプレ付き】
休職のまま退職した場合、失業保険の給付ができるのをご存じでしょうか?本記事では失業保険の基礎知識から受給条件や手続きまで詳しく解説し、休職の状態で退職した場合の失業保険についての疑…
詳しくみる年金制度改正法とは?2022年4月施行に備えて徹底解説!
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が2020年5月に成立し、2022年4月から施行されます。この改正により厚生年金の加入の対象となる被保険者が増加するほ…
詳しくみる社会保険の任意加入とは?メリットや任意適用事業所の申請手続きを解説!
厚生年金と健康保険からなる社会保険は、適用事業所に所属し、条件を満たした全従業員が加入しなければならない強制保険制度です。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。…
詳しくみる社会保険の改定まとめ!社会保険の種類・対象・保険料の計算方法も解説
日本の社会保険制度は大きな改定期を迎えており、企業の人事・法務担当者や被保険者にとって最新情報の把握が欠かせません。社会保険改定のポイントとして、短時間労働者への適用拡大、保険料率…
詳しくみる