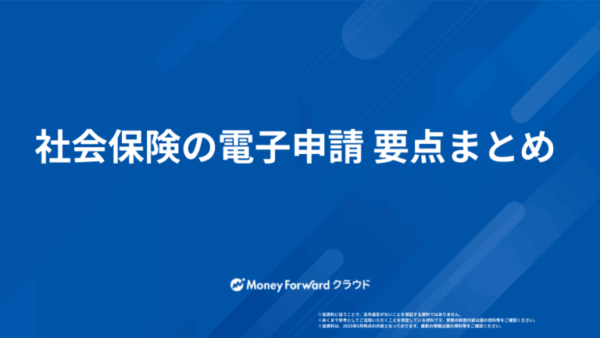- 更新日 : 2025年11月25日
算定基礎届の電子申請のやり方は?いつからできる?GビズIDでの手続きも徹底解説
算定基礎届の電子申請とは、GビズIDとe-Govを利用することで、事業所のパソコンからオンラインで手続きを完結させる方法です。2020年4月から特定法人で義務化された背景もあり、算定基礎届のオンライン申請が主流となりつつあります。
この記事では、電子申請のメリット・デメリットから、GビズID(ジービズID)を利用した具体的な手続きのやり方、いつから準備を始めるべきかというスケジュール、そしてスムーズに進めるための事前準備まで詳しく解説します。
目次
算定基礎届の電子申請とは?
算定基礎届の電子申請とは、紙媒体で作成・提出していた「被保険者報酬月額算定基礎届」を、インターネット経由で行政機関に提出する手続きのことです。これにより、事業所の担当者はオフィスにいながら申請でき、業務の効率化が図れます。
政府は行政手続きのデジタル化を推進しており、社会保険や労働保険関連の手続きも例外ではありません。特に、資本金1億円超の特定法人においては、2020年4月から電子申請が義務化されており、中小企業においても利用が推奨されています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選
業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
社会保険の電子申請 要点まとめ
社会保険の電子申請に関する主要なポイントを、簡潔にまとめた資料です。
電子申請の概要把握や、実務を進める上での確認用資料としてご活用ください。
算定基礎届を電子申請を行うメリット・デメリット
電子申請への切り替えは、業務効率の向上とコスト削減という大きなメリットがある一方、導入する際にはシステム設定等の手間がかかるというデメリットも存在します。
電子申請のメリット
- 時間と場所の制約がない
24時間365日、土日祝を問わず、パソコンで申請が可能です。年金事務所の開庁時間に合わせて窓口へ行ったり、郵便局へ足を運んだりする必要がなくなります。 - コストの削減
申請書類の印刷代、封筒代、郵送費(切手代)といった直接的なコストが不要になります。また、担当者が役所へ移動するための交通費や人件費も削減できます。 - 事務作業の効率化と正確性向上
多くの労務管理ソフトは、給与計算データから算定基礎届のデータを自動連携・作成する機能を備えています。これにより、手作業による転記ミスを防ぎ、正確性が向上します。また、e-Govの入力チェック機能により、形式的な不備を申請前に検知できます。 - 進捗状況の可視化
e-Govのマイページ上で、申請した手続きが「受付中」「審査終了」など、現在のステータスをいつでも確認できます。郵送のように「無事に届いただろうか」と心配する必要はありません。 - ペーパーレス化の推進
提出書類や控えを紙で保管する必要がなくなり、オフィスの省スペース化にもつながります。また、過去の申請データも電子化して管理できるため、検索や参照がしやすくなります。 - 返戻書類のスピーディーな受け取り
提出した書類に不備があった場合、これまでは郵送で返戻されていましたが、電子申請の場合はe-Gov上で通知が届きます。修正・再申請までのリードタイムを大幅に短縮できます。
電子申請のデメリット
- 初期設定の手間がかかる
電子申請には「GビズID」のアカウント取得が必要です。取得には申請から承認まで1〜2週間程度かかる場合があるため、余裕を持って準備をすることが必要です。また、利用するPCがe-Govの推奨環境に適合しているか確認し、設定する手間もかかります。 - システムメンテナンス
e-Govは定期的にシステムメンテナンスを行うため、その間は申請手続きができません。提出期限間際に慌てないよう、メンテナンスのスケジュールを公式サイトで確認しておくことが重要です。 - 操作への慣れが必要
初めて利用する場合、e-Govの画面操作や申請データの作成方法に戸惑う可能性があります。事前にマニュアルを確認したり、テスト的に操作したりする時間を見込んでおくと安心です。
算定基礎届の電子申請の方法
算定基礎届の電子申請には、主に3つの方法があります。
1. GビズIDを利用したe-Govからの申請
国が運営するポータルサイト「e-Gov」に、GビズIDでログインし、Webブラウザ上で申請する方法です。
GビズIDとは、1つのアカウントで複数の行政サービスにログインできる、法人・個人事業主向けの共通認証システムで、無料で取得できます。
- 特定のソフトウェアに依存せず、Webブラウザだけで申請が可能です。
- 日本年金機構が提供する「届書作成プログラム」で作成したCSVファイルをアップロードして申請できます。
- コストをかけずに電子申請を始めたい企業におすすめです。
2. 労務管理ソフトからの直接申請(API連携)
現在利用している労務管理ソフトや給与計算ソフトから直接申請する方法です。
- 給与データから算定基礎届の作成、申請までをシームレスに行えるため、作業効率が格段に向上します。
- ソフトウェア内で申請状況の管理も可能です。
API連携に対応しているかは、お使いのソフトの公式サイト等でご確認ください。
3. 電子媒体(CD/DVD)による届出
作成した申請データをCDやDVDに記録し、管轄の年金事務所へ郵送または持参する方法です。これは厳密にはオンライン申請ではありませんが、インターネット経由での申請が難しい場合の代替手段として認められています。
- 大量の被保険者を抱える事業所などで、インターネット回線の状況に左右されずに提出したい場合に利用されます。
- 郵送の手間や媒体の準備が必要なため、利便性はe-GovやAPI申請に劣ります。
算定基礎届の電子申請を行うための事前準備
電子申請をスムーズに行うには、提出期間である7月上旬から逆算し、計画的に準備を進めることが重要です。特に、GビズIDの取得には時間がかかるため、遅くとも6月中旬までにはID取得の申請を済ませておきましょう。
1. GビズIDアカウントの取得
e-Govを利用した電子申請に必要なGビズIDアカウントを取得します。審査に通常1〜2週間程度かかるため、早めに手続きを行いましょう。
- GビズID公式サイトへアクセス:公式サイトから「GビズIDアカウントの作成をはじめる」を選択し、申請を開始します。
- 申請書を作成:画面の指示に従い、法人情報や代表者情報を入力し、申請書を印刷します。
- 必要書類を準備:作成した申請書、印鑑証明書(発行3ヶ月以内)、代表者印(実印)を準備します。
- 郵送:申請書に代表者印を押印し、印鑑証明書と合わせてGビズID運用センターへ郵送します。
- 承認とパスワード設定:審査完了後、承認メールが届きます。メール内のリンクからパスワードを設定すれば利用可能になります。
2. 利用するPCの環境設定
電子申請を行うパソコンが、e-Govの推奨環境を満たしているかを確認・設定します。
- OS:Windows、Macに対応しています。
- ブラウザ:Microsoft Edge、Google Chromeなどが推奨されています。
- その他:必要に応じて、e-Govサイトからブラウザの拡張機能(e-Gov電子申請アプリケーション)のインストールを求められる場合があります。
事前にe-Govのトップページにアクセスし、GビズIDでログインできるかテストしておくと安心です。
3. 算定基礎届の作成に必要な情報の収集
申請データを作成するために、必要な情報を手元に揃えます。これは紙で提出する場合と同様です。
これらの情報を基に、日本年金機構の「届書作成プログラム」や労務管理ソフトで申請用のCSVデータを作成します。
GビズIDを使った算定基礎届の電子申請マニュアル
ここでは、最も一般的な「e-Gov」と「GビズID」を利用した申請手順を5つのステップで解説します。従業員数が多い場合は、事前に作成したCSVファイルをアップロードする方法が効率的です。
1. e-Govにログインする
まず、e-Govの公式サイトにアクセスし、ログイン手続きを行います。
- e-Gov公式サイトのトップページ右上にある「ログイン」ボタンをクリックします。
- ログイン方法の選択画面で「GビズIDでログイン」を選択します。
- GビズIDのログイン画面に遷移するので、登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
2. 手続きを検索し、申請書入力フォームを開く
ログイン後、マイページから申請する手続きを探します。
- マイページ上部の検索窓に「算定基礎届」または「被保険者報酬月額算定基礎届」と入力し、検索します。
- 検索結果の中から「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」を選択し、「申請書入力へ」ボタンをクリックします。
3. 被保険者情報を入力・CSVファイルで一括登録する
申請画面で、事前に作成したCSVファイルをアップロードします。
- e-Govの申請画面で「ファイル添付」や「CSV登録」といったボタンをクリックします。
- 「届書作成プログラム」等で作成しておいた算定基礎届の申請用CSVファイルを選択し、アップロードします。
- アップロードが完了すると、ファイルの内容が自動的に申請フォームに反映されます。
4. 内容を確認し、電子署名を付与して申請する
登録内容に誤りがないか最終確認を行い、申請を完了させます。
- 事業所情報や各被保険者の報酬月額などに間違いがないか、画面上で念入りに確認します。
- 問題がなければ、「署名付与」ボタンをクリックします。GビズIDログインの場合、通常は追加操作なしで電子署名が付与されます。
- 最後に「申請」ボタンをクリックすれば、手続きは完了です。
5. 申請後の状況を確認する
e-Govのマイページで、申請が正常に受理されたか、審査状況を確認します。
- e-Govのマイページにログインし、「申請案件一覧」や「状況確認」メニューをクリックします。
- 申請した算定基礎届のステータスが表示されます。ここで到達番号や受理日が確認できれば、無事に提出が完了したことになります。
算定基礎届の申請データの作成方法
算定基礎届の電子申請で用いるCSVファイルは、日本年金機構が公式サイトで無償提供している「届書作成プログラム」を利用して作成するのが一般的です。
この「届書作成プログラム」は、算定基礎届だけでなく、月額変更届や被保険者資格取得届など、さまざまな社会保険手続きの届書や電子申請用データを作成できる便利なツールです。日本年金機構の公式サイトからダウンロードしてPCにインストールすることで利用できます。
- プログラムの起動:インストールした「届書作成プログラム」を起動します。
- 事業所情報の登録:事業所整理記号や所在地などの基本情報を入力・登録します。
- 届書の選択:作成する届書の一覧から「算定基礎届」を選択します。
- 被保険者情報の入力:賃金台帳などの情報に基づき、被保険者一人ひとりの氏名、基礎年金番号、4月〜6月の報酬月額、支払基礎日数などを画面の指示に従って入力します。
- 電子媒体届書作成:全員の入力が完了したら、メニューから「電子媒体届書作成」を選択し、「CSV形式」で保存します。これでe-GovにアップロードするためのCSVファイルが完成します。
算定基礎届の電子申請でよくある質問(Q&A)
ここでは、算定基礎届の電子申請において担当者がつまずきやすいポイントをQ&A形式で解説します。
算定基礎届の提出期限はいつまでですか?
原則として毎年7月1日から7月10日までで、この期間は電子申請でも紙の申請でも同じです。提出期限の最終日はアクセスが集中し、サーバーが重くなる可能性があります。予期せぬトラブルを避けるためにも、7月5日頃までには申請を完了させることをお勧めします。
算定基礎届のCSVファイルはどこでダウンロードできますか?
CSVファイルそのものをダウンロードするのではなく、日本年金機構の公式サイトで無償提供されている「届書作成プログラム」をダウンロードし、そのソフトを使って作成します。また、市販の労務管理ソフトの多くも同様のCSVファイル出力機能を備えています。
算定基礎届の申請時にエラーが出た場合の対処法はありますか?
まずエラーメッセージの内容をよく読み、原因を特定することが重要です。e-Govのチェック機能で表示されるエラーの多くは、全角/半角の入力間違い、必須項目の入力漏れ、報酬月額と支払基礎日数の関係が不適切といった形式不備が原因です。対処方法としては、エラーが示す箇所を特定後、元のCSVデータや入力フォームを修正して再申請してください。それでも解決しない場合は、管轄の年金事務所やe-Govのヘルプデスクに問い合わせましょう。
算定基礎届のオンライン申請をスムーズに進めるために
本記事では、算定基礎届の電子申請について、メリットから具体的なやり方、注意点までを詳しく解説しました。
電子申請は、単に手続きをオンライン化するだけでなく、企業の労務管理全体の効率化とペーパーレス化を促進する重要な手段です。特に、GビズIDを利用したe-Govからの申請は、コストをかけずに始められるため、多くの中小企業にとって最適な選択肢となるでしょう。ぜひ本記事を参考にしながら、余裕を持った準備を進め、来たる提出期間に備えてみてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労災保険の各種手続き
労災保険とは、労働者が勤務時間中に遭った災害や出退勤中に災害に遭った場合に、本人やその家族に補償するために、保険金を支払う制度です。 そのため、使用する従業員が正社員や契約社員、ア…
詳しくみる特別支給の老齢厚生年金とは?受給要件と金額・手続きを解説
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金加入歴が1年以上あり、昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれた人に支給される年金です。受給開始年齢は生年月日や性別によって定め…
詳しくみるアルバイトの健康診断は義務?費用は自己負担?対象条件や受けたくない場合も解説
「アルバイト先から健康診断を受けるように言われたけど、これって義務なの?」「費用は自己負担って本当?」 アルバイトの健康診断について、このような疑問や不安を抱えている方は少なくあり…
詳しくみる建設業で外国人雇用するには?手続きや注意点を徹底解説
建設業で外国人を雇用するには、適切な在留資格の確認と必要な手続きを正しく行うことが重要です。 特定技能や技能実習などの業務内容に応じた在留資格があるか確認し、労働環境を整えることで…
詳しくみる親を社会保険の扶養に入れることはできる?条件や保険料を解説!
社会保険には扶養という家族の生計を支援する大事な制度があります。そんな扶養制度ですが、親と同居していなくても親を扶養に入れることはできるのか、親を扶養に入れる際の条件は、など親を扶…
詳しくみる厚生年金基金の8つのメリット
厚生年金基金とは、企業年金の一種であり、厚生年金保険料の一部を「代行部分」として運用し、その運用益による「プラスアルファ部分」を公的年金に上乗せ支給する制度です。厚生年金基金の仕組…
詳しくみる