- 更新日 : 2025年12月24日
単身赴任手当10万円は妥当?相場や内訳をわかりやすく解説
会社からの辞令で、家族と離れて暮らすことになる単身赴任。その際に支給される「単身赴任手当」が10万円というのは、果たして妥当な金額なのでしょうか。
企業の規模や赴任先の地域によって手当の相場は異なりますが、家賃の補助などをすべて含めて考えると、10万円という金額はひとつの目安になるかもしれません。
この記事では、単身赴任手当10万円の妥当性について、その相場観や内訳、支給条件などをわかりやすく解説します。従業員の家計の事情にもふれながら、企業が知っておきたいポイントを一緒に見ていきましょう。
目次
単身赴任手当10万円は妥当?気になる相場
月額10万円という単身赴任手当は、一般的な相場から見ると高い水準といえます。ただし、その金額だけで妥当性を判断するのは早計で、手当の内訳や赴任先の生活コストをふまえて考える必要があります。
単身赴任手当の相場は月額約5万円
単身赴任手当の相場は、月額でおおよそ5万円弱です。
厚生労働省が公表している「令和2年就労条件総合調査」の調査によると、単身赴任手当やそれに類する手当の平均支給額は、月額で47,600円でした。
この平均額と比較すると、月額10万円という金額は相場の2倍以上であり、非常に手厚い水準にあるといえるでしょう。
企業規模による相場の違いはほとんどない
単身赴任手当の金額は、会社の規模によって大きく変わるわけではないようです。
先ほどの調査結果を企業規模別に見ても、その傾向は変わりません。
| 企業規模(従業員数) | 単身赴任手当の相場(月額) |
|---|---|
| 1,000人以上 | 47,600円 |
| 300~999人 | 47,700円 |
| 100~299人 | 46,100円 |
| 30~99人 | 49,600円 |
このように、大企業から中小企業まで、手当の平均額に著しい差は見られません。会社の規模よりも、それぞれの企業が設ける賃金規程や福利厚生の考え方によって、支給額が決まることがわかります。
10万円が妥当かを判断するポイント
10万円という金額の妥当性を判断するには、次の3つのポイントをふまえることが大切です。
- 手当の内訳: 10万円に家賃補助や地域手当が含まれているか。
- 赴任先の地域: 赴任先の家賃や物価はどのくらいか。
- 課税の有無: 手当は課税対象か、手取り額はいくらになるか。
これらのポイントを総合的に見ることで、提示された金額の実質的な価値がはっきりします。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
エンゲージメント向上につながる福利厚生16選
多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。
本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。
令和に選ばれる福利厚生とは
本資料では、令和に選ばれている福利厚生制度とその理由を解説しております。
今1番選ばれている福利厚生制度が知りたいという方は必見です!
福利厚生 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)
福利厚生に関する就業規則の記載例資料です。 本資料には、一般的な就業規則も付属しております。
ダウンロード後、貴社の就業規則作成や見直しの参考としてご活用ください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
単身赴任手当10万円の主な内訳
「単身赴任手当10万円」の内訳は、生活費のみなのか、あるいは家賃補助など他の手当を含んだ合計額なのかで、意味合いが大きく異なります。
二重生活の負担を補う「基本手手当」
単身赴任手当の核となるのが、二重生活によって生じる追加の生活費を補うための基本的な手当です。家族と離れて暮らすことで、食費や光熱費、雑費などが余分にかかることへの配慮として支給されます。
相場である約5万円は、主にこの基本手当を指していると考えるとわかりやすいでしょう。
家賃負担を軽くする「住宅手当(家賃補助)」
二重生活で最も大きな経済的負担となるのが、赴任先での家賃です。この負担を軽減するために支給されるのが住宅手当です。支給形態には、おもに次の3つのパターンがあります。
- 定額支給: 赴任先の家賃に関わらず、毎月決まった金額が支給される。
- 割合支給: 実際の家賃の〇%を会社が補助する。
- 借り上げ社宅: 会社が法人契約で住居を借り上げ、従業員は一部の自己負担で住むことができる。
もし10万円の手当にこの住宅手当が含まれていない(たとえば、会社が住居を別に用意してくれる)のであれば、非常に恵まれた条件といえます。
逆に、10万円の中から全額家賃を支払う必要がある場合は、赴任先の家賃相場によっては生活が苦しくなる可能性も考えられます。
物価の高い地域で支給される「地域手当」
地域手当は、勤務地による物価の違いを調整するために支給される手当です。とくに東京や大阪などの大都市圏は、地方に比べて家賃や食費などの物価が高くなる傾向にあります。
この生活コストの差を埋め、従業員がどの地域に赴任しても公平な生活水準を保てるようにするのが、地域手当の役割です。
帰省の交通費を補助する「帰省手当」
家族との関係を維持するために、赴任先から自宅へ帰る際の交通費を補助する手当です。支給方法は会社によってさまざまで、「月1回分の往復交通費を実費で精算する」ケースや、「毎月一律で〇万円を支給する」といったケースがあります。
遠隔地への赴任になるほど、この手当の有無は大きな違いを生むでしょう。
単身赴任手当10万円を支給するための条件
単身赴任手当は、法律で定められた義務ではなく、あくまでも会社の福利厚生制度です。そのため、手当が支給されるかどうかは、会社が定める就業規則や賃金規程の条件を満たしているかによります。
会社の業務命令による転勤であること
支給の前提となるのは、会社からの正式な業務命令による転勤であることです。従業員自身の希望や都合で勤務地を変更する場合には、単身赴任手当の支給対象外となるのが一般的です。
家族と別居せざるを得ないやむを得ない理由があること
単身赴任手当は、家族と離れて二重生活を送ることへの経済的補助が目的です。そのため、帯同できない「やむを得ない理由」の存在が条件となります。
たとえば、以下のような理由が挙げられます。
- 子どもの学校や受験の問題で、転校が難しい。
- 持ち家があり、簡単に転居できない。
- 配偶者が仕事をしており、退職が困難である。
- 親の介護が必要で、現在の居住地を離れられない。
自宅から赴任先への通勤が困難であること
現在の住まいから新しい勤務先まで、公共交通機関などを利用して毎日通勤することが現実的に不可能であると会社が判断した場合も、支給条件となります。どのくらいの距離や時間を通勤困難とするかの基準は、それぞれの会社の規定によって定められています。
支給条件は就業規則の確認が必須
ここに挙げたのは一般的な条件であり、最終的には自社の就業規則や賃金規程にどう書かれているかがすべてです。赴任が決まった際には、まず自社のルールを確認し、不明な点があれば人事・総務部門に問い合わせることが、誤解や後のトラブルを防ぐためにもっとも大切です。
単身赴任手当が「もらえない」ケースとは
手厚い単身赴任手当ですが、転勤するすべての人がもらえるわけではありません。会社の規定によっては、支給条件から外れてしまうケースもあります。ここでは、手当が支給されない代表的な例を解説します。
本人が希望した転勤
会社の制度として、従業員のキャリア形成やスキルアップを目的とした「社内公募制度」や「自己申告制度」を設けている場合があります。こうした制度を利用して従業員自らが異動を希望し、転勤が決定した場合は、会社命令による転勤とは見なされず、単身赴任手当の対象外となることがほとんどです。
独身者の転勤
単身赴任手当は、家族との別居による「二重生活」の経済的負担を軽減することを目的としています。そのため、もともと一人暮らしをしている独身の従業員が転勤する場合は、二重生活にはあたらないため、支給の対象外となるのが一般的です。
ただし、会社によっては、転勤に伴う負担を考慮して、別途「転勤手当」や一時金などが支給されることもあります。
赴任先で家族が同居する
当然のことながら、転勤先の新しい住居に家族全員で引っ越す場合は、単身赴任には該当しません。この場合、単身赴任手当は支給されませんが、会社によっては家族の引っ越し費用や、新しい住居を探すための支度金などが支給されることがあります。
就業規則に手当の定めがない
単身赴任手当は、法律で支給が義務付けられているものではありません。あくまでも企業が任意で設ける福利厚生のひとつです。そのため、会社の就業規則や賃金規程に単身赴任手当に関する定めがなければ、たとえ単身赴任になったとしても手当は支給されません。中小企業などでは、制度自体が存在しないケースも少なくありません。
単身赴任手当があっても「家計が苦しい」と感じる理由と企業の対応
月額10万円という手厚い手当が支給されても、実際に生活してみると「思ったより家計が苦しい」と感じることがあります。その背景には、いくつかの見落としがちな理由が存在します。ここでは、その理由と、企業側の対応や個人でできる工夫について解説します。
理由①:都市部の家賃が高すぎる
家計を圧迫する最大の要因は、赴任先の家賃です。とくに東京23区や大阪、名古屋といった大都市圏では、ワンルームや1Kの単身者向け物件でも家賃が8万円から10万円以上になることは珍しくありません。
もし支給される10万円の手当に家賃補助が含まれている場合、家賃を支払うだけで手当のほとんどが消えてしまうことになります。そうなると、二重生活で増えるはずの光熱費や食費を、自己資金から捻出しなければならず、家計が苦しくなるのは当然といえるでしょう。
理由②:手当は「課税対象」で手取りが減る
見落としがちなのが税金の問題です。単身赴任手当は、原則として給与所得の一部と見なされるため、所得税と住民税の課税対象となります。ただし、帰省旅費や赴任先の引越費用など実費弁償的な性質を持つ部分については、一定の条件下で非課税となる場合もあります。
つまり、額面の10万円がそのまま銀行口座に振り込まれるわけではありません。課税対象となる部分については、所得税率にもよりますが、おおよそ1割から2割程度が税金として天引きされると考えると、手取り額は想定より少なくなる可能性があります。
この「額面」と「手取り」の差を認識しておかないと、資金計画に狂いが生じることになります。
理由③:見えないコストの積み重ね
単身赴任では、家賃以外にもさまざまな「見えないコスト」が積み重なります。
これらの細かい出費が積み重なり、手当だけでは賄いきれずに家計を圧迫する原因となります。
企業の対応と働き手の工夫
企業側も、こうした従業員の負担を軽減するために、さまざまな制度を用意している場合があります。たとえば、家賃負担を抑えるための「借り上げ社宅制度」は、多くの企業で導入されています。
また、住宅取得を支援するための「住宅資金融資制度」を設けている企業もあります。厚生労働省の「令和6年 就労条件総合調査の概況」によると、常用労働者30人以上の企業のうち3.4%がこの制度を導入しています。
とくに1,000人以上の大企業では21.1%が導入しており、こうした制度の有無を確認するのもよいでしょう。
働き手としては、赴任前に自社の福利厚生制度を隅々まで確認し、利用できる制度は最大限活用することが大切です。人事・総務部門に相談し、手当の内訳や社宅制度の有無、その他に利用できるサポートがないかを確認することで、経済的な不安を少しでも和らげることができるはずです。
単身赴任手当の10万円は総合的に判断する
単身赴任手当として月額10万円が支給される場合、それは相場から見ると高水準ではあるものの、「妥当かどうか」は一律に判断できるものではありません。
手当に住宅補助や地域手当、帰省費用などが含まれているか、また赴任先の物価や家賃水準、課税による手取りの減少など、複数の要素を総合的に見る必要があります。
制度上は福利厚生であり、就業規則に明記された条件を満たして初めて支給対象となるため、額面だけで判断せず、中身の内訳や自分の勤務条件、生活環境と照らし合わせて検討することが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
報酬制度とは?目的や種類、インセンティブとの違いから設計・管理方法まで徹底解説
報酬制度は、従業員のモチベーション向上、優秀な人材の確保・定着を左右する、企業の経営戦略と密接に連動し、その実現を支える基盤となる、極めて重要な人事制度です。 本記事では、人事労務の担当者が知っておくべき報酬制度の基本的な意味から、その目的…
詳しくみる【社労士監修】労働基準法施行規則第18条とは?有害業務の具体例や罰則、判例をわかりやすく解説
労働基準法施行規則第18条は、一定の危険性や健康への悪影響が懸念される「有害業務」について、1日あたりの残業時間に制限を設けた規定です。企業が労働時間を延長する際、対象業務によっては上限が厳しく管理されなければなりません。 本記事では、労働…
詳しくみる労働契約とは?雇用契約との違いや締結ルール、契約書の書き方まで解説!
労働契約は労働者と会社との間で交わす、労働や賃金についての契約です。雇用契約と同じとして取り扱われ、労働契約書と雇用契約書のどちらかの名称で契約書が作成・交付されます。労働基準法と労働契約法に則って、変更や更新、終了についてルールが定められ…
詳しくみるアカハラとは?アカデミックハラスメントの具体例や対策、大学での事例
アカハラはアカデミックハラスメントで、大学などの教育機関、研究機関で起きるハラスメントのことをいいます。パワハラの一種で、立場の違いから権力が強い人が弱い人に対して、嫌がらせなどの不快にさせる行為です。具体的には学習や研究を妨害したり、卒業…
詳しくみる労使協定方式の締結方法とは?派遣先均等・均衡方式の違いとあわせて解説
派遣労働者の同一労働同一賃金に対応するため、労使協定方式の導入を検討している人もいるでしょう。 しかし労使協定を締結する際に必要な情報を把握していなければ、派遣労働者に対して適切な労働環境を提供していないとみなされる可能性があります。 労使…
詳しくみる労働者名簿は一覧形式でも問題ない?無料テンプレートも
労働者名簿は、一覧形式で作成しても問題ありません。労働基準法には労働者名簿の様式についての具体的な指定がないため、必要な情報がすべて記載されていれば、1人1枚の形式でも一覧形式でも構いません。 ただし、一覧形式にする際にはいくつかの注意が必…
詳しくみる
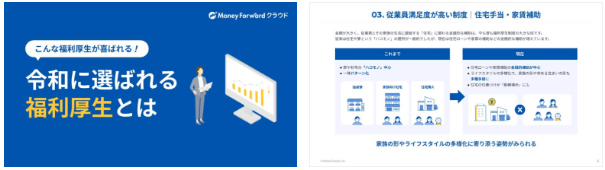
.jpg)
