- 更新日 : 2025年11月13日
怒鳴るのはパワハラ?適切な指導との違いや対処方法を解説
仕事で指導をしたものの、何らかの理由で怒りの感情をコントロールできなくなり、結果的にパワハラに該当してしまったケースもあるようです。
本記事では、職場で怒鳴ったことでパワハラとなる事例を交えながら、適切な対処法について解説します。
目次
怒鳴るのはパワハラ?
パワハラとは、次の3つの要素を全て満たす言動を指します。
- 優越的な関係を背景としている
⇒ 行為者に対して抵抗したり拒絶したりすることができない場合
職位の上下だけに限りません。職位の上下だけでなく、専門スキルの高さなども該当する場合がある - 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
⇒ 業務上の必要性がなく、かつ、仕事の上のものとしては度を越した状態
同じことをしつこく繰り返すなどの場合も行き過ぎた行為とみなされる - 就業環境が害されている
⇒ 言動によって身体的・精神的苦痛を受け、就業に支障がきたす状態
怒鳴るという行為は、一般的に業務上の必要性がなく、業務にふさわしい行動でもありません。多くの場合、相手を威嚇する目的となっているため、相手への精神的な攻撃となり、就業環境が害される可能性が生じます。このような観点から考えてみると、パワハラに該当する可能性が高いと言えるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
パワハラの判断基準と実務対応
従業員からパワハラの相談を受けた際、適切な調査方法や判断基準がわからず、対応に苦慮している企業は少なくありません。
本資料では実際の裁判例も交えながら、パワハラの判断方法と対応手順を弁護士が解説します。
ハラスメント調査報告書(ワード)
本資料は、「ハラスメント調査報告書」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご利用いただけます。
ぜひ貴社のハラスメント調査における報告書作成の実務にご活用ください。
パワハラのNGワード&言い換えまとめ
職場におけるパワーハラスメント防止対策は進んでいますでしょうか?本資料は、「パワハラのNGワード」と、その「言い換え」についてまとめた資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社のハラスメント対策やコミュニケーションの参考としてご活用ください。
怒鳴るのがパワハラと認定された事例
ここでは、部下を怒鳴る行為がパワハラに該当すると認定された事例を紹介します。
【名古屋地判(2014(平成26)年1月15日)】
設備や機械を損傷するミスが重なった従業員に対し、上司が「ばかやろう」「どうしてくれるんだ」などと怒鳴ったうえ、損害を家族で弁償する旨を記載した退職願を強制的に書かせたケース。
⇒判決では、怒鳴る行為は、仕事上のミスに対する叱責の範囲を超えており、パワハラに該当すると認定。退職願についても不法行為であると認定した。
仮に従業員に問題があった場合でも、人格を否定するような言動はパワハラです。
怒鳴るパワハラと業務上の適切な指導の違い
指導のつもりで怒鳴っても、それが少しも指導にならないのは、指導の目的を見失い、自分の感情を制御できていないことの表れです。ここでは、怒鳴るという行為と、適切な指導の違いについて解説します。
「怒鳴るパワハラ」は業務上の必要性や相当性の範囲を超えている
怒鳴るパワハラとは、職場での優越的な立場を利用して、業務上の必要性や相当性を超えて大声で相手を圧迫し、精神的、身体的な苦痛を与えるなど仕事に支障をきたすといった行為です。5分、10分という長時間にわたって怒鳴り続ける、同じことを繰り返し大声で張り上げる行為は、パワハラと認定される可能性が高いと考えられます。
「指導」は客観的な事実を指摘し、具体的な改善方法を伝える
「指導」とは、相手の成長を支援するためのものです。どこでミスをしたのか、なぜそれが誤りなのかといった事実を確認し、その改善策を的確に伝えるからこそ、指導の効果が見られるのです。
医療現場や工事現場など小さなミスが命取りになるところでは、時には厳しい指摘・指導や物言いがあってもやむを得ないとの判例もあります。
怒鳴られた場合の対処法
被害者の業務や人間性に問題がある場合でも、人格を否定するような言動はパワハラに該当します。ここでは怒鳴られた場合にしておきたい対処法を解説します。
原因を確認して自分の態度を振り返る
怒鳴られることには何かしらの理由があると考えられます。例えば、あってはならないような重大なミスを犯したとか、同じようなミスを繰り返していながら少しも改善を図る努力をしていない、または自分自身に課題がある場合などです。まずは、仕事の進め方や仕事に対する姿勢を反省してみることも不可欠です。
証拠を記録しておく
怒鳴られる理由に心当たりがない場合、犯したミスに対し過剰な怒鳴り方の場合、何かにつけて頻繁に怒鳴られる場合などは、パワハラの兆候かもしれません。どのような理由でどんなことを言われたのかを、できるだけ詳しく記載し、日付、時刻、場所、その時に人物について記録しておきましょう。可能であればスマートフォンを使って音声なども記録しておくと効果的です。
人事や各窓口に相談する
怒鳴られることが繰り返されるようであれば、証拠になるものをそろえたうえで、パワハラ相談窓口または人事セクションに相談しましょう。相談を先送りしてしまうと、相手の行動がエスカレートするリスクが高くなります。なお、強い苦痛を与えるような怒鳴り方であれば、1回だけであっても就業環境を害する行為と判断されるでしょう。
落ち着いた言葉遣いは説得力を持つ!
人材育成に適切な指導が不可欠です。しかし、その指導が行き過ぎて怒鳴ってしまい、パワハラと認定されるようでは本末転倒です。自身の安全確保のために大声を出す場合や、事の重大さを理解させるために口調を強めるといった場合を除き、指導の際には怒鳴らないよう相手が納得できる話し方を心がけることが重要です。パワハラに関する3要素や6類型について十分理解することが求められます。パワハラと誤解されることがないよう、冷静かつ落ち着いた言葉遣いを意識し、相手をどう支援していくか考えてみてはいかがでしょうか。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
正社員の雇用契約書は義務ではない!作成方法や注意点を解説
「雇用契約書ってどうやって作成すればいいんだろう?」「必須の記載事項が何かわからない…」 はじめて雇用契約書を作成する際、上記の疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。…
詳しくみるパワハラで内部通報制度の利用があったらどうする?匿名や退職後のケースについても解説
公益通報者保護法の改正により、アルバイト、派遣労働者、契約社員なども含め常時301人以上の労働者を使用する企業には内部公益通報制度の整備が義務付けられました。 本記事では、内部通報…
詳しくみるシャドーITとは?セキュリティリスクや原因、企業の対策について解説
シャドーITとは、企業内での利用が認められていないITサービスやIT機器を無断で使用することです。これらのサービスやIT機器は適切に管理されない傾向にあり、セキュリティ上のリスクに…
詳しくみるその社宅管理、本当に最適?フローの見直し方法を理解してコストと手間を削減しよう
「うちの社宅管理、もっと効率化できないかな?」「コストや手間がかかりすぎている気がする…」と感じていませんか。社宅管理の業務フローは一度決めたまま見直さず、非効率な状態になっている…
詳しくみる社員管理とは?メリットや課題、導入事例から成功ポイントまで徹底解説
社員管理は、働き方が多様化する現代企業において重要性が増しています。特に、リモートワークの普及や労働環境の多様化に伴い、社員の勤務状況や健康状態、モチベーションなどを適切に把握・管…
詳しくみるサテライトオフィスとは?メリット・デメリットや利点を解説
テレワークやリモートワークなど、出社を要しない新しい働き方もすっかり定着しています。そのような中で注目されているのが、「サテライトオフィス」です。 当記事では、サテライトオフィスに…
詳しくみる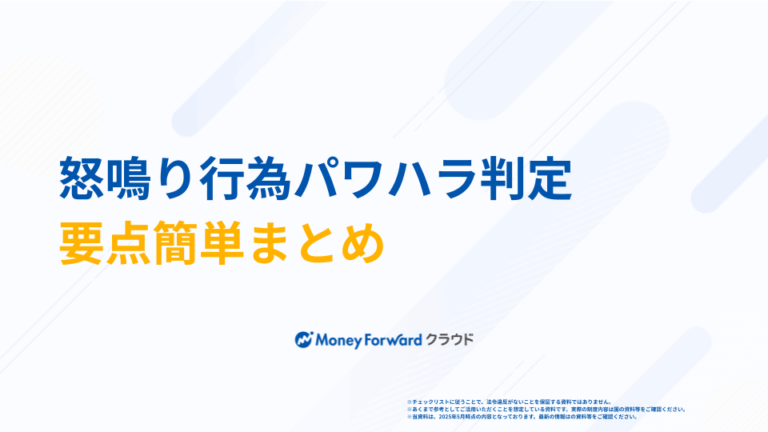


-e1762259162141.png)
