- 更新日 : 2025年11月18日
調整手当とは?目的や種類・支給パターンを解説
調整手当とは、企業が従業員の給与バランスを保つために支給する給与の一部です。通常は一時的ですが、固定給の一部として継続的に支給されることもあり、初任給や基本給が低い場合に使用されます。公務員や教員にも適用されます。
本記事では、調整手当がどのようなものなのか、目的や種類、支給パターンなどについて解説します。
目次
調整手当とは?
調整手当とは、企業が従業員に対して特定の状況下で支給する給与の一部です。従業員間の給与バランスを適正に保つ目的があるため、調整給とも呼ばれます。
調整手当は通常、一時的なものであるケースが多いです。しかし実際には、固定給の一部のように継続的に支給されることがよくあります。このような状況が続くと、給与査定の基準が不明確になり、社員のモチベーションが低下する原因にもなりかねません。したがって、調整手当は可能な限り発生させないことが理想的です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
従業員の賃上げに潜むリスクと、企業が打つべき対策
人手不足や物価上昇などを背景に、賃上げが企業経営の重要テーマとなっています。しかし、賃上げには様々なリスクを伴います。
本資料では、企業が賃上げを進める際に注意すべきリスクと対策について解説します。
住宅手当申請書(ワード)
住宅手当の申請にご利用いただけるテンプレートです。 Wordファイル形式のため、直接入力や編集が可能です。
ダウンロード後、必要事項をご記入の上、申請手続きにお役立てください。
休業手当の計算シート(エクセル)
休業手当の計算にご利用いただける、Excel形式の計算シートです。
Excelファイル形式のため、ダウンロード後自由にご使用いただけます。 業務での休業手当の計算を行う際にお役立てください。
割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)
割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。
本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。
調整手当の目的
調整手当を支給する目的は、以下のとおりです。
- 従業員満足度の向上
- 給与の増減の防止
- 人事制度の改定があった場合
- 従業員の給与バランスの維持
ただし、具体的な支給のケースや調整手当の種類、注意点などは企業ごとに異なるため、詳細は各企業の人事部門に確認が必要です。以下で、それぞれの内容を解説します。
従業員満足度の向上
調整手当は、従業員が自身の給与に満足感を持つための一助となります。特に、他の従業員と比較して自分の給与が不適切であると感じた場合や、前職の給与と比較して不利益を被っていると感じた場合には、調整手当がその不満を解消する役割を果たすでしょう。その結果、従業員の満足度を向上させ、組織へのコミットメントを高める効果が期待できます。
給与の増減の防止
給与の大幅な増減を防ぐ役割も果たすことも、調整手当の目的の1つです。例えば、組織内での役職変更や人事異動により、基本給が大幅に下がる可能性がある場合、調整手当を用いて給与の大幅な減少を防げます。従業員の生活水準の維持や、モチベーションの維持につなげることが可能です。
人事制度の改定があった場合
人事制度の改定にともない、給与体系が変更されることがあります。その際、新しい給与体系により従業員の給与が大幅に下がる可能性がある場合、調整手当を用いて給与の大幅な減少を防ぐことが可能です。給与改正などによる従業員からの不満を、抑制する効果が期待できます。
従業員の給与バランスの維持
調整手当は、組織内の給与バランスを維持するためにも用いられます。すべての従業員が同じ仕事をしているわけではないため、給与に差が出るのは普通です。しかしその差が大きすぎる場合、組織内での不公平感を生む可能性があります。そのため、調整手当を用いて給与のバランスを調整します。組織内の公平感を維持し、従業員のモチベーションを維持することが期待できるでしょう。
調整手当の種類
調整手当にはさまざまな種類があり、目的に応じて使い分けられます。ここでは、おもな調整手当の種類をご紹介します。
生活費調整手当
生活費調整手当は、従業員の生活水準を維持するために支給されます。物価や住居費が高い地域で働く従業員に対して、生活費の安い地域で働く従業員と同じ生活水準を保てるようにするための手当です。従業員が生活する地域の物価指数や、家賃相場などを考慮に入れて計算されます。従業員は生活費の高い地域でも安心して働けるようになるでしょう。
能力給調整手当
能力給調整手当は、従業員のスキルや成果に応じて変動する手当です。従業員のモチベーション維持や能力向上を促す目的で支給され、高いパフォーマンスを発揮した従業員には、手当が増額することもあります。従業員のスキルセットや経験、業績などを評価し、それに応じて支給額が決定される点が特徴です。従業員は、自身のスキルアップや成果に応じた報酬を得られます。
地域調整手当
地域調整手当は、同じ企業や自治体で働く従業員が、勤務する地域の生活費を調整するために支給されるものです。地域ごとの生活費の違いを補うものであり、地域の物価や生活環境に応じて変動します。地域間での生活費の差を補い、従業員が公平に働ける環境を提供します。
看護師の調整手当
医療分野では、他の産業分野に比べて賃上げが追いついていない状況です。そのため、処遇改善を行い、看護職員の定着を図る必要があります。2024年度の診療報酬改定では、看護師をはじめとする医療関係従事者に対する調整手当として、処遇改善加算(ベースアップ評価料)が新設されました。
ベースアップ評価料は、賃上げ(ベースアップ)が目的です。2024年度に2.5%、2025年度には2.0%の賃金上昇を行なうために必要な特例対応として、訪問看護ステーション職員の賃金を改善する場合に算定可能となっています。
保育士の調整手当
保育士の調整手当は、保育士の給与を向上させるために国や自治体が提供する補助金のことです。正式には「保育士処遇改善加算」と呼ばれています。
2013年から認可保育園を対象に実施されており、具体的には職員の平均勤続年数に応じて給料が上がる「処遇改善加算Ⅰ」、所定の役職についた場合の「処遇改善加算Ⅱ」、2022年2月から期間限定で9,000円が上乗せされる「処遇改善加算Ⅲ」の3種類です。
補助金は保育士ではなく保育園に支給され、分配方法は園ごとに異なります。ただし認可保育園のみが対象で、認可外保育園や他の保育施設は対象外です。
介護士の調整手当
介護職員の待遇改善を図るための調整手当として、介護職員処遇改善加算の制度が設けられています。
加算はⅠからⅢまでの3つの区分が設けられており、それぞれの区分に応じて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすことが必要です。最大となる加算Ⅰでは、介護職員ひとり当たり月額37,000円相当が支給されます。
国家公務員の地域手当
国家公務員の地域手当は、地域の物価や民間賃金水準を補填するための手当で、首都圏や都市部など物価が高い地域で働く公務員に支給されます。
支給額は「俸給+特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当」の月額に支給割合を乗じて算出され、支給割合は地域ごとに異なります(1級地20%、2級地16%、3級地15%、4級地12%、5級地10%、6級地6%、7級地3%)。
地域手当は6ヶ月以上勤務する条件を満たすと、異動後も3年間保証され、ボーナスにも影響するのが特徴です。
地方公務員の地域手当
地方公務員の地域手当は、特定の地域で働く公務員に対して、地域の物価や民間企業の賃金水準などの生活コストの差を補填するために支給される手当です。
全国の市区町村1,724のうち、約23.5%の405市区町村が該当します。計算方法は「地域手当=(基本給+管理職手当など+扶養手当)×支給率」で、支給率は地域によって異なり、最高は東京23区の20%です。
調整手当の支給パターン
調整手当の支給パターンは、おもに以下の3つです。
- 固定給に組み込まれる
- 不定期に変動して支給
- 特定の条件を満たした場合のみ支給
それぞれのパターンを、以下で解説します。
固定給に組み込まれる
調整手当を、従業員の固定給の一部として組み込むパターンがあります。
毎月の給与として支払われ、給与明細に明記されることが一般的です。従業員が毎月受け取る給与額を予測しやすい点がメリットです。
不定期に変動して支給
業績や季節性など、特定の要因に基づいて変動した調整手当が支給されるパターンもあります。
企業が経済状況や業績に応じて給与を調整できる柔軟性があるのは、このパターンのメリットだといえるでしょう。
特定の条件を満たした場合のみ支給
特定の目標を達成したり、特定のプロジェクトを完了したりした場合など、調整手当が特定の条件を満たした場合にのみ支給されるパターンがあります。
従業員のパフォーマンスを奨励し、目標達成に向けた動機付けを提供する点が特徴です。
調整手当の具体例
調整手当は、具体的にどのような形で支給されるのでしょうか。ここでは、調整手当の具体例を3つご紹介します。
生活費調整手当
生活費調整手当は、従業員が勤務する地域ごとの生活費の差額を補助するために支給されます。物価の高い地域で勤務する従業員に対して支給されます。生活費調整手当の支給により、物価の高い地域に転勤することになっても、従前の生活水準の維持が可能です。
能力給調整手当
採用直後の従業員に対して、基本給を抑える目的で、能力給調整手当が支給される場合もあります。手当を支給することで、基本給を抑えつつ、能力やスキルに応じた柔軟な給与変動が可能となります。
地域調整手当
地域調整手当は、地域による給与差を調整する目的で支給される手当です。遠隔地への転勤に対して支給される場合もあります。また、積雪地帯への異動に対して支給される寒冷手当なども地域調整手当の一種です。
調整手当の計算方法
調整手当の計算方法は、従業員の職位、能力、経験、勤務地に基づいて異なります。例えば、役職や特定のスキル・資格、業務経験年数、勤務地の生活費が考慮されることが一般的です。
ただし、これらの要素は企業の内部ポリシーや市場の動向、地域の生活費に基づいて設定されるため、具体的な計算方法は企業ごとに異なります。詳細な計算方法については、各企業の人事部門や、労働基準監督署に確認しましょう。
調整手当の一般的な金額
調整手当は、企業の人事戦略や給与体系により大きく異なるため、具体的な金額を一概にはいえません。それぞれの企業で、従業員の能力や業績、役職などを考慮して決定されます。
そのため、具体的な金額についても、企業や業種、地域などにより大きく異なります。一部の業界では、各手当が数千円から数万円が一般的です。また、例えば基本給が18万円だった場合でも、調整手当が22万円ついていた場合には、合計で40万円の給与が支給されることもあるでしょう。
調整手当を支給するまでの手続き
従業員に調整手当を支給するためには、一定の手続きが必要です。以下で具体的な内容を確認しておきましょう。
① 支給の条件・要件を定める
調整手当を支給する場合には、支給条件を明確にしなければなりません。曖昧な支給基準では、従業員間で不公平感が生まれてしまいます。
雇用形態や役職、勤務地、経済情勢の変動度合いなど、明確な支給条件を定め、就業規則などに明記しましょう。
② 調整手当の管理体制を整える
調整手当を適切に管理するためには、以下2つのポイントを考慮することが必要です。
- 給与査定基準の更新
- 調整給の運用方法
給与査定基準を妥当なものに更新し、調整手当が必要かどうかを見極めなくてはなりません。従業員の役割や業績評価を考慮して、給与の適正性を判断しましょう。
また、調整給を残すケースとなくすケースを検討し、社員の納得度と成長につながる給与体系を示すことも必要です。透明性を高め、社員とのコミュニケーションを深める必要があります。
③ 必要であればソフトウェアやサービスを検討する
調整手当の管理には、必要に応じてソフトウェアやサービスの活用も考慮しなくてはなりません。ただし、選択するツールは組織のニーズに合ったものを選ぶことが大切です。
例えば、給与計算ソフトウェアや人事管理システムを導入することで、効率的な管理を実現できます。
調整手当を支給する上でのポイント
調整手当を支給する際には、いくつかのポイントを押さえなくてはなりません。以下で、おもなポイントをご紹介します。
初任給での調整手当の支給はOK?
初任給での調整手当の支給は、一般的には避けるべきです。初任給は基本的に経験や実績が少ない段階であり、給与のバランスを調整するために調整手当を支給することは、ほぼありません。
給与査定基準を妥当なものに更新し、初任給での調整手当の必要性を見極めることが重要です。
基本給の低さを調整手当でカバーするケース
基本給が低い場合、調整手当を活用して給与バランスを調整することがあります。
ただし、基本給が最低賃金を下回らないように注意が必要です。調整手当は一時的なものであるべきですが、適切な運用を行い、給与査定基準を透明に保つことが大切です。
調整手当で最低賃金をクリアするケース
調整手当を活用して最低賃金をクリアするケースもあります。最低賃金を下回る給与を受けている従業員に対して、調整手当を支給してバランスを取ることで、最低賃金法を遵守できます。
ただし、適切な運用と透明性を保つことが重要です。
自社に適した調整手当制度を構築することが重要
調整手当は、企業が従業員に特定の状況下で支給する給与の一部で、給与バランスを適正に保つためのものです。通常は一時的ですが、固定給の一部として継続的に支給されることもあります。
調整手当の目的は、従業員満足度の向上、給与の増減の防止、人事制度改定時の給与減少防止、給与バランスの維持などです。支給パターンは固定給に組み込む、不定期に変動して支給、特定の条件を満たした場合に支給の3つがあります。具体例として、時間外労働手当、休日出勤手当、深夜労働手当があり、支給の手続きには、条件設定、管理体制の整備、適切なツールの導入が必要です。
本記事の内容を参考に、適切な調整手当の制度構築をしてもらえれば何よりです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
賃金台帳に賞与は記載する?記入例やテンプレートを紹介
労働基準法第108条にもとづき、賃金台帳には従業員の賞与を記載しなければいけません。 従業員が働きやすい環境に整えるためにも、必要な項目を記載した賃金台帳の作成が重要です。 本記事…
詳しくみる【未払い時の対応リスト付】給料は何時に振り込まれる?土日の扱いや退職後を解説
給料が口座に反映される時間は、金融機関により異なりますが「支給日当日の午前0時から午前10時頃」が一般的です。これは銀行のシステム(全銀システム)や企業側の振込手続きの方法によって…
詳しくみる定額減税で手取りが増える?いくら増えるかを解説
近年物価の上昇が続いており、国民の生活は厳しいものとなっています。賃上げを行う企業も多く見られますが、それでも物価の上昇は大きな負担となっており、対策が必要です。 当記事では、物価…
詳しくみる【図解】住民税決定通知書とは?入手方法や見方、再発行について解説
地方税である住民税では、自治体から毎年5〜6月頃に「住民税決定通知書」が交付されます。普通徴収は納税者の自宅宛に、特別徴収は納税者が勤める会社宛に、納付書と合わせて送付されます。 …
詳しくみる【給与計算シート付】産休中の給与は?計算方法や社会保険料の控除を解説
産前や産後、育児中は、業務を行うことが困難です。そのため、公的な休業制度を定めることで、母体の保護や子育て支援が行われています。また、休業中の給与は社会保険料等の扱いについて、特別…
詳しくみる年金払い退職給付とは?公務員が押さえておくべき制度を解説
公務員は平成27年9月末で共済年金の職域加算部分が廃止になり、平成27年10月から新たな公務員共済制度年金の「年金払い退職給付」が創設されました。 この年金払い退職給付には「退職年…
詳しくみる
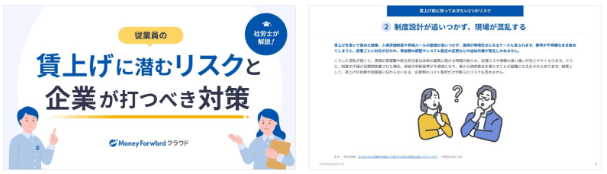
-e1763436002347.jpg)
-e1763436316712.jpg)
.png)