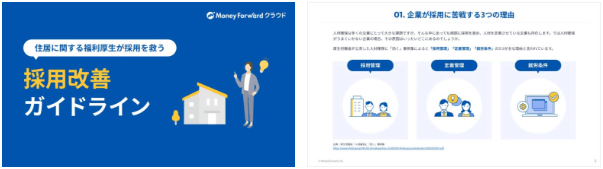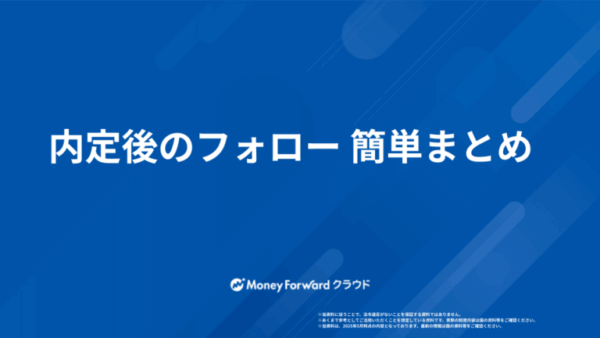- 更新日 : 2025年2月3日
入社手続きは電子化すれば効率化できる!書類の電子化や電子申請の流れを解説
多くの書面を使用する入社手続きは、電子化することで効率が良くなります。紙書類のやり取りと比べ、郵送や印刷、人件費などのコスト削減につながるためです。ただし電子化には、気をつけるべき事項もあります。
本記事では、電子化できる入社手続き例、電子化のメリットや注意点、電子契約や電子申請の導入方法などについて紹介します。
目次
入社手続きは電子化できる
以前は紙の書類で行われていた入社手続きですが、近年、急速に電子化が進みました。電子化が進んだ背景と、電子化可能な入社手続きについてみていきましょう。
電子化が進む背景
電子化が進んだ理由の一つに、コロナ禍によるテレワークの増加が挙げられます。
テレワーク下では、紙書類の受け渡し手段は主に郵送でした。しかし郵送は時間がかかるうえ、コスト面でも効率が悪かったため、PCで作成した書類をメール送信したり、クラウド上でやり取りしたりする「電子化」に注目が集まりました。
この方法は郵送コストや印刷コストがかからず、書類の授受も瞬時に行えるなどメリットが多かったため、多くの企業が導入し、書類の電子化が急速に進みました。
更に、2021年に改正された電子帳簿保存法が、会計書類の電子化を推奨、一部を義務化したことも、書類電子化の普及を後押ししています。
電子化が可能な入社手続き
従業員の入社時には、多くの書類がやり取りされます。そのうち電子化が可能な書類には、どのようなものがあるでしょうか。
入社前に提出してもらう書類としては、入社誓約書や扶養控除等申告書が挙げられます。また雇用保険被保険者番号や個人番号などのデータも、事前に取得しておく必要があるでしょう。
入社前に提出する書類は、従業員が自宅PCなどで作成し、メールやクラウドを利用して会社に提出します。また労務管理システムを使用している会社では、新入社員にパスワードを渡し、システムに直接入力してもらう方法もあるでしょう。
会社が入社予定者に渡す書類には、内定通知書や労働条件通知書などがあります。こうした書類は、メールに添付して送信できます。また電子契約書として授受することも可能です。
入社後の社会保険手続きも電子化されています。具体的には、雇用保険被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届などの届書は、電子申請できます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
入社手続きを電子化するメリット・注意点
入社手続きを電子化する会社が増えています。入社手続きの電子化には、どのようなメリットがあるのでしょうか。注意点もあわせて説明しましょう。
メリット
入社手続きを電子化するメリットとしては「効率が良い」「コスト面で優れている」「セキュリティ上の問題が軽減される」などが挙げられます。
効率が良い
入社時の手続きでは、氏名や生年月日、住所など、同じ情報が繰り返し使われます。紙書類の場合は、手続きごとに逐一書き込まなければなりませんが、電子化すれば入力頻度はずっと低く済み、効率良く書類が作成できるでしょう。
コスト面で優れている
入社手続きを電子化すれば、郵送や移動、印刷などのコストが削減できます。社会保険手続きの郵送申請では返信用の封筒も同封するため、郵送コストは軽視できません。また、電子情報を保存することにより、書類の保管場所を取らないこともメリットです。
セキュリティ上の問題が軽減される
紙書類の場合、郵送・保存の過程において、盗難や紛失のリスクをゼロにはできません。しかし電子データのやり取りであれば、適切なセキュリティ対策を講じることにより、リスクを大幅に軽減できるでしょう。
注意点
入社書類を電子化するときの注意点としては、「システムの導入に費用がかかる」「適切なデータ管理が必要」といったことが挙げられます。
システムの導入に費用がかかる
電子化のために労務管理システムやソフトウェアを導入すると、一定の費用がかかります。
労務管理システムには、雇用保険や社会保険手続きができるもの、給与計算機能があるものなど多くの種類がありますが、搭載されている機能によって導入費用が変わってくるでしょう。自社の人数やニーズに合致したシステムを選定することが重要です。
適切なデータ管理が必要
入社手続きを電子化すると、電子契約書や電子申請の決定通知書などの電子データを扱う機会が増加します。
紙の書類に比べ、電子データは劣化や焼失などの危険がない一方、消失や情報漏えいのリスクは、むしろ高いといえるでしょう。
こうしたリスクを回避するには、定期的にバックアップを取る、アクセス権を適正に管理するなどの工夫が必要です。
入社手続きを電子化する方法
従来は紙の書類を使っていた入社手続きですが、電子化する会社が増えてきました。ここでは、入社手続きを電子化する方法について説明します。
労務管理・電子契約のシステムを導入する
労務管理システムや電子契約システムを選定し、導入します。
労務管理システムとは、従業員の生年月日や住所などの管理、マイナンバーの管理、社会保険手続きなどを行うシステムです。
労働者名簿の調整や年次有給休暇の管理なども可能で、システムによっては給与計算機能を持つものもあります。
電子契約システムとは、インターネット回線を使用し、電子ファイルに電子署名やタイムスタンプを記録して契約を締結するものです。
電子契約システムを使用すれば、書類を一旦紙に印刷して捺印するといった手間がかからず、電子データに直接、電子署名が付されます。
電子申請を利用する
社会保険の手続きには、e-Gov(イーガブ)というシステムを使います。e-Govとは、インターネット上に設置されている行政の窓口で、現在はデジタル庁が運営しているものです。
e-Govの電子申請機能を利用すれば、労働保険や社会保険の手続きをオンラインで24時間・365日行うことが可能です。なおe-Govは無料で利用できます。
労務管理システムによってはe-Govと連携しているものもあり、そうしたシステムを利用すれば、より効率良く申請ができます。
なお、労務管理システムを使用しなくても、電子申請自体は可能です。
入社書類を電子化する流れ
入社手続きを電子化するには、どのような準備をすればよいのでしょうか。ここでは、主に電子契約システム導入の流れについて説明します。
電子化の同意を得る
入社書類を電子化する場合、書類によっては、事前に入社する従業員の同意が必要です。
従来は書面での交付が義務づけられていた労働条件通知書ですが、2019年からファクシミリや電子メールなどを使って交付できるようになりました。ただし電子メール等での交付には従業員の同意を要するため、事前に同意を取っておきます。
電子契約システムを利用する場合も同様に、従業員の事前同意が必要です。
締結手続きを行う
まず、労働契約書などの書類を準備します。PDF化した書類をアップロードすることもできますが、電子契約システムによっては、オンラインで書類を作成できることもあります。
書類を作成したら、記載事項をよく確認しましょう。
書類をクラウド上にアップロードした上で、入社従業員に対して、電子署名をするよう依頼します。このとき入社従業員には、その旨のメールが送られます。
入社従業員がオンラインで書面の内容に同意すると、書類に電子署名が記され,、契約が締結される仕組みです。
適切に保存する
関係者の電子署名が終わったら、電子契約書が完成します。この電子契約書は、法定保存期間に従い、適切に保存します。後で検索しやすいよう、フォルダを整理した上でファイル名も統一しておくとよいでしょう。
社会保険・労働保険の手続きを電子申請する流れ
入社に伴う社会保険手続きは、e-Gov(政府が設置したインターネット上の窓口)を通じて電子申請できます。ここではe-Govを使った社会保険手続きの方法について、順に説明します。
e-Govの事前準備をする
初めてe-Govを利用する場合は、次の事前準備が必要です。
- 電子申請に必要な電子証明書やアカウントを準備する
- e-Govアプリをインストールする
アカウントとしては、e-GovアカウントやGビズIDなどが利用できます。またe-Govアプリは、e-Govのサイトからインストールデータを取得できます。
入社手続きを迅速に進めるために、こうした事前準備は余裕をもって済ませておきましょう。
e-Govから電子申請を行う
従業員が入社したら、e-Govで電子申請を行います。入社日前にあらかじめ電子申請書類を作成し、e-Gov内に一時保存しておくことも可能です。
なお、日本年金機構が無償配布している届出作成プログラムを使用すると、電子申請に添付するファイルを簡単に作成できます。
また、e-Govに連携している労務管理システムを利用すれば、より容易に電子申請ができるでしょう。
公文書をダウンロードする
電子申請後には「健康保険・厚生年金保険資格取得確認通知書」「雇用保険被保険者証」などの公文書が交付されます。公文書はe-Gov画面からダウンロードが可能です。
ダウンロードした電子公文書は、会社で適正に保管します。「雇用保険被保険者証」などはすみやかに従業員に交付しましょう。
なお申請書類に不備やあったり、添付資料に不足があるときは、行政官庁から補正通知書が届きます。その場合は指示に従って再申請する流れになります。
電子化で入社手続きは効率化できる
入社手続きの電子化とは、従来、紙で行っていた書類の受け渡しや行政手続きを、オンラインで行うことです。多くの書類を必要とする入社手続きは、紙の書類で行うとコストや時間がかかりますが、電子化することにより、郵送・移動・手間・保管場所などの大幅な削減が可能です。
電子化には、パソコンで作成した入社書類をメール添付で送信するほか、労務管理システム、電子契約システム、電子申請システム(e-Gov)などを利用する方法があります。労務管理システムや電子契約システムの中は、提供会社により利用料が異なるため、自社の人数やニーズに合致したシステムを選定することが重要です。
電子化を推進して、入社手続きの効率化を考えてみてはいかがでしょうか。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
テレワークの通勤手当は不要?社会保険料の計算や在宅手当の注意点
テレワークの普及にともない、通勤手当をどうするか見直しが課題となっています。通勤手当を廃止してもよいのか、在宅手当を支給すべきか、在宅勤務と出社が混在する場合はどう支給すべきか、判断に迷うこともあるでしょう。 通勤手当の見直しは可能ですが、…
詳しくみる配置転換を拒否できる正当な理由とは?退職勧告やパワハラの対処法、企業側の注意点も解説
「突然、縁もゆかりもない部署への配置転換を命じられた」「これまでのキャリアが無駄になるような異動を打診され、到底受け入れられない」――。従業員にとって、自らのキャリアや生活を大きく左右する配置転換は、深刻な悩みとなります。一方で、企業側も「…
詳しくみる70歳以上の高齢者雇用は義務?企業が押さえるルール、給付金を解説
70歳以上の高齢者雇用は義務ではありませんが、企業には70歳までの就業機会確保が努力義務として課されています。2025年4月からは、経過措置がなくなり、65歳までの希望者全員を対象に雇用確保が義務化されました。そのため、今後さらに対応が求め…
詳しくみる労働契約とは?雇用契約との違いや締結ルール、契約書の書き方まで解説!
労働契約は労働者と会社との間で交わす、労働や賃金についての契約です。雇用契約と同じとして取り扱われ、労働契約書と雇用契約書のどちらかの名称で契約書が作成・交付されます。労働基準法と労働契約法に則って、変更や更新、終了についてルールが定められ…
詳しくみる怒鳴るのはパワハラ?適切な指導との違いや対処方法を解説
仕事で指導をしたものの、何らかの理由で怒りの感情をコントロールできなくなり、結果的にパワハラに該当してしまったケースもあるようです。 本記事では、職場で怒鳴ったことでパワハラとなる事例を交えながら、適切な対処法について解説します。 怒鳴るの…
詳しくみる試用期間について雇用契約書に記載するべき?記載例や書くべき情報も紹介
試用期間に関する情報は、雇用契約書に記載するべきです。 ただ「どのような情報を記載するの?」「雇用契約書の記載例を参考にしたい」などと思っている人もいるでしょう。そこで本記事では、雇用契約書に記載するべき試用期間の項目や記載例などを解説しま…
詳しくみる