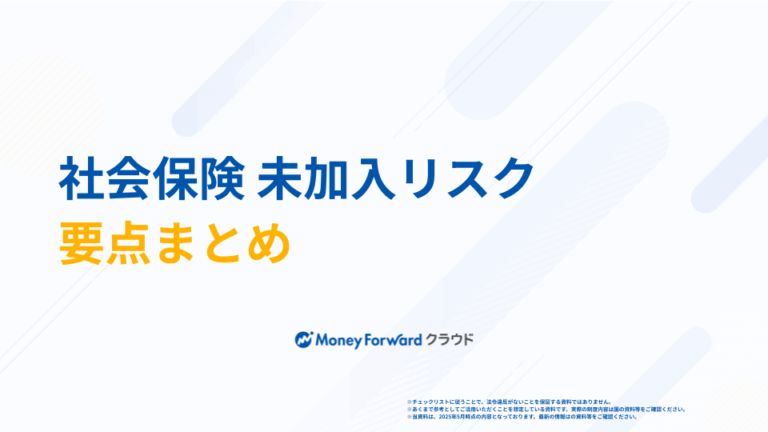- 更新日 : 2025年11月19日
社会保険未加入の問題点は?加入が義務づけられる条件や罰則について解説
会社は従業員を社会保険に加入させる義務があります。ただし、条件によっては義務とならない会社もあります。この記事では、社会保険に加入する義務がある会社の条件や未加入の場合の罰則などについて説明します。
目次
社会保険とは
医療、介護、高齢、疾病など、私たちの生活にはさまざまな変化が訪れ、困窮する可能性があります。そのため、社会全体でお互いに助け合う「相互扶助」の考え方に基づいて、社会保険の仕組みが整えられています。
社会保険という言葉には狭義と広義があります。狭義では会社員などが加入する健康保険と厚生年金保険のことをいい、広義では以下の5つのことをいいます。
- 健康保険
- 厚生年金(年金保険)
- 介護保険
- 労災保険
- 雇用保険
では、それぞれの社会保険について説明していきましょう。
健康保険
けがや病気で病院にかかったとき健康保険を利用した経験は、誰でもあるでしょう。治療費などの自己負担が1~3割で済み、安心して医療を受けることができます。日本では「国民皆保険制度」をとっており、すべての国民が健康保険を利用することができるのです。
なかでも社会保険と呼ばれるのは、会社員とその扶養家族が加入する健康保険です。会社員となったときに、全国健康保険協会または各社の健康保険組合に加入します。保険料を会社と折半で支払う点が国民健康保険と大きく違う点です。
また、40歳から65歳未満になると介護保険料も会社と折半で健康保険料とともに徴収されます。介護保険とは、高齢者を社会で支えるための保険です。65歳以上で要支援・要介護と認定された人、または40~64歳で特定疾病に罹り要介護と認定された人が受給できます。
参考:健康保険制度について|全国健康保険協会
参考:介護保険制度について|厚生労働省
厚生年金
厚生年金は、会社員などが加入する公的年金です。公的年金も基本的には「国民皆年金制度」であり、20歳以上60歳未満の全員が加入する国民年金の制度があります。学生や自営業などの人は国民年金に加入し、会社員は国民年金に加えて厚生年金に加入します。
一般的に社会保険と呼ばれるのは、厚生年金の部分です。厚生年金は、20歳未満であっても会社に勤め始めた時点から加入し、加入年齢の上限は70歳未満です。なお、健康保険料と同様に、年金保険料は会社と折半で支払います。
国民年金(基礎年金)と厚生年金両方に加入しているため、よく2階建てと例えられます。受給する際には基礎年金と厚生年金両方を合計した額を受給できます。
年金には、65歳から受給できる老齢年金、けがや病気で障害の状態となったときに受給できる障害年金、本人が死亡した場合に遺族が受給できる遺族年金があります。
労災保険
労災保険とは、従業員の業務に関連したけがや病気、通勤時のけがや病気などに給付される保険です。また、社会復帰の促進にも使用されます。従業員が保険料を負担するのではなく、すべて雇い主が負担します。
いかなる業種、いかなる職業にも適用され、原則として事業主は1人でも従業員を雇っていれば労災保険へ加入しなければなりません。この場合の従業員とはアルバイト・パートなどの雇用形態も関係なく、雇用されている全員が対象です。
参考:労災補償|厚生労働省
雇用保険
雇用保険とは、離職して収入がなくなった場合の失業給付や新たな職業に就くための教育訓練費の給付、ハローワークでの求職支援などに使用できる保険です。加入の手続きは事業主が行います。労災保険と同様に、1人でも従業員を雇っている事業主は、加入手続きを行わなくてはなりません。新しく人を雇い入れた場合には、その都度(具体的には、雇い入れた日(被保険者となった日)の翌月10日まで)加入手続きを行います。
加入の対象となるのは、以下の適用条件を満たしている従業員です。アルバイト・パートなどの雇用形態は問わず、条件を満たしたすべての従業員が対象となります。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
なお、事業者は手続きを行った際に交付される「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」を従業員本人に渡し、手続きした旨を確実に知らせなければなりません。また、従業員は、自分の雇用保険の手続きがされているかどうかをハローワークに確認することができます。行うべき手続きがされていなかった場合、遡って加入することもできます。
参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省
参考:雇用保険に加入していますか|厚生労働省
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
社会保険に未加入だと複数の罰則がある
社会保険は、条件によりますが従業員を雇っているほとんどの事業所に加入義務があるものです。未加入のままでいると罰則もあります。懲役や罰金、立ち入り検査など、罰則を受けることは事業所の信用に関わることです。また、従業員からの信用も失って人材の流出などにつながりかねません。
故意がいけないのは言うまでもありませんが、ミスや怠慢で未加入が起こらないよう注意が必要です。ここでは、社会保険未加入の罰則についてみていきましょう。
6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
健康保険、厚生年金の加入義務があるのに加入していない事業所は、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科される恐れがあります。何度も加入指導を行っているのに従わない、虚偽の申告を行うなど、悪質な場合に適用されます。
また、雇用保険に加入していない場合には、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を科される恐れがあります。
参考:厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取組|日本年金機構
過去2年間に遡及して保険料を徴収
社会保険の未加入が発覚し、年金事務所などの立ち入り検査を受け、強制加入となった場合、過去2年まで遡って保険料を徴収される恐れがあります。健康保険や厚生年金の保険料は事業所と従業員折半で支払いますが、一度事業所がすべて立て替えて支払います。その後、従業員に請求することはできますが、退職などで連絡がとれない元従業員の分などはすべて事業所が負担することになります。
また、労災保険、雇用保険についても同様に、過去2年間まで遡って保険料を納付しなければなりません。
延滞金が発生する
厚生年金などの保険料を期限までに納付しないと、督促状が届きます。その督促状に記載された指定期限までに納付しない場合、延滞金がかかります。この場合、督促状の指定期限ではなく、本来の納付期限の翌日から納付日の前日までの分の延滞金が請求されますので、注意が必要です。延滞金の金額は、延滞した日数により決められた割合を掛けて計算されます。
督促状の期限までに納付をすれば延滞金は発生しませんが、本来の期限を守って納付するようにしましょう。
ハローワークに求人を出せない
社会保険への加入義務があるのに未加入の事業所は、ハローワークに求人を出すことができません。これもやはり信用の問題となるでしょう。
社会保険加入の義務と条件
社会保険には加入条件があります。法人事業所や個人事業所の加入には強制加入と任意加入があり、強制加入の義務を怠ると罰則があるのは既に述べたとおりです。従業員は、正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、労働時間などの条件により加入できるかどうかが決まります。では、実際の条件をみてみましょう。
企業の条件
事業所のうち、必ず健康保険(介護保険)・厚生年金保険に加入しなければならないと法律で義務付けられている事業所を「強制適用事業所」といいます。強制適用事業所とは、以下のような条件の事業所です。
- 従業員を常時1人以上雇用している法人事業所
- 国、地方公共団体を含む
- 従業員がおらず、事業主1人のみの場合も対象となる
- 学校法人は厚生年金ではなく私立学校職員共済制度に加入
- 従業員を常時5人以上雇用している個人事業所
- 農林業、水産業、畜産業、サービス業の一部、士業、宗教などは任意加入が可能
労災保険、雇用保険については、法人・個人に関わらず常時1人でも従業員を雇っている事業所には加入の義務があります。正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態も関係ありません。ただし、雇用保険については短時間労働者などについて加入の条件があります。
なお、個人経営の農業、水産業は常時雇用が5人未満、林業は常時雇用がおらず労働者数が延べ300人未満であれば任意加入できます。
また、労災保険には特別加入として、中小事業主や一人親方・特定作業従事者、海外派遣者などが加入できます。
参考:社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?|厚生労働省・日本年金機構
従業員の条件
勤務する事業所が社会保険の強制適用事業所である場合、基本的に正社員、法人の代表者、役員は全員社会保険の被保険者(加入者)となります。また、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の就労者の4分の3以上の従業員も、被保険者です。
短時間労働者でも、以下の5つの条件にすべて当てはまる従業員は被保険者となります。
- 従業員が501人以上の企業に勤めている
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8.8万円以上
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 学生以外
なお、法改正により、令和4年(2022年)10月からは従業員が101人以上の企業も上記条件の対象となります。
参考:社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?|厚生労働省・日本年金機構
参考:従業員数500人以下の事業主の皆様へ|厚生労働省
従業員の生活を守る社会保険
社会保険は、国民全員が加入する国民健康保険や国民年金保険に加えて、企業で働く人が加入するさまざまな保険の総称です。企業の規模によって強制加入となるものも多く、未加入の場合には罰則も設けられています。また、健康保険や年金、労災保険、雇用保険などの加入は、その保険料の半分または全部を雇用主が負担します。社会保険への加入は、従業員を守るための雇用主の義務なのです。
よくある質問
社会保険とは?
企業などで働く従業員が加入する健康保険や厚生年金、介護保険、労災保険、雇用保険のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険未加入だとどうなる?
企業に対しては6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(健康保険、厚生年金の場合)が科せられる場合があります。また、保険料を過去2年間遡及して徴収されるなど、複数の罰則が適用されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社会保険の氏名は旧姓のままでも大丈夫?変更しないとどうなる?
働き方改革の施策の一つに、女性の活躍推進があります。最近は女性の社会進出を背景に、結婚後も職場で旧姓の使用を認める企業が増えています。 仕事で使う名刺やメールアドレスなどで旧姓を表記するというものですが、社会保険の手続きでも旧姓を使用するこ…
詳しくみる厚生年金における標準報酬月額表について見方を解説!
標準報酬月額表は、報酬額に応じた厚生年金の保険料をまとめた一覧表です。「給料ごとの保険料の早見表」とも言い換えられます。 標準報酬月額表を参照すれば、被保険者と企業の負担額を一目で確認することが可能です。ここでは、厚生年金における標準報酬月…
詳しくみる自己都合退職の失業保険はいつから・いくらもらえる?最新のルールを解説
自己都合退職でも失業保険を受給できます。自己都合退職は会社都合退職に比べて、最終的に受け取れる金額の総額や、必要な雇用保険加入期間(被保険者期間)などの点で差がある点が特長です。そのため、退職を検討している方は、自己都合退職のデメリットや失…
詳しくみる通勤中の事故は労災になる?認められないケースは?
通勤途中に発生したケガや交通事故は、状況によっては「労災保険」の対象になります。とはいえ、すべての通勤中の事故が労災として認定されるわけではなく、判断には法律上の基準や過去の運用実例が関係します。企業の人事担当者にとって、従業員から通勤中の…
詳しくみる社会保険料のダブルチェック方法は?計算ミスを防ぐダブルワーク時の注意点
社会保険料の計算ミスを防ぐには、複数担当者によるダブルチェックが大切です。特に、従業員がダブルワーク(副業・兼業)を行っている場合、各事業所の給与を合算して保険料を決定するため手続きがより複雑になり、二重徴収や計算ミスが生じる可能性が高まり…
詳しくみる労災で医療費が10割負担?払えないときの対応や返金手続きを解説
労災(労働災害)によるけがや病気で病院を受診したにもかかわらず、医療費を全額(10割)請求されることがあります。受診した医療機関が労災指定病院でない医療機関を受診した場合や、必要書類がそろっていなかった場合などに発生するケースです。高額な医…
詳しくみる