- 更新日 : 2025年6月24日
会社は福利厚生で保険を導入すべき?社会保険との違いや種類、メリット、導入方法を解説
企業が福利厚生として導入する保険制度は、従業員の満足度や安心感を高め、企業にとっても人材の定着率向上や優秀な人材確保に効果的な制度です。しかし、「どのような保険を導入すればよいか」「そもそも福利厚生として保険が必要なのか」と疑問を抱える担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、福利厚生の保険の基本的な知識、社会保険との違いや種類ごとの特徴、導入のメリット・デメリットや具体的な導入方法までわかりやすく解説します。
目次
福利厚生の保険とは
福利厚生の保険とは、会社が従業員のために任意で加入するさまざまな保険制度のことを指します。法律で加入が義務付けられている社会保険(健康保険や厚生年金など)とは異なり、企業が自主的に導入し、従業員の病気や事故といった万が一の事態に備えるものです。
福利厚生として保険を導入する主な目的には、次のようなものがあります。
- 従業員やその家族の生活の安定をサポートするため
- 病気や事故など万が一の場合に、経済的負担を軽減するため
- 従業員の満足度や安心感を高め、企業への信頼を深めるため
- 離職率を低下させ、人材の定着を促進するため
従業員が安心して働ける環境をつくることで、企業の安定的な成長や競争力強化につなげることを目的としています。
福利厚生の保険の対象者
福利厚生の保険の対象者は、主に正社員や契約社員ですが、企業によってはパートやアルバイトまで範囲を広げることも可能です。対象範囲は自由に決定できるため、自社の状況や人事戦略に応じて柔軟に設定できます。
福利厚生の保険と社会保険の違い
福利厚生として企業が提供する保険と、法律上加入が義務付けられている社会保険には、明確な違いがあります。以下の表で違いを確認しておきましょう。
| 項目 | 福利厚生の保険 | 社会保険 |
|---|---|---|
| 加入義務 | 任意加入(企業が自由に決定) | 法律により加入義務あり |
| 主な保険の種類 | 団体生命保険、医療保険、がん保険など | 健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険 |
| 保険料の負担方法 | 企業が負担または企業と従業員が分担 | 企業と従業員が決められた割合で分担(労災保険料は企業のみ負担) |
| 導入目的 | 従業員の福利厚生の充実、人材の定着促進 | 従業員の生活安定、社会的セーフティネット |
社会保険に加入しない場合の法的リスク
社会保険への加入は法的義務であるため、未加入が発覚すると、年金事務所や労働基準監督署からの調査・指導を受ける可能性があります。指導に従わない場合、悪質とみなされれば行政処分の対象となり、最悪の場合は企業名公表や刑事罰(罰金や懲役)が科されることもあります。
また、過去に遡って保険料の未払い分を一括請求されるリスクもあります。特に未加入期間が長期化している場合は、多額の支払いが発生するため、企業の経営を大きく圧迫することになります。未払いの保険料に加えて延滞金も請求されるため、負担は非常に大きくなります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
エンゲージメント向上につながる福利厚生16選
多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。
本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。
令和に選ばれる福利厚生とは
本資料では、令和に選ばれている福利厚生制度とその理由を解説しております。
今1番選ばれている福利厚生制度が知りたいという方は必見です!
福利厚生 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)
福利厚生に関する就業規則の記載例資料です。 本資料には、一般的な就業規則も付属しております。
ダウンロード後、貴社の就業規則作成や見直しの参考としてご活用ください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
福利厚生の保険の種類
福利厚生として導入される保険には、企業が従業員のさまざまなリスクに備えるための複数の種類があります。ここでは、保険の種類ごとに特徴を詳しく解説します。
団体生命保険
団体生命保険とは、企業が契約者となり、従業員が死亡または高度障害状態になった場合に、従業員本人やその家族に対して保険金が支払われる保険制度です。個人で加入する生命保険に比べて、保険料が割安で手続きが簡単な点が特徴です。企業によっては保険料の一部または全額を負担するケースもあり、従業員の経済的な安心を確保しつつ、企業にとっても節税メリットがあります。
団体医療保険
団体医療保険とは、従業員が病気やケガで入院や手術をした際に、かかった医療費の一部または全部を補償する保険制度です。
社会保険(健康保険)だけでは補いきれない自己負担分をカバーする役割があります。入院日数や手術の種類などに応じて給付金が支払われるため、従業員は経済的な不安を軽減でき、企業側も従業員の早期復帰をサポートすることにつながります。
がん保険
がん保険とは、従業員ががんと診断された場合に、一時金や入院・手術・通院にかかる費用を給付する保険です。がんは治療が長期化し、治療費も高額になりやすい疾病であるため、通常の医療保険以上に手厚い保障を提供することが特徴です。診断時にまとまった一時金が支払われるタイプが一般的であり、従業員が治療に専念しやすくなるメリットがあります。
三大疾病保険
三大疾病保険とは、「がん」「心筋梗塞」「脳卒中」の三大疾病に対して保障を行う保険です。これらの病気は治療費が非常に高額になりやすく、長期的な療養が必要になることも多いため、治療費や療養中の収入減少に備えることができます。保障内容としては、診断一時金、入院給付金、手術給付金などが主な内容となっています。
所得補償保険
所得補償保険とは、病気やケガによって従業員が働けなくなった場合に、一定期間、収入の一部を補償する保険です。通常は給与の50〜70%程度が保険金として支払われます。社会保険の傷病手当金よりも長期間にわたり給付が可能であるため、従業員が長期的な病気療養に入った場合の経済的負担を大幅に軽減できます。
傷害保険
傷害保険とは、従業員が仕事中やプライベートを問わず、突然の事故によるケガや障害、死亡などが生じた場合に補償される保険です。団体で加入することにより、個人加入よりも保険料が安く抑えられ、企業側としても福利厚生として導入しやすい保険です。特に外回りや出張の多い企業では、万一の事故に備える目的で導入されることが多くあります。
介護保険
介護保険(民間の団体型)は、従業員本人や家族が要介護状態になった場合に、一時金や介護費用を給付する保険です。近年では、高齢化に伴い、従業員の親や家族の介護による離職が問題となっているため、その負担を軽減するために企業が導入するケースが増加しています。介護離職を防ぎ、従業員の働きやすい環境を整備することを目的としています。
福利厚生として保険を導入するメリット
企業が福利厚生として保険を導入することで、従業員と企業の双方にさまざまなメリットがあります。ここでは、福利厚生の一環として生命保険や医療保険などを導入する具体的なメリットを解説します。
従業員や家族の経済的な安心感が生まれる
福利厚生保険の最も重要なメリットは、従業員本人やその家族が病気、ケガ、万一の死亡や高度障害に見舞われた場合に、経済的負担を大幅に軽減できることです。企業が提供する生命保険は死亡や重い障害が起きた際の保障を、医療保険は入院や手術の際の医療費補助を行うため、従業員や家族の安心感や生活安定につながります。
従業員満足度や企業への信頼感が向上する
充実した保険制度を福利厚生として整備している企業では、従業員が自分や家族の将来について安心して働けるため、満足度が高くなります。また、従業員の健康や安全を重視する企業としての信頼感やロイヤリティも高まるため、企業への帰属意識の強化やモチベーション向上にもつながります。
優秀な人材の採用が強化できる
福利厚生として充実した保険を提供している企業は、人材市場での競争力が向上します。求職者は会社を選ぶ際、給与だけでなく福利厚生の内容を重視する傾向が強く、生命保険や医療保険などの充実は、優秀な人材を惹きつける大きな要素となります。結果として、人材採用や定着の向上に効果があります。
個人加入よりも保険料が割安になる
企業が団体として加入する保険は、個人が加入するよりも保険料が割安になることが多くあります。また、企業が保険料の一部を負担することも多いため、従業員の経済的負担を減らしながら、より充実した保障内容を提供できます。
従業員の健康管理・リスク管理が促進される
保険制度を通じて企業が従業員の健康やリスクへの意識を高めることで、健康経営の推進や、病気や事故を未然に防ぐ意識が浸透します。従業員自身が自らの健康や万が一の事態に備える意識を持つことは、生産性の向上や健康的な職場環境づくりにも効果があります。
企業にとって節税効果も期待できる
福利厚生の保険料を企業が負担した場合、その保険料は福利厚生費として経費計上が可能な場合があります。結果として、企業側にも節税メリットが生まれ、経営効率の向上につながります。従業員に対して手厚い福利厚生を提供しながら、税務上のメリットを享受できるのは大きな利点です。
福利厚生として保険を導入するデメリット・注意点
福利厚生として保険を導入すると、従業員にとって安心感が増すなど多くのメリットがありますが、一方で注意すべき点やデメリットもあります。この章では、企業が保険を導入する前に知っておくべきデメリットや注意点を詳しく解説します。
企業の保険料負担が増える
福利厚生として保険を導入すると、多くの場合、企業が保険料の一部または全額を負担することになります。そのため、企業にとっては経費負担が増加します。従業員数が多い企業や保障内容が充実した保険を選択する場合は特に、毎年の保険料負担が経営を圧迫する可能性があります。導入時には、企業の財務状況や将来的な負担を慎重に考慮する必要があります。
保険手続きに伴う事務負担が発生する
保険制度を導入すると、従業員の加入手続きや給付金の請求手続きなどで、担当部署の事務的負担が増加します。特に従業員数が多い企業ほど、事務手続きや保険会社とのやり取りが煩雑になりがちです。導入前に事務負担がどの程度増えるかを把握し、人事や総務など担当部署のリソースを考慮して制度設計を行う必要があります。
従業員によってニーズが異なる
保険の内容によっては、従業員全員のニーズに一致するとは限りません。例えば、若い従業員は死亡保障より医療保険や所得補償保険を重視し、高齢の従業員はがん保険や三大疾病保険を求める傾向があります。画一的な保険制度を導入してしまうと、一部の従業員から「不要な保障に保険料を払っている」と不満が生まれる可能性があります。従業員の意見や希望を丁寧に調査し、バランスを取る必要があります。
従業員への説明不足によるトラブルの可能性がある
保険制度の内容や給付条件が従業員に十分理解されていないと、実際に給付が必要となった際にトラブルが発生する可能性があります。特に給付条件や免責事項などを曖昧に説明した場合、従業員が給付金を受け取れない状況になり、企業への不信感につながる恐れがあります。制度導入時や新規加入時には、内容をしっかり説明し、十分な理解を得ておく必要があります。
保険内容の見直しが難しい場合がある
福利厚生として保険を導入すると、後から保険内容を変更することが難しい場合があります。一度導入すると従業員の既得権益となるため、経営環境の変化で保険料を負担できなくなった場合に、廃止や変更する際に従業員からの抵抗が起こる可能性があります。導入前に将来的な経営環境の変化も考慮し、無理のない内容で導入することが重要です。
福利厚生の保険がいらないケース
福利厚生として保険を導入する企業は多いものの、導入が不要なケースもあります。企業ごとに保険導入の目的や従業員の状況を明確に把握し、必要性を慎重に検討することが重要です。
健康保険組合の制度が充実している場合
健康保険組合とは、企業または同業種の企業グループが自主的に設立・運営する公法人で、主に健康保険制度を運営する組織です。中小企業などが加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と異なり、比較的規模の大きい企業やグループ会社が自ら設立し運営しています。健康保険組合は、法律で定められた健康保険制度を実施することに加えて、独自の付加給付や健康増進事業を行うことができます。特に大企業や業界団体の健康保険組合に加入している場合は、一定のリスクがすでにカバーされているため、企業が独自に追加の保険を導入する必要性が低い場合もあります。
保険以外の福利厚生で十分な場合
住宅手当や健康診断の充実、休暇制度の拡充など、保険以外の福利厚生のほうが従業員に喜ばれる場合があります。特に企業規模が小さい場合や限られた予算で最大の効果を得たい場合、必ずしも保険がベストな選択肢とは限りません。他の福利厚生と比較し、総合的に判断する必要があります。
福利厚生の保険が企業風土に合わない場合
ベンチャー企業やスタートアップ企業などでは、福利厚生として保険を導入するよりも、給与やインセンティブとして従業員に還元するほうが従業員の満足度が高まることがあります。このように企業の風土や従業員の志向によっては、そもそも保険という形態の福利厚生がマッチしない場合もあります。
福利厚生の保険を導入する方法
福利厚生として保険を導入する場合、単に保険会社を選ぶだけでなく、従業員のニーズ把握から契約手続き、導入後の運用まで、計画的な進め方が必要です。この章では、福利厚生保険を企業に導入するまでの具体的な手順を解説します。
従業員のニーズ調査を行う
最初に、どのような保険が従業員から求められているかを把握することが重要です。アンケート調査や個別面談を行い、次のような点を確認します。
- 従業員の年齢層や家族構成
- 病気やケガへの不安、所得保障の必要性
- 生命保険やがん保険などへの希望の有無
こうした調査を丁寧に行うことで、保険導入の目的を明確にし、無駄のない制度設計が可能になります。
導入する保険の種類を決定する
企業が福利厚生として保険を導入する際は、従業員の年齢層、家族構成、健康状態などを考慮し、どのような保険を組み合わせるのか検討する必要があります。例えば、若い従業員が多い場合は医療保険や所得補償保険、中高年が多い場合はがん保険や三大疾病保険などを充実させるといった、従業員の実情に即した保険設計を行うことが重要です。企業の予算や従業員の希望を踏まえ、最適な組み合わせを検討することが求められます。
保険会社や保険商品の比較検討を行う
導入する保険の種類を決定したら、具体的な保険会社や商品を比較検討します。複数の保険会社から見積もりを取り、次のポイントを比較します。
- 保険料の費用対効果
- 保険の保障範囲や給付条件の明確さ
- 保険加入や給付手続きの簡便さ
- 保険会社の信頼性やサポート体制の充実度
最終的に、最も条件に合う保険会社と商品を選定します。
保険料の負担割合を決定する
保険料の負担を企業と従業員でどのように分担するかを決定します。企業が保険料を全額負担するケースもあれば、一部を従業員が負担するケースもあります。一般的には、企業が保険料の一部を負担するケースが多く、従業員が負担する割合は給与から天引きする形が一般的です。
社内での説明・周知を行う
導入する保険制度について、従業員に丁寧に説明し、理解を促します。説明する際は以下の点を明確に伝えます。
- 保険の種類や具体的な保障内容
保険料負担の仕組み(自己負担の有無、金額) - 保険給付の条件や手続き方法
社内説明会を開いたり、資料を作成して配布したりすることで、誤解やトラブルを未然に防ぎます。
保険会社との契約手続きを進める
保険会社との契約手続きを進めます。契約には従業員名簿の提出や加入申込書の作成など、保険会社が指定する書類手続きが必要になります。また、導入予定日や保険料の支払い方法などについても、保険会社と細かな調整を行います。
導入後の運用体制を整える
福利厚生保険を導入した後も、定期的なメンテナンスが必要です。具体的には以下の業務が発生します。
- 新入社員の加入手続きや退職者の脱退手続き
- 給付金の請求手続きのサポート
- 定期的な制度の見直しや従業員のニーズ調査
担当部署(総務部・人事部)での運用体制を整備し、担当者が円滑に業務を進められるように準備します。
定期的な見直しを行う
導入後は定期的に保険制度の効果を検証し、見直しを行います。見直しにあたっては、従業員の満足度調査や、保険料のコストパフォーマンス評価を行い、必要に応じて制度の改善を進めます。
福利厚生保険を導入する際には、上記のステップを順序よく進め、計画的に制度構築を進めることが重要です。従業員に歓迎され、企業にとってもメリットのある保険制度を導入しましょう。
福利厚生の保険に関してよくある質問
福利厚生の保険を企業で導入する際に、多くの担当者や従業員からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。実際に制度を検討したり、導入したりする際の参考にしてください。
福利厚生の保険を導入する義務はある?
福利厚生として導入する保険(団体生命保険、団体医療保険、所得補償保険など)は任意加入であり、法律で義務付けられている社会保険(健康保険や厚生年金など)とは異なります。企業が自主的に導入を決定できる制度であるため、導入義務はありません。
福利厚生の保険料は企業が全額負担する?
いいえ、必ずしも企業が全額を負担する必要はありません。企業が全額負担するケースもあれば、企業と従業員で保険料を分担するケースもあります。企業の財政状況や従業員の負担可能な範囲を考慮し、自由に設定できます。
派遣社員やパート社員も福利厚生の保険に加入できる?
企業の判断により、派遣社員やパート社員も福利厚生の保険に加入することができます。加入条件や範囲は企業ごとに設定可能であり、雇用形態や労働時間数などに応じて対象者を決定できます。
福利厚生の保険は途中で解約や変更ができる?
福利厚生の保険は一般的に契約更新のタイミング(年1回など)で見直しや変更が可能です。ただし、契約途中での解約や変更は保険会社との交渉が必要であり、場合によっては難しいケースもあります。導入時には将来的な状況変化も考慮して慎重に検討しましょう。
福利厚生の保険に税務上のメリットはある?
企業が福利厚生保険の保険料を負担する場合、福利厚生費として損金(経費)処理できる場合があります。ただし、保険内容や契約形態によって処理方法が異なるため、導入前に税理士など専門家に相談することをおすすめします。
これらの質問と回答を参考に、福利厚生としての保険を適切に導入・運用してください。
福利厚生として自社に合った保険を導入しましょう
福利厚生としての保険導入は、従業員が安心して働ける環境づくりに貢献し、企業の成長を支える重要な施策の一つです。ただし、保険の導入が必ずしも全ての企業に適しているわけではありません。自社の従業員の状況や企業の財務状況を十分に把握し、適切な保険を選ぶことが大切です。従業員のニーズを丁寧に調査し、制度導入後も定期的な見直しを行い、保険制度を最大限活用できるように運用しましょう。この記事が、福利厚生保険導入を検討する皆様の一助となれば幸いです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
入社書類に不備がある場合の対応方法とは?流れや予防策を解説
Point入社書類の不備対応まとめ入社書類に不備がある場合の対応は、迅速な内容確認とリスト化を行い、相手に配慮した具体的な修正・再提出依頼を速やかに実施することが核心です。 対応手…
詳しくみる外国人労働者が増加している理由とは?企業側のメリットも紹介
日本で外国人労働者がなぜ増えているのか疑問に感じる方もいるでしょう。 本記事では日本で外国人労働者の数や増加している理由を解説します。また、これから外国人労働者の雇用を検討している…
詳しくみる人的資本投資とは?企業における効果や導入事例を紹介
人的資本投資とは、従業員のスキルや能力を高め、企業価値を向上させるための戦略的な投資です。 近年、企業には人的資本の情報開示が義務化され、従業員への投資を強化する必要があります。本…
詳しくみる一人暮らし向け社宅のメリット・デメリットは?導入のポイントを解説
一人暮らし向け社宅の導入は、企業と従業員双方に大きなメリットをもたらします。福利厚生の充実により企業イメージを向上し、採用活動が有利になります。従業員側にも転居手続きの簡素化やコス…
詳しくみる退職勧奨で弁護士に同席してもらうことは可能?メリットや費用を解説
退職勧奨の場では、弁護士の同席が認められる場合があります。 本記事では、弁護士が同席することで得られる利点や注意点、一般的な費用の目安などについて解説します。また、退職勧奨に詳しい…
詳しくみる異動したいのはわがまま?希望を通すコツや気まずくならないポイントも解説
部署異動を希望しているものの「自分のわがままではないか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、異動希望を通すためのコツや言いづらい場合の対処法、異動後に気まずくな…
詳しくみる
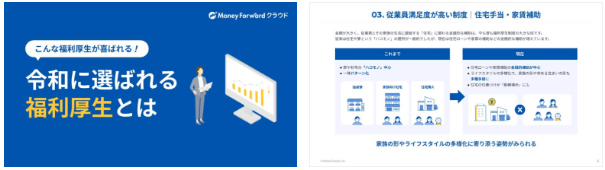
.jpg)
