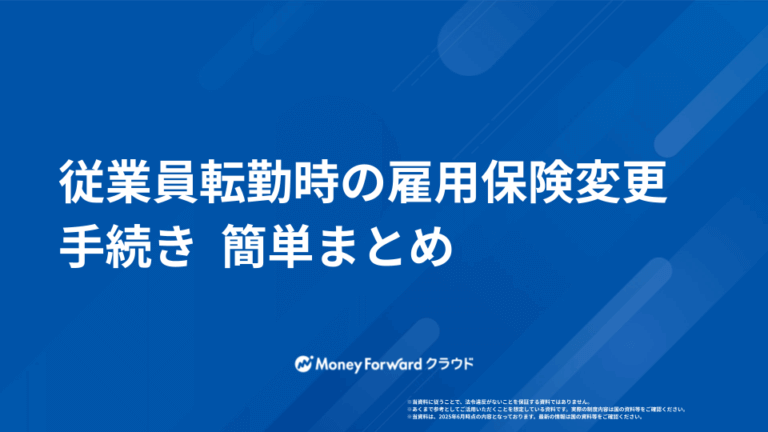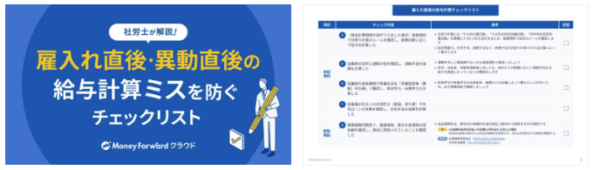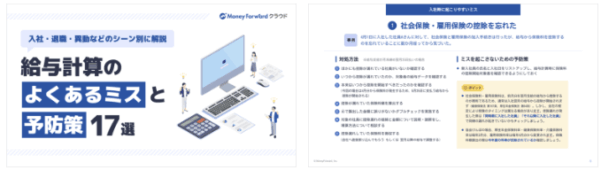- 更新日 : 2025年11月19日
従業員が異動(転勤)したら雇用保険の変更はどう行う?手続き方法や電子申請について解説
従業員が異動(転勤)した場合、事業主は14日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を管轄のハローワークに提出する必要があります。この手続きは、事業所の所在地が変更になることで、雇用保険の適用事業所が変わるためです。
本記事では、従業員の転勤時の雇用保険手続きについて、電子申請の方法も含めて詳しく解説します。
目次
従業員を異動させたら、雇用保険の手続きは誰が行う?
従業員が転勤する場合、雇用保険の手続きは事業主が行わなければなりません。これは雇用保険法および同法施行規則に定められた法的義務であり、手続きの遅延や漏れは事業主の責任となります。
従業員が転勤した場合、事業主が雇用保険の手続きを行う
事業主は、従業員が転勤する際には転勤日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。
詳しくは後述します。
転勤と出張・駐在の違い
転勤と出張・駐在は、雇用保険の手続きにおいて明確に区別されます。転勤は、同一事業主の一つの事業所から他の事業所への勤務場所の変更を指し、以下の要素を総合的に判断して決定されます。
- 辞令の交付の有無
- 直接の指揮監督者の変更
- 給与支給場所の変更
一方、出張や駐在は一時的な勤務場所の変更であり、通常2~3ヶ月程度の短期間の変更の場合は転勤とは認められません。この場合、従来の事業所に勤務しているものとして取り扱われ、雇用保険の異動手続きは不要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
給与計算にミスがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、内容によっては労働基準法違反となる可能性もあります。
本資料では、雇入れ直後・異動直後に焦点を当て、給与計算時のチェックポイントをまとめました。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
この資料では、各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にまとめました。
【異動時も解説!】給与計算のよくあるミスと予防策17選
給与計算で起きやすいミスをシーン別にとりあげ、それぞれの対処方法を具体的なステップに分けて解説します。
ミスを事前に防ぐための予防策も紹介していますので、給与計算の業務フロー見直しにもご活用ください。
従業員が転勤した場合の雇用保険の変更手続き
従業員の転勤が発生した際、事業主は適切な書類を準備し、定められた期限内に手続きを行う必要があります。以下で、手続きの流れについて解説します。
届出用紙名
従業員の転勤に伴う雇用保険の変更手続きには、雇用保険被保険者転勤届(則様式第10号)を使用します。この届出用紙は、ハローワークのインターネットサービスからダウンロードできます。
なお、書面の印刷にあたっては等倍で印刷すること、印刷用紙は白でなければならないなど細かい規定があるため、よく確認しておきましょう。
提出期限
雇用保険被保険者転勤届は、転勤の事実があった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければなりません。
時間的余裕がそれほどあるわけではないため、期限を意識して早めの手続きを心がけましょう。
提出先
雇用保険被保険者転勤届は、転勤先の事業書を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
提出方法は窓口への直接提出か電子申請システムを利用したオンライン提出のいずれかを選択できます。なお、資本金1億円を超える法人については、電子申請が義務化されています。
転勤届以外に必要な可能性がある書類
従業員の転勤に伴う雇用保険の変更手続きの際には、雇用保険被保険者転勤届のほかにも以下の添付書類が必要になるケースがあります。
雇用保険被保険者転勤届は電子申請できる?
雇用保険被保険者転勤届は、電子申請が可能です。電子申請を利用すれば、365日24時間いつでも申請でき、ハローワークの窓口に出向く必要がありません。
雇用保険被保険者転勤届の電子申請には、以下の方法があります。
- e-Gov電子申請システムを利用する方法
- 労務会計ソフトウェア(API連携方式)を利用する方法
電子申請を行う際は、転勤後の事業所の電子署名を行わなければなりません。なお、通常の書面申請で必要となる労働者名簿などの添付書類は、電子申請の場合は原則不要です。
電子申請が義務化される特定の法人
2020年4月以降、以下の法人については雇用保険被保険者転勤届の電子申請が義務化されています。
- 資本金または出資金が1億円を超える法人
- 保険業法で規定された相互会社
- 投資信託及び投資法人に関する法律で規定された投資法人
- 資産の流動化に関する法律で規定された特定目的会社
ただし、電気通信回線の故障や災害などにより電子申請が困難と認められる場合は、従来の書面による申請も認められています。
従業員が在籍出向する場合、雇用保険は出向元・出向先のどちらで適用する?
在籍出向の場合、雇用保険の適用は出向元と出向先のどちらか一方のみとなります。以下で、具体的な適用基準と手続きについて解説します。
雇用保険を適用するのは、主に給与を支払う側
在籍出向の場合、出向労働者は出向元と出向先の両方と雇用関係を持ちますが、雇用保険は生計を維持するために必要な主たる賃金を支払う企業で適用されます。例を挙げると出向元が給与の3分の2を負担する場合、より多くの給与を支払う出向元が主たる事業主となり、出向元の被保険者として取り扱われます。
なお、例のように出向元と出向先で給与を分担して支払う場合でも、雇用保険は給与負担の多い方の企業でのみ適用になる点に注意が必要です。
出向先で雇用保険を適用する場合の手続きの流れ
出向先で雇用保険を適用することになった場合は、以下の手続きが必要です。
- 出向元での資格喪失手続き:出向元の事業所で雇用保険被保険者資格喪失届を提出
- 出向先での資格取得手続き:出向先の事業所で雇用保険被保険者資格取得届を提出
これらの手続きは、出向開始日から10日以内に、それぞれの事業所を管轄するハローワークで行います。手続き完了後、出向先の事業所から出向者本人に雇用保険被保険者証が交付される流れです。
従業員が転勤した場合の社会保険の変更手続き
従業員が転勤する場合の社会保険手続きは、被保険者のマイナンバーと基礎年金番号の紐づけ状況によって対応が異なります。
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
被保険者のマイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている被保険者については、住所変更の届出は原則として必要ありません。紐づけが行われている場合は日本年金機構が被保険者のマイナンバー情報から住所変更を自動的に把握しているため、特段の手続きは不要です。
事業主は、従業員のマイナンバーと基礎年金番号の紐づけ状況を「ねんきんネット」や管轄の年金事務所で確認できます。
被保険者のマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない場合
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない被保険者の転勤時には、事業主は「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を提出する必要があります。この届出は、被保険者から転居の申出があった日から速やかに、管轄の年金事務所に持参、または事務センターに郵送します。
また、以下のケースでも住所変更手続きが必要です。
- 健康保険のみに加入している被保険者
- 海外居住者や短期在留外国人
- 住民票の住所と実際の居住地が異なる場合
従業員の転勤時に確認すべき社会保険関連の手続き
従業員が転勤した場合、雇用保険と同様、社会保険においても資格喪失と資格取得の手続きが必要です。しかし、それ以外でも、企業が確認すべき手続きが複数発生します。
住所変更がある場合は「被保険者住所変更届」
転勤に伴って従業員の住民票上の住所が変わる場合、企業は「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」の提出が原則不要となっています。これは、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば、日本年金機構が住民票情報を自動的に参照できる仕組みが整っているためです。
ただし、マイナンバーが未提出であったり、紐づけがされていない場合には、住所変更届を企業が提出する必要があります。本人確認書類の提出を求められる場合もあるため、事前に従業員へ確認することが望ましいです。
被扶養者の情報更新と保険証の再交付の確認
転勤による住所変更や居住形態の変化に伴い、被扶養者の情報にも変更が生じる可能性があります。たとえば、別居の扱いになる、または同居に変わる場合は、扶養認定の再確認が必要になることもあります。
加えて、健康保険証の発行元が事業所単位で異なる場合、新しい保険証の再交付が発生します。そのため、転勤後は速やかに保険証の差し替えを行い、被保険者・被扶養者のいずれにも不利益が生じないようにすることが求められます。
被保険者住所変更届の提出までの流れ
「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」とは、被保険者(従業員)の住民票上の住所が変更された場合に、その情報を日本年金機構に届け出るための書類です。ただし、現在ではマイナンバー制度の導入により、提出が不要となるケースもあるため、状況に応じた判断が必要です。
提出が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合は、住所変更届の提出が必要です。
- 被保険者のマイナンバーが未登録、または基礎年金番号と紐づいていない
- 海外居住者、短期在留外国人
- 健康保険にのみ加入している
- 住民票以外の居所を登録する場合
マイナンバーと基礎年金番号が正しく紐づいている場合、日本年金機構は住民票の情報を参照できるため、原則として届出は不要です。
手続きの流れ
① 従業員から住所変更の申告を受ける
転勤・引越しなどで住所が変更された場合、本人からの申告(住民票ベース)を受けてください。
② 被保険者住所変更届を作成
「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(様式第3号)」に、以下の内容を記入します。
- 被保険者氏名
- 基礎年金番号またはマイナンバー
- 旧住所・新住所
- 変更年月日(住民票の異動日)
提出先・提出期限
提出先は事業所を管轄する年金事務所です。電子申請(e-Gov)でも提出可能です。明確な提出期限は定められていませんが、事実発生後速やかに行うことが必要です。
従業員の転勤により被扶養者の条件が変わる場合の対応方法
従業員の転勤により家族との居住形態や生活状況が変わると、社会保険における「被扶養者の認定条件」も影響を受けることがあります。企業の人事・労務担当者は、異動に伴う手続きの有無を見落とさないよう、転勤時の扶養状況の確認と必要書類の案内・管理を徹底することが求められます。
転勤で家族と別居になる場合
従業員が転勤により単身赴任となり、配偶者や子と別居状態になるケースでは、扶養認定を継続するには「生計維持関係」が保たれていることを証明する必要があります。企業としては、仕送りの実績が確認できる書類(振込明細や通帳コピーなど)の提出を従業員に案内し、保険者への提出書類として回収・管理します。
また、加入する健康保険によって判断基準が異なることがあるため、企業側であらかじめガイドラインを確認し、従業員に正確な情報を共有することが重要です。
転勤を機に家族と同居を開始した場合
転勤を機に、これまで別居していた家族(例えば、親や子など)と同居を開始するケースでは、新たに扶養に加えることが可能となる場合があります。この場合、住民票や同居の事実が確認できる書類が必要になります。
企業としては、転居後すぐに従業員に対して扶養追加希望の有無を確認し、条件を満たす場合には「被扶養者(異動)届」の提出とともに必要書類を揃えるよう案内を行います。タイミングを逃さず適切に処理することで、保険証の発行遅延や未加入によるトラブルを防ぐことができます。
扶養状況の再確認と事務処理の注意点
転勤時は、住所や勤務先だけでなく、家族構成や生計状況の変化も発生しやすいタイミングです。そのため、企業側は転勤処理に付随して扶養情報の再確認をセットで実施する体制を整えておくことが効果的です。
「扶養に変更がないか」「扶養解除が必要ではないか」など、従業員に対するヒアリングとともに、変更がある場合は速やかに異動届を提出するよう案内します。変更日から原則5日以内の届出が求められるため、手続き遅延がないよう定型業務として組み込みましょう。
雇用保険の変更手続きのポイントを押さえておこう
従業員の転勤に伴う雇用保険の手続きは、事業者側に責任があります。福利厚生の一環であり従業員の権利のひとつでもあるため、漏れや遅延なく確実に手続きを行うことが求められます。
在籍出向時など、通常とは扱いが異なるケースについても把握しておきましょう。また、企業によっては電子申請が必須の場合もあります。適切な手続きができるよう、常に厚生労働省などの最新情報も確認しておくことをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
健康保険の被扶養者の要件について
日本に在住する人であれば、短期滞在者を除いて国籍にも性別にも年齢にも関係なく、どの人に対しても加入が義務付けられているのが健康保険です。 この健康保険により、病気や負傷、出産や亡く…
詳しくみる厚生年金の受給額はいくら?計算方法も解説
企業などに雇われている方のほとんどは、給与から社会保険料として年金や健康保険、雇用保険などを天引きされていることでしょう。このうち年金については、実際にはどのような仕組みで将来いく…
詳しくみる社会保険とは?種類や扶養・パートの加入条件、内訳も解説!
社会保険とは、広義には【健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険】の5種類を指します。一方で、狭義では【健康保険、厚生年金保険、介護保険】の3種類の総称として使用される…
詳しくみる社会保険料の納入告知書(納付書)とは?領収書としても使える?
社会保険料の納付時には、日本年金機構より納入告知書(納付書)が発行されます。普段何気なく受け取っている社会保険の納入告知書(納付書)ですが、記載項目などを正しく把握しているでしょう…
詳しくみる国民健康保険に扶養はある?加入手続きの注意点も解説
日本は国民皆保険制度を採っているため、全国民に健康保険への加入を義務付けています。退職によって社会保険の資格を喪失した際や、フリーター・アルバイトで親の扶養から外れた場合、自営業の…
詳しくみる厚生年金は何年払えばもらえる?受給資格期間について解説!
厚生年金保険は、会社員や公務員が加入し、老齢になったときや障害を負ったとき、遺族に対して年金の給付を行います。老齢厚生年金は、老齢基礎年金と一緒に支払われます。老齢基礎年金の受給資…
詳しくみる