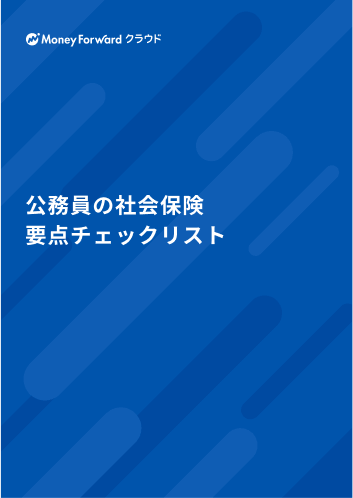- 更新日 : 2025年11月6日
公務員の社会保険は会社員と違う!?自営業についても解説!
公務員と会社員の社会保険には、同じ点もあれば違う点もあります。公務員の年金は会社員と同じ厚生年金保険ですが、健康保険は会社員が協会けんぽや健康保険組合に加入するのに対し、公務員は共済組合に加入する点が異なります。
共済組合には国家公務員共済組合や地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度があります。
目次
社会保険の種類についておさらい
社会保険とは病気やケガ、高齢化、障害、要介護といった誰もが抱えるリスクに対して、社会全体で備える仕組みのことです。医療や年金といった給付を行う公的制度で、健康保険や年金制度などが該当します。
社会保険には広義の社会保険と狭義の社会保険があり、単に社会保険という場合は狭義の社会保険を指すのが一般的です。
- 広義の社会保険の種類健康保険・介護保険・公的年金・労災保険・雇用保険
- 狭義の社会保険の種類健康保険・介護保険・厚生年金保険
この記事では狭義の社会保険について、公務員・会社員・自営業の違いを説明します。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
会社員・公務員・自営業が加入する社会保険は違う
社会保険の加入先は、会社員・公務員・自営業で以下のように異なります。
| 会社員 | 公務員 | 自営業 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 組合健保か協会けんぽ | 共済組合 | 国民健康保険 |
| 年金制度 | 国民年金+厚生年金 | 国民年金+厚生年金 | 国民年金のみ |
公務員の社会保険(共済)の保険料計算方法
公務員は、加入する共済組合に対して保険料を支払います。国民年金は保険料負担義務のない第2号被保険者に該当するため、納付する必要はありません。
共済組合に対する保険料支払額は「標準報酬月額(賞与の場合は標準賞与額)×保険料率」で計算します。保険料率は共済組合によって異なります。
例)標準報酬月額30万円の公務員が支払う社会保険料
- 共済組合掛金30万円×各共済組合の定める料率×1/2※共済組合掛金の半分は雇用先が負担します。
会社員・自営業の保険料計算方法
では、会社員や自営業が支払う社会保険料はどうなっているのでしょうか。計算方法や金額について説明します。
会社員の保険料計算方法
会社員は加入する協会けんぽや組合健保と、厚生年金に対して保険料を支払います。国民年金は保険料負担義務のない第2号被保険者に該当するため、納付する必要はありません。
社会保険料支払額は、公務員と同じように「保険料支払額は標準報酬月額(賞与の場合は標準賞与額)×保険料率」で計算します。協会けんぽや組合健保に対して支払う健康保険料の率は協会けんぽの場合は都道府県、組合健保の場合は団体によって変わります。厚生年金保険料率は18.30%です。
例)標準報酬月額30万円の会社員が支払う社会保険料
- 健康保険料30万円×協会けんぽや組合健保が定める料率×1/2
- 厚生年金保険料30万円×0.183×1/2=2万7,450円※健康保険料・厚生年金保険料ともに、半分は事業主が負担します。
自営業の保険料計算方法
自営業者は、国民健康保険料と国民年金保険料を支払います。
国民健康保険料支払額は市区町村によって異なり、国民年金保険料は月額1万6,520円(2023年度)です。
介護保険はすべての職種で共通
介護保険は市区町村を保険者とする社会保険であるため、公務員・会社員・自営業といった職種による違いはありません。介護保険料は40歳以降から支払いが必要になり、健康保険料と一緒に徴収されます。
リスクの備えとなる社会保険をよく理解し、必要な知識を身につけよう
公務員は共済組合に加入し、各共済組合が定める料率で計算される社会保険料を支払います。会社員が加入する健康保険は協会けんぽか組合健保、加入する年金は厚生年金で、協会けんぽや組合健保が定める料率で計算される健康保険料と、保険料率18.30%で計算される厚生年金保険料を支払います。
自営業者は国民健康保険に加入し、月額1万6,520円の国民年金保険料を支払います。介護保険について、公務員・会社員・自営業の違いはありません。
社会保険は、誰もが抱えるリスクに備えるための大切な制度です。必要な知識を身につけるため、公務員・会社員・自営業の加入先や保険料について正しく理解しましょう。
よくある質問
公務員が加入する社会保険について教えてください。
共済組合に加入し、各共済組合が定める料率で計算される保険料を支払います。詳しくはこちらをご覧ください。
会社員と自営業の人が加入する社会保険は、公務員のものとは別ですか?
公務員は会社員や自営業とは別の、国家公務員共済組合や地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度といった共済組合に加入します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
事業主代理人とは?社会保険との関わりから解説
労働社会保険に関わる労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の各法律には、「事業主代理人」という概念があります。開業社会保険労務士のように多くの企業の手続業務をしている…
詳しくみる育休手当の雇用保険の加入期間は?2人目、3人目はどうなる?
育児休業(育休)を取得している期間は、基本的に雇用保険料が免除されます。 育休は、労働者であればだれもが取得できる権利ですが、育休中は働いていないため無給です。雇用保険料は、働いた…
詳しくみる労働保険の申告書、従業員なし・0人の書き方は?継続・廃止の記入方法
労働保険の年度更新の時期(毎年6月1日~7月10日)が近づくと、申告書の準備が必要になります 。しかし、「前年度は従業員が0人だった」「年度の途中で全員退職して、現在は従業員がいな…
詳しくみる社会保険の厚生年金とは
社会保険に含まれる厚生年金保険はその名のとおり「保険」の意味をもちます。社会保険は主に会社員が保険の加入者(被保険者)となり、万が一の場合には被保険者やその家族を対象に年金の給付が…
詳しくみる給付制限期間中のアルバイトは20時間以上働いても問題ない?注意点を解説
給付制限期間中に20時間以上アルバイトをすると雇用保険の加入条件を満たしてしまい、失業手当(失業給付)を受け取れなくなる可能性があります。 しかし、条件次第では失業手当を受け取りつ…
詳しくみる65歳以上の従業員の社会保険手続き
昨今の高年齢者の増加に伴い、60歳を過ぎた方々が就業を続けるケースが増えてきました。 これは、社会保険の「高年齢者雇用安定法の改正」や「厚生年金の受給開始年齢の65歳への段階的引上…
詳しくみる