- 更新日 : 2025年11月19日
休日出勤手当とは?計算方法や割増率に関して解説!
業務量の増加や急なトラブル対応で、休日出勤をしたことがある方も多いことでしょう。休日出勤をさせた場合、事業主は労働者に対し休日出勤手当を支給しなければなりません。しかし、労使間で協議し事前に振替休日の日程等を定めている場合は、休日出勤手当の支給は不要です。この記事では、休日出勤手当の概要と計算方法、相場等を紹介します。
目次
休日出勤手当とは?
休日出勤手当について紹介する前に、休日の定義について解説しましょう。労働基準法第35条には、
従業員を雇用し働かせている使用者は、労働者に対し週に1日もしくは4週間に4日以上の休日を付与しなければならない
と定められています。労働基準法の定めに従い付与することが義務付けられた休日が「法定休日」です。
一方、週休2日制などで土日に休暇を設けている企業も多いかもしれません。法定休日以外に、労使間の合意に基づき就業規則等に定められた休日を「所定休日」といいます。
例えば週休2日制の場合、1日は法定休日、もう1日は所定休日です。何曜日を法定休日とするかは、業務形態等によって自由に決められます。法定休日と所定休日では扱いが大きく異なるため、混同しないように注意しましょう。
ここでは、法定休日に出勤した場合の割増賃金等について紹介します。
法定休日出勤時の割増賃金とは
冒頭でも紹介したとおり、従業員を雇用している事業主は、労働者に対して一定の休日を付与することが義務付けられています。事前の想定を超える業務量の増加や急なトラブル対応等で法定休日に労働を課した場合は、割増賃金を支給しなければなりません。割増賃金率は、労働基準法第37条および内閣の政令に従い35%となっています。
なお、休日労働を課す場合は、労使間で「時間外・休日労働に関する協定届」を締結し、所管の労働基準監督署に届け出なければなりません。
労働基準法第36条に基づく労使協定であるため、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。36協定には、労働基準法に基づいた時間外労働の上限時間等に関する規定が必要です。通常予見できない急な業務量の増加等で当該上限規定を超えて労働を課さなければならない場合は「特別条項」付与した36協定を締結しなければなりません。特別条項付き36協定には休日労働の上限についても規定されるため、超過しないように十分注意しましょう。
一方、所定休日に出勤した場合は休日労働に該当しないため、休日労働割増賃金を支給する必要はありません。通常の賃金と、時間外労働が伴った場合は時間外労働割増賃金を支給することになります。所定休日労働と法定休日労働では賃金計算上の取り扱いが異なるため混同しないよう気をつけましょう。
参考:労働基準法(第三十七条) | e-Gov法令検索
参考:労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 | e-Gov法令検索
参考:労働基準法(第三十六条) | e-Gov法令検索
振替休日と代休で扱いが異なる
休日出勤した場合、振替休日や代休が付与される会社も多いかもしれません。これらはともに、法定休日に労働を課した代わりに他の労働日を休日とする制度です。一見同じような制度に思われがちですが、賃金計算上の取り扱いは全く異なるため気をつけましょう。
振替休日は、法定休日に労働を課さなければならない場合、「事前」に労使間で協議し代わりの休日を定めます。法定休日と労働日を入れ替える制度であるため、休日に働いても休日労働とは扱われず、割増賃金は支給されません。
一方代休は、業務量の増加等で急遽法定休日に労働を課した場合、「事後」に休日を付与する制度です。法定休日労働に該当するため、当然割増賃金が支給されます。
振替休日と代休の違いを整理すると、下記の通りです。
※1:時間外労働が伴う場合は36協定を締結し時間外労働割増賃金の支給が必要です。
※2:個別に労使協定を締結することで付与することも可能です。
なお、振替休日を付与する場合は、事前に根拠規定を就業規則等に規定しておくか、個別に労使協定を締結する必要があります。一方、代休の場合は就業規則への規定は不要ですが、法定休日労働を課すために36協定の締結が必要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド5選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
有給休暇管理の基本ルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
年次有給休暇管理帳(ワード)
従業員の年次有給休暇の管理は、適切に行えていますでしょうか。
本資料は、すぐにご利用いただけるWord形式の年次有給休暇管理帳です。ぜひダウンロードいただき、従業員の適切な休暇管理にご活用ください。
休日・休暇の基本ルール
休日・休暇の管理は労務管理の中でも重要な業務です。本資料では、法令に準拠した基本のルールをはじめ、よくあるトラブルと対処法について紹介します。
休日・休暇管理に関する就業規則のチェックリスト付き。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
休日出勤手当が発生する場合
休日出勤手当は、休日に出勤したからといって必ず支給されるものではありません。ここでは、どのような場合に休日出勤手当が発生するのか、逆にどのような場合は休日出勤手当が発生しないのかを解説します。
休日出勤手当が発生するケース
事前に振替休日を定めることなく、急遽法定休日に働いた場合に休日出勤手当が発生します。後日代休が付与されたとしても、休日出勤として扱われるため割増賃金の付与対象です。ただし、働いた休日が労働基準法に定められた法定休日である必要があります。何曜日を法定休日とするかは就業規則等に明示されているため、事前に確認しておきましょう。
休日出勤手当が発生しないケース
働いた休日が所定休日だった場合、休日労働に該当しないため休日出勤手当は発生しません。例えば土曜日を所定休日、日曜日を法定休日と就業規則等に定められている場合、土曜日に働いても割増賃金の付与対象外です。労使間の協議に基づき事前に振替休日を定めていた場合も、法定休日労働としては扱われず休日出勤手当は支給されません。
ただし、代わりの休日を定めるタイミングが事後になった場合は、代休扱いなので休日労働割増賃金が支給されます。また、休日出勤の割増にはならないものの、土曜日を出勤することにより週40時間を超える場合は時間外割増(25%)は必要となります。
休日出勤手当が発生するケースに該当する場合は、たとえ1時間だけ働いた場合でも休日労働割増賃金が支給されます。一方、休日出勤手当が発生しないケースに該当する場合は、何時間働いても休日出勤手当なしです。法定労働時間内であれば基本給のみが、時間外労働が伴った場合は残業手当が追加で支給されます。ケースに応じて賃金計算の方法が異なるため気をつけましょう。
休日出勤手当の計算方法
ここまで、休日の定義および休日出勤手当の概要を紹介しました。休日に働いたからといって、必ずしも休日出勤手当が支給されるとは限りません。賃金計算を行ううえでは、前章で紹介した休日出勤手当が出るケースと出ないケースを明確に区別して扱う必要があります。ここでは、休日出勤手当が支給される場合の賃金計算方法を紹介しましょう。
休日手当の割増賃金の計算方法
休日出勤手当は、原則35%の割増賃金です。時給制の場合は、時給の35%が休日労働割増賃金に該当します。月給制の場合にいくら支給されるのかを計算する場合は、まず所定労働時間を確認してください。
所定労働時間とは、労働条件通知書や就業規則に定められた労働時間です。労働基準法で定められた、いわゆる法定労働時間である1日8時間以内であれば、労使間合意に基づき自由に決めることができます。所定労働時間に年間労働日数を乗じ、12ヶ月で除した値が1ヶ月あたりの平均所定労働時間です。
さらに、1ヶ月あたりの平均所定労働時間で月の基礎賃金を除した値が賃金単価となります。
賃金単価の35%が、月給制の方が休日労働した際に支給される割増賃金です。なお、基礎賃金には、一部を除く各種手当が含まれます。労働基準法施行規則第21条に従い基礎賃金から除外する手当は下記の通りです。下記に該当しない手当は、名称に関わらず原則すべて含まれるため気をつけましょう。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
参考:労働基準法施行規則(第二十一条) | e-Gov法令検索
法定休日以外の休日に出勤した場合
基本的に、法定休日以外の所定休日に出勤した場合は手当なしで通常の賃金が支給されます(ただし、土曜日の出勤で週40時間を超える場合には時間外割増(25%)が必要となります)。
時給制の方は通常の時給に労働時間を乗じた金額、月給制の場合は賃金単価に労働時間を乗じた金額です。ただし、1日8時間の法定労働時間を超えて労働した場合は、25%の時間外労働割増賃金が支給されます。
また、会社によっては所定休日労働であっても割増賃金を支給する場合もあるでしょう。通常、就業規則に割増賃金に関する規定があるため、今一度確認してみましょう。その際、祝日の取り扱いについても確認してください。そもそも、祝日は労働基準法に定められた法定休日には該当しないため、1週1休もしくは4週4休の原則さえ守っていれば休日とする義務はありません。就業規則等で祝日を休日として規定している場合でも、所定休日に該当するため割増賃金は支払われないのが一般的です。なお、祝日が会社の所定休日の場合で勤務が発生した場合には、法定内残業として1倍の賃金を支払う必要があります。
例)基本給20万 平均所定労働時間160時間
法定休日・所定休日は休みが取得できたものの、祝日に1日のみ出勤して8時間勤務した場合。
祝日の勤務は法廷内残業の扱いとなるため、基本給20万+法定内残業手当1万=合計21万の支給が必要。
深夜勤務を休日に行った場合
労働基準法には、22時から翌5時の深夜時間帯に労働を課した場合、25%の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。ここで、改めて労働基準法に定められた割増賃金を整理すると下記の通りです。
| 時間外労働 | 休日労働 | 深夜労働 | ||
|---|---|---|---|---|
| 月60時間以下 | 月60時間超 | |||
| 大企業 | 25% | 50% | 35% | 25% |
| 中小企業 | 25% | 25%(※) | 35% | 25% |
※2023年4月以降は大企業と同様に50%となります。
法定休日の深夜時間帯に労働した場合は、労働基準法施行規則第20条に従い割増賃金率が合算され60%となります。ただし、時間外労働の割増賃金と同時に適用されることはありません。なお、所定休日の深夜時間帯に労働した場合は、25%の割増賃金となります。法定休日ならびに所定休日における割増賃金をまとめると下記の通りです。
| 法定時間内労働 | ||
| 法定時間外労働 | ||
| 月60時間超の法定時間外労働 | ||
| 深夜労働 | ||
| 法定時間外労働かつ深夜労働 | ||
| 月60時間超の法定外労働かつ深夜労働 |
参考:労働基準法施行規則(第二十条) | e-Gov法令検索
年俸制・裁量労働制・フレックスタイム制における休日出勤手当の取り扱い
給与体系や勤務制度が多様化する中で、年俸制・裁量労働制・フレックスタイム制を採用する企業も増加しています。これらの制度下でも、休日出勤手当の取り扱いには注意が必要です。
年俸制でも休日出勤手当の支払い義務は生じる
「年俸制だから残業代や休日出勤手当が不要」と誤解されることがありますが、年俸制は給与を年額で契約しているにすぎず、労働基準法の適用を免れるわけではありません。たとえば、法定休日(日曜など)に出勤した場合には、通常の賃金の35%以上の割増手当を支払う義務があります。
年俸制であっても、通常の労働者と同様に時間外や休日、深夜の割増手当を支給する必要があることを忘れないようにしましょう。「年俸制だから手当は不要」などと考えていると未払いの問題が生じてしまいます。
裁量労働制でも休日出勤は例外的に手当の対象になる
裁量労働制は、業務の性質上、労働時間の算定が難しい場合に、あらかじめ定めた「みなし労働時間」に基づいて給与を支払う制度です。このため、通常の時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払い義務は限定的とされています。
ただし、裁量労働制の適用者であっても、法定休日に実際に業務に従事した場合は、休日労働とみなされ、35%以上の割増手当の支払いが必要になります。つまり、裁量労働制が適用されていても、休日出勤については別途把握しなければならず、割増賃金を支払う必要もあるということです。
また、裁量労働制の対象業務や制度の導入要件(労使協定・労使委員会設置など)を満たしていないと、制度そのものが無効となり、通常の時間管理が適用される点も重要です。
フレックスタイム制では清算期間内の労働時間を基準に判断する
フレックスタイム制では、あらかじめ定められた清算期間内(最大3ヶ月)で所定労働時間を満たすように、従業員が日々の始業・終業時刻を自由に決められます。この制度下では、清算期間全体で所定労働時間を超過した場合に限り、時間外労働として割増賃金が発生します。
しかし、法定休日労働については、他の制度と同様に労働基準法により明確に保護されており、35%以上の割増手当の支払いが必要です。
フレックスタイム制では、出退勤時間の自由度が高い反面、休日勤務や清算期間を超える労働の発生に対しては、管理者側の明確な記録と精算が求められます。
管理監督者に対する休日出勤手当の適用除外と注意点
労働基準法では、一部の労働時間規制が管理監督者には適用されないと定められています。しかし、休日出勤手当の取り扱いについても一律に除外されるわけではなく、誤解されやすいポイントです。ここではその法的根拠と注意点を整理します。
管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定が適用除外
労働基準法第41条では、管理監督者については、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されないと明記されています。これにより、原則として管理監督者には残業手当や休日出勤手当の支払い義務がありません。
ここで言う管理監督者とは、単に役職名が課長や部長であるという形式的なものではなく、「経営者と一体的な立場にあり、労働時間の裁量が認められている者」を指します。人事権や予算決定権などの権限、出退勤の自由度、賃金・待遇の面での管理職としての扱いが要件となります。
この「管理監督者性」を正しく理解しないまま、名目上の肩書だけで手当を支払わない対応を取ると、後に不当な労働条件と見なされ、未払い賃金の請求やトラブルに発展するリスクがあります。
管理監督者でも深夜割増は除外されない
多くの企業が見落としがちなのが、管理監督者であっても深夜労働(22時~翌5時)に対する割増賃金の支払い義務は残るという点です。労働基準法では深夜割増については第41条の除外対象とはされておらず、最低25%の割増が必要です。
つまり、管理監督者が休日出勤し、その勤務が深夜時間帯に及んだ場合、休日手当は不要でも深夜手当の支払いは法的義務となります。この点を区別し、勤怠記録を正確に把握することが重要です。
名ばかり管理職への誤認対応に注意する
いわゆる「名ばかり管理職」は、外形上は管理職であっても実質的には労働時間の裁量がなく、待遇も一般社員と変わらないケースを指します。このようなケースで休日出勤手当や残業代を支払わない場合、後に労働基準監督署の指導や裁判により、管理監督者として認められず、未払い手当を請求される可能性があります。
裁判例においても、実態として管理監督者に該当しないと判断された事例は多数あり、企業には慎重な判断と適切な処遇が求められます。管理監督者として扱う場合には、就業規則や労働条件通知書への明示、業務内容と裁量の明確化が重要です。
休日出勤手当の未払いが企業にもたらすリスク
休日出勤手当の支払いは、労働基準法で明確に定められた義務のひとつです。これを怠ると、給与計算ミスにとどまらず、企業に重大な法的・経営的リスクをもたらす可能性があります。ここでは、未払いが招くリスクを整理します。
労働基準法違反による行政指導・罰則
休日出勤手当は、労働基準法第37条に基づき、法定休日に労働が行われた場合に、35%以上の割増賃金を支払う義務があります。これを怠った場合、企業は労働基準法第119条により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される恐れがあります。
また、労働基準監督署による是正勧告や調査対象となることがあり、企業名が公表されたり、行政処分が下されたりするリスクもあります。これにより、企業の社会的信用や採用活動、取引先との関係に悪影響が生じる可能性があります。
従業員からの未払い請求と訴訟
休日出勤手当の未払いは、従業員個人からの未払い賃金請求の対象となるほか、集団訴訟や労働組合による団体交渉の原因にもなります。過去にさかのぼっての請求が認められた場合、多額の未払い金と付加金(遅延損害金)を支払う必要があります。
法改正により、2020年4月以降は賃金請求権の消滅時効が「5年(当面3年間)」に延長されており、それ以前よりも企業の責任期間が長くなっています。これにより、過去数年分の休日出勤に関する手当の未払いが発覚した場合、損害額が数百万円に及ぶケースも想定されます。
社内の労務環境の悪化と離職
休日出勤手当の未払いが常態化している企業では、従業員の不満や不信感が蓄積し、職場のモチベーション低下や離職率の上昇にもつながります。手当が支払われるべき対象者と支払われない管理職の線引きが曖昧な場合、「不公平感」が原因で組織の信頼性が損なわれることもあります。
一度社内で不満が広がると、内部通報やSNSなどを通じて情報が外部に漏れ、企業の評判に傷がつくおそれも否定できません。
休日出勤手当を適正に管理するポイント
休日出勤手当は労働基準法に基づく義務であり、適正に管理しなければ法令違反や未払いリスクにつながります。管理の精度を高め、労使トラブルを未然に防ぐためには、仕組みの整備と日常的な運用ルールの徹底がカギとなります。
休日出勤の事前申請・承認フローを明確にする
適正管理の第一歩は、休日出勤が発生する際の事前申請と承認プロセスを整備することです。従業員が勝手に休日出勤し、後から手当を請求するような事態を防ぐためにも、上長の承認を経た業務命令として記録を残す必要があります。
休日出勤申請書を設け、実施日時・理由・業務内容・承認者などを記載し、紙またはシステム上で保存する仕組みを導入することが推奨されます。口頭での指示や曖昧な指示での対応は避け、記録に基づいた管理を徹底しましょう。
勤怠システムや帳票で労働実績を正確に記録する
休日出勤の手当を正しく計算するためには、勤務時間の把握が前提です。タイムカードや勤怠管理システムでの打刻を義務づけ、実際に出勤した時間を記録する仕組みを整備しましょう。
特に休日勤務では、「出社時刻だけ記録されていて退社時刻がない」「自己申告に頼っている」といったケースがトラブルの原因となります。実働時間をきちんと記録・集計し、労働時間が割増賃金の対象となる法定休日か、振替休日か、所定外労働かを正確に区別する必要があります。
就業規則や給与規定に基づいて計算基準を統一する
休日出勤手当の支給基準は、就業規則や給与規程に明確に定めておくことが重要です。支給基準や支給率などを明文化し、条文化されたルールを設けることで、公平で一貫性のある処理が可能になります。
また、給与計算の締め日や手当の反映タイミングも従業員に説明しておくことで、不安や誤解を防ぎ、信頼関係を築くことができます。
法定休日手当に関して理解を深め、適切な勤怠管理を行いましょう!
法定休日手当について紹介しました。法定休日手当とは、労働基準法に定められた法定休日に労働を課した場合、事業主が労働者に支給しなければならない手当です。
労働基準法では、35%の割増賃金と定められています。一方、労使間合意に基づき就業規則等に規定された所定休日に働かせた場合は、休日労働には該当しないため割増賃金の支給は不要です。所定休日に働いた場合は、通常の賃金が支払われることになります。また、事前に労使間で協議し振替休日の日程を定めていた場合も割増賃金は支払われません。ただし、休日労働の事後に代休を付与した場合は割増賃金の支給が必要です。
休日出勤手当が支給されるケースと支給されないケースを明確に区別し、適切に勤怠管理を行いましょう。
よくある質問
休日出勤手当とは?
休日手当とは、労働基準法に定められた法定休日に労働を課した場合、事業主が労働者に支給しなければならない手当です。労使間合意に基づく所定休日に働いた場合は支給されないため気をつけましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
休日出勤手当の計算のコツは何ですか?
まず、法定休日と所定休日を区別しましょう。法定休日労働は休日出勤手当が支給されます。一方、所定休日労働は支給されません。また、事前に振替休日を定めていた場合も支給対象外です。代休の場合は支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
マイナンバー制度で「住民税のごまかし」が効かなくなる!
マイナンバー制度が導入されると住民税額を計算する際の行政上の手続きが一段とスマートになります。今回はそもそも住民税額はどのように決められているのかというところから、「住民税のごまか…
詳しくみる住民税<普通徴収と特別徴収の違いとは?>
普段は意識しないことですが、税金には国に納める「国税」と地方に納める「地方税」の2種類があります。 住民税は地方税の普通税に該当し、地方自治体が地方税法に則って徴収しています。 地…
詳しくみる有給休暇の基準日を統一することはできる?方法や注意点を解説
有給休暇の基準日を、全社で統一することは可能です。ただし、運用の仕方を間違えると、従業員に不利益が生じたり、法律違反に該当したりする可能性があります。 2019年4月1日に労働基準…
詳しくみる社員紹介で「報酬金50万円」ゲット 税金は引かれる?
近年、にわかに注目を浴びている「リファラル採用」。社員が自社に適任だと思う知人に声を掛け、人事に紹介し、選考へつなげる採用活動です。「採用氷河期」の今、採用コストを抑え、定着率の高…
詳しくみる賃金総額とは?労働保険での意味と平均賃金の計算方法も解説
賃金総額とは、使用者が従業員に対して払う給与や手当などその名前に関わらず、労働の対価として支払われるすべての合計金額を指すものです。労働保険において賃金総額から平均賃金を算出し、さ…
詳しくみる昇給とは?種類や基準、昇給率を用いた計算方法を紹介!
昇給とは、年齢、勤続年数、評価や成績に応じて給与が上がることをいいます。 日本の会社で利用されている昇給制度は、定期昇給とベースアップです。では、それぞれの制度の説明と違いについて…
詳しくみる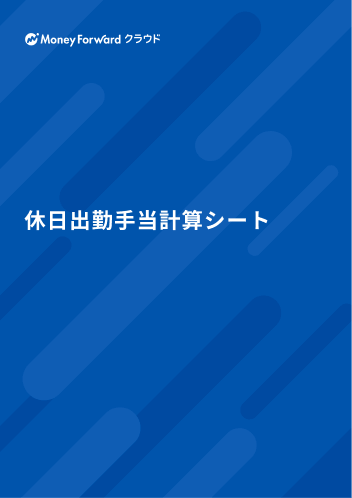


-e1761054979433.png)

