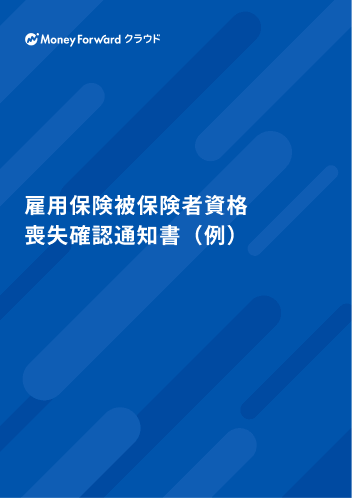- 更新日 : 2025年11月6日
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道やもらうタイミングを紹介
退職した時や雇用保険の加入要件を満たさない労働契約に変更になった際に「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」という書類を受け取りますが、この書類は何に使うか知っていますか。
名称からわかるかもしれませんが、雇用保険の加入者がその資格を喪失したことを通知する書類です。今回は、この通知書の使い道や注意点について見ていきます。
目次
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、退職者に雇用保険の被保険者資格を喪失した証明として渡す書類のことです。
この通知書は、失業給付の受給手続きが不要で離職票を受け取る必要がない場合には発行されますが、離職票の発行を希望した場合には発行されません。
離職票を受け取る場合には、離職票-1が雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を兼ねているからです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
年度更新の手続きガイドブック
年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。
本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
労災対応がよくわかるガイド
前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。
一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の使い道
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、雇用保険の被保険者資格を喪失したことを本人に通知するための書類ですが、基本的に何かの手続きに使用するというものではありません。
ただし、通知書の中の項目に雇用保険被保険者番号、離職日が記載されていますので、それらを証明する書類として使うことはできます。
ですので、雇用保険被保険者証がない場合には、確認通知書でも雇用保険被保険者番号や離職日の確認をすることもできるのです。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書はいつもらえる?
会社は、退職者が被保険者ではなくなった日の翌日から10日以内に雇用保険の資格喪失手続きをしないといけないことになっています。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、資格喪失の手続きが終わり次第、会社から郵送などで受け取ることができます。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の注意点
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をなくした場合は再発行することができるのでしょうか。また、退職者には雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を送りますが、事業主に通知される書類はないのでしょうか。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に関する注意点について見ていきましょう。
再発行の手続き
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を紛失した場合は、ハローワークで所定の手続きを行えば再発行してもらうことが可能です。
具体的には、「雇用保険関係各種届出書等再作成・再発行申請書」に記入して提出することになります。
事業主通知用の書類はある?
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の事業主用の書類としては、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」があります。
事業主通知用の書類も、労働者が雇用保険の資格喪失を行ったことを確認するための書類になりますので、手続き後の書類は会社で保管してください。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは別に退職時に受け取る書類
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、退職時に雇用保険資格喪失の確認のために受け取る書類です。
通常はあまり使うことのない書類かもしれませんが、雇用保険被保険者証がない場合などに雇用保険被験者番号を確認することができます。
中途入社の労働者などが「雇用保険被保険者番号がわからない」と言ってきた場合に、代わりに確認できる書類として労働者に話ができるように覚えておきましょう。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書のテンプレート(無料)
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の使い道を再確認しましょう
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、退職時に雇用保険資格喪失の確認のために受け取る書類です。
通常はあまり使うことのない書類かもしれませんが、雇用保険被保険者証がない場合などに雇用保険被験者番号を確認することができます。
中途入社の労働者などが「雇用保険被保険者番号がわからない」と言ってきた場合に、代わりに確認できる書類として労働者に話ができるように覚えておきましょう。
よくある質問
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とはなんですか?
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、退職者に雇用保険の被保険者資格を喪失した証明として渡す書類のことです。離職票が必要ない場合には発行されますが、離職票の発行を希望した場合には発行されません。詳しくはこちらをご覧ください。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の使い道について教えてください
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、雇用保険の被保険者資格の喪失を本人に通知する書類です。しかし、雇用保険被保険者番号、離職日が記載されていますので、それらを証明する書類とすることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
教育訓練給付金とは?種類や支給要件、手続き方法を解説
教育訓練給付金とは、スキルアップや資格取得などを目的に対象となる講座を受講した際、受講費用の一部が支給される国の制度です。リスキリングや再就職支援にも活用できる制度であり、年収や年…
詳しくみる社会保険の資格取得届とe-Gov電子申請手続きのやり方
社会保険の資格取得届は、社会保険の取得義務が発生した場合に提出する書類です。資格取得届を提出するのは、社会保険の適用事業所が新たに従業員を雇った場合、および勤務形態の変更により社会…
詳しくみる借り上げ社宅制度とは?従業員・会社側のメリットや節税シミュレーション
借り上げ社宅制度とは、企業が契約した賃貸物件を従業員に貸し出す制度のことです。従業員は相場より安い家賃で住めるうえ、企業側にも節税などのメリットがあるため、双方にとって魅力的な制度…
詳しくみる再就職手当とは?受給額の計算方法や手続き方法を解説
再就職手当とは、失業して基本手当をもらっている人になるべく早く再就職するように促すための手当です。早く再就職できた場合の祝い金のようなものとイメージしていただけるとよいでしょう。今…
詳しくみる社会保険の随時改定を行う3つの条件!月額変更届の書き方や残業の影響を解説
昇格などで賃金に大幅な変動があれば、それに伴い社会保険の保険料も改定が必要になります。この手続きを社会保険の随時改定といいます。ただし、臨時手当により1ヶ月だけ賃金が増加したり、残…
詳しくみる厚生年金・健康保険の被保険者資格喪失届とは?手続きや関連書類を解説!
被保険者資格喪失届は、従業員の退職や死亡により健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失する場合の他、転勤や雇用形態変更で同日得喪と呼ばれる処理を行う場合に提出が必要になる書類です…
詳しくみる