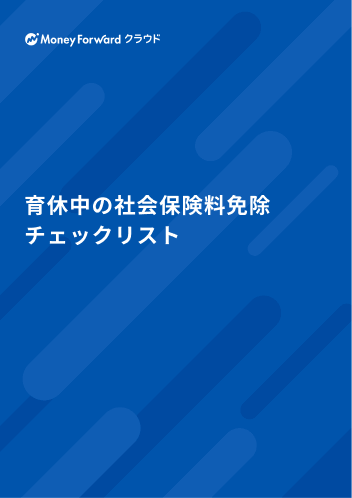- 更新日 : 2025年11月12日
育休中は社会保険料が免除に?手続きの流れや計算方法を解説
社会保険は毎月の給与から保険料が控除されますが、育児休業期間中は免除されます。育児休業とは、育児・介護休業法に定められた1歳に満たない子を養育するための休業期間です。
育休中は事業主が日本年金機構に申請することで保険料の免除を受けることができます。2022年10月から免除要件が変更されたので、詳しく解説します。
目次
育休における社会保険料免除について
従来の免除要件である育休開始日が属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までの保険料に加え、育休開始日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した場合も当該月の社会保険料が免除されます。ただし、育休期間中に就業予定がある場合は、当該就業日は除外となるため気を付けましょう。一方、土日祝日等は期間に含まれます。免除要件をまとめると下記の通りです。
- 育休開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料
- 育休開始日の属する月内に14日以上育児休業を取得した際の当該月の社会保険料
改正によって、開始日と終了日が同一月内にあり、末日に休業していない場合であっても、保険料が免除されるようになりました。例えば、10月5日に育休を開始し10月25日に終了した場合、従来は社会保険料の免除を受けられませんでしたが、2022年10月1日以降は免除対象となります。
10月5日に育休を開始し10月25日に終了した場合

ただし、連続して複数の育児休業を取得した場合は、まとめて1つの育児休業と見なして扱われるため注意しましょう。例えば、10月5日に育休を開始し10月25日に終了、さらに10月26日から11月25日まで育児休業を取得した場合、11月分の社会保険料は免除されません。
10月5日に育休を開始し10月25日に終了、さらに10月26日から11月25日まで育児休業を取得した場合

同時に、賞与にかかる社会保険料の免除要件も変更されています。従来の免除要件では、育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除対象でした。2022年10月1日以降は、賞与を受け取った月の末日を含む、連続した1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限り社会保険料が免除されます。例えば、10月5日に賞与を受け取り10月15日から11月5日まで育休を取得した場合、従来は免除対象でしたが、2022年10月1日以降は免除されません。対して、10月5日に賞与を受け取り10月15日から11月25日まで育休を取得した場合などは免除対象となります。
10月5日に賞与を受け取り10月15日から11月5日まで育休を取得した場合

10月5日に賞与を受け取り10月15日から11月25日まで育休を取得した場合

参考:
育児休業等期間中の 社会保険料免除要件が見直されます。|日本年金機構
令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました|日本年金機構
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
育休の社会保険料免除はいくら?
社会保険料がいくら免除されるのか具体的に計算してみましょう。まず、社会保険料の計算方法は下記の通りです。
健康保険
賞与にかかる健康保険料=標準賞与額×保険料率÷2(労使折半)
賞与にかかる健康保険料=標準賞与額×18.3%(保険料率)÷2(労使折半)
社会保険料
標準報酬月額と標準賞与額は保険料算定の基礎となる値です。健康保険の保険料率は都道府県ごとに異なっており、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合から毎年提示されます。厚生年金の保険料率は全国一律18.3%です。
それでは、下記の条件の方が育児休業を取得した場合、いくら社会保険料が免除されるのかを計算してみましょう。
- 東京都内在住の20代
- 1月5日から12月25日まで育休取得(社会保険料免除対象期間11ヶ月)
- 報酬月額25万円(標準報酬月額24万円)
- 賞与30万円(標準賞与額30万円)
- 賞与は5月30日と11月30日に支給
まず、毎月の給与と賞与にかかる社会保険料を計算してみます。
健康保険
給与にかかる健康保険料=240,000円×(9.81%/100)÷2=11,772円
5月賞与にかかる健康保険料=300,000円×(9.81%/100)÷2=14,715円
11月賞与にかかる健康保険料=300,000円×(9.81%/100)÷2=14,715円
厚生年金保険
給与にかかる厚生年金保険料=240,000円×(18.3%/100)÷2=21,960円
5月賞与にかかる厚生年金保険料=300,000円×(18.3%/100)÷2=27,450円
11月賞与にかかる厚生年金保険料=300,000円×(18.3%/100)÷2=27,450円
社会保険料
給与にかかる社会保険料=11,772円+21,960円=33,732円
5月賞与にかかる社会保険料=14,715円+27,450円=42,165円
11月賞与にかかる社会保険料=14,715円+27,450円=42,165円
社会保険料の免除対象期間は1月から11月までの11ヶ月です。12月は免除対象外なので気を付けましょう。さらに、5月30日と11月30日に支給される賞与にかかる社会保険料も免除対象です。すなわち、休業期間中に免除される社会保険料の総額は下記の通りです。
免除総額=(33,732円×11ヶ月)+42,165円+42.165円=455,382円

参考:令和4年度保険料額表(令和4年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
育休における社会保険料免除の手続き方法
社会保険料の免除を受けるには、事業主を通して日本年金機構に申請しなければなりません。そのため、出産や育児休業の予定が決まったら事業主に申し出ましょう。
1. 従業員から事業主へ申し出る
- 従業員は、育児休業を取得する旨を事業主に申し出ます。
- 事業主は、従業員から「育児休業取得申出書」など、育休の取得に必要な書類の提出を受けます。
2. 事業主が「育児休業等取得者申出書」を作成・提出する
- 事業主は、従業員が育児休業を取得する際に、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/育児休業等終了届」(以下、「育児休業等取得者申出書」)を作成します。
- この申出書を、管轄の年金事務所または健康保険組合に提出します。
- 提出時期
原則として、従業員が育児休業を開始した日(産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は、産後休業終了予定日の翌日)から起算して、その育児休業の期間中に提出します。ただし、実務上は育休開始後速やかに提出することが一般的です。 - 提出方法
電子申請、郵送、または窓口持参などの方法があります。
- 提出時期
3. 社会保険料の免除開始
- 年金事務所または健康保険組合が「育児休業等取得者申出書」を受理すると、育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
- 賞与にかかる社会保険料も、育児休業期間中に支払われる賞与については、その月の末日を含め連続して1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に免除の対象となります(事前に「育児休業等取得者申出書」を提出している必要があります)。
4. 育児休業の延長・終了
- 育児休業を延長する場合
当初の育児休業期間を延長する場合、再度「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。 - 育児休業を終了する場合
従業員が予定より早く育児休業を終了する場合や、育児休業期間が満了した場合には、事業主は「育児休業等取得者終了届」を速やかに年金事務所または健康保険組合に提出します。
従業員(被保険者)が行うこと
- 育児休業の取得を会社に申し出る。
- 会社から求められた書類(育児休業申出書など)を提出する。
- 育児休業期間の変更(延長・短縮)がある場合は、速やかに会社に申し出る。
留意点
- 健康保険組合に加入している場合には、手続きの詳細が異なる場合があります。不明な点は、会社の担当者や加入している健康保険組合、または年金事務所にご確認ください。
- 産前産後休業期間中も、別途手続きを行うことで社会保険料が免除されます(「産前産後休業取得者申出書」の提出が必要です)。育児休業と合わせて手続きを行うことが一般的です。
- 社会保険料の免除を受けている期間も、将来の年金額の計算においては、保険料を納めた期間として扱われます。
育休の社会保険免除手続きに必要な書類
育児休業(育休)中に社会保険料の免除を受けるために必要な書類と提出先についてご説明します。
主に以下の書類が必要となります。
従業員
育児休業の取得を事業主(会社)に申し出る
- 提出先
- 勤務先の事業主(会社の人事・労務担当部署など)
- 補足・注意点
- 通常、会社所定の「育児休業申出書」などの書類を提出します。
事業主
「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)」の作成・提出
- 提出先
- 以下のいずれか該当する先へ提出します。
- 事務センター または 管轄の年金事務所
- 加入している健康保険組合
- 以下のいずれか該当する先へ提出します。
- 補足・注意点
- 従業員からの申し出に基づき作成します。原則として育児休業期間中に提出します(多くは育休開始後速やかに)。電子申請、郵送、窓口持参で提出可能です。
(上記申出書作成のために)従業員から「育児休業申出書」などを受理(社内手続き)
育児休業が終了(または予定より早く終了)した場合、「育児休業等取得者終了届」の作成・提出
- 提出先
- 上記「育児休業等取得者申出書」と同じ提出先
- 補足・注意点
- 育児休業終了後、速やかに提出します。
育休に入るときは社会保険料の免除を受けよう
2022年10月から変更された、育児休業における社会保険料の免除要件について紹介しました。通常社会保険料は毎月の給与と賞与から控除されますが、育児休業取得中は免除されます。給与と賞与それぞれに要件が定められていますが、2022年10月以降は免除要件が変更されています。
給与にかかる社会保険料については、14日以上連続して育児休業を取得した場合、育休開始日と終了日が同一月内にあり、末日に休業していなくても当該月の社会保険料が免除対象となりました。
要件が緩和されたことで、短期間の育休も取得しやすくなったでしょう。一方、賞与にかかる社会保険料については、支給後1ヶ月を超えて継続した育休を取得している場合に限り免除対象となり、要件が厳しくなっています。当記事を参考に新制度の概要を理解し、適切に社会保険料の免除を受けましょう。
よくある質問
2022年10月から適用された、育休における社会保険料免除の変更点について教えてください
給与にかかる社会保険料は、14日以上連続して育児休業を取得した場合、当該月の社会保険料も免除対象となりました。賞与にかかる社会保険料は、支給後1ヶ月以上継続して育休を取得した場合に限り免除対象です。詳しくはこちらをご覧ください。
新制度において、社会保険料はおおよそどの程度免除されますか?
東京都在住の20代の方で、月給25万円、5月30日と11月30日に各30万円ずつ賞与を受け取った方が1月5日から12月25日まで育休を取得した場合、免除期間11ヶ月で免除総額は413,217円です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社会保険の必要書類と手続き方法を紹介! 全体の流れを解説
社会保険ではさまざまな場合で必要な届けを提出します。会社が新たに社会保険の適用を受けるとき、任意適用事業所の申請を行うとき、従業員が入社・退職するとき、家族を被扶養者にするときなど…
詳しくみる社会保険の算定基礎届とは
社会保険料は、会社と従業員である被保険者が必要な金額を折半して負担します。 そして、被保険者が負担する保険料は、毎月支払われる給与や賞与などの報酬に比例した金額です。 しかし、実際…
詳しくみる65歳以上の従業員の社会保険手続き
昨今の高年齢者の増加に伴い、60歳を過ぎた方々が就業を続けるケースが増えてきました。 これは、社会保険の「高年齢者雇用安定法の改正」や「厚生年金の受給開始年齢の65歳への段階的引上…
詳しくみる労働保険への加入方法
労働保険(労災保険と雇用保険)への加入方法を知っていますか?ここでは、労働保険に加入するため手続き、労働保険の加入に必要な各種届出、申告書の主な内容について解説します。 労働保険へ…
詳しくみる週20時間で社会保険加入になる?条件やシミュレーション、手順など解説
「パートのシフトを週20時間以内に抑えるべきか?」「社会保険料はいくらか?」 2024年10月の法改正で51人以上の企業まで適用が拡大され、2025年以降は全企業への導入も議論され…
詳しくみる育休とは?期間や男性の取得、給付金(手当)、給与、会社の手続きまとめ
育児休業は、育児・介護休業法で定められた子育てのための休業制度ですが、産後パパ育休やパパ・ママ育休プラスなどが新設され、制度内容が複雑だと感じる人もいるでしょう。 本記事では、育休…
詳しくみる