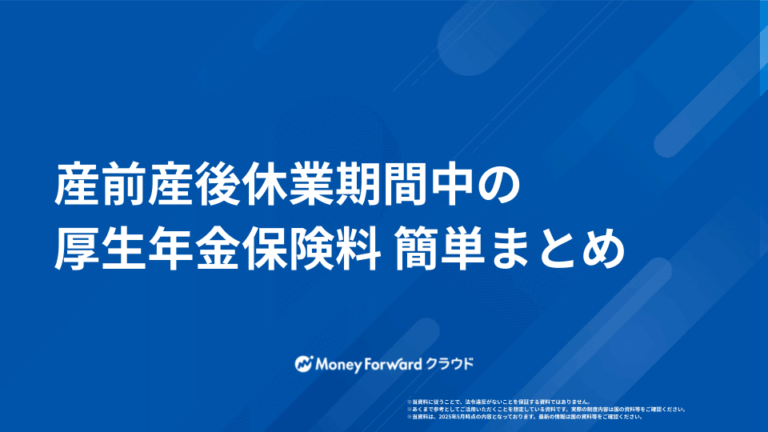- 更新日 : 2025年12月24日
産前産後休業期間中は厚生年金保険料は免除される?育児休業等期間中も解説
経済的な理由で従業員が休業取得をためらうようなことがないように、産前産後休業期間中や育児休業期間中にはさまざまな経済的支援制度が用意されています。
産前産後休業や育児休業期間中に健康保険、厚生年金保険の保険料の免除を受けるには、企業からの申出が必要です。この記事では、免除を受けるための条件や手続きについて解説します。
目次
産休・育休中は厚生年金保険料が免除される?
産前産後休業期間中や育児休業等期間中は、企業が日本年金機構や健康保険組合に申出をすることで、健康保険や厚生年金保険の保険料の支払いが免除されます。
「産前産後休業期間」とは、出産日以前の42日(多胎妊娠のケースでは98日)と産後(出産日の翌日以後)56日目までの期間のうち、妊娠・出産のために勤務しなかった期間のことです。出産日が出産予定日よりも遅くなった場合には、出産予定日以前の42日間が産前休業となります。
したがって、出産予定日より実際の出産日が遅れた場合、産前休業は出産が遅れた日数分だけ長くなることがあります。「出産」とは、妊娠4ヵ月(85日目)以後の分娩を指し、早産、死産、流産、人工妊娠中絶も含まれます。
「育児休業等期間」には、以下の期間が含まれます。
- 1歳に満たない子を養育するための育児休業
- 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳ヵ月に達する日までの育児休業
- 保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
- 1歳(上記イの場合は1歳6ヵ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
- 産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)
引用:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き|日本年金機構
免除期間中は保険料を支払ったものとして取り扱われます。保険料が免除された期間分も従業員が将来受け取る年金額に反映されるため、年金額が少なくなるようなことはありません。
保険料は、従業員負担分だけではなく企業負担分も免除されます。企業と従業員双方にメリットがある制度となっていますので、従業員が産休・育休を取得する際には手続きを忘れることがないようにしましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐
妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。
仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。
育休中の給料・ボーナス 要点簡単まとめ
育休中の給料・ボーナスについて、スライド形式で要点を簡潔にまとめた分かりやすいガイドです。
従業員への配布用にもご活用いただけますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。
産後パパ育休制度の創設で、企業が取り組むべき7つのこと
育児・介護休業法の改正により、新たに「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」が創設されました。
この資料では、産後パパ育休制度の概要と創設される背景をふまえて、経営者や人事労務担当者が取り組むべき実務のポイントを解説します。
産前産後休業期間中の厚生年金保険料免除とは?
産前産後休業期間中は、従業員負担分、企業負担分ともに社会保険料が免除されます。保険料が免除される条件や手続きについて詳しく見ていきましょう。
厚生年金保険料免除の条件
厚生年金保険料が免除されるのは、産前産後休業開始日が属する月から終了予定日の翌日が属する月の前月までの期間です。産前産後休業終了予定日が月末となるケースでは、産前産後休業終了月までとなります。
産前産後休業の取得が保険料免除の条件となりますが、期間中の給与の支払いについての決まりはなく、有給・無給を問いません。厚生年金保険の被保険者となる従業員から産前産後休業取得の申出があった際に、企業が年金事務所に申し出ることによって、厚生年金保険の保険料が免除されます。
厚生年金保険料免除の金額
厚生年金保険料免除の金額は、毎月の厚生年金保険の保険料を計算するもととなる従業員の「標準報酬月額」や、1,000円未満の端数を切り捨てて計算した「標準賞与額」に、厚生年金保険料率(18.300%)を乗じることで算出することができます。
また、標準報酬月額や厚生年金保険料額は、全国健康保険協会のホームページで確認することもできます。
厚生年金基金に加入している場合には、厚生年金保険料率や厚生年金基金の掛金が厚生年金基金ごとに異なるため、それぞれ加入している厚生年金基金で確認するのがよいでしょう。
参考:令和4年度保険料額表(令和4年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
厚生年金保険料免除に必要な手続き
手続きは「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を提出することで行います。この手続きは、産前産後休業中に行うことも、産前産後休業終了後に行うことも可能です。産前産後休業終了後に手続きをする場合には、終了日から1ヵ月以内に提出しなければなりません。
産前休業は出産日以前42日のうち、妊娠・出産のために勤務しなかった期間です。出産予定日より子どもが早く生まれた場合には、出産予定日を基準に計算した産前休業開始年月日よりも実際の産前休業開始日が早まることがあります。
「産前産後休業取得者申出書」記載の際には、産前産後休業開始日と終了日をよく確認しましょう。
厚生年金保険料免除に必要な書類
必要な書類は「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」のみで、添付書類は原則必要としません。ただし、1ヵ月の期限内に手続きができなかった場合には、理由書や出勤簿・賃金台帳などの休業していることが確認できる書類が必要となります。
書式は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。提出先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターです。提出方法には、電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)による方法があります。
産前産後休業を変更・終了したときの手続き
出産予定日より前に子どもが生まれたり、出産予定日より後に子どもが生まれたりすることもあれば、休業していた従業員が予定よりも早く職場復帰をすることもあるでしょう。
産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出していると、産前産後休業期間に変更が生じることや、休業終了予定日よりも早く休業期間が終了することがありますので注意しましょう。
産前産後休業期間に変更が生じたときや、産前産後休業終了予定日より前に休業を終了した際には、速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければなりません。「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」と兼ねていますので、必要事項を記載して提出します。
育児休業等期間中の厚生年金保険料免除とは?
育児休業等期間中は、産前産後休業中と同様に、従業員負担分、企業負担分ともに社会保険料が免除されます。保険料が免除される条件や手続きについて詳しく見ていきましょう。
厚生年金保険料免除の条件
毎月の給与における厚生年金保険料が免除されるのは、育児休業等を開始した日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの期間です。
育児休業終了日が月末となるケースでは、育児休業終了月までとなります。また、開始日と終了日の翌日が属する月が同一月となる場合、開始日が含まれる月に14日以上(土日などの休日を含む暦日)育児休業等を取得することが条件となりますので注意が必要です。
賞与における厚生年金保険料も免除の対象となります。ただし、賞与の場合は、賞与が支払われた月の末日を含む1ヵ月超の休業を取得した場合に免除の対象とされます。
期間中の給与の支払いについての決まりはありませんが、育児・介護休業法に基づく育児休業等を取得することが保険料免除の条件となります。厚生年金保険の被保険者となる従業員から育児休業取得の申出があった際に、企業が年金事務所に申し出ることによって、厚生年金保険の保険料が免除されます。
厚生年金保険料免除の金額
厚生年金保険料免除の金額は、産前産後休業中と同様、毎月の厚生年金保険の保険料を計算するもととなる従業員の「標準報酬月額」や、1,000円未満の端数を切り捨てて計算した「標準賞与額」に、厚生年金保険料率(18.300%)を乗じることで算出することができます。
厚生年金保険料免除に必要な手続き
厚生年金保険料免除の手続きは「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出することで行います。この手続きは、育児休業等の期間中に行うことも、育児休業等の終了後に行うことも可能です。育児休業等の終了後に手続きをする場合には、終了日から1ヵ月以内に提出しなければなりません。
産前産後休業期間中の社会保険料免除については、被保険者となっていれば事業主や会社役員の方も対象です。しかし、育児休業期間中の社会保険料免除は、事業主や会社の役員などは労働者とみなされないため育児・介護休業法が適用されず、申出を行うことができないことになっています。
厚生年金保険料免除に必要な書類
必要な書類は「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」のみで、添付書類は原則必要としません。2022年10月以降、育児休業は分割して取得することが可能となったこともあり、育児休業等を同月内に複数回に分けて取得する際には、育児休業期間の内訳をまとめて記載できる書式になっています。
育児・介護休業法の改正により、育児休業は分割取得が可能となりました。また、新しく産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されたこともあり、休業期間中に一部就労するなど、休業の取得方法もより柔軟になっています。
育児休業等の取得日の計算方法が複雑でわからない場合には、ハローワークで記載方法を問い合わせるのがよいでしょう。
書式は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。提出先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターです。提出方法には、電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)による方法があります。
育児休業等期間を変更・終了したときの手続き
育児休業期間を延長する際や、予定よりも早く職場復帰したり、別の子どもが生まれて産前産後休業を取得したりするなど、育児休業終了予定日より前に休業を終了する際には、延長や終了の手続きが必要です。
育児休業と産前産後休業の保険料免除期間が重複するケースでは、産前産後休業の保険料免除が優先的に適用されることも併せて覚えておきましょう。
書式は日本年金機構のホームページからダウンロードすることが可能です。「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」と同じ書式を兼ねていますので、必要事項を記載して提出します。
育児休業等取得者申出書を出し忘れるとどうなる?
育児休業等取得者申出書を出し忘れて1ヵ月の期限内に手続きができなかった場合には、理由書や出勤簿・賃金台帳などの休業していることが確認できる書類が必要となります。
また、育児休業等取得者申出書の提出を怠ると保険料の免除が受けられないため、毎月休業している従業員の厚生年金保険料が発生し、保険料の支払いが必要となります。この場合、育児休業等取得者申出書を後から提出することで保険料免除が認められれば後日保険料が還付・清算されますが、それまでの間、企業が保険料を負担することになるでしょう。
産前産後休業開始時から育児休業終了時までには、多くの手続きが発生します。手続き漏れが発生しないようにするには、産前産後休業から育児休業終了までの手続きの進捗を管理する工夫が必要となるでしょう。
産前産後休業期間・育児休業期間を正確に把握し、出産手当金・育児休業給付金の申請と併せて、保険料免除の申請・変更・終了の手続きを一元管理できるチェックリストなどを作成すると効果的です。
産休・育休中に利用できる経済的支援制度を有効に活用しましょう
産前産後休業開始時から育児休業終了時までには、社会保険料の免除・出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金など、従業員はさまざまな経済的支援制度が受けられます。
出産から育児までの制度を活用して従業員を支援することは、働きやすい職場環境の実現や従業員のモチベーションアップによる生産性の向上にもつながります。産休・育休中に利用できる経済的支援制度を有効に活用して産休・育休の取得促進を図ることができれば、育児休業人材確保、離職防止、定着率の向上、企業イメージアップなど、企業にさまざまなメリットをもたらすことでしょう。
よくある質問
産前産後休業期間中の厚生年金保険料免除とは?
産前産後期間中に厚生年金保険料の従業員負担分、企業負担分がともに免除される制度のことです。手続きは、企業が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出することで行います。詳しくはこちらをご覧ください。
育児休業等期間中の厚生年金保険料免除とは?
育児休業等期間中に厚生年金保険料の従業員負担分、企業負担分がともに免除される制度のことです。手続きは、企業が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に提出することで行います。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労災で複数の病院にかかった場合、手続きや補償はどうなる?請求方法を解説
労災(労働災害)でケガや病気を負った場合、治療を受ける病院は1か所とは限りません。救急搬送された後、自宅近くの病院に通院を切り替えたり、専門治療やリハビリ目的で複数の医療機関を受診…
詳しくみる雇用保険適用事業所番号とは?必要なケースや取得・確認方法を解説
雇用保険適用事業所番号とは、雇用保険に加入している企業に対して割り当てられる番号です。ハローワークで雇用保険に関連する手続きを行う際に雇用保険適用事業所番号が必要になります。 従業…
詳しくみる厚生年金の加入で年金が2万増える?保険料と受給額の計算方法を解説!
会社員や公務員の方が加入する厚生年金保険。厚生年金保険に加入すると、将来もらえる年金額が増加します。 厚生年金保険料は会社から受け取る給与をいくつかの等級に分けて区分した標準報酬月…
詳しくみる社会保険の健康保険料はどのくらい?計算方法や標準報酬月額の仕組みを解説
健康保険料や厚生年金保険料がどのように計算されるかは、実務に携わる者として当然備えておくべき基礎知識です。社会保険に関する知識が不足したまま給与計算を行うと、従業員から徴収すべき保…
詳しくみる健康保険未加入のリスク
会社に勤めている間は、自分では何もしなくても、会社の社会保険に自動的に加入することになります。しかし、会社を退職したら自分で国民健康保険等の加入手続きを行わなくてはなりません。 転…
詳しくみる失業保険の自己都合は3ヶ月給付?1ヶ月短縮ルールや例外ケース、注意点を解説
「自己都合退職だと、失業保険が出るまで3ヶ月待つ必要がある」 この常識は、近年の法改正により大きく変わりました。特に2025年(令和7年)4月以降は、原則として給付制限期間が「1ヶ…
詳しくみる