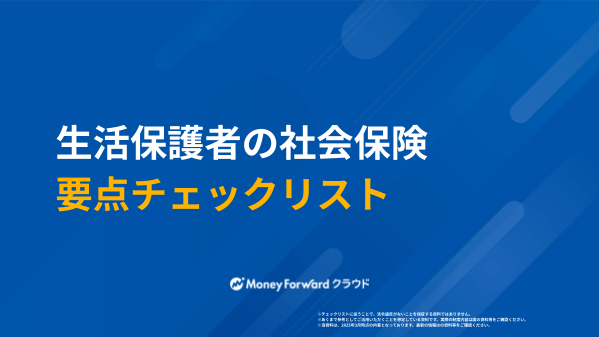- 更新日 : 2025年11月6日
生活保護を受けていても社会保険に加入できる?会社の対応方法
日本では、貧困化が進んでいるといわれています。厚生労働省「被保護者調査」によると、令和6年7月分ですと、生活保護の被保護実人員は2,013,327人となっています。
生活保護における扶助は衣食住がよく知られていますが、医療などの社会保険はどのようになっているのでしょうか。受給者の中には事業所に勤務している人もいます。
本稿では、生活保護を受けている場合の社会保険の加入可否の他、勤務している場合の取り扱いなどについて解説します。
目次
生活保護を受けていても社会保険に加入できる?
生活保護には衣食住の生活扶助・住宅扶助を含めて、教育、介護、出産など8つの扶助があります。
もちろん、疾病や負傷した場合の治療や療養のために医療機関に支払う費用に対する医療扶助もあり、全額を扶助で負担するのが原則となっています。
日本の社会保険には医療保険制度として健康保険・国民健康保険がありますが、生活保護の医療扶助とどのような関係になっているのでしょうか。
生活保護とは?各種保険との関係
生活保護は生活に困窮している人々に対し、生活保護法によって憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々が自立した生活ができるよう援助する制度です。
国が制度の枠組みや全国的な基準を設定しますが、実施機関は市町村を管轄する都道府県です。
医療保険制度は、会社員のように雇用される労働者が加入する「被用者保険」と自営業者などが加入する「地域保険」のに分けられます。ただし、75歳になると全員が「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
被用者保険は健康保険が該当し、全国健康保険協会と健康保険組合が保険者として運営しています。地域保険は国民健康保険が該当し、生活保護と同様に市町村や都道府県が運営しています。
生活保護の受給者の大半は傷病者世帯、高齢者世帯、障害者世帯、母子世帯などですが、最近はその他の世帯も増えています。
これらの世帯は無職、非正規社員、自営業者が大半を占め、医療保険では国民健康保険や後期高齢者医療制度の対象となります。
しかし国民健康保険、後期高齢者医療制度のいずれも、生活保護受給者は加入できません。すでに被保険者となっている場合は、国民健康保険・後期高齢者医療制度から脱退する手続きが必要です。
一方、被用者保険である健康保険に加入している労働者が生活保護受給者になっているケースもあります。確認できるデータでは、被用者保険加入率は2.4%(平成18年被保護者全国一斉調査)です。
国民健康保険、後期高齢者医療制度とは異なり、生活保護受給者となっても脱退する必要はありません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
生活保護受給者の社会保険について会社はどう対応する?
健康保険では、適用事業所に正社員として雇用されれば本人の意思に関係なく、自動的に被保険者となります。事業主は、資格取得の手続きをしなければなりません。
資格取得に給与の金額は問われないため、不況が長引く中、事業所によっては最低賃金程度の低賃金で雇用することもあります。
収入が最低生活費に満たない場合は、不足部分を補うために生活保護費が支給されるため、生活保護受給者であり健康保険の被保険者になっている被用者が生じることになります。最近はその他の世帯が増加していますが、このようなケースもあるでしょう。
生活保護受給者は健康保険を脱退する必要はありませんが、どのような対応関係になっているのでしょうか。
事業所としては対応関係の他、保険料や保険証の扱いについても本人に説明しておく必要があります。
医療扶助と健康保険の対応
生活保護の医療扶助と健康保険の給付は併用されます。
疾病にかかったり負傷したりすると、場合によっては健康保険から療養のための保険給付(原則7割)が優先され、自己負担となる3割部分が生活保護の医療扶助から給付される関係になっています。
自己負担分については自治体から医療券を発行してもらい、本人が医療機関に提出することで無料になりますが、自治体によっては医療機関に医療券を直接送付するところもあるので、確認しておきましょう。
社会保険料は発生する?
生活保護受給者となっても健康保険の被保険者であり、医療費の7割分の保険給付は受けられるため、健康保険料は発生します。また、40歳以上65歳未満であれば介護保険料の納付義務もあります。
なお、生活保護費に加算して支給されるため、実質的な負担はありません。
保険証は発行する?
国民健康保険の場合と異なり、健康保険では被保険者の資格は継続しており、保険証(被保険者証)は発行されます。
前述のとおり自己負担分を生活保護で無料にするために、医療券も発行してもらう必要があります。
生活保護を受けていても社会保険に加入できるか知っておこう!
生活保護を受けている場合の社会保険の加入可否や、事業所に勤務している場合の取り扱いなどについて解説しました。
生活保護受給者数のピークは過ぎたとはいえ、減少に向けた効果的な施策があるわけではありません。
会社が非正規社員として雇用した短時間労働者が、生活保護受給者となる可能性もあります。ギリギリのところで社会保険の適用基準を満たしていれば、健康保険の被保険者になることもあるでしょう。
会社としては、生活保護と社会保険の関係を理解しておくことが大切です。
よくある質問
生活保護を受けていても社会保険に加入できますか?
健康保険には加入できますが、国民健康保険と後期高齢者医療制度には加入できません。詳しくはこちらをご覧ください。
生活保護受給者に対して、会社はどう対応すればよいですか?
健康保険と生活保護の対応関係や、保険料・保険証などについて説明しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【社保⇔国保】転職・退職時の切り替え手続きガイド!金額や期限を解説
会社を退職後、再就職までに1日でも空白期間ができる場合は、原則として社会保険の切り替えが必要です。 その際の選択肢としては、「国民健康保険への切り替え」「健康保険の任意継続」「配偶…
詳しくみる被保険者整理番号とは?健康保険・厚生年金の確認方法と必要な場合を解説
被保険者整理番号とは社会保険の加入手続きの際に発行され、登録内容を変更する際に必要となる番号です。 本記事では、自分の被保険者整理番号が不明という方や人事部の方へ被保険者整理番号に…
詳しくみる雇用保険の喪失手続きはどんなときに必要?期限や書き方も合わせて解説
雇用保険の喪失手続きは、従業員が退職したときや役員に就任したときに行う必要があります。 しかし「どのように手続きすれば良いか分からない」「手続きの流れや期限を把握してスムーズに対応…
詳しくみる派遣社員は産休が取れる?契約期間の関係や給与、給付金を解説
派遣社員として働く方でも、一定の条件を満たせば産休(産前産後休業)を取得できます。ただし、契約期間が短い、契約終了が近いといった場合、手続きや支給対象に不安を抱える方も少なくありま…
詳しくみる労働保険料の納付のしかたをわかりやすく解説
労働保険料は、今年度の保険料を概算で申告・納付すると同時に、昨年度に概算で申告した概算保険料と実際に支払った賃金額から計算した確定保険料との差額の清算を行う「年度更新」と呼ばれる複…
詳しくみる社会保険の扶養はいくらまで?年収130万円・106万円の壁と手取り額
会社員などの扶養家族となっている配偶者や子どもでも、一定金額を超えなければ扶養のまま、パート・アルバイト収入などを得られます。しかし、定められている金額を超えてしまうと、扶養から外…
詳しくみる