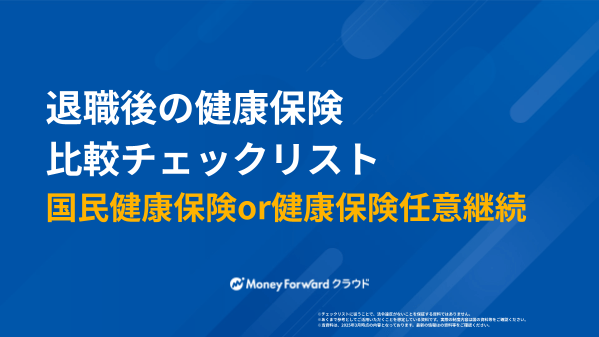- 更新日 : 2025年11月19日
任意継続被保険者の保険料はいくら?加入期間やメリットについても解説!
退職しても任意継続によって、健康保険被保険者資格をそのまま継続することができます。保険料は会社による1/2負担がなくなるため全額を支払う必要がありますが、国民健康保険保険料と比較して安いほうを選べるというメリットがあります。期間は2年間で、任意継続で支払う保険料は確定申告で控除を受けることができます。
目次
そもそも任意継続とは?
会社を退職すると健康保険の被保険者資格を喪失します。別の会社に入社する場合は、その会社で健康保険被保険者資格を取得しますが、そうでない場合は国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、退職する従業員の希望により、国民健康保険被保険者資格を取得せず、健康保険被保険者資格を継続させることができます。この制度を健康保険の任意継続といいます。
任意継続に加入する条件は?
健康保険の任意継続に加入するためには、退職日の前日までに2カ月以上の被保険者期間があることが必要です。2カ月は通算ではなく、継続していなければなりません。また75歳以上は後期高齢者医療制度の対象となるため、任意継続に加入することはできません。
任意継続に加入するメリットは?
任意継続では、保険料について会社からの1/2負担がなくなります。全額が自己負担となり、退職前の2倍の健康保険料を支払わなければならなくなります。ただし、保険料に上限が定められている場合があります。全国健康保険協会の場合、標準報酬月額30万円の保険料が上限に定められています。国民健康保険に加入する場合と比較して安いほうを選ぶことができます。
任意継続に加入する手続きは?
任意継続に加入するには、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書の提出が必要です。
【健康保険任意継続被保険者資格取得申出書の提出方法】
提出先:保険者(全国健康保険協会の場合は事業所の所在地を管轄する全国健康保険協会支部)
提出期限:退職日の翌日から20日以内
添付書類:被扶養者がいる場合は下記の書類
- 戸籍謄(抄)本または続柄の記載された世帯員全員の住民票
- 所得証明書などの年間収入が確認できる書類
- 世帯員全員が記載された住民票(同居の場合)
- 預金通帳の写しなどの仕送りの事実と送金額が確認できる書類
また保険料は、月初めに送付される納付書を用いて、10日までに納付します。金融機関窓口やATM、コンビニエンスストア、インターネットバンキングが利用できるほか、口座振替も可能です。また前納制度があり、6カ月や12カ月をまとめて払うことが可能です。
任意継続に加入できる期間は?
任意継続に加入できる期間は2年間です。2年を越した場合は、国民健康保険に加入するか家族の被扶養者になるかによって、健康保険の給付を受けられるようにする必要があります。
任意継続被保険者の資格を喪失する条件は?
任意継続被保険者は次の条件に該当した場合、資格を喪失します。
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を納付しなかったとき
- 再就職して健康保険被保険者となったとき
- 船員保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者が希望したとき
3.について任意継続被保険者は保険料支払いが1日でも遅れると、資格を喪失します。ただし初めて保険料を納付する場合、正当な理由があると保険者が認めた場合は除かれます。
7.については、2022年(令和4年)1月の健康保険法改正で追加されました。希望の申出があった月の末日に資格を喪失します。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
任意継続の保険料はいくら?
健康保険の任意継続で支払う保険料の金額は、退職時の標準報酬月額で決定されます。
任意継続の保険料はいつから支払いが開始する?
任意継続の保険料は、加入した月から支払いが必要になります。月単位で計算され、月の途中に加入した場合も1カ月分の保険料支払いが必要です。1日に加入した場合も月末に加入した場合も同じ金額の保険料を支払わなければなりません。
任意継続の保険料が途中で変わるケースはある?
任意継続の保険料は加入しているあいだ、原則的に変わりません。ただし、次の場合は保険料が変更になります。
- 40歳に到達し、介護保険第2号被保険者になった場合
- 65歳に到達し、介護保険第2号被保険者でなくなった場合
- 健康保険料率や介護保険料率に変更があった場合
- 標準報酬月額の上限が変更された場合
- 保険料率の違う都道府県に引っ越した場合
任意継続の保険料は確定申告で社会保険料控除の対象となる?
任意継続で支払った保険料は、確定申告において全額が社会保険料控除の対象となります。確定申告では領収書を添付する必要がありますが、紛失してしまった場合は領収書の代わりになる保険料納付証明書の発行を受けることができます。また口座振替で保険料を納付している場合にも、保険料納付証明書が発行されます。
確定申告についての詳細は、次の記事を参照にしてください。
任意継続ではなく国民健康保険に加入する選択肢も
退職すると健康保険被保険者資格を喪失しますが、任意継続被保険者になると健康保険加入が継続されます。保険料は全額の負担が必要ですが、2年間の任意継続が可能です。
また退職後の健康保険は任意継続する以外に、国民健康保険に加入するという方法もあります。国民健康保険は自営業や学生などが加入する、都道府県と市町村による健康保険です。保険料は前年度の収入により決定されるため、次年度以降は任意継続の保険料より安くなる可能性があります。
退職後の健康保険については、次の記事で詳しく説明しています。参考にしてください。
退職後の健康保険はよく考えて任意継続か国民健康保険かを選ぼう
任意継続は会社員が退職した場合に、健康保険加入を継続できる制度です。希望により、退職日から20日以内に申し出ることによって任意継続被保険者となることができます。ただし保険料は、全額を負担しなければなりません。また任意継続できる期間は2年間に限られます。
退職後の健康保険は任意継続以外に、国民健康保険に加入する方法もあります。国民健康保険は自営業などが加入する、都道府県と市町村による健康保険です。任意継続とは加入できる期間や、保険料の金額・決定方法が違っています。相違点についてよく理解し、十分に比較・検討を行った上で任意継続か国民健康保険かを選ぶようにしましょう。
よくある質問
任意継続の保険料はいくら?
任意継続で被保険者が支払わなければならない保険料は、健康保険被保険者資格喪失時(退職時)の標準報酬月額による金額の全額です。詳しくはこちらをご覧ください。
任意継続の保険料は、確定申告で社会保険料控除の対象となる?
任意継続の保険料は確定申告の際に領収書などを添えて申告することで、所得税計算において社会保険料控除の対象とすることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
退職時に会社側が行う社会保険手続きは?離職票と離職証明書の違いも解説!【テンプレ付き】
従業員が退職する際には、決められた期限までに健康保険や雇用保険の喪失届を提出する必要があります。また、従業員が退職後にハローワークに基本手当など失業時に受け取れる給付を申請すること…
詳しくみる厚生年金保険料の計算方法
所得税や雇用保険料ほか、給料からはさまざまな税金や保険料が天引きされていることと思います。 そのなかのひとつ、厚生年金保険料の計算方法をご存じですか? 保険料は、毎月の給料とボーナ…
詳しくみる国民健康保険の免除について
国民健康保険は、病気やけがになったときに、相互に助け合い、経済的な負担を分かち合う制度です。 加入者がそれぞれ保険料を出し合い、さらに国や自治体が税等を出して医療費を負担するもので…
詳しくみる扶養手当とは?支給条件や金額、家族手当との違いについて解説
扶養手当とは、企業が福利厚生の一環として、扶養家族のいる従業員に対して支給する手当のことです。本記事では扶養手当の金額の相場や支給条件、家族手当との違いを解説します。また、育休中や…
詳しくみる法定福利厚生とは?種類や費用、法定外福利厚生との違いを解説!
会社が費用を負担する従業員の福利厚生のうち、法律で定められているものを福利厚生、法律で定められていないものを法定外福利厚生といいます。法定福利厚生は健康保険、厚生年金保険、雇用保険…
詳しくみる算定基礎届の提出期限はいつ?遅れた場合の対処法や提出方法を解説
算定基礎届は社会保険料を決定する大切な届出書で、毎年決まった時期の提出が必要です。提出方法には窓口での提出や郵送、電子申請などがあり、会社の規模やシステム環境によって選択できます。…
詳しくみる