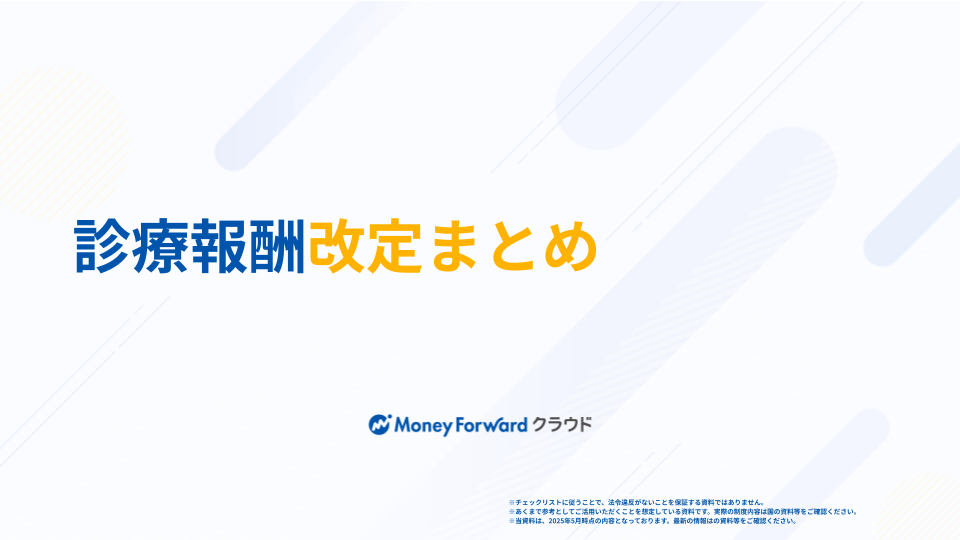- 更新日 : 2025年11月13日
厚生年金の死亡一時金 – 手続きや支給金額について
国民年金に加入し、一定期間保険料を収めていた被保険者が亡くなった際に、遺族は死亡一時金を受け取ることができます。厚生年金加入者が亡くなると遺族厚生年金が支給されますが、条件を満たした場合は死亡一時金も併給が可能です。
この記事では、死亡一時金受給時の手続き方法やいつもらえるのか、また金額はいくらなのかをご紹介します。
目次
厚生年金の死亡一時金とは?
年金保険の被保険者が亡くなった場合、被保険者によって生計を維持されていた親族は遺族厚生年金・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などを受け取ることが可能です。
会社員や公務員など、厚生年金に加入していた第2号被保険者が死亡した場合は遺族厚生年金が、国民年金に加入していた第1号被保険者が亡くなった場合は遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のいずれかが支給されます。
条件を満たした場合は、遺族厚生年金と遺族基礎年金もしくは死亡一時金の併給も可能です。寡婦年金については、1人1年金の原則に従い遺族厚生年金と寡婦年金のいずれか一方を選択受給することになります。
死亡一時金は、国民年金法に定められた給付の1つです。国民年金第1号被保険者として一定期間保険料を納付していた被保険者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま亡くなった際に、被保険者と同一生計の親族に支給されます。
年金ではなく一時金なので、支給されるのは1度だけです。ただし、死亡一時金の申請は被保険者の死亡日から2年以内に行う必要があり、2年を過ぎてしまうと時効となって受給できなくなってしまうため注意しましょう。詳細な受給要件については、次の章でご紹介します。
参考:死亡一時金|日本年金機構
参考:身近な方が亡くなったとき|日本年金機構
参考:年金の併給または選択|日本年金機構
参考:国民年金法 | e-Gov法令検索
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
厚生年金の死亡一時金の受給条件
死亡一時金を受け取るには、死亡した被保険者と遺族の双方に受給要件が定められています。
死亡した被保険者は、国民年金第1号被保険者として36ヶ月(3年)以上保険料を納付していなければなりません。納付期間には法定免除含む全額免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間は含まれませんが、4分の3免除期間は4分の1ヶ月、半額免除期間は2分の1ヶ月、4分の1免除期間は4分の3ヶ月として算入されます。
ただし、後日保険料を追納した場合は「保険料納付済期間」として合算対象です。さらに、生前に障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないことも要件となります。
死亡した被保険者の受給要件をまとめると、下記の通りです。
- 国民年金第1号被保険者として36ヶ月(3年)以上保険料を納付していた
- 障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
遺族の要件としては、亡くなった被保険者と同一生計で、遺族基礎年金の受給資格がなく寡婦年金も受給していない必要があります。同一生計と認められる要件は下記の通りです。
- 住民票上同一の世帯に属していたとき
- 住民票上世帯を異にしていたが、住所が住民票上同一であったとき
- 住民票上住所が異なっていたが、次のいずれかに該当したとき
- 寝食を共にし、消費生活上の家計を一つにしていたと認められるとき
- 単身赴任、就学、病気療養等の止むを得ない事情により住民票上住所が異なっていたが、定期的な音信や訪問があり、生活費や療養費等の経済的な援助を受けていたとき。また、その事情が消滅したときは寝食を共にし、消費生活上の家計を一つにしたと認められるとき
死亡一時金を受給できるのはあくまで同一生計の親族で、亡くなった被保険者に生計を維持されていた必要はありません。そのため、遺族の収入要件などは考慮不要です。
遺族基礎年金が受給できる場合は、死亡一時金は支給されません。また、寡婦年金の受給要件も満たしている場合は、死亡一時金と寡婦年金のどちらか一方を選択して受給することになります。遺族の受給要件をまとめると、下記の通りです。
- 亡くなった被保険者と生計を同じくしていた
- 遺族基礎年金を受給できない
- 寡婦年金を受給していない
死亡一時金の受給には優先順位が定められており、最も優先順位の高い親族のみが受け取ることができます。優先順位は下記の通りです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
なお、前章でもご紹介した通り死亡一時金には時効があるため、被保険者が亡くなってから2年以内に申請するようにしましょう。
参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
参考:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構
厚生年金の死亡一時金を受け取る上の手続き。いつもらえる?
死亡一時金を受給するには、「国民年金死亡一時金請求書」を市区町村、または所管の年金事務所に提出する必要があります。必要書類は下記の通りです。
- 国民年金死亡一時金請求書
- 亡くなった方の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)(提出できないときは、その理由書が必要)
- 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記載することで省略可能)
- 死亡者の住民票の除票(住民票の写しに含まれる場合は不要)
- 受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要
一時金請求を行うと、概ね105日以内に日本年金機構から「一時金支給決定通知書」が送付され、通知書受領後50日程度で一時金を受け取ることが可能です。
なお、死亡の時期が明確ではない場合は「死亡の推定」もしくは「失踪宣告」をもって死亡日となります。
船舶または航空機が沈没・墜落・滅失・行方不明となった際、生死が3ヶ月間わからない場合、もしくは死亡が3ヶ月以内に判明し正確な死亡日がわからない場合は、その船舶または航空機が沈没・墜落・滅失・行方不明となった日が死亡推定日です。東日本大震災によって行方不明となった被災者についても同様に扱われます。
失踪宣告は、一定期間生死不明の状態が続いた者を、法律上死亡したものとみなす制度です。何年もの間音沙汰がなく、生きているのか死んでいるのか分からない場合は「普通失踪」、自然災害や事故によって安否不明の状態が続いている場合は「特別失踪」として扱われます。
普通失踪の場合は行方不明日から7年後、特別失踪の場合は1年後が失踪宣告日です。普通失踪においては失踪宣告日が死亡日として扱われ、死亡一時金の請求権が発生します。特別失踪は、危難が去った日が死亡日です。
死亡一時金における要件判定日をまとめます。
| 死亡の推定 | 普通失踪 | 特別失踪 | |
|---|---|---|---|
| 保険料納付要件 | 行方不明日(死亡推定日) | 行方不明日 | |
| 生計同一関係 | |||
| 身分関係 | 失踪宣告日 | 危難が去った日 | |
参考:死亡一時金、寡婦年金 お手続きガイド|厚生労働省
厚生年金の死亡一時金はいくらもらえる?
死亡一時金の支給金額は、被保険者が国民年金第1号被保険者として保険料を納付していた月数に応じて決まります。老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる「付加保険料」を36ヶ月以上納付していた場合は加算を受けることも可能です。ここでは、死亡一時金の受給金額と厚生年金との併給について詳しくご紹介します。
厚生年金の死亡一時金の受給金額
冒頭でもご紹介した通り、死亡一時金は被保険者が生前に国民年金第1号被保険者として何ヶ月保険料を納付していたかによって支給金額が決まります。保険料納付月数ごとの支給金額は下記の通りです。
| 保険料納付月数 | 支給金額 |
|---|---|
| 36ヶ月以上180ヶ月未満 | 120,000円 |
| 180ヶ月以上240ヶ月未満 | 145,000円 |
| 240ヶ月以上300ヶ月未満 | 170,000円 |
| 300ヶ月以上360ヶ月未満 | 220,000円 |
| 360ヶ月以上420ヶ月未満 | 270,000円 |
| 420ヶ月以上 | 320,000円 |
付加保険料を36ヶ月以上納めていた場合は、上記に8,500円が加算されます。付加保険料とは「国民年金付加年金制度」に係る年金保険料で、月々400円の付加保険料を追加納付することで、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
なお、死亡一時金は非課税所得として扱われ所得税が課税されないため、年末調整や確定申告を行う必要はありません。
参考:死亡一時金、寡婦年金 お手続きガイド|厚生労働省
参考:付加年金|日本年金機構
参考:付加保険料の納付のご案内|日本年金機構
死亡一時金と厚生年金の併給はできる?
公的年金には1人1年金の原則があり、一部の例外を除いて複数の年金を同時受給できないようになっています。しかし、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」「障害厚生年金と障害基礎年金」「遺族厚生年金と遺族基礎年金」などは、同じ事由で支給される同一の年金として扱われるため併給が可能です。
遺族の中に遺族基礎年金を受け取れる「子のある配偶者」や「子」がいない場合は、遺族厚生年金と死亡一時金を併給できます。遺族基礎年金の受給権を有する遺族がいる場合は、条件次第で遺族厚生年金と遺族基礎年金の併給が可能です。さらに、自身の老齢厚生年金・老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給をしている場合でも、死亡一時金は別途受け取ることができます。
死亡一時金の概要を把握し万が一の事態に備えよう
死亡一時金の概要と手続き方法、受給金額、支給時期などをご紹介しました。死亡一時金は遺族基礎年金を受け取ることができない遺族のための制度で、条件を満たせば最大32万円の一時金を受け取ることが可能です。条件次第では遺族厚生年金との併給も可能ですが、請求期間が被保険者の死亡後2年以内と定められているため注意しましょう。当記事を参考に死亡一時金の概要と受給資格を把握し、万が一の事態に備えてください。
よくある質問
厚生年金の死亡一時金とはなんですか?
国民年金第1号被保険者として36ヶ月以上保険料を納付していた被保険者が亡くなった際に遺族が受け取ることができる一時金です。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生年金の死亡一時金の受給条件について教えてください
「亡くなった被保険者と同一生計」「遺族基礎年金を受給できない」「寡婦年金を受給していない」の3点が死亡一時金の受給条件です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
契約社員も育休をとれる!取得条件や手続き方法を分かりやすく解説
出産後も仕事を続ける予定でいるけれど、契約社員でも育休はとれるの?と不安を抱いている方もいるでしょう。しかし、契約社員も一定の条件を満たせば、法律上育休を取得できます。 とはいえ、…
詳しくみる社会保険完備は福利厚生の基本?法定・法定外の種類や福利厚生費についても解説
学生が就職先を決める際は給料や年間休日日数の他、福利厚生がどれだけ充実しているかを重視するといわれています。しかし、多くの人が「社会保険完備」という言葉の意味を深く知らないまま、そ…
詳しくみる週30時間未満の従業員、パートの社会保険加入とは?適用範囲の拡大の変更点を解説
労働時間が週30時間未満のパート・アルバイトについて、2022年10月より社会保険の適用範囲が広がりました。さらに、2024年10月からは常時雇用される従業員数が51人以上の企業ま…
詳しくみる育休中に年金を払わなくても将来減らない?産後パパ育休との違いも解説
育児休業を取得すると年金の支払いはどうなるのか、将来の年金額に影響はあるのかと不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。人事労務担当者や育休を予定している従業員にとって、年…
詳しくみる労働保険の一般拠出金の申告とは?書き方や計算方法を解説
労働保険の年度更新の時期になると、事業主や労務担当者の方は「労働保険料・一般拠出金申告書」の作成に取り組みます。この申告書には労働保険料だけでなく、「一般拠出金」という項目もありま…
詳しくみる労災保険の適用対象者とは?特別加入者についても解説!
労災保険の補償対象は、業務災害と通勤災害です。対象者はすべての労働者で、特別加入制度により中小企業事業主や一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者も給付を受けられます。療養補償等給付…
詳しくみる