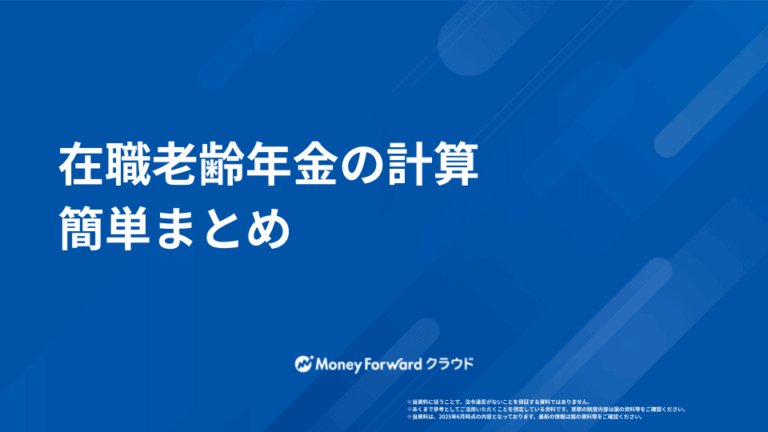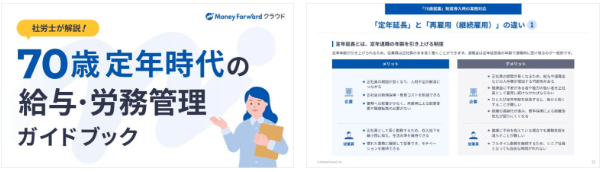- 更新日 : 2025年7月30日
在職老齢年金とは?手続きの有無や計算方法を解説
会社員等は老齢厚生年金を受けられる年齢になっても在職している場合は、年金を受給しながら厚生年金保険に加入し続けることができます。
ただし、収入によっては年金額が支給停止されてしまう場合があるのです。これを「在職老齢年金」と言います。
今回は在職老齢年金とはどのような制度か、手続きや年金額の計算方法について解説します。
目次
在職老齢年金とは?
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受け取りながら在職して、厚生年金保険に加入し続けながら受ける老齢厚生年金のことです。
年金額と給料・賞与の合計が47万円を超える額の場合、47万円を超えた金額の2分の1が年金額から支給停止されます。70歳以上の方は保険料の支払いはなくなりますが、支給停止については同じ取り扱いです。
在職老齢年金については、下記で詳しく解説していますので参照してください。
また、2022年4月施行の法改正による在職老齢年金の支給停止の基準の改正などについては、下記の記事で解説していますので参考にしてください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
在職老齢年金の支給停止期間は?
老齢厚生年金をもらいながら、かつ、厚生年金保険の被保険者である場合に、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額によって年金額が支給停止になる場合があります。
支給停止の条件である基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えている間は支給停止になります。この支給停止中であっても、年金額は改定される場合があります。
ここでは、在職定時改定、退職時改定について見ていきます。
在職定時改定
令和4年3月までは、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であった場合、65歳以降の被保険者期間については、年金額は退職時や70歳到達時の資格喪失時にのみの改定でした。
令和4年4月の法改正により、年金額は在職中であっても毎年10月分から改定する「在職定時改定」という制度が導入されました。
具体的には、毎年9月1日時点での老齢厚生年金受給者の年金額については、前年9月から当年8月までの1年間の被保険者期間を算入し、毎年10月分の年金から改定されることになります。
対象となるのは65歳以上70歳未満である老齢厚生年金の受給者です。
退職時改定
厚生年金保険の被保険者となっている老齢厚生年金の受給権者が会社等を退職した場合、厚生年金保険の資格を喪失します。
その被保険者の資格を喪失した日から再度被保険者になることなく1か月経った場合は、1か月を経過した月から年金額が改定されます。
この改定を「退職時改定」と言います。
在職老齢年金の手続きは必要?
在職老齢年金は、日本年金機構に対して行った手続きにより支給されるかどうかが決まります。
厚生年金保険の老齢年金は、年金の基本月額と給料・賞与によって決められる総報酬月額相当額の合計額に応じて、年金額の一部または全部が自動的に支給停止になります。
給料に変動があったことにより、給料によって決められる標準報酬月額が改定になった場合には、会社が日本年金機構に届け出を行うことになっています。また、賞与が支給される毎に、会社は日本年金機構に届け出を行うことにもなっています。
その結果、総報酬月額相当額が変動し支給される在職老齢年金の年金額が変わった時には、直接本人に日本年金機構からお知らせが届きます。
在職老齢年金の計算方法
在職老齢年金は、以下のようにして判定・計算されます。

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を境にして計算方法が変わります。それぞれの場合の計算方法を見ていきましょう。
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合
在職老齢年金による調整はなく、老齢年金は全額支給されます。
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円超の場合
在職老齢年金による調整後の年金支給月額は、以下の式で計算して求めます。
在職老齢年金を正しく理解して生活設計を立てましょう
在職老齢年金は、年金をもらいながら働き続ける場合に、総報酬月額相当額に応じて受給できる年金が一部または全部支給停止になることがあると説明しました。
年金が調整されて支給停止になるかどうかは、会社が日本年金機構に対して手続きを行った結果の個人個人の総報酬月額相当額によります。
- 自分の総報酬月額相当額は支給停止になるのかどうか
- 支給停止になるとしたらいくらが支給停止になるのか
自分で計算する、会社に相談する、年金事務所で相談するなどの方法で把握して、生活設計をしていきましょう。
よくある質問
在職老齢年金とは?
厚生年金保険に加入し続けながらもらえる老齢厚生年金の制度のことです。年金月額と給料・賞与の合計が47万円を超えた場合、その半額が年金額から支給停止されます。47万円以下の場合は支給停止されません。詳しくはこちらをご覧ください。
在職老齢年金の計算方法は?
年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合には、超えた分の半額、式に示すと「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2」が支給停止されて基本月額から減額されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
全国健康保険協会(協会けんぽ)とは? わかりやすく解説
公的医療保険には、自営業者が加入する国民健康保険(市町村と都道府県が運営)と、会社員が加入する健康保険があります。このうち、健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)と、健康保険組…
詳しくみる一日で辞めた社員も社会保険料が発生する?退職日と保険料の関係を解説!
健康保険や厚生年金保険などの社会保険料は月単位で計算されます。また、月の途中で従業員が退職した場合には、原則として資格喪失月の保険料は発生しません。では、入社してすぐに従業員が退職…
詳しくみる所定労働時間における週20時間とは?計算方法や超える場合の対応について解説
人事労務管理において「週20時間」は、社会保険・雇用保険の適用ラインを決める最も重要な分岐点です。しかし、これが実労働時間ではなく「所定労働時間」で判断される点は、意外と正しく理解…
詳しくみる社会保険料の改定はいつ?タイミングや手続きと計算方法を解説
社会保険料の改定時期は、原則として年1回の「9月」ですが、給与が大きく変動した場合はその「4カ月後」にも変わります。 保険料は、4月から6月の給与平均額をもとに決定される「定時決定…
詳しくみる転職する従業員の社会保険手続き
従業員が転職をするときの社会保険手続きは、現在勤めている会社での社会保険喪失手続き後、転職先の会社での取得手続きの順で行われます。 転職者から回収する書類 転職のために現在の会社を…
詳しくみる週30時間未満の従業員、パートの社会保険加入とは?適用範囲の拡大の変更点を解説
労働時間が週30時間未満のパート・アルバイトについて、2022年10月より社会保険の適用範囲が広がりました。さらに、2024年10月からは常時雇用される従業員数が51人以上の企業ま…
詳しくみる