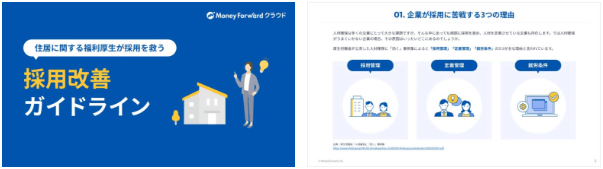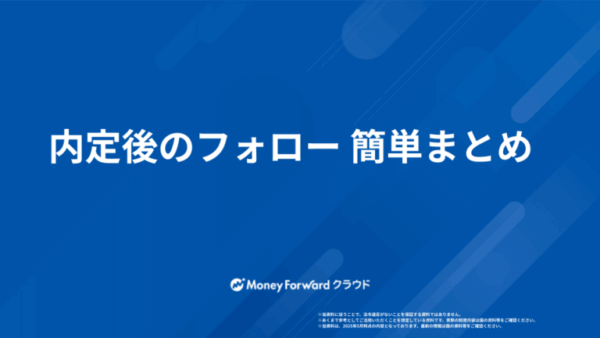- 更新日 : 2025年11月25日
本採用とは?試用期間との違いや拒否(解雇)の可否、企業がすべきことを解説
「本採用」とは、試用期間を経て従業員を正式な一員として受け入れる、人事労務における重要なプロセスです。しかし、この本採用と「試用期間」の法的な違いや、万が一の際に本採用を拒否できるのかについて、正確に理解できているでしょうか。
本記事では、本採用とは何かという基本的な問いに答えながら、試用期間との決定的な違い、本採用拒否が法的に解雇と見なされる理由、そして企業が適切な判断を下すための注意点など、人事労務の初心者がつまずきやすいポイントを分かりやすく解説します。
目次
本採用とは?
本採用とは、試用期間が満了し、企業がその従業員を正規の構成員として長期的に雇用することを最終決定するプロセスを指します。一般的に「正式採用」と同義で使われる言葉です。
試用期間は、従業員の能力や勤務態度、職場への適性などを見極めるための「お試し期間」と捉えられがちですが、法的にはその位置づけが異なります。判例上、企業と従業員の間では、試用期間が始まった時点で既に法的な労働契約は成立していると解されています。
そのため、本採用への移行は新たな契約を結ぶのではなく、試用期間という特殊な状態が終了し、通常の労働契約に移行することを意味します。
本採用の法的な位置づけ:解約権留保付労働契約の終了
本採用の法的なポイントは、試用期間が「解約権留保付労働契約」であるという点にあります。
これは「採用した従業員に適性がないと判断した場合、企業は労働契約を解約する権利を留保(保持)している」という特殊な契約状態を指します。つまり、労働契約自体は使用者と労働者の合意の時点で成立しているのです。
そして、試用期間が問題なく終了し、企業がこの解約権を行使しなかった場合、留保されていた権利は原則として消滅すると解され、以後は解約権の留保がない通常の労働契約として取り扱われます。これが本採用の法的な実態です。
正式採用との違い
本採用と「正式採用」に、法的な意味での明確な違いはありません。どちらも試用期間が無事に終了し、従業員が企業の正規メンバーとして雇用される状態を指す言葉として、ほぼ同じ意味で使われています。
ただし、企業文化や慣習によって、以下のようなニュアンスで使い分けられることがあります。
- 本採用:試用期間の終了を強調する場合
- 正式採用:採用プロセス全体の完了を指し、より広範な意味で使われる場合
どちらの言葉を使うにせよ、重要なのは「試用期間満了後、通常の雇用関係に入った状態」を指すという共通認識です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
本採用と試用期間の決定的な違いは?
本採用後と試用期間中の最も大きな違いは「解雇のハードルの高さ」です。法的には、試用期間中の「本採用拒否」も解雇の一種ですが、本採用後の解雇に比べて、判例上、本採用拒否(留保解約権の行使)は通常解雇より広い裁量が認められ得ます。
ただし、その場合でも「解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」ことが必要です。この違いを理解するために「目的」「労働契約上の位置づけ」「待遇」の3つの観点から比較してみましょう。
| 項目 | 試用期間中 | 本採用後 |
|---|---|---|
| 目的 | 従業員の能力・適性・勤務態度の見極め | 長期的な雇用を前提とした人材育成・配置 |
| 労働契約 | 解約権留保付労働契約 | 通常の労働契約(解約権の留保なし) |
| 解雇の有効性 | 客観的に合理的な理由があれば、本採用後よりは広い範囲で解雇(本採用拒否)が認められる可能性がある | 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない限り、権利濫用として無効となる(労働契約法第16条) |
目的の違い:見極め期間と長期育成
- 試用期間は、履歴書や面接だけでは判断できない従業員の実際の働きぶりや人柄、企業文化へのフィット感などを評価するための「見極め期間」です。
- 本採用後は、その従業員が企業の重要な一員であるという前提に立ち、長期的な視点で教育や研修を行い、能力を伸ばしていくフェーズに入ります。
労働契約上の位置づけの違い:解約権の有無
前述の通り、試用期間は「解約権留保付労働契約」という特殊な状態です。この「留保された解約権」を行使することが「本採用拒否」にあたります。 一方、本採用後はこの権利が消滅するため、従業員を解雇するには、労働契約法第16条が定める「解雇の有効性に関する判断基準」を満たす必要があります。ただし、試用期間中であっても、客観的合理的理由のない解雇や本採用の拒否は、解雇権濫用法理により無効とされる恐れがあるため、慎重に決定しなければなりません。
待遇(給与・福利厚生)の違い:原則同一が望ましい
試用期間中と本採用後で給与などの労働条件に差を設けること自体が直ちに違法となるわけではありません。ただし、その差は「待遇ごとの性質や目的に照らして合理的」である必要があり、不合理な待遇差は、たとえ就業規則に明記しても違法と判断される可能性があります(同一労働同一賃金の原則)。
注意点として、試用期間中の給与を低く設定する場合でも、都道府県ごとに定められている最低賃金を下回ることは許されません。また、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災保険)は、試用期間中であっても加入要件を満たす限り、加入させる義務があります。
試用期間のルール(期間・延長・対象者)はどうなっている?
試用期間の長さ
試用期間の長さについて、法律上の上限はありませんが、実務上は3ヶ月から6ヶ月程度の期間が一般的です。過去の裁判例では1年の試用期間を認めたケースもあれば、合理的ではないとして無効と判断したケースもあり、最終的には業務の性質や個別の事情によって判断されます。
試用期間の延長有無
試用期間は、延長されるケースもあります。ただし、企業が一方的に延長することは認められません。延長するには、あらかじめ就業規則などに延長の可能性・要件を定めた上で、個別の事情においても客観的で合理的な理由(例:長期間の欠勤で評価が困難だったなど)が必要です。
試用期間の対象者
試用期間は、新卒採用か中途採用かを問わず、企業の就業規則などに基づいて適用されます。また、雇用形態も問わないため、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトに対しても試用期間を設定すること自体は可能です。
ただし、期間の定めがある有期契約の場合、契約期間中の解雇は「やむを得ない事由」がなければ認められないなど、無期契約よりも厳格なルールが適用されるため注意が必要です。
試用期間中の労働条件(給与・残業・休暇)はどうなる?
給与や社会保険
- 給与:試用期間中の給与を本採用後よりも低く設定すること自体は合法です。ただし、その場合は雇用契約書に明記する必要があり、都道府県ごとに定められた最低賃金を下回ることは原則として許されません。
- 社会保険・雇用保険:健康保険、厚生年金、雇用保険は「週の所定労働時間が20時間以上」など、それぞれの加入要件を満たす限り、試用期間の初日から加入させる義務があります。
- 労災保険:労災保険は、従業員を一人でも雇用する事業所に強制適用されます。労働者は個別に加入手続きをするのではなく、入社した時点で自動的に保険の保護対象となります。
残業や賞与(ボーナス)
- 残業代:試用期間中の従業員であっても、労働基準法は等しく適用されます。企業が36協定を締結していれば残業を命じることができ、その場合は正規の従業員と同様に残業代を支払う必要があります。
- 賞与(ボーナス):賞与の支払いは法律上の義務ではないため、企業の裁量によります。就業規則などで「試用期間中の者には賞与を支給しない」と定められていれば、それに従うことになります。
有給休暇の付与日
年次有給休暇は①雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されます。
ここでの「雇入れの日」とは、試用期間が開始した日を指します。そのため、試用期間も勤続年数に通算されます。例えば試用期間が3ヶ月であれば、その3ヶ月と本採用後の3ヶ月を合わせて6ヶ月が経過した時点で、要件を満たしていれば有給休暇が付与されます。
試用期間中に本採用を拒否(解雇)することは可能?
可能ですが、それには「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる」ことが絶対条件となります。単に「期待していた能力と違った」「社風に合わない気がする」といった抽象的・主観的な理由だけで本採用を拒否することは、不当解雇と判断されるリスクが非常に高いです。
本採用拒否は、法的には「解雇」に該当します。試用期間中であるからといって、企業が自由に従業員を辞めさせられるわけではないことを、まず大前提として理解しておく必要があります。
本採用拒否が認められる正当な理由
どのような理由であれば本採用拒否が認められるかは、個別の事案ごとに判断されます。過去の裁判例では、主に以下のような類型でその有効性が争われてきました。
- 職務能力や適格性の著しい不足:指導を重ねても改善が見られず、求める水準に著しく達しない場合。
- 重大な経歴詐称:採用の判断を左右するような重要な経歴を偽っていた場合。
- 勤務態度や協調性の著しい不良:頻繁な無断欠勤や、企業の秩序を著しく乱す行為が、指導後も改善されない場合。
いずれのケースでも、企業側が具体的な指導や改善の機会を与えたかが、判断の重要なポイントとなります。
本採用拒否が認められない不当な理由
一方で、以下のような理由での本採用拒否は、権利の濫用として無効になる可能性が高いでしょう。
- 抽象的な能力不足(例:「期待に満たなかった」「成長が遅い」)
- 軽微なミスが数回あった
- 上司や同僚との相性が悪い
- 性格や価値観が社風に合わない
- 企業の業績が悪化した(業績悪化のみを理由に本採用を拒否することは原則として認められず、人員整理が必要な場合は「整理解雇」の厳格なルールに沿って判断される必要があります)
本採用拒否を伝える際の手続きと注意点
もし、やむを得ず本採用の拒否を決定した場合でも、適切な手続きを踏まなければなりません。手続きを誤ると、たとえ拒否理由に正当性があったとしても、紛争に発展する可能性があります。
- ステップ1:問題行動の記録と指導 勤務態度の問題や能力不足が判明した場合、その都度具体的に記録し、本人に対して面談などで注意・指導を行います。指導した内容や、それに対する本人の反応も記録しておくことが重要です。
- ステップ2:改善機会の付与 一度の注意で終わらせるのではなく、改善に向けた具体的な目標を設定し、達成のためのサポート(研修やOJTなど)を行います。本採用拒否は、あくまで「改善の機会を与えたにもかかわらず、改善が見られなかった」場合の最終手段です。
- ステップ3:解雇予告(または解雇予告手当の支払い) 本採用拒否(解雇)では、原則として30日以上前の予告、または30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。ただし、試用期間中で入社14日以内の従業員に限り、この予告は不要となります。
- ステップ4:解雇理由証明書の交付 従業員から請求があった場合、企業は本採用を拒否した理由を具体的に記載した「解雇理由証明書」を交付する義務があります(労働基準法第22条)。ここで曖昧な理由を記載すると、後の紛争で不利になる可能性があります。
試用期間中に従業員から退職することは可能?
従業員が自らの意思で退職することは、法的に認められた権利です。ただし、雇用形態によってルールが異なります。
正社員など「期間の定めのない雇用」の場合
民法第627条に基づき、退職の意思を伝えてから原則として2週間が経過すれば、退職することができます。
多くの会社の就業規則では「退職希望日の1ヶ月前まで」といった規定がありますが、これは円滑な業務引継ぎのための協力依頼の意味合いが強いものです。法律上の効力としては、2週間前の申し出が優先されます。
契約社員など「期間の定めのある雇用」の場合
原則として、契約期間が満了するまでは退職できません。ただし、自身の病気や家族の介護といった「やむを得ない事由」が発生した場合は、契約期間の途中でも退職することが認められます。また、契約開始から1年が経過した後であれば、従業員は期間中であっても自由に退職可能となります。
企業が本採用を見据えて試用期間中にすべきことは?
企業は、従業員の適性を客観的に評価し、適切なフィードバックと成長支援を行うとともに、万が一に備えてコミュニケーションの記録を整備しておく必要があります。トラブルを未然に防ぎ、円滑に本採用へ移行するための具体的なアクションプランが重要です。
評価基準の明確化と共有
試用期間が始まる前に、どのようなスキル、行動、成果を期待しているのか、評価基準を具体的に設定し、本人に明確に伝えておきましょう。「頑張り」といった曖昧なものではなく、「〇〇の業務を一人で完遂できる」「△△のツールを使いこなせる」など、客観的に判断できる基準が望ましいです。
定期的な面談とフィードバック
1ヶ月ごとなど、定期的に1対1の面談(フィードバック面談)の機会を設けましょう。良かった点は具体的に褒め、改善が必要な点については、なぜ改善が必要なのか、どうすれば改善できるのかを丁寧に伝えます。この対話を通じて、認識のズレをなくし、従業員の成長を促します。
指導・教育の実施
従業員の能力が不足していると感じた場合、それを放置するのではなく、OJT(On-the-Job Training、オン・ザ・ジョブ・トレーニング)担当者をつけたり、必要な研修を実施したりして、企業として育成する責任があります。指導や教育を行ったという事実は、万が一の際の重要な証拠にもなります。
コミュニケーション記録の作成と保管
面談の内容、指導記録、注意指導を行った際の書面など、従業員とのコミュニケーションは客観的な形で記録し、保管しておきましょう。これらの記録は、本採用の可否を判断する際の客観的な根拠となり、労務トラブルから会社を守る盾となります。
本採用と試用期間を正しく理解し、健全な労使関係を築くために
この記事では、本採用とは何か、そして試用期間との法的な違いについて詳しく解説しました。重要なポイントは「試用期間も労働契約が成立している」こと、「本採用と試用期間の最大の違いは解雇のハードルの高さにある」こと、そして「本採用拒否(解雇)には客観的で合理的な理由が不可欠」であるという3点です。
企業の人事労務担当者にとっては、試用期間を単なる「お試し」ではなく、従業員の成長を支援し、適性を公正に評価するための重要なプロセスと位置づけることが、後のトラブルを防ぎます。適切な手続きと丁寧なコミュニケーションを通じて、健全な労使関係を築き、円滑な正式採用へと繋げてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
メンタルモデル診断とは?デメリットやメリット、導入時のポイントを解説
社員同士のすれ違いや組織内コミュニケーションの停滞に悩んでいませんか? メンタルモデル診断は、個人やチームの考え方のクセを可視化し、相互理解と信頼関係を深めるツールです。 本記事で…
詳しくみるマネジメント経験とは?求められる基準や役職経験がない場合のアピール方法を解説!
企業が求める人材の中で、マネジメント能力は重要な要素の一つです。しかし、「マネジメント経験」という言葉の意味は必ずしも明確ではありません。単に管理職を経験したことだけでなく、プロジ…
詳しくみるDX人材とは?求められる理由・スキル・育成・採用方法を解説
PointDX人材とは何を指す? DX人材とは、デジタル技術を活用して組織変革を実行する人材です。 ITとビジネスの橋渡し役 経営課題を技術で解決 5タイプに専門分化 DX人材とI…
詳しくみるくるみん認定とは?マークの種類や認定基準、申請方法を解説!
くるみん認定とは、仕事と子育ての両立をサポートする企業に対し、厚生労働省が与える証です。くるみん認定を受けると、自社HPや求人広告にくるみんマークが表示できるほか、さまざまな利点が…
詳しくみる昇進とは?昇格との違いや昇進できる人の特徴、基準の策定方法を解説【無料テンプレ付き】
昇進とは一般社員から主任、主任から課長になるなど、従業員の役職を上げる人事のことです。職能資格制度のもとで等級が上がる昇格とは意味が異なります。昇進の基準・プロセスには、主に人事評…
詳しくみるアルバイトの責任範囲はどこまで?企業が知るべき責任の線引きと離職を防ぐ対策
アルバイトのミスやトラブルが起きたとき、「どこまでアルバイトの責任なのか」判断に悩む場面は少なくありません。 金銭トラブルやSNS炎上、衛生管理の不備などの問題が発生すると、店舗の…
詳しくみる