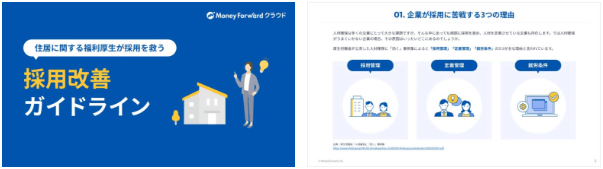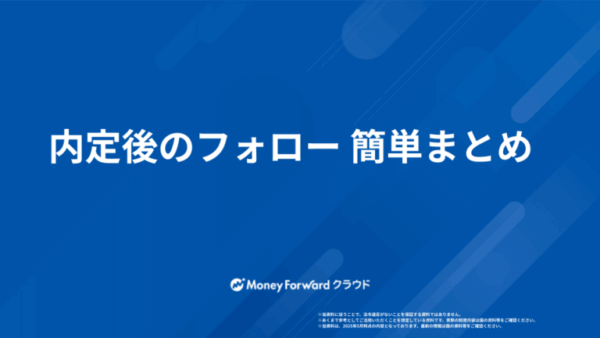- 更新日 : 2025年10月31日
新卒採用のトレンドは?学生の志向変化と企業が取るべき戦略
少子化による学生数の減少などを背景に、新卒採用は、企業が学生を選ぶ時代から、学生が企業を選ぶ「売り手市場」へと移行し、その状況が続いています。採用活動の「早期化」や、学生の価値観の変化に対応した「採用手法の多様化」も進んでおり、従来のやり方では優秀な人材の確保が難しくなっています。
この記事では、最新のデータや調査結果をふまえ、2026年卒以降の新卒採用市場で注目すべきトレンドをわかりやすく整理し、厳しい採用競争を勝ち抜くための具体的な戦略を解説します。
目次
新卒採用のトレンドを語る上で欠かせない「売り手市場」の現状
現在の新卒採用市場を理解する上で、まず押さえておくべきなのが、学生優位の「売り手市場」が続いているという現状です。ここでは、具体的なデータを基に、なぜ採用競争が激化しているのか、その背景を詳しく見ていきましょう。
求人倍率1.66倍、学生母数減も続く背景
2026年3月卒業予定の大学生・大学院生対象の大卒求人倍率は1.66倍にのぼります。これは、民間企業の求人総数と学生の民間企業への就職希望者数の不均衡が起きていることが要因です。少子化の影響で学生の母数自体が減っており、今後もこの傾向は続くと予測されます。企業にとっては、一人の学生を獲得するための競争がますます激しくなっている状況といえるでしょう。
出典:第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)|リクルートワークス研究所
中小企業では約9社で1人争奪戦
とくに、従業員300人未満の中小企業における求人倍率は、2026年卒実績で8.98倍という非常に高い水準でした(2025年卒は6.50倍)。これは、約9社で1人の学生を奪い合う計算になります。大手企業に人気が集中しやすいなか、中小企業はより厳しい採用環境に置かれているのが実情です。知名度や規模以外の魅力をいかに伝え、学生との接点をつくっていくかが大きな課題となっています。
出典:第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)|リクルートワークス研究所
人気学生への争奪戦と市場の傾向
売り手市場のなかでも、とくに専門性の高いスキルを持つ学生や、地頭の良さ、コミュニケーション能力に長けた学生には、複数の企業から内定が集中する傾向があります。企業側は、こうした人気学生層にいかに早くアプローチし、自社の魅力を伝えられるかが採用成功の分かれ目となります。そのため、従来の画一的な採用活動ではなく、個々の学生に合わせたアプローチや、より早期からの接触が求められるようになっています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
新卒採用のトレンド「早期化」と「長期化」の実態
売り手市場を背景に、新卒採用のスケジュールは年々「早期化」しています。同時に、学生との接触期間が長くなる「長期化」という側面も持ち合わせています。この2つのトレンドを理解することが、現代の採用戦略を立てる上で欠かせません。
選考解禁前のプレ期スタートの企業多数
政府が要請する採用選考活動の開始時期は、卒業・修了年度の6月1日以降とされています。しかし、実態としては、それよりも前に多くの企業がインターンシップや会社説明会といった名目で学生との接触を開始しています。事実上の選考活動が「プレ期」に前倒しされており、6月の選考解禁を待っていては、すでに多くの学生が内々定を得ているという状況も珍しくありません。
大学2年〜3年から動き出す学生との接点設計
企業の動きに呼応するように、学生側の就職活動開始時期も早まっています。大学3年生の夏に行われるサマーインターンシップへの参加は一般的になり、最近では大学1・2年生向けのキャリアイベントやインターンシップを実施する企業も増えてきました。企業としては、より早い段階から学生との接点を持ち、自社を認知してもらうための長期的な関係構築が求められています。
活動の長期戦スタイルが主流に
採用活動の早期化は、結果として採用期間の「長期化」をもたらします。大学3年生の春から始まり、内定式、そして入社後のフォローまで含めると、一人の学生との関係は2年近くに及ぶこともあります。この長い期間のなかで、学生の志望度を維持・向上させ、内定辞退を防ぐための継続的なコミュニケーションが重要です。採用活動は短期決戦ではなく、長期的なエンゲージメントを築く活動へと変化しているのです。
【Z世代の価値観】新卒採用トレンドにみる学生の企業選び
採用活動を成功させるには、ターゲットである学生、いわゆる「Z世代」の価値観や就職活動に対する考え方を理解することが不可欠です。彼らが企業選びで何を重視しているのかを知ることで、より効果的なアプローチが可能になります。
初任給を重視する傾向
近年の物価上昇などを背景に、学生が企業選びで「給与水準」を重視する傾向が強まっています。初任給の高さを「社員にきちんと還元する企業」という評価指標の一つとして捉えていることの表れかもしれません。給与体系の透明性を高め、その根拠を丁寧に説明することが求められます。
リアル志向&情報透明性重視が増加傾向
Z世代は、オンラインでの情報収集に長けている一方で、企業の実態については「リアル」な情報を求める傾向があります。企業のウェブサイトやパンフレットにあるきれいな情報だけでなく、実際に働く社員の生の声や、職場の雰囲気、ときには企業の抱える課題といった、オープンで透明性の高い情報に価値を感じます。オンライン説明会とあわせて、対面でのイベントや社員との座談会を設け、等身大の姿を見せることが学生の信頼感につながるでしょう。
SNS・動画採用など「等身大」の発信が響く時代
情報収集の主な手段としてSNSを日常的に利用するZ世代にとって、SNSを通じた企業からの情報発信は非常に有効なアプローチです。とくに、テキストだけでなく、動画やショート動画を活用し、社員の日常や働く様子をカジュアルに伝えるコンテンツは、学生に親近感を与えます。作り込まれた広報用のコンテンツよりも、社員が登場する「等身大】の発信が、彼らの心に響きやすい時代といえます。
新卒採用トレンドを反映した多様な採用手法
売り手市場と学生の価値観の変化に対応するため、企業が用いる採用手法も多様化しています。従来のナビサイトに登録して待つだけの「待ちの採用」から、企業側から積極的にアプローチする「攻めの採用」へとシフトしています。
ダイレクトリクルーティングが浸透中
ダイレクトリクルーティングは、企業がデータベースなどから自社に合いそうな学生を探し、直接スカウトを送る採用手法です。ナビサイトでは出会えない層の学生にアプローチできる点や、学生一人ひとりに合わせたメッセージで熱意を伝えられる点がメリットです。多くのサービスが登場しており、新卒採用における主要な手法の一つとして定着しつつあります。
SNS採用・リファラル・オンライン選考など多チャネル化
採用チャネルは多岐にわたります。X(旧Twitter)やInstagramなどを活用した「SNS採用」、社員の知人や友人を紹介してもらう「リファラル採用」、地理的な制約なく選考を進められる「オンライン選考」など、さまざまな手法を組み合わせることが一般的になっています。
自社の採用ターゲットやカルチャーに合ったチャネルを複数活用し、学生との接点を最大化することが重要です。
| 採用手法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ダイレクトリクルーティング |
|
|
| SNS採用 |
|
|
| リファラル採用 |
|
|
| オンライン選考 |
|
|
採用DX/ATS導入による効率化
採用活動が多様化・長期化するなかで、人事担当者の業務負担は増大しています。そこで注目されているのが、テクノロジーを活用して採用業務を効率化する「採用DX」です。
とくに、応募者情報を一元管理し、選考の進捗状況などを可視化する「ATS(Applicant Tracking System:採用管理システム)」の導入は、煩雑な事務作業を削減し、人事担当者が学生とのコミュニケーションといったコア業務に集中するために有効な手段です。
新卒採用後は内定辞退防止と入社後の定着が重要
厳しい採用競争を勝ち抜き、ようやく内定を出しても、安心はできません。学生一人あたりが複数の内定を保持することが当たり前になった今、「内定辞退の防止」と、入社後の「早期離職を防ぐための定着支援」が、採用活動におけるきわめて重要なテーマとなっています。
内々定率が過去最高水準(87.8%)に
2026年卒の学生の就職内々定率は、2025年7月末時点で87.8%と、同時期としては過去最高値を記録しています。これは、採用活動の早期化がいかに進んでいるかを示すデータです。多くの学生が早い時期に複数の内定を持っているため、企業は内定を出した後も、学生の志望度を維持し、自社を選んでもらうための働きかけを継続しなくてはなりません。
出典:【26卒採用】2025年7月末の内々定率は「87.8%」で過去最高。理系は“9割超え”を維持|HRpro
内定者フォローは必須施策に
内定から入社までの期間、学生の不安を解消し、入社意欲を高めるための「内定者フォロー」は、今や必須の施策です。定期的な連絡はもちろん、内定者同士や先輩社員との懇親会、社内イベントへの招待、入社前研修などを通じて、学生との関係性を深めていきます。
学生が「この会社で働くのが楽しみだ」と感じられるような、丁寧で継続的なコミュニケーションが内定辞退を防ぐ鍵となります。
早期定着のためのエンゲージメント構築
採用は、学生が入社したら終わりではありません。入社後のミスマッチによる早期離職は、企業にとっても本人にとっても大きな損失です。採用段階から、企業のありのままの姿を伝え、期待値を適切にコントロールすることが重要です。
また、入社後も定期的な面談(1on1ミーティング)やメンター制度などを通じて、新入社員の状況を把握し、孤立させないためのサポート体制を整えることが、エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高め、早期定着につながります。
2026年卒以降の新卒採用トレンドをふまえた実践的戦略
これまで見てきたトレンドをふまえ、2026年卒以降の採用活動で成功するために、企業はどのような戦略をとるべきでしょうか。ここでは、明日からでも始められる具体的なアクションプランを3つ紹介します。
インターンシップと採用を連携させる戦略
もはやインターンシップは、単なる就業体験の場ではありません。学生にとっては企業を深く知る機会であり、企業にとっては自社の魅力を伝え、優秀な学生と早期に接点を持つための重要な採用活動の一環です。とくに、一定期間、実際の業務に近い内容を体験してもらう実践的なインターンシップは、学生の入社意欲を高め、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
インターンシップで得た学生の情報をその後の選考に活かすなど、採用プロセス全体と連携させた戦略的な設計が求められます。
大学との関係構築とリクルーター活用
大学のキャリアセンターや就職課との良好な関係構築は、採用活動の基盤となります。定期的に訪問して情報交換を行ったり、学内での説明会を積極的に開催したりすることで、自社に合った学生を紹介してもらえる可能性が高まります。
また、自社の若手社員に「リクルーター」として母校を訪問してもらい、後輩である学生と直接コミュニケーションをとってもらう方法も有効です。学生にとっては、年齢の近い先輩からリアルな話を聞ける貴重な機会となり、企業への親近感を醸成することにつながるでしょう。
採用ブランディングの必要性と方法
採用ブランディングとは、「この会社で働きたい」と学生に思ってもらうための魅力づくりとその発信活動のことです。単に求人情報を出すだけでなく、「自社がどのような価値観を大切にし、社会にどう貢献しているのか」「ここで働くとどのような成長ができるのか」といったストーリーを伝えることが重要になります。自社のウェブサイトやSNS、社員インタビュー記事などを通じて、一貫性のあるメッセージを発信し続けることで、企業のファンを増やし、採用競争における独自のポジションを築くことができます。
新卒採用のトレンドを理解し変化に対応する戦略が成功のポイント
本記事では、新卒採用市場における最新のトレンドについて解説しました。市場は「売り手市場」が続き、活動の「早期化・長期化」が進んでいます。また、Z世代の価値観の変化に対応し、ダイレクトリクルーティングやSNS活用といった「攻めの採用」へとシフトしています。
同時に、内定辞退防止や入社後の定着支援もこれまで以上に重要度を増しています。これらの変化は、一部の大企業だけのものではありません。2026年卒、2027年卒の採用を成功させるためには、こうしたトレンドを正しく理解し、自社の状況に合わせて採用戦略を柔軟にアップデートしていくことが不可欠です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
パーソナルスペースとは?男女による違いや職場や商談での活用について解説
「パーソナルスペース」という言葉は、プライベートスペースの親密な関係について語られることも多いです。しかし、今回はビジネスパーソンに向けて、職場や商談といったビジネスシーンでのパーソナルスペースに焦点を当てます。本記事で紹介するのは、パーソ…
詳しくみるフォロワーシップとは?意味や定義を具体例をもちいて解説
フォロワーシップとは、組織の成功や発展を目的にリーダーや周囲のメンバーを支援することです。組織が成果を生み出すにはリーダーシップだけではなく、フォロワーシップも欠かせません。本記事ではフォロワーシップの定義や育て方、フォロワーシップが発揮さ…
詳しくみるTAL適性検査とは?結果の活かし方や採用、人材配置までの活用術を解説
採用活動において、応募者の人柄やストレス耐性といった内面を面接だけで見抜くのは難しい課題です。その解決策として注目されているのが「TAL適性検査」。この記事では、TAL適性検査とは何か、SPIとの違いといった基礎知識から、検査結果を採用選考…
詳しくみるアンケートの作り方と例文を徹底解説!人事・採用担当者が押さえるべきコツとは
採用活動や社内施策の改善で欠かせない「アンケート」ですが、次のような悩みを抱える人事・採用担当者も多いのではないでしょうか。 「質問項目が多くなりすぎて回答率が下がる」 「どんな設問形式にすれば有効なデータが取れるのかわからない」 「結果を…
詳しくみる裁量権とは?定義やメリット・デメリット、裁量労働制について解説!
働き方改革が叫ばれる中、企業には従業員一人ひとりに合った柔軟な勤務体制の整備が求められています。その一つの選択肢として「裁量権の付与」と「裁量労働制の導入」があります。この記事では、裁量権の意味と効果的な運用の仕方、裁量労働制の概要とメリッ…
詳しくみるキッズウィークとは?実施の目的や取り組み・メリットなどを解説
少子化対策や働き方改革の観点から、注目を集めているのがキッズウィークです。 本記事では、キッズウィークの概要や実施の目的、実際に制度を導入した自治体および導入を検討している自治体を紹介します。 企業がキッズウィークを導入するメリットやデメリ…
詳しくみる