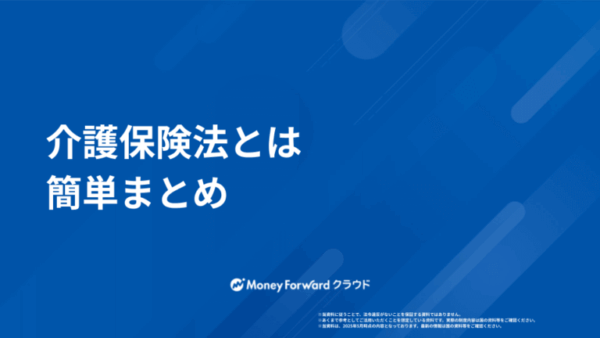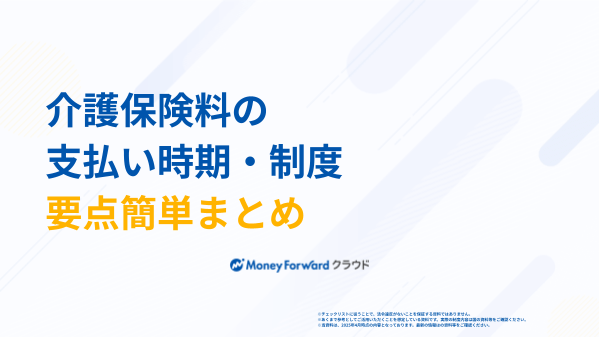- 更新日 : 2025年9月26日
介護保険料は年齢でどう変わる?40歳から65歳以上をシミュレーション
「40歳になったら、給与の手取りが減った気がする」「65歳になったら年金から何か引かれている」。それは、「介護保険料」ではないでしょうか。介護保険料は、将来の介護に備えるための重要な社会保険料ですが、年齢によって支払う金額や納付方法が変わります。
この記事では、介護保険料が年齢によってどう変わるのか、いつからいつまで支払うのか、そして「いくら払うのか」を具体的なシミュレーションを交えて、わかりやすく解説します。
目次
介護保険料は年齢で区分!何歳から何歳まで払う?
介護保険料は、40歳から一生涯にわたって支払う公的な保険料です。ただし、年齢によって保険の加入資格が2種類に区分されており、保険料の計算方法や納付方法が大きく異なります。まずは、この基本的な仕組みを理解することが第一歩です。
介護保険料の支払いは40歳からスタート
介護保険の被保険者(加入者)となるのは、国内に住所がある40歳以上の方です。したがって、保険料の支払い義務は、40歳に達したときから始まります。具体的には、40歳の誕生日の前日が属する月から、保険料の徴収が開始されます。
たとえば、8月15日が40歳の誕生日であれば、8月分から介護保険料を支払うことになります。
第2号被保険者(40歳~64歳)の仕組み
40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」に区分されます。この期間の介護保険料は、会社員や公務員であれば、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)の保険料と一体で徴収されます。
つまり、毎月の給与から健康保険料とセットで天引きされる形が一般的です。自営業の方などは、国民健康保険料に上乗せして納付します。
第1号被保険者(65歳以上)の仕組み
65歳になると「第1号被保険者」に切り替わります。ここが大きな変更点です。保険料は、それまで加入していた健康保険から切り離され、お住まいの市区町村が直接徴収する形に変わります。
納付方法は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となりますが、年金額によっては納付書や口座振替で納める場合(普通徴収)もあります。
介護保険料は一生涯支払う必要がある
介護保険料の支払い義務は、生涯続きます。「いつまで」という終わりはなく、亡くなるまで納付が必要です。これは、介護保険制度が、現役世代が高齢者を支えるだけでなく、高齢者自身も負担し合うことで成り立っているためです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐
妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。
仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
介護保険法とは かんたん解説ガイド
介護保険法の概要や仕組みについて、わかりやすく解説したガイド資料です。
制度への理解を深めるための学習用資料や、社内研修の参考情報としてご活用ください。
介護保険料の支払い時期・制度 要点簡単まとめ
介護保険料の支払い時期や制度の仕組みについて、要点を簡潔にまとめた資料です。
実務における確認用や、制度理解を深めるための参考資料としてご活用ください。
介護保険料の計算方法は年齢でどう違う?
介護保険料が年齢によって異なる理由は、その計算方法が40歳~64歳(第2号)と65歳以上(第1号)で異なるからです。ここでは、それぞれの計算の仕組みを詳しく見ていきましょう。
第2号被保険者(40歳~64歳)は「加入する健康保険」で料率が変わる
会社員や公務員の場合、第2号被保険者の介護保険料は給与や賞与の額(標準報酬月額・標準賞与額)に、加入する健康保険ごとに定められた「介護保険料率」を掛けて計算されます。
この介護保険料率は、全国一律ではありません。 全国健康保険協会(協会けんぽ)や、各企業が設立している健康保険組合などが、それぞれ独自に料率を設定しています。そのため、給与が同じでも、勤め先の会社がどの健康保険に加入しているかによって、支払う保険料が変わります。
計算式(賞与):標準賞与額 × 介護保険料率
保険料は会社と従業員で半分ずつ負担(労使折半)します。たとえば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、2025年度の全国一律の料率は1.59%です(労使折半で自己負担は0.795%)。
第1号被保険者(65歳以上)は「所得と自治体」で負担額が変わる
65歳以上の方の保険料は、お住まいの市区町村ごとに定められた「基準額」と、本人の前年の所得に応じた「所得段階別の保険料率」によって決まります。
「基準額」は、その市区町村で必要とされる介護サービスの総費用を、65歳以上の人口で割って算出され、3年ごとに見直されます。
所得段階は、多くの自治体で9~16段階程度に設定されており、低所得者には負担が軽く、高所得者には重くなるよう調整されています。
こちらも、全国一律ではありません。 基準額そのものが市区町村の介護サービス費用や高齢者人口によって異なります。そのため、介護サービスが充実している都市部や、高齢者人口の多い自治体では基準額が高くなる傾向があります。
介護保険料はいくら払う?年齢別でシミュレーション
では、実際にどれくらいの介護保険料を支払うことになるのでしょうか。具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。
年収400万円の45歳会社員(第2号)のケース
東京都在住で、協会けんぽに加入する45歳の会社員Aさんのケースで見ていきます。
- 年収:400万円(月収約33万円、賞与なしと仮定)
- 標準報酬月額:34万円
- 介護保険料率:1.59%(2025年度 協会けんぽ)
Aさんの月々の介護保険料の総額は、
このうち、会社が半分を負担するため、Aさんが給与から天引きされる自己負担額は、 5,406円 ÷ 2 = 2,703円 となります。
年金月額20万円の70歳(第1号)のケース
東京都新宿区に在住し、年金収入のみで暮らす70歳のBさんのケースです。
- 年金収入:年額240万円(月額20万円)
- 新宿区の基準額(第9期:2024~2026年度):月額6,600円
- 所得段階:合計所得金額125万円以上250万円未満の場合「第7段階」と仮定
- 保険料率:1.2倍
Bさんの月々の介護保険料は、
となります。 この金額が、原則としてBさんの年金から天引きされます。
※実際の基準額や所得段階区分は、お住まいの市区町村の公式サイトで必ずご確認ください。
介護保険料の納付方法は年齢でどう変わる?
介護保険料の納付方法は、年齢(被保険者の区分)によって明確に異なります。とくに65歳になるタイミングで自動的に切り替わるため、注意が必要です。
40歳~64歳は「給与天引き」が基本
第2号被保険者の場合、会社員であれば健康保険料とあわせて給与から天引きされます。給与明細には「介護保険料」として記載されているか、健康保険料の内訳に含まれています。自営業の方などの国民健康保険加入者は、国民健康保険料と合算して納付します。
65歳以上は「年金天引き」が基本
第1号被保険者になると、原則として年金からの天引き(特別徴収)に切り替わります。対象となるのは、年間の年金受給額が18万円以上の方です。年金支給時(偶数月)に、2ヶ月分の保険料が自動的に差し引かれます。
年金受給額が年18万円未満の方や、年度の途中で65歳になった方、他の市区町村から転入してきた方などは、市区町村から送られてくる納付書や口座振替で個別に納める「普通徴収」となります。
年齢で変わる介護保険料の注意点
介護保険料は、私たちの生活を支える大切な制度ですが、支払いに関して注意すべき点もあります。年齢区分ごとに見落としやすいポイントを確認しておきましょう。
滞納すると介護サービスが制限されるリスク
介護保険料を滞納してしまうと、ペナルティが課せられます。1年以上滞納すると、介護サービスを利用した際に、一度費用の全額を自己負担し、後から払い戻しを受ける形になります。さらに滞納期間が長くなると、自己負担割合が引き上げられたり(通常1割→3割)、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりと、給付が制限されます。
支払い方法の切り替え時の注意
65歳になると、多くの人が給与天引きから年金天引きに切り替わります。ただし、年金天引きが開始されるまでには半年から1年ほど時間がかかる場合があります。
その間は、市区町村から届く納付書で支払う「普通徴収」となるため、二重払いや払い忘れが起きないよう注意が必要です。
自営業やフリーランスの支払い方法
自営業やフリーランスの方は、第2号被保険者(40~64歳)の間は国民健康保険料の一部として、第1号被保険者(65歳以上)になってからは市区町村へ直接、保険料を納めます。会社員と違い、保険料の全額が自己負担となるため、計画的な資金準備がより大切になります。
所得が低く介護保険料の支払いが困難な場合
所得が著しく低い、あるいは災害や失業などで一時的に保険料の支払いが困難になった場合のために、負担を軽減する制度が設けられています。
低所得者向けの減免・猶予制度
第1号被保険者(65歳以上)で、所得が一定基準を下回る世帯などに対しては、市区町村が独自に保険料の減額や免除、または納付の猶予を行う制度を設けている場合があります。
また、災害で大きな被害を受けた、事業の休廃止や失業などで収入が著しく減少したといった特別な事情がある場合も、申請により保険料が減免・猶予されることがあります。困ったときには、まずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口に相談することが重要です。
介護保険料は年齢で変わる仕組みを理解し将来に備える
介護保険料は、40歳になると支払い義務が始まり、65歳を境に被保険者の区分が「第2号」から「第1号」へと変わります。40〜64歳は加入している健康保険を通じて給与から天引き、65歳以上は市区町村によって所得段階別に決まり、多くは年金から天引きされます。
計算方法や納付方法が変わるのが特徴であり、滞納すると給付制限がかかるリスクもあるため注意が必要です。
もし支払いが困難な事情が生じた場合には、減免制度などの公的な支援もありますので、まずは自治体の窓口に相談しましょう。
将来のライフプランを考える上で、年齢区分ごとの仕組みを理解し、計画的に備えることが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
健康保険の年齢は何歳まで?70歳以上を雇用する場合の手続きを解説【テンプレート付き】
健康保険は、労働者が医療機関を受診する際に必要となる制度です。年齢によって扱いが変わるため、労働者を雇用する際には注意しなければなりません。手続きに誤りがあれば、一旦治療費を全額自己負担しなければならない場合もあります。今回は70歳以上の健…
詳しくみる社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入におけるメリット
社会保険に加入していることで保障される内容やメリットについての説明をします。 社会保険の加入義務 社会保険への加入義務がある事業所は、以下のとおりです。 強制適用事業所 事業所が次のいずれかに該当する場合は、社会保険の強制適用事業所になりま…
詳しくみる労働保険の年度更新とは?時期や電子申請・申告書の作成方法、効率化を解説
労災保険や雇用保険の年度更新は、電子申請の導入により、効率的な申告が可能となっています。これにより、平日の日中に労働局や労働基準監督署に出向く必要がなく、休日や夜間でも自宅から申告できるようになりました。 本記事では、労働保険の年度更新につ…
詳しくみる試用期間中も社会保険への加入は必要?転職先で加入しないとどうなる?
従業員を正社員として採用した場合でも、試用期間を設けている企業は少なくありません。「転職したが、試用期間中という理由で社会保険に加入させてくれない」という話を聞くことがありますが、法的に問題はないのでしょうか。 本稿では試用期間中の社会保険…
詳しくみる社会保険の出産育児一時金とは
出産は病気ではありません。そのため、健康保険は使えず、原則的には全ての費用が自己負担となります。しかし、産院での入院費など出産にかかる費用は高額で、どうしてもまとまった金額が必要になるのが現実です。こうした出産時の経済的負担を軽くしようとい…
詳しくみる社会保険労務士(社労士)とは?試験の内容や業務内容について解説!
社会保険労務士の資格は人気の国家資格の1つです。人気の理由は、企業の人事・総務で労働・社会保険の手続き、就業規則の作成、ハラスメント対策などの実務を行うことも、独立して開業することもできることにあります。 今回は、年金問題、働き方改革、ハラ…
詳しくみる