- 更新日 : 2025年12月24日
安全衛生委員会の設置基準は?50人未満の場合やメンバー構成、進め方まで解説
労働安全衛生法では、一定規模以上の事業場に対して、安全衛生委員会の設置を義務付けています。しかし、「どんな場合に設置が必要なの?」「メンバーはどうやって選べばいいの?」「委員会では具体的に何を話し合うの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、安全衛生委員会の設置基準から具体的な運営方法、関連する法律上の決まりまで分かりやすく解説します。
目次
安全衛生委員会とは
安全衛生委員会は、労働者の危険や健康障害を防ぐための対策について調査審議し、事業主に対して意見を述べるための組織です。労働安全衛生法で定められており、労使が一体となって職場の安全衛生水準の向上を目指すことを目的としています。
参考:安全委員会、衛生委員会について教えてください。|厚生労働省
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
メンタルヘルス不調者への実務ガイドブック
入社や異動が多く発生する時期は、環境の変化によるストレスでメンタルヘルス不調に陥りやすくなります。
本資料は職場でメンタルヘルス不調者が発生した際の対応手順のほか、休職時トラブルへの対処方法も解説しています。
健康診断のご案内(ワード)
従業員へ健康診断の実施を案内する際に活用できる、ワード形式のテンプレートです。
社内周知にかかる作成工数を削減し、事務連絡を円滑に進めるための資料としてご活用ください。
安全衛生委員会の設置基準
安全衛生委員会の設置基準についても見ていきましょう。
設置義務は労働者50人以上の事業場
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、業種に応じて安全委員会と衛生委員会の設置がそれぞれ義務付けられています。そして、これら両方の委員会を設けるべき事業場では、それぞれの委員会の設置に代えて、両方の機能をあわせ持った安全衛生委員会を設置できます。
この設置義務を怠った場合、労働安全衛生法第120条の規定により、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
労働者50人未満の事業場での取り組み
労働者が50人未満の事業場には安全衛生委員会の設置義務はありませんが、労働者の意見を聴く機会を設ける努力義務があります。
関係する労働者から意見を聴く場として、定期的なミーティングを開くなど、委員会の制度を参考に、自社の実情に合った方法で安全衛生活動を進めることが大切です。
安全衛生委員会のメンバー構成と役割
安全衛生委員会のメンバー構成は、その機能性を左右する重要な要素です。誰をメンバーに選ぶべきか、法律で明確なルールが定められています。
議長
委員会の議長は、原則として総括安全衛生管理者や事業場のトップなど、事業の実施を統括管理する者が務めます。議長は1名で、委員会の議論をまとめ、円滑な議事進行に責任を持ちます。なお、議長は委員の定数には含まれません。適切な人物が議長を務めることで、委員会での決定事項が経営層に直接伝わり、実行に移されやすくなります。
議長以外の委員
議長以外の委員は、以下の者の中から事業主が指名します。この安全衛生委員会のメンバーは法律によって役割が期待されており、それぞれの専門的な視点から意見を出すことが求められます。
- 安全管理者および衛生管理者
- 産業医
- 当該事業場の労働者で、安全または衛生に関する経験を持つ者
事業場の規模や特性に応じて、作業主任者やその他の専門知識を持つ従業員を指名することも効果的です。
最も重要なルールは労働者側委員を半数以上にすること
委員会を構成するうえで重要な要件の一つが、議長を除く全委員のうち、労働者側の委員を半数以上にすることです。これは、労働者の意見を十分に反映させるための法律上の規定です。
労働者側の委員は、労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名する必要があります。このバランスが、労使双方にとって納得感のある議論と決定の土台となります。
委員の任期と届出について
委員の任期について法律上の定めはありませんが、活動の継続性を考慮し、1年〜2年程度で定めるのが一般的です。
また、安全衛生委員会の設置自体を労働基準監督署へ届け出る必要はありません。ただし、委員となる安全管理者、衛生管理者、産業医を選任した際は、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があるため注意しましょう。
安全衛生委員会の進め方
委員会を設置した後は、定期的に開催し、実質的な活動を行う必要があります。ここでは、委員会の運営に関する具体的な進め方やルールについて解説します。
開催頻度と成立要件
安全衛生委員会は、毎月1回以上の開催が義務付けられています。
委員会の成立には、明確な定足数の定めはありませんが、労使双方の意見を反映させるという趣旨から、議長と、労働者側・使用者側の両方の委員が出席している必要があります。議論の質を保つためにも、できるだけ多くの委員が出席することが望ましいです。開催日時や場所は事前に全委員へ通知し、参加しやすい環境を整えましょう。
審議する内容の具体例
委員会では、労働災害の原因調査と再発防止策、労働者の健康障害防止対策、安全衛生に関する規程の作成など、幅広いテーマを調査審議します。具体的には、以下のようなテーマが挙げられます。
- ヒヤリハット事例の共有と対策の検討
- 長時間労働者への対策
- メンタルヘルス不調の予防と対応
- 夏場の熱中症対策や冬場の感染症対策
- 職場巡視の結果報告と改善策の審議
議事録の作成・周知・保存は必須
審議した内容については、遅滞なく議事の概要を議事録として作成し、全労働者に周知しなければなりません。周知の方法としては、事業所の見やすい場所への掲示、社内イントラネットへの掲載、メールでの配信などがあります。労働安全衛生規則第24条第4項に基づき、議事録は3年間保存する義務があります。
安全衛生委員会を活性化させるポイント
委員会を形骸化させないためには、いくつかの工夫が必要です。
- 安全衛生委員会の組織図を作成する
組織図があることで、誰がどの分野に責任を持っているのかが一目で分かり、従業員からの相談や提案がしやすくなります。 - 年間活動計画を立てる
月ごとにテーマを決めておくことで、計画的かつ継続的な活動ができます。例えば、健康診断の結果が出る時期にはその結果を分析し、夏前には熱中症対策を話し合うなど、時期に合わせたテーマ設定が活動を具体的にします。
安全衛生委員会の設置基準を理解しましょう
この記事では、安全衛生委員会の設置基準から、法律で定められたメンバー構成、具体的な進め方までを説明しました。一定の事業を営み、常時50人以上の労働者がいる事業場では、安全委員会と衛生委員会の設置に替えて安全衛生委員会を設置することが可能です。また、この委員会は毎月1回以上の開催が義務付けられています。特に、議長を除く委員の半数以上を労働者側から選出するというルールは、労使協力の観点から非常に重要です。
委員会で話し合われた内容は議事録として記録し、全従業員に周知することで、職場全体の安全衛生意識を高めることができます。安全衛生委員会を形式的なものと捉えず、職場のリスクを洗い出し、誰もが安心して働ける環境を構築するための中心的な仕組みとして機能させていきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
離職票が届かない場合はどうすべき?届くまでの通常日数や届かない原因も解説
離職票は失業保険を申請するときに必ず提出しなければならない書類です。通常であれば退職してから10日~2週間ほどで届きます。 ただ失業手当を受給しようと考えている人の中には「なかなか離職票が届かない」「離職票が届かない場合はどうすればいい?」…
詳しくみるリーダーに必要なスキル・能力とは?具体的な役割や特徴を紹介
優れたリーダーに恵まれると、そのチームのメンバーは能力を発揮し、成長し、相乗効果によりチームの成果もより大きなものとなります。リーダーの役割と使命は何か、条件やスキルには何が求められるのでしょうか。 リーダーの意味や役割、条件、リーダーに向…
詳しくみる外国人雇用において遵守すべき労働関係法規と注意点を解説
外国人雇用に関する労働関係法規は多く、法改正もあるため、理解しにくいと感じる人もいます。法令違反などのトラブルを避けるためにも、入管法や雇用対策法など、外国人特有の法律についても理解が必要です。 この記事では、外国人雇用において遵守すべき労…
詳しくみる【テンプレ&例文あり】訃報とは?連絡のタイミングや書き方を解説|社長・役員の場合
訃報とは、人が亡くなったことを関係する人達に伝えることです。訃報の連絡方法には、電話、手紙、電報、メール、SNSなど、連絡相手の立場や亡くなった方との関係性により様々です。本記事では、訃報の書き方や例文、返信方法などについて解説します。 訃…
詳しくみる人前での吊し上げはパワハラ?該当するケースや適切な指導との違いを解説
職場での「吊し上げ」は、内容によってはパワハラに該当する行為とみなされることがあります。そのため、問題が深刻化しないよう、適切な指導との違いを正しく理解しておくことが重要です。本記事では、人前での吊し上げがパワハラとされるケースや、正当な指…
詳しくみる退職勧奨された場合でも失業保険を受給できる?ハローワークでの手続き方法も紹介
退職勧奨によって退職した場合でも、失業保険の受給条件を満たしていれば申請可能です。 ただ、失業保険に実際に申請しようと考えている人の中には「退職理由は何になる?」「受給できる金額や給付制限期間については?」と気になっている人もいるでしょう。…
詳しくみる

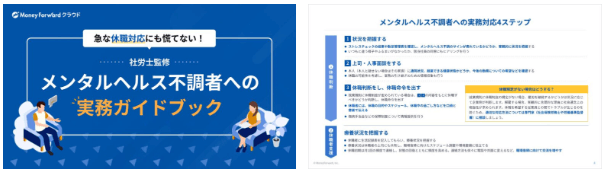
-e1763463724121.jpg)