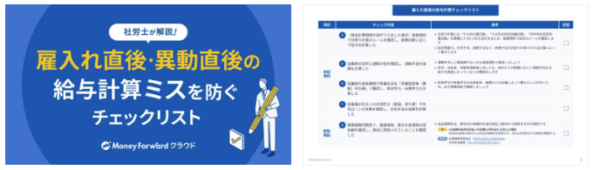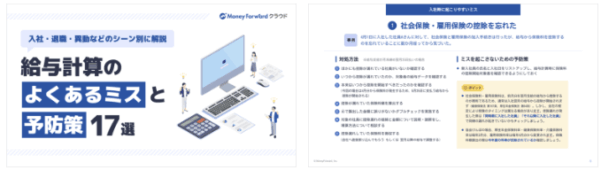- 更新日 : 2025年8月20日
配置転換を拒否できる正当な理由とは?退職勧告やパワハラの対処法、企業側の注意点も解説
「突然、縁もゆかりもない部署への配置転換を命じられた」「これまでのキャリアが無駄になるような異動を打診され、到底受け入れられない」――。従業員にとって、自らのキャリアや生活を大きく左右する配置転換は、深刻な悩みとなります。一方で、企業側も「事業計画のために必要な配置転換を、従業員に拒否されてしまった」と対応に苦慮するケースは少なくありません。
この記事では、どのような場合に配置転換を拒否できるのか、正当な理由を具体的に解説します。また、もし拒否した場合にどうなるのか、退職勧奨やパワハラなど、不当な扱いに合わないための具体的な対処法まで解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
配置転換は原則として拒否できない
まず理解しておくべき大原則は、企業の配置転換命令に従業員は基本的に従う義務があるということです。これは、企業が持つ人事権という強力な権限にもとづいています。なぜ企業がこのような権利を持つのか、その根拠を見ていきましょう。
企業の人事権とは
人事権とは、企業が事業を円滑に運営するために、従業員の採用、異動、昇進、解雇などを決定する権限を指します。企業は、組織全体の生産性向上や事業戦略の実現を目指し、従業員の能力や適性、人員計画を総合的に判断して人材を配置します。
人事権は、個々の従業員の希望よりも、企業全体の利益が優先される場面で効力を発揮します。したがって、「今の仕事が好きだから」といった個人的な感情だけでは、有効な拒否理由にならないのが実情です。
就業規則の法的効力
人事権の具体的な根拠となるのが、就業規則です。多くの企業の就業規則には、「会社は業務上の都合により、従業員に配置転換(職務内容や勤務地の変更を含む)を命じることがある」という趣旨の条項が含まれています。
従業員は入社時にこの就業規則に同意していると見なされるため、この条項は労働契約の内容の一部となります。結果として、従業員は会社の配置転換命令に包括的に同意しているという法的解釈が成り立ちます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
給与計算にミスがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、内容によっては労働基準法違反となる可能性もあります。
本資料では、雇入れ直後・異動直後に焦点を当て、給与計算時のチェックポイントをまとめました。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
この資料では、各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にまとめました。
【異動時も解説!】給与計算のよくあるミスと予防策17選
給与計算で起きやすいミスをシーン別にとりあげ、それぞれの対処方法を具体的なステップに分けて解説します。
ミスを事前に防ぐための予防策も紹介していますので、給与計算の業務フロー見直しにもご活用ください。
配置転換を拒否できる正当な理由とは
企業の人事権は強力ですが、決して無制限ではありません。従業員の不利益を一切顧みないような配置転換命令は、権利の濫用(労働契約法第3条5項)として無効になる場合があります。ここでは、正当な理由として認められやすい代表的な3つのケースを解説します。
業務上の必要性が認められないケース
配置転換は、あくまで企業の事業運営のために認められるものです。そのため、業務上の合理的な理由がなく、他の不当な動機に基づく命令は無効となる可能性があります。
例えば、気に入らない従業員を退職に追い込むための追い出し部屋への異動や、個人的な恨みによるパワハラ目的の配置転換などがこれにあたります。このようなケースでは、命令の業務上の必要性が乏しいため、権利の濫用と判断されやすくなります。
労働者の不利益が著しく大きいケース
配置転換によって労働者が受ける生活上の不利益が、社会通念上、甘受すべき程度を著しく超える場合も、拒否の正当な理由になり得ます。
具体的には、転居を伴う異動で要介護状態の親族の介護が不可能になる場合や、専門的な治療が必要な持病の通院が困難になる場合などです。近年では、共働き世帯における配偶者のキャリアや、子どもの教育環境への深刻な影響も、裁判で考慮される要素となっています。これらの不利益を主張する際は、客観的な証拠が重要です。
職種や勤務地が限定されているケース
労働契約を結ぶ際に、職務内容や勤務地を特定して合意している場合は、配置転換を拒否する強力な根拠となります。例えば、経理職限定や東京支社勤務限定といった合意が契約書に明記されていれば、会社はその範囲を超えて一方的に配置転換を命じることはできません。
このような限定合意があるにもかかわらず、会社が配置転換を強行しようとする場合は、契約違反となり、拒否することが可能です。
配置転換を拒否した場合のリスク
正当な理由なく配置転換を拒否し続けると、従業員は業務命令違反者として、相応のリスクを負うことになります。感情的に拒否する前に、起こりうる事態を冷静に理解しておくことが重要です。
業務命令違反による懲戒処分の可能性
正当な理由がない拒否は、就業規則に定められた懲戒事由に該当します。その場合、会社は従業員に対して懲戒処分を下すことができます。
処分の重さは、けん責や始末書の提出といった比較的軽いものから、減給、出勤停止、そして最も重い懲戒解雇まで様々です。通常は、会社からの再三の説得や警告を経てもなお拒否し続ける場合に、段階的に重い処分が検討されます。
退職勧奨や解雇に発展する可能性
配置転換に応じない従業員に対し、会社が「それなら会社を辞めてはどうか」という退職勧奨を行うことがあります。これはあくまでお願いであり、応じる義務はありません。
しかし、拒否が続けば、最終的には業務命令違反を理由とする普通解雇に至る可能性も否定できません。ただし、会社が従業員を解雇するには厳しい要件(解雇権濫用法理)があるため、配置転換の拒否だけを理由とした解雇が常に有効とは限りません。
配置転換を拒否するためのステップ
配置転換の内示を受け、拒否したいと考えた場合、感情的に反発するだけでは事態は好転しません。冷静かつ戦略的に対応することが重要です。
まずは会社の意図を確認する
なぜ自分が配置転換の対象になったのか、その背景や目的を人事担当者や上司に具体的に確認しましょう。一方的に拒否の姿勢を示すのではなく、まずは会社の考えをヒアリングする姿勢が大切です。もしかしたら、あなた自身が気づいていないキャリアアップの機会かもしれません。対話を通じて、配置転換以外の選択肢が見つかる可能性もあります。
拒否の意思と正当な理由を伝える
対話してもなお、配置転換を受け入れがたい場合は、拒否する意思を明確に伝えます。その際、単に嫌だと伝えるのではなく、「要介護の親がおり転居は困難である」といった正当な理由を示しましょう。口頭でのやり取りだけでなく、後々の証拠として残すために、理由を記載した書面を作成し、内容証明郵便で会社に送付することも有効な手段です。
一人で抱え込まず専門家へ相談する
会社との交渉がうまくいかない場合や、退職勧奨などの圧力を受けた場合は、一人で抱え込まずに外部の専門家へ相談しましょう。相談先としては、企業の労働組合、地域のユニオン(合同労組)、労働基準監督署内の総合労働相談コーナー、そして労働問題に詳しい弁護士などが挙げられます。法的な観点から、あなたの状況で配置転換を拒否することが妥当か、また今後どのように対応すべきか、具体的な助言を得ることができます。
従業員が配置転換を拒否した場合の対応
従業員から配置転換を拒否された際、企業側が感情的になったり、高圧的な態度を取ったりするのは最悪の選択です。訴訟リスクを回避し、組織へのダメージを最小限に抑えるためには、冷静かつ法的に適切な対応が求められます。
理由を丁寧にヒアリングする
最初にすべきは、一方的に命令を繰り返すのではなく、従業員がなぜ拒否するのか、その理由を真摯に聞くことです。そこには、会社が把握していなかった家庭の事情(育児・介護)や本人の健康問題など、配慮すべき正当な理由が隠れている可能性があります。
対話を通じて従業員の状況を正確に理解することが、問題解決の第一歩です。このヒアリングを怠ると、後の法的措置の妥当性が問われることになりかねません。
配置転換の必要性と目的を改めて説明する
次に、企業側は「なぜこの配置転換が必要なのか」「なぜ、あなたでなければならないのか」を、従業員が納得できるよう具体的に説明する責任があります。
事業戦略上の位置づけや、当該従業員の能力をどう活かしてほしいのか、将来的なキャリアパスなどを丁寧に伝えることで、従業員の理解を得られる可能性が高まります。一方的な命令ではなく、誠実な説得努力を尽くしたという事実は、万が一の際の企業側の正当性を補強します。
懲戒処分を検討する場合は慎重に
対話を重ねても従業員が正当な理由なく拒否を続ける場合、企業は懲戒処分を検討せざるを得ません。しかし、その判断は慎重に行う必要があります。
安易な懲戒処分、特に解雇は権利の濫用として無効となるリスクが常に伴います。処分を下す前には、配置転換命令自体に業務上の必要性や合理性があったか、従業員の被る不利益は過大ではなかったか、説得努力を尽くしたか、などを多角的に検証し、顧問弁護士などに相談することが賢明です。
配置転換の拒否に関してよくある質問
正社員だけでなく、パートタイマーや契約社員、あるいは育児中の方など、状況によって配置転換への対応も異なります。ここでは、よくあるケースについて解説します。
パート・契約社員でも配置転換を拒否できる?
可能です。特にパートや契約社員の場合、雇用契約書における勤務地や職務内容の記載が決定的に重要です。これらの項目が明確に限定されていれば、その範囲を超える配置転換は契約違反となり、拒否できます。限定がない場合でも、正社員と同様に権利の濫用にあたるケースでは拒否が可能です。
育児・介護中の配置転換は拒否できる?
配慮される可能性が高いです。育児・介護休業法では、事業主は労働者の配置転換に際し、その育児や介護の状況に配慮しなければならないと定められています。この配慮義務は企業の重要な責務であり、育児・介護を理由とする拒否は、正当な理由として認められやすい傾向にあります。
復職時の配置転換は拒否できる?
ケースによります。私傷病などによる休職からの復職は、原則として元の職場への復帰が基本です。しかし、本人の健康状態への配慮や組織再編などを理由に、別の部署への配置転換が打診されることもあります。その際は、復職後の業務が負担過重にならないか、主治医の意見も交えて会社と慎重に協議することが不可欠です。
配置転換を拒否して退職した場合は自己都合になる?
配置転換を拒否した結果、自らの意思で退職届を提出した場合、原則として自己都合退職として扱われます。しかし、配置転換命令が明らかに違法であり、それが原因で退職せざるを得なかったと証明できる場合は、会社都合退職として認められる可能性があります。会社都合となれば、失業保険の受給で有利になります。交渉の経緯を示すメールや面談の録音など、客観的な証拠を確保しておくことが重要です。
配置転換の対応は慎重に行いましょう
配置転換は、従業員のキャリアや生活、そして企業の組織運営に深く関わる、非常にデリケートな問題です。
従業員は、会社の業務命令に原則として従う義務がある一方、自らの生活を著しく脅かす不当な命令に対しては、法的な根拠をもって拒否する権利があります。企業側は、従業員への配慮を欠いた命令は権利の濫用として法的なリスクを招くことを認識しなければなりません。
労使間の無用な紛争を避け、双方にとって納得のいく着地点を見出すためには、一方的な命令や拒絶ではなく、誠実な対話を通じた相互理解が重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
イノベーションとは?意味や定義をわかりやすく解説
イノベーションとは、モノやサービス、仕組みなどに新しい考え方や技術を採り入れ、新しい価値を生み出して社会に変革を与えることを意味します。社会にとって必要な理由や定義について、具体例を挙げてまとめました。また、チェスブロウやクリステンセンによ…
詳しくみるストライキとは?意味や仕組み、企業の賃金対応や防止策について簡単に解説
本記事ではストライキの意味・仕組み・権利としての性格について紹介します。さらに過去の事例に簡単に触れ、企業の対応や防止策についてもわかりやすく解説していきます。 ストライキとは? 「ストライキ」は英語「Strike」に由来する外来語です。遡…
詳しくみる【テンプレ&例文あり】お詫び状とは?書き方やメール・電話で伝えるコツを紹介
お詫び状とは、ビジネスシーンでお客様や取引先に不快な思いをさせたり不手際があったりした際に、謝罪の気持ちを伝える書状です。お詫び状を送付する機会が少ない方は、送るタイミングや送り方、記載すべき内容や書き方がわからず苦慮することも多いかもしれ…
詳しくみる人事とは?役割や仕事内容、労務との違いなどを解説!
企業が成長するためには、優秀な人材を獲得することが必要です。人材採用を担当する部署である人事が有効に機能していなければ、優秀な人材を獲得できず、企業の成長も望めないでしょう。 当記事では、人事について解説を行っています。役割や仕事内容はもち…
詳しくみる2022年1月の電子帳簿保存法の改正で人事労務分野が対応すべきことを解説
税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律「電子帳簿保存法」が2021年に改正されました。法改正によって、人事労務分野はどのようなことに対応しなければならないのでしょうか。 この記事では、電子帳簿保存法の概要や改正内容や人事が対応すべきこ…
詳しくみる育休中でも住宅ローンは組める?審査ポイント・種類・注意点を解説
育児休業(以下、育休)は、家族が増え、マイホームの購入を検討し始める方も少なくない時期です。新しい生活への期待が膨らむ一方で、「育休中に住宅ローンは本当に組めるのだろうか?」「審査が通常より厳しくなるのでは?」といった不安を抱えるのは自然な…
詳しくみる