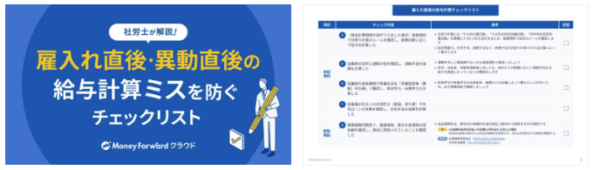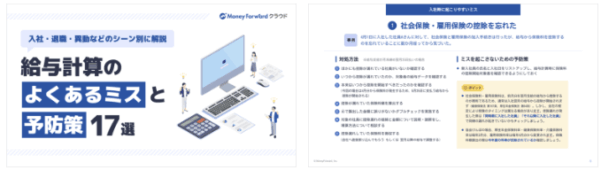- 更新日 : 2025年9月2日
転勤命令の拒否は原則不可?トラブルを防ぐために企業が知るべき対応方法
本記事では、転勤命令の拒否に関する企業側の適切な対応を解説します。転勤命令の拒否で正当な理由が認められるケースから、転勤命令を拒否した従業員への具体的な対処法、従業員へ転勤命令を出す前の準備、そしてトラブル回避のポイントまでご紹介します。
従業員の心に寄り添いながら、企業と従業員双方にとって最善の道を見つけ、信頼関係を深めていきましょう。
目次
転勤命令を拒否することは原則不可
従業員は原則として、会社の正当な転勤命令を拒否することはできません。なぜなら、会社には事業を円滑に運営するため、従業員の勤務場所や職務内容を決定する広範な権限「配転命令権」が認められているからです。
この原則を裏付ける重要な判例が「東亜ペイント事件(最判昭61.7.14)」です。この事件で最高裁判所は、たとえ従業員側に共働きの妻や高齢の母親を置いていくといった家庭の事情があったとしても、転勤に伴う不利益が「通常甘受すべき程度を著しく超えるもの」でない限り、業務上の必要性に基づく転勤命令は有効である、と判断しました。これにより、従業員の個人的な事情だけを理由に転勤を拒否することは、原則として認められないという考え方が確立されました。
なお、配転命令権は就業規則や労働契約に根拠を持つ広い裁量権ですが、業務上の必要性・動機の正当性・労働者が被る不利益の程度という判例上の枠内でしか行使できません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
給与計算にミスがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、内容によっては労働基準法違反となる可能性もあります。
本資料では、雇入れ直後・異動直後に焦点を当て、給与計算時のチェックポイントをまとめました。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
この資料では、各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にまとめました。
【異動時も解説!】給与計算のよくあるミスと予防策17選
給与計算で起きやすいミスをシーン別にとりあげ、それぞれの対処方法を具体的なステップに分けて解説します。
ミスを事前に防ぐための予防策も紹介していますので、給与計算の業務フロー見直しにもご活用ください。
転勤命令の拒否が認められる「権利の濫用」とは?
会社の転勤命令権は絶対というわけではありません。その権利の行使が、特定の状況下で従業員の権利を不当に侵害するとみなされる場合、それは「権利の濫用」として法的に無効になります。つまり、従業員はその転勤命令を拒否できるのです。
権利の濫用とは、形式的には正当な権利を持っているように見えても、その権利を社会のルールや常識から逸脱した目的や方法で使うことは許されない、という法律上の考え方です。転勤命令の文脈で言えば、会社には従業員に転勤を命じる権利がありますが、その権利を嫌がらせや退職強要の手段として使ったり、従業員の生活を破綻させるほどの不利益を無視して強行したりすることは、権利の「濫用」とみなされます。
裁判所は、会社の業務上の必要性と、従業員が被る不利益の大きさを天秤にかけ、権利の濫用にあたるかどうかを個別に判断します。権利濫用の禁止は、民法第1条3項にて明示されています。
転勤命令が無効・有効となった判例
転勤命令が権利の濫用にあたるかどうかは、最終的に「会社の業務上の必要性」と「従業員が被る不利益」を天秤にかけて判断されます。では、実際の裁判ではどのように判断されているのでしょうか。育児や介護といった家庭の事情が焦点となった判例を中心に、命令が無効とされたケースと有効とされたケースを比較して見ていきましょう。
育児・介護を理由に無効と判断されたケース
育児や介護といった、従業員の生活基盤を揺るがす事情が重視された判例があります。
たとえば、共働きで重度のアトピー性皮膚炎の子どもを養育する従業員への転勤命令について、裁判所は「転勤によって妻の退職が不可避となり、従業員が受ける不利益は通常甘受すべき範囲を著しく超える」として、命令を無効と判断しました(明治図書出版事件:東京地裁 平成14年12月27日判決)。
また、工場の部門廃止に伴う転勤命令であっても、重い病気の家族を看護していた従業員らに対しては、その業務上の必要性を認めつつも、転勤による不利益の大きさが優先され、命令は無効とされています(ネスレ日本事件:大阪高裁 平成18年4月14日判決)。
近年の判例の一部では、育児・介護休業法第26条で定められた企業の「配慮義務」の趣旨が、転勤命令の有効性を判断する際の考慮要素として引用されています。この法律は、企業が転勤を命じる際に、その従業員が担う育児や介護の状況に配慮することを求めています。裁判所は、この配慮を欠いた一方的な転勤命令を、権利の濫用として厳しく判断する傾向にあるのです。
業務上の必要性が優先され有効となったケース
従業員に家庭の事情があれば、いかなる場合でも転勤を拒否できるわけではありません。会社の業務上の必要性が高く、従業員の不利益が通常甘受すべき程度を著しく超えないと判断されれば、命令は有効となります。
冒頭で紹介した「東亜ペイント事件(最判 昭和61年7月14日)」は、まさにこの転勤命令権の基本的な枠組みを示した判例です。この判例は、権利の濫用にあたるケースを「業務上の必要性がない場合」「不当な動機・目的がある場合」「労働者が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を被る場合」の3つに限定するという、今日にも続く重要な基準を確立しました。
また「NECソリューションイノベータ事件(大阪地裁 令和3年11月29日判決〈労判1277号〉)」では、子の疾病と親の介護を理由に事業所閉鎖に伴う転勤命令を拒否した社員への懲戒解雇を、東亜ペイント判決の3要件を満たすとして有効と判断しました。控訴後の2022年8月29日に大阪高裁で和解が成立しており、確定判決は残っていません。
本件は、企業が転勤時の配慮義務を尽くすには、従業員側からの十分な事情説明が不可欠であることを示唆しています。
出典:NECソリューションイノベータ事件|労働基準判例検索-全情報(一般社団法人 全国労働基準関係団体連合会)
転勤命令の判例から学ぶ、企業が押さえるべき重要ポイント
1. 育児・介護休業法が定める配慮義務を果たす
企業の配慮義務は、育児・介護休業法第26条に定められています。これは、転勤を命じる際に、企業が従業員の育児や介護の状況を十分に聞き取り、可能な範囲で代替策を検討するなどの努力を求めるものです。
この配慮を欠いたと判断される転勤命令は、権利の濫用とみなされやすくなります。単に話を聞くだけでなく、従業員の家庭で誰が、どのようなケアを担っているのか、他に代われる人はいるのかといった具体的な状況まで踏み込んでヒアリングし、記録に残すことが重要です。
出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | e-Gov 法令検索
2. 著しい不利益の有無を個別事情から総合的に判断する
裁判所は、転勤命令が従業員に「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を与えるかどうかを、画一的な基準ではなく、個別の事情を総合的に見て判断します。特に、育児や介護の継続が困難になるなど、生活の基盤が揺らぐほどの不利益は重く見られます。
具体的には、従業員本人の健康状態、家族の状況(病気や介護の程度)、育児・介護の必要性、他にそれを担える親族の有無、会社の業務上の必要性の高さ、転勤先の支援環境、代替策の有無といった多様な要素を多角的に比較衡量します。
「前例ではこうだったから」という安易な判断は避け、一件一件、丁寧に向き合うことがトラブル回避の鍵です。
3. 従業員からの説明責任を促す環境を整備する
企業が適切な配慮や判断を行うためには、労働者側の説明責任も重要です。従業員が自身の家庭の事情を会社に正確かつ具体的に伝えなければ、企業は配慮のしようがありません。そのため企業は、従業員が必要な情報をためらわずに開示できるよう、日頃から信頼関係を築き、プライバシーに配慮した面談の機会を設けることが不可欠です。
その上で、必要であれば診断書や介護保険被保険者証といった客観的な証拠の提出を丁寧に依頼するプロセスを定めておきましょう。従業員からの情報提供があって初めて、企業は適切な配慮と判断が可能になるのです。
転勤命令でトラブルを防ぐための手順
転勤命令は従業員の生活に大きな影響を与えるため、企業は細心の注意を払って手順を踏む必要があります。適切な手順を踏むことで、後々のトラブルを未然に防ぎ、従業員の納得を得やすくなります。
1. 法的有効要件の確認
まず、有効な転勤命令の前提となる要件を確認します。就業規則や労働契約での明記はもちろんのこと、その命令が企業の組織運営や人材育成といった業務上の必要性に基づいているか、そして嫌がらせなどの不当な動機・目的ではないかを精査する必要があります。
2. 命令を出す前の準備と対話
次に、正式な命令を出す前の準備を進めます。対象となる従業員に対して転勤の目的や理由を事前に説明し、意見を聴取することは、法律上の配慮義務を果たす上で不可欠です。あわせて、転勤先の業務内容や勤務環境、住居や手当に関する情報を提供することで、従業員の不安を軽減し、円滑な合意形成を促します。
3. 転勤命令書の作成と交付
命令は口頭ではなく書面で明確に交付することで、後の紛争対応で証拠化できます。命令書には、転勤日、転勤先、転勤後の業務内容といった必須事項を漏れなく記載し、命令の存在と内容を正確に記録として残しましょう。
4. 転勤命令後のフォローアップ
転勤は従業員にとって大きな環境変化です。命令後も適切なサポートを忘れてはいけません。引っ越し費用や各種手当といった転居支援を支給したり、新しい環境での適応状況を確認するために、定期的な面談の機会を設けたりと、フォローをしっかりと行いましょう。
転勤拒否を理由に従業員を解雇できるか?
まず知っておきたい普通解雇と懲戒解雇の違い
転勤拒否を理由とする解雇には、主に2つの種類があります。
- 普通解雇: 業務命令に従えず、労働契約の本来の履行が期待できないことを理由とする解雇です。従業員の債務不履行を根拠とします。
- 懲戒解雇: 就業規則違反に対する「罰」として行われる最も重い懲戒処分です。就業規則に「正当な理由なく業務上の命令に従わない場合は懲戒解雇とする」といった明確な根拠規定が必要です。
一般的に、懲戒解雇の方が普通解雇よりも有効性が認められにくく、より厳格な判断がなされます。
解雇の有効性を左右する判断ポイント
解雇が有効と認められるには、大前提として転勤命令そのものが有効であることが必要です。転勤命令が業務上の必要性の欠如・不当な人選・従業員への過大な不利益などにより権利濫用と判断される場合、その命令を拒否したことを理由とする解雇は、労働契約法16条および「東亜ペイント事件(最判 昭和61年7月14日)」に照らして無効とされます。
その上で、解雇という手段の重さに鑑み、解雇以外の手段を尽くしたかが問われます。たとえば、会社が十分な説得や注意・指導を繰り返し行ったか、戒告や減給といったより軽い懲戒処分を段階的に行ったか、といった点が考慮されます。これらのプロセスを経ずに、転勤拒否を理由に解雇を直ちに行えば、解雇権の濫用として無効と判断されるケースが少なくありません。
解雇が無効と判断されたらどうなるのか
もし解雇が無効と判断された場合、企業は以下のようなリスクを負うことになります。
- 解雇期間中の賃金の遡及支払い(バックペイ)
- 慰謝料などの損害賠償責任
- 従業員の地位の回復(復職)
- 違法・不当解雇が報道やSNSで拡散することによる企業の評判低下(レピュテーションリスク)
このように、安易な解雇は企業の経営に深刻なダメージを与えかねません。解雇を検討する際は、必ず事前に労働問題に強い弁護士に相談してください。
転勤を拒否された場合の会社の対応フロー
従業員に転勤を拒否された場合、企業は感情的にならず、以下のステップに沿って慎重に対応を進める必要があります。
ステップ1:まずは拒否理由を丁寧にヒアリングする
最初のステップとして、なぜ従業員が転勤を拒否するのか、その具体的な理由を改めて丁寧に聞き取ります。従業員が説明する事情に、これまで会社が把握していなかったやむを得ないものはないか、権利の濫用にあたる可能性はないかを確認する最後の機会です。
このヒアリングの結果、従業員の主張に正当性があると判断した場合は、命令の撤回や代替案の再検討も視野に入れます。
ステップ2:解雇以外の懲戒処分を検討する
ヒアリングを経てもなお、従業員の拒否に正当な理由がないと判断した場合、業務命令違反として解雇以外の懲戒処分を検討します。処分の重さは事案とのバランスが重要であり、戒告(口頭または書面による注意)、譴責(始末書提出)、減給といった軽い処分から段階的に検討することが望ましいです。
ステップ3:退職勧奨で合意退職を目指す
懲戒処分を行っても従業員が応じない場合や、処遇に苦慮する場合には、退職勧奨という選択肢も現実的に存在します。
これは、従業員に対して合意による退職を促すもので、あくまで「お願い」ベースの働きかけです。従業員が応じる義務はなく、執拗な退職勧奨は退職強要(違法行為)とみなされるリスクがあるため、慎重なアプローチが求められます。
ステップ4:最終手段としての解雇
ここまでの手段を尽くしても解決しない場合、最終手段として解雇を検討します。ただし、前章で解説した通り、解雇には極めて高いハードルとリスクが伴います。実行する際は、必ず事前に弁護士へ相談し、その有効性について慎重に検討を重ねてください。社会保険労務士や労働局の総合労働相談コーナーも活用できます。
転勤命令拒否を巡る企業と従業員の関係を円滑にするために
転勤命令拒否という課題は、企業と従業員が共に協力し、理解を深め合うことが大切です。法的側面を正確に理解し、コミュニケーションを密にすることで、不要なトラブルを回避し、従業員が安心して働ける職場環境を構築できるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
従業員貸付制度は信用情報に影響する?理由や利用するデメリットなども解説
従業員貸付制度は、従業員が急な出費や生活費の確保を目的に会社から有利な条件でお金を借りられる制度です。一方、制度の利用にあたって気になるのが、自分の信用情報への影響でしょう。この記…
詳しくみるキャリアアップ助成金に対応した就業規則の作成・変更方法は?雛形や記載例も紹介
キャリアアップ助成金を申請し、企業の成長と従業員の待遇改善を目指す上で、就業規則の適切な整備は避けて通れない重要なポイントです。しかし、「キャリアアップ助成金に対応した就業規則とは…
詳しくみる労働者名簿をエクセルで作成するには?無料テンプレートや取扱いの注意点を解説
労働者名簿をエクセルで作成するとき、法的要件を満たす内容にしなければならないことに加え、適切に管理することが求められます。本記事では、労働者名簿をエクセルで管理する際のポイントや必…
詳しくみる高齢者の雇用延長65歳、70歳の義務とは?2025年改正や企業の手続きを解説
少子高齢化が進む日本では、高齢者の雇用延長が企業経営の課題となっています。2025年の法改正により、65歳までの雇用義務に加え、70歳までの就業確保が努力義務として求められるように…
詳しくみるセクハラの始末書とは?書き方や注意点を解説【無料テンプレートつき】
ハラスメントには、パワハラやマタハラなど、様々な類型があります。どれもが決して許されるものではありませんが、なかでもセクハラは、被害者の心に深い傷を残してしまいます。セクハラが起き…
詳しくみる就業規則の悩みは弁護士に相談!費用や社労士との違い、依頼できる内容を徹底解説
職場の秩序を維持し、従業員が安心して能力を発揮できる環境を整えるためには、法的に適切で、かつ企業の実情に即した就業規則の存在が不可欠です。しかし、労働基準法をはじめとする関連法規は…
詳しくみる