- 更新日 : 2025年8月20日
産業医の役割とは?医療行為はできない?役立たずと言われる理由や選任するポイントも解説
従業員の健康は、企業の持続的な成長を支える重要な経営資源です。しかし、「産業医を選任しているものの、具体的にどのような役割を担っているのかよくわからない」といった疑問を抱える経営者や人事労務担当者も少なくありません。
この記事では、法律で定められた産業医の基本的な役割から、病院の医師との違い、そして「産業医は役立たず」と言われる理由や対策まで徹底解説します。
目次
そもそも産業医とは
産業医とは、事業場において従業員の健康管理や指導を行う役割を持つ医師です。労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。
産業医は、会社側でもなく、従業員側でもなく、あくまで医学的な正しさと労働者の健康を最優先する専門的・中立的な立場から、企業に対して指導や助言を行います。単に病気の治療をするのではなく、予防医学の観点から職場環境そのものに働きかけ、従業員が心身ともに健康な状態で働ける環境づくりをサポートする点が大きな特徴です。
産業医と臨床医(主治医)との違い
同じ医師免許を持っていても、産業医と病院にいる臨床医(主治医)では、立場と目的が大きく異なります。
| 比較項目 | 産業医 | 臨床医(主治医) |
|---|---|---|
| 目的 | 働く人全体の健康維持・増進、職場環境の改善 | 患者個人の病気や怪我の治療 |
| 対象 | 事業場で働く労働者全体 | 病気や怪我を抱える患者個人 |
| 立場 | 企業と労働者に対して中立・専門的な立場 | 患者の立場に立つ |
| 医療行為 | 原則として行わない(指導・助言が中心) | 行う(診断・投薬・手術など) |
臨床医の目的が患者個人の治療であるのに対し、産業医の目的は労働者の健康保持・増進と予防にあります。そのため、産業医が直接的な診断や投薬といった医療行為を行うことは原則としてありません。
産業医になるための資格
産業医になるためには、医師免許に加えて、労働安全衛生法で定められた特定の要件を満たす必要があります。最も一般的なのは、日本医師会や産業医科大学が実施する所定の研修を修了することです。
この研修を通じて、労働衛生に関する法規、作業環境管理、メンタルヘルス対策など、産業保健活動に必要な専門知識と技術を習得します。これらの資格は5年ごとの更新制となっており、産業医は常に最新の知識を学び続けることが求められます。
産業医の年収
産業医の年収は、勤務形態によって大きく異なります。
- 専属産業医
企業に常勤で雇用される形態。企業の規模や経験年数にもよりますが、年収は1,000万円を超えることが一般的です。 - 嘱託産業医
月に1〜数回、特定の事業場を訪問する形態。1月の報酬は、従業員に応じ5万円から20万円程度となります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
メンタルヘルス不調者への実務ガイドブック
入社や異動が多く発生する時期は、環境の変化によるストレスでメンタルヘルス不調に陥りやすくなります。
本資料は職場でメンタルヘルス不調者が発生した際の対応手順のほか、休職時トラブルへの対処方法も解説しています。
健康診断のご案内(ワード)
従業員へ健康診断の実施を案内する際に活用できる、ワード形式のテンプレートです。
社内周知にかかる作成工数を削減し、事務連絡を円滑に進めるための資料としてご活用ください。
労働安全衛生規則における産業医の役割
産業医の具体的な職務は、労働安全衛生規則第14条第1項に定められています。ここでは、特に重要な4つの役割について解説します。
1. 健康診断の実施と事後措置
産業医は、健康診断の結果すべてに目を通し、異常の所見があった労働者に対して、健康を保持するために必要な措置について意見を述べます。
- 就業判定
「通常勤務」「就業制限」「要休業」などの区分で、健康状態に合わせた働き方が可能か判断します。 - 受診勧奨
「要再検査」の通知を放置している従業員に、産業医から直接受診を促したり、面談を設定したりします。 - 就業上の配慮に関する助言
診断結果に基づき、事業者に対して労働時間の短縮や作業内容の変更といった、具体的な配慮を助言します。
2. 長時間労働者への面接指導
時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務があります。
産業医は面接指導を担当し、睡眠や食事の状況、疲労感などを確認します。その結果に基づき、セルフケア指導を行うとともに、事業者に対して深夜業の回数減少といった事後措置に関する意見書を作成し、健康障害を未然に防ぎます。
3. ストレスチェックの実施と高ストレス者への対応
産業医は、ストレスチェック制度において中心的な役割を担います。計画段階での助言、実施者としての業務、そしてストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された労働者から申し出があった場合の面接指導を行います。
面接指導では、ストレスの原因を評価し、メンタルヘルス不調のリスクを判断します。その上で、適切なセルフケア方法を指導するとともに、必要に応じて事業者へ職場環境の改善に関する助言を行います。
4. 職場巡視と作業環境の管理・改善
産業医には、少なくとも毎月1回(条件によっては2ヶ月に1回)作業場などを巡視し、作業方法や衛生状態に問題がないかを確認する義務があります。巡視では、以下のような多角的な視点で問題点がないかを確認します。
- 物理的な作業環境
照明の明るさ、騒音のレベル、換気の状態、オフィスの整理整頓状況など - 作業方法
PCモニターの高さは適切か、不自然な姿勢での作業が続いていないかなど - 労働者の様子
従業員の表情や挨拶の声、コミュニケーションの活発さなど
問題点を発見した場合は、その場で衛生管理者に指導を行ったり、後日、安全衛生委員会で報告し、具体的な改善策を提言したりします。
産業医は役立たずと言われる原因
「産業医がいても役に立たない」と感じる背景には、産業医・企業・従業員の三者に原因がある場合があります。
1. 産業医自身の問題
厚生労働省の調査では、認定産業医の約半数が実際には積極的な活動をしておらず、職場巡視や面談が形式的になるケースも少なくないと報告されています。残念ながら、実際に業務を果たさず報酬だけを受け取る「名義貸し」の産業医も存在し、摘発例や罰則(50万円以下の罰金)も確認されています。
2. 企業側の問題
企業側が産業医の役割を正しく理解せず、単に法律上の義務を果たすためだけに選任し、具体的な活動を依頼していない場合も少なくありません。産業医に何を相談して良いかわからず、宝の持ち腐れになっているケースです。
3. 従業員側の問題
従業員が「相談内容が会社に筒抜けになるのでは」と不信感を抱き、産業医との間に壁を作ってしまうことも原因の一つです。実際に「産業医に話した内容が会社に伝わるのが怖い」と感じている従業員がいることは、複数の調査や事例でも確認されています。
産業医には守秘義務があり、本人の同意なく相談内容が会社に伝わることはありませんが、そのことが周知されていないケースが多く見られます。
産業医を選任するポイント
良い産業医と連携するためには、選任時の見極めが重要です。複数の候補者と面談し、自社の業種や事業内容、抱えている健康課題への理解度を確認しましょう。
特に、コミュニケーション能力が高く、親身に相談に乗ってくれるか、メンタルヘルス対応の経験が豊富か、といった点は重要な判断基準です。また、産業医の専門分野が自社のニーズと合っているかも確認するとよいでしょう。
契約前に、具体的な活動内容をすり合わせ、双方の認識を一致させることがミスマッチを防ぎます。
産業医がいる会社の具体的な連携方法
産業医を選任するだけでは意味がありません。企業と産業医が密に連携し、その専門性を最大限に活用する体制を整えましょう。
効果的な産業医面談
産業医面談は、単なる形式的な手続きであってはなりません。従業員が安心して相談できる環境を整えることが重要です。面談の目的を明確にし、プライバシーが保護された個室を用意しましょう。
人事労務担当者は、事前に産業医へ対象者の勤務状況などの情報を提供し、面談後は産業医からの意見書に基づき、具体的な就業上の措置や環境改善を速やかに実行する体制を構築することが求められます。
安全衛生委員会での連携
安全衛生委員会は、労働者の健康や安全に関する事項を調査審議する重要な場です。産業医は、この委員会の構成員として、専門的な立場から意見を述べることが期待されています。例えば、毎月の職場巡視の結果報告、健康診断結果の傾向分析、長時間労働の状況、ヒヤリハット事例などを議題として取り上げ、産業医の医学的知見に基づいた改善策を議論することで、委員会の活動を実質的なものにできます。
職場環境改善への専門的なアドバイス
産業医は、個別の面談や職場巡視を通じて、特定の部署や職場全体が抱える健康上の課題を客観的に把握しています。例えば、「特定の部署でメンタルヘルス不調者が多い」「腰痛を訴える従業員が特定の作業に集中している」といった情報を集団的に分析し、その根本原因を探ります。
その分析結果を基に、作業プロセスの見直し、適切な休憩の導入、管理職への研修などを産業医から提案してもらうことで、より効果的な職場環境改善が実現します。
産業医は会社の成長を支えるパートナー
従業員の心身の健康を守り、誰もが安心して働ける職場環境を構築することは、企業の生産性向上、人材定着、そしてリスク低減に直結します。産業医を企業の健康経営を推進する重要なパートナーと位置づけ、その専門性を最大限に引き出すことで、会社の持続的な成長を実現する力強い土台を築くことができるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
安全管理者の役割とは?仕事内容、資格の取り方から巡視頻度までわかりやすく解説
安全管理者という言葉を聞いたことはあっても、具体的な仕事内容や、どのような場合に選任が必要なのか、どうすればなれるのか、正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。 この記事…
詳しくみる紛失届とは?テンプレートを基に必要項目や書き方、会社の対応を解説
企業が社員に貸与した物品や機器を紛失した場合、当然のことながら適切な対応が求められます。紛失届は、そのための大切な書類です。この記事では、紛失届の概要から、必要項目の記載例、会社の…
詳しくみる退職は何日前に伝える?2週間前でもよい?ルールや円満退職のコツを解説
退職を考えたとき、退職の意思をいつ伝えるかはとても重要です。法律上、正社員であれば2週間前に申し出ることで退職できますが、円満退職を目指すなら早めの退職申し出が望ましいです。 本記…
詳しくみるシャドーITとは?セキュリティリスクや原因、企業の対策について解説
シャドーITとは、企業内での利用が認められていないITサービスやIT機器を無断で使用することです。これらのサービスやIT機器は適切に管理されない傾向にあり、セキュリティ上のリスクに…
詳しくみる雇用契約書がないとどうなる?トラブル例と作成方法を解説
労働契約は雇用契約書がなくても成立します。しかし、書面で労働条件を明確にしない場合、認識のずれや法的なトラブルが生じやすくなります。 契約内容に関する争いが生じると、双方に不利な結…
詳しくみる行動指針とは?企業事例や作り方・社内への浸透方法をわかりやすく解説
企業の成功と持続可能な成長は、明確な行動指針によって大きく左右されます。行動指針は、従業員が日々の業務を遂行する際の道しるべとなり、組織の価値観や目指すべき方向性を示します。本記事…
詳しくみる

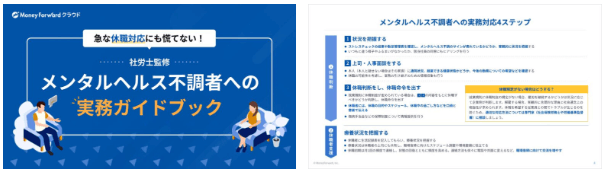
-e1763463724121.jpg)