- 更新日 : 2025年12月18日
会社のストレスチェック義務化とは?いつから?50人未満企業が進める実施手順も解説
ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止を目的とし、労働安全衛生法に基づいて企業に義務付けられています。とくに50人未満の事業場も令和10年度には義務化される見込みとなりました。この記事では、最新の義務化動向、50人未満企業がとるべき具体的な実施手順、高ストレス者への対応、そして労務管理システムを活用した効率的な実施のポイントをわかりやすく解説します。
目次
【最新動向】50人未満の事業場へのストレスチェック義務化はいつから?
令和6年11月の厚生労働省の検討会提言を受け、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が令和7年5月14日に公布されました。
施行期日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、最長でも令和10年5月までには50人未満の企業を含むすべての事業場で義務化される見込みです。準備期間を確保するため、早めに体制整備を始めることが非常に重要です。
50人未満の企業や、従業員数が50人未満の支社・拠点を有する企業は、この施行期日を見据えて、ストレスチェックの実施体制の整備など、早めに準備を始めることが非常に重要です。
出典:労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要|厚生労働省
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
メンタルヘルス不調者への実務ガイドブック
入社や異動が多く発生する時期は、環境の変化によるストレスでメンタルヘルス不調に陥りやすくなります。
本資料は職場でメンタルヘルス不調者が発生した際の対応手順のほか、休職時トラブルへの対処方法も解説しています。
健康診断のご案内(ワード)
従業員へ健康診断の実施を案内する際に活用できる、ワード形式のテンプレートです。
社内周知にかかる作成工数を削減し、事務連絡を円滑に進めるための資料としてご活用ください。
ストレスチェック義務化とは
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的として2015年12月から義務化されました。
具体的には、定期的な検査によって労働者自身のストレスの状態を把握してもらい、高ストレスと判断された場合は医師による面接指導につなげることで、早期のケアを実現します。また、検査結果を分析し、職場全体の環境改善につなげることも重要な目的の一つです。
関連資料|〖社労士監修〗急な休職対応にも慌てない! メンタルヘルス不調者への実務ガイドブック
関連記事|ストレスチェックとは?概要や目的、義務化の対象拡大について解説
ストレスチェック義務化の対象となる事業場
この制度の対象となるのは、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。常時50人以上の労働者とは、正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトなど期間の定めのない労働者を含めた人数で判断します。50人以上の事業場には、年に1回のストレスチェックの実施が義務づけられています。
一方、常時使用する労働者が50人未満の事業場については、これまでは努力義務にとどまっていました。
ストレスチェック制度の法的根拠(労働安全衛生法)
ストレスチェック制度の法的根拠は、労働安全衛生法です。
同法第66条の10において、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、年に1回、医師や保健師などによるストレスチェックの実施が義務付けられています。また、高ストレス者からの申し出があった場合の医師による面接指導の実施も定められています。
関連記事|労働安全衛生法のストレスチェック制度とは?条文をもとに対象者や項目、罰則などを解説
50人未満の事業所が先行実施する3つのメリット
現時点で努力義務の50人未満企業であっても、ストレスチェックを先行して実施することで、将来の義務化への対応だけでなく、企業経営においても多くの利点が得られます。
メンタルヘルス不調による休職・離職の防止
ストレスチェックを先行して導入する最大のメリットは、従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見し、休職や離職を未然に防ぐことができる点です。
中小企業では、一人の従業員が抜けることによる業務負荷増大の影響が大きくなりがちです。定期的なチェックは、従業員が自身のストレス状態に気づくきっかけとなり、企業側も高ストレス者に対して適切な時期に面談や職場環境の調整といったサポートを提供できるようになります。
関連記事|メンタルヘルスとは?意味や不調が招く疾患、職場での対策方法
生産性の向上
ストレスチェックの結果を部署やチームといった集団ごとに分析(集団分析)することで、職場全体の課題を客観的に把握し、生産性向上の具体的なきっかけを見つけられます。
業務分担の見直しや、管理職向けのコミュニケーション研修の実施といった対策をとることで、働きやすい環境が整備され、結果的に従業員のモチベーションと生産性の向上につながります。集団分析は、従業員一人ひとりの負担を減らし、組織としての活力を高めるための重要なツールになります。
関連資料|業務改善報告書(ワード)
企業イメージの向上
従業員の健康と安全に配慮する安全配慮義務を果たす姿勢を示すことは、企業の信頼性を高める上で非常に重要です。
ストレスチェックの先行実施は、企業が従業員の心身の健康を重視していることの明確な証拠となります。これにより、万が一メンタルヘルス不調に関するトラブルが発生した場合の法的リスクの軽減につながるだけでなく、「従業員を大切にする企業」として企業イメージが向上し、優秀な人材の確保や定着率の向上にも良い影響をもたらすでしょう。とくに、採用市場において、健康経営に取り組む企業としての評価は、大きな差別化要因となります。
関連記事|社員の健康管理とは?企業が取り組むべき施策・成功事例・メリットを徹底解説
50人未満企業の企業のストレスチェック実施7ステップ
50人未満企業がストレスチェックを実施する際も、50人以上企業の手順をふまえて進めることで、義務化された際にスムーズに対応できるようになります。ここでは、担当者が進めるべき7つのステップを解説します。
ステップ1:実施体制を明確にする
ストレスチェックの実施にあたっては、まず、実施体制を明確にしましょう。
具体的には、実施事務従事者(人事・労務担当者など、チェックの事務作業を行う者)の選任や、ストレスチェックの結果を判定し、面接指導を行う実施者(産業医や保健師など)を選定します。
次に、ストレスチェックの目的、対象者、実施方法、費用負担、高ストレス者の選定基準、面接指導の実施方法、結果の利用と保管方法、プライバシー保護のルールなどを定めた社内規程(実施規程)を作成する必要があります。
関連記事|安全衛生委員会の設置基準は?50人未満の場合やメンバー構成、進め方まで解説
ステップ2:ストレスチェックの実施
作成した規程に基づき、実際にストレスチェックを実施します。
原則として、事業場のすべての労働者が対象ですが、実施日を基準として休職中の従業員など、メンタルヘルスに配慮して受検の判断が難しい場合は、実施者の判断のもと、例外的に非対象とすることもあります。
検査は、質問紙を用いて行われ、厚生労働省が提供する標準的な質問票(57項目)を利用するのが一般的です。
関連資料|ストレスチェック案内文(ワード)
ステップ3:結果の通知
ストレスチェックの結果は、実施者(産業医など)から直接、受検した従業員本人へ通知されます。
この際、企業側は、原則として個人の結果を把握することはできません。結果通知では、ストレスレベルと、高ストレスと判定された場合の医師による面接指導の申し出方法が示されます。高ストレスと判定された従業員に対しては、面接指導の申し出を促す必要があります。
ステップ4:高ストレス者への医師による面接指導
高ストレス者から申し出があった場合、企業は速やかに(申し出から概ね1ヶ月以内)医師による面接指導を実施する必要があります。
面接指導では、医師が従業員の健康状態や生活状況、ストレスの要因などを詳細に把握し、必要な助言や指導を行います。面接指導の場所は、プライバシーが確保できる静かな環境を用意することが重要です。面接指導を終えた医師は、従業員の同意を得た上で、業務上の措置(たとえば、残業の制限や配置転換など)に関する意見を企業に提供します。企業は、医師の意見をふまえて、従業員の健康保持に必要な就業上の措置をとる必要があります。措置をとる際は、従業員本人の意見も尊重し、慎重に進めます。
関連記事|産業医とは?医師との違いや設置要件について分かりやすく解説
関連記事|産業医委嘱契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
ステップ5:集団分析の実施と職場環境の改善
集団分析は、原則として高ストレス者の面接指導が終了した後、従業員の同意を得た上で実施されます。
集団分析とは、部署やチームなどの集団単位でストレスの傾向を分析し、職場環境の課題を洗い出すことです。たとえば、分析の結果、特定の部署で「仕事のコントロール度」のスコアが低い場合、従業員の裁量を増やしたり、業務の進め方を見直したりする改善策が考えられます。集団分析の結果は、匿名化され、個人が特定されない形で行われるため、企業はこれを人事施策や職場環境改善のための基礎データとして活用できます。
関連資料|実務ステップで学ぶ! 休職者対応ガイドブック
関連資料|労働安全衛生委員会議事録(ワード)
ステップ6:結果のデータ保存・記録管理
ストレスチェックの結果、および医師による面接指導の記録は、5年間保存することが義務付けられています(労働安全衛生規則第52条の14)。
この記録には、検査年月日、受検者の氏名、検査結果の概要、面接指導の有無とその結果などが含まれます。とくに、高ストレス者への対応履歴は、将来的に安全配慮義務違反を問われた際の重要な証拠ともなりえます。これらの機密性の高いデータを適切に、かつ安全に管理するためには、労務管理システムの活用が非常に有効です。
ステップ7:労働基準監督署への報告
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、ストレスチェックの実施後、年に1回、所轄の労働基準監督署に報告書を提出する義務があります。
この報告書には、検査を実施した期間や、受検した人数、面接指導を実施した人数などを記載します。50人未満の事業場には報告義務はありませんが、将来的な義務化に備え、記録自体は適切に作成しておくことが望ましいと考えられます。報告書の作成や提出を怠ると、後述する罰則の対象となるため、50人以上の企業は提出期限に十分注意する必要があります。
50人未満企業が知っておくべきストレスチェックの注意点
ストレスチェック制度は、罰則だけでなく、企業の信頼や法的責任に関わる重要な注意点がいくつかあります。実施担当者として知っておくべきリスクと対策を解説します。
罰則はないが報告義務違反には罰金
常時50人以上の事業場がストレスチェックの実施を怠ったとしても、その行為自体に対する直接的な罰則(懲役や罰金)はありません。
しかし、実施後、労働基準監督署への報告書の提出を怠った場合や、ストレスチェック結果の記録を5年間保存しなかった場合など、労働安全衛生法上の報告義務違反や記録保存義務違反があった場合には、労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。50人未満の企業には報告義務はないものの、50人以上の企業は提出を忘れないように注意し、記録はすべての企業で適切に行う必要があります。
関連記事|労働安全衛生法の概要、2025年の改正をわかりやすく解説
関連資料|労働基準監督署の調査準備チェックリスト(PDF)
プライバシー保護を十分にする
ストレスチェックの結果は、非常に機密性の高い個人情報です。
企業は、ストレスチェックの結果を従業員本人の同意なく不当に入手したり、利用したりしてはなりません。個人の検査結果が企業に提供されるのは、原則として従業員本人が同意した場合、または医師による面接指導の申し出があった場合に限定されます。
また、結果を理由として、解雇、降格、異動などの不利益な取り扱いをすることも労働安全衛生法で明確に禁止されています。
プライバシー保護の体制が不十分だと、従業員の制度への信頼が失われ、受検率の低下にもつながります。
関連資料|従業員個人情報保護同意書(ワード)
従業員のストレスチェック拒否には適切な対応を
ストレスチェックの対象となる従業員が検査の受検を拒否するケースもあります。
ストレスチェックは、あくまで従業員の「同意」に基づいて実施されるため、受検を強制することはできません。
企業としては、制度の目的(従業員自身の健康維持のためであること)や、結果のプライバシーが厳重に保護されることなどを丁寧に説明し、受検を促すようにしましょう。
関連資料|休職者対応時の労務トラブル回避メソッド
関連資料|〖社労士が解説〗育児/介護/病気/メンタルヘルス/労災 休業・休職時の給与計算ガイド
ストレスチェック導入にかかる費用相場とコスト削減のヒント
ストレスチェックの導入・実施には費用がかかります。とくに50人未満企業の場合、コストを抑えながら効果的に導入するための費用相場とヒントを解説します。
自社実施と外部委託(サービス)の費用相場比較
ストレスチェックの実施方法には、「自社実施」と「外部委託」の大きく2つがあります。
| 実施方法 | 費用相場(年額) | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自社実施 | 低コスト | 自社の状況に合わせた柔軟な対応ができる | 担当者への負荷、プライバシー保護の体制構築が必要 |
| 外部委託 | 従業員一人あたり数百円~2,000円程度 | 事務負担が大幅に軽減、専門的な分析やサポートが得られる | 費用は高くなる場合がある、自社にノウハウが蓄積されにくい |
自社実施は、質問票や結果通知の用紙代、産業医・保健師への依頼費用(面接指導や結果分析)、労務担当者の人件費などが主なコストです。
外部委託は、Web受検システム、結果の集計・分析、実施事務代行、産業医紹介料などが含まれます。外部委託は費用がかかるものの、専門的な知見を活用でき、担当者の業務負担を大きく軽減できるため、トータルで見た効率は高くなることが多いです。
関連資料|システム導入して終わりじゃない! 労務管理を進化させるDX戦略ガイド
50人未満企業におすすめの助成金制度の活用
50人未満の事業場がストレスチェックを導入する場合、国や自治体の助成金制度を活用することで、コストを大幅に削減できる可能性があります。
代表的なものとして、厚生労働省の「小規模事業場産業医活動助成金」がありましたが、現在は廃止されています。ストレスチェック関連の助成金としては「団体経由産業保健活動推進助成金」が現存しており、商工会議所等の事業主団体を通じて申請する助成金です。ストレスチェックの実施支援やストレスチェック実施後の職場環境改善支援、面接指導の実施が主な助成対象です。この助成金を活用することで、中小企業が個別に導入することが困難だった産業保健サービスの活用の促進が期待できます。
関連資料:団体経由産業保健推進助成金のご案内(令和7年度版)
外部委託先の選び方
外部委託先を選ぶ際は、費用だけでなく、以下の点をふまえて選定することが重要です。
- 信頼性・実績
多くの企業の実施実績があり、個人情報の取り扱いに関するセキュリティ体制が整っているか(ISMS認証やプライバシーマークなど)。 - 利便性
従業員が容易に利用できるWeb受検システムがあるか、結果の集計や集団分析機能が充実しているか。 - サポート体制
産業医の紹介や、高ストレス者対応のアドバイス、労働基準監督署への報告に関するサポートが含まれているか。面接指導を外部の医師に依頼できるサービスがあるかどうかも重要な判断基準になります。 - 労務管理システムとの連携
将来的なデータの一元管理を見据え、自社で利用している、または導入を検討している労務管理システムと連携できるか。データ連携ができれば、管理業務が格段に効率化されます。
ストレスチェック義務化の要件を把握し、適切な実施を
ストレスチェックの義務化は、従業員50人以上の事業場にとっては必須の対応ですが、令和10年度にはすべての事業場に義務化が拡大する見込みであり、50人未満の企業にとっても、先行実施によるメリットは大きく、リスク回避の面からも重要性が高まっています。
最新の動向をふまえ、自社の労務管理の最適化を図るためのストレスチェックの導入を前向きに進めていくことをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【始末書テンプレート付き】パワハラ防止法とは?法改正の内容や対策法を解説!
パワハラ防止法の対策方法を検討する企業が増えています。2022年4月には法改正が行われ、中小企業もパワハラ防止法の対象となりました。パワハラ防止法に違反すると職場環境が悪化するだけ…
詳しくみる【チェックシート付】モラルハラスメントとは?無自覚なモラハラを防ぐ方法や企業の対応を徹底解説
モラルハラスメント(モラハラ)は、言葉や態度により、相手を精神的に苦しめることを指します。侮辱する発言をしたり執拗に叱責を繰り返したり、プライベートに立ち入ったりすることが挙げられ…
詳しくみる産休・育休ガイド|期間、条件、手当の計算方法、いつもらえるかを徹底解説【2026年最新】
産休や育休は、子どもを迎えるにあたり、家計やキャリアプランに直結する非常に重要なライフイベントです。特に2025年の法改正によって、男女ともに育児休業が取得しやすくなる今、制度を正…
詳しくみるローパフォーマーの社員に退職勧奨するべき?注意点やよくある質問なども解説
企業にとってローパフォーマーの社員の存在は、組織の生産性に関わる課題のひとつです。ローパフォーマーの社員に対して退職勧奨を行うべきなのか、判断に悩む人事担当者も少なくありません。 …
詳しくみる【無料テンプレ付】降格とは?実施の流れや対応、必要書類、違法のケースを解説
降格とは、従業員の役職や職位などを引き下げることです。懲戒処分による降格、人事異動による降格の2パターンがありますが、いずれも従業員の不利益につながる可能性があり、訴訟等のリスクが…
詳しくみる人事戦略を立案するには?具体的な手順や注意するべきポイントを解説
企業の持続的な成長において、人事戦略の立案は経営の根幹をなす重要な要素です。単なる採用や労務管理にとどまらず、経営目標と人材をいかに連動させるかが、企業の競争力を大きく左右します。…
詳しくみる

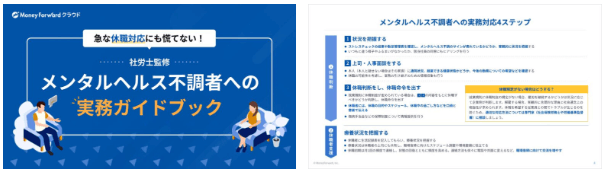
-e1763463724121.jpg)