- 更新日 : 2025年8月14日
テレワークでの健康管理の方法は?厚生労働省の指針やルール作りの事例、法改正まで解説
テレワークは、通勤時間の削減や柔軟な働き方を実現するというメリットがある一方で、従業員の心身に不調をきたすという新たな健康問題も浮上しています。企業には、従業員が働く場所を問わず、その安全と健康に配慮する義務があります。
本記事では、厚生労働省が示すガイドラインをもとに、企業が実践すべきテレワークの健康管理について、具体的な対策やルール作りのポイントを詳しく解説します。さらに、2025年4月に施行された法改正の動向も踏まえ、企業が取り組むべきことを明らかにします。
目次
テレワークで求められる健康管理とは
テレワークの普及は、私たちの働き方に大きな変化をもたらしましたが、同時にこれまでにない健康課題を生み出しています。主な問題は、以下の3つに大別されます。
- 長時間労働による心身の疲労
オフィス勤務と異なり、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。結果として、無意識のうちに長時間労働に陥り、心身の疲労を蓄積させてしまうケースが少なくありません。 - コミュニケーション不足による精神的不調
同僚との雑談や気軽な相談の機会が激減することで、孤独感や業務上の不安を抱えやすくなります。これが引き金となり、メンタルヘルスに不調をきたす従業員も増加しています。 - 運動不足による身体的な問題
通勤という日常的な身体活動がなくなることで、運動不足に陥りがちです。その結果、肩こり、腰痛、体重増加といった身体的な不調を引き起こす要因となります。
これらの健康問題は、従業員個人の課題であると同時に、企業が組織として主体的に対策を講じるべき重要な経営課題です。
法律で定められた企業の安全配慮義務
労働契約法第5条において、企業は「従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするもの」と定められています。
この安全配慮義務は、オフィスや工場といった物理的な場所だけでなく、従業員がテレワークを行う自宅などにも当然適用されます。心身の健康も安全に含まれるため、企業はテレワーク中の従業員の健康状態を適切に把握し、問題が発生しないよう予防策を講じる法的な責任を負っています。万が一、この義務を怠り従業員に健康被害が生じた場合、企業は損害賠償責任を問われる可能性があります。
厚生労働省のガイドラインのポイント
厚生労働省は、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」で企業が留意すべき事項を具体的に示しています。特に健康管理において重要なのは、以下の4つのポイントです。
参考:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン |厚生労働省
- 健康相談体制の整備
従業員が心身の不調を感じた際に、気軽に相談できる窓口を設置することが求められます。チャットツールやWeb会議システムを活用し、産業医や保健師、カウンセラーへ繋がるオンライン相談体制を整えることが有効です。 - 長時間労働の抑制
テレワーク特有の働きすぎを防ぐための仕組み作りが不可欠です。時間外労働を原則禁止としたり、事前申請制を導入したりするルールが推奨されています。 - メンタルヘルスケア
孤独感や不安を軽減するため、管理職が部下の変化に気づき、適切な声かけや対応を行うラインケアの教育が重要です。従業員自身がストレスに対処する方法を学ぶセルフケアの機会提供も求められます。 - 作業環境の整備
自宅の作業環境が、必ずしも安全で快適とは限りません。企業は、従業員が安全に業務を遂行できるよう、デスクや椅子、照明などの作業環境に関する実態把握と支援に努める必要があります。
これらの指針は、企業が安全配慮義務を具体的にどう果たすべきかを示したものであり、テレワークの健康対策を講じる上での基本となります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
メンタルヘルス不調者への実務ガイドブック
入社や異動が多く発生する時期は、環境の変化によるストレスでメンタルヘルス不調に陥りやすくなります。
本資料は職場でメンタルヘルス不調者が発生した際の対応手順のほか、休職時トラブルへの対処方法も解説しています。
健康診断のご案内(ワード)
従業員へ健康診断の実施を案内する際に活用できる、ワード形式のテンプレートです。
社内周知にかかる作成工数を削減し、事務連絡を円滑に進めるための資料としてご活用ください。
テレワークの健康問題を防ぐための対策
従業員の健康を守るためには、日々の業務の中で実践できる具体的な対策を多角的に講じることが不可欠です。
適切な労働時間の管理
客観的な労働時間の把握が、長時間労働を抑制する第一歩です。
- 勤怠管理システムの導入
PCのログオン・ログオフ時間と連動するなど、客観的な労働時間を記録するシステムを導入します。 - ルールの明確化
始業・終業時刻の報告をチャットやメールで義務付け、時間外労働や休日労働は事前承認制とするルールを設けます。 - システムによる制御
深夜時間帯や休日に業務用システムへアクセスできないよう制限したり、一定の残業時間を超えた従業員とその上司に自動でアラートを送信したりする仕組みも有効です。
これにより、従業員自身も働き方を意識し、メリハリのある業務遂行が可能になります。
コミュニケーション不足の解消
テレワークにおける孤独感や疎外感は、メンタル不調の大きな原因です。意図的にコミュニケーションの機会を創出することが重要になります。
- 定例ミーティングの実施
毎日短時間でもチームの朝礼や終礼をWeb会議で行い、顔を合わせる機会を作ります。 - 雑談の場の提供
業務連絡だけでなく、雑談専用のチャットチャンネルを設け、偶発的なコミュニケーションを促します。 - 1on1ミーティングの設定
上司と部下が定期的に1対1で対話する時間を設け、業務の悩みや心身の状態について話せる信頼関係を築きます。 - バーチャルオフィスツールの活用
バーチャルオフィスツールを導入し、仮想空間上でアバターを介して集まることで、オフィスにいるかのような一体感を醸成している企業もあります。
メンタル不調へのアプローチ
従業員の心の健康を守るためには、不調のサインを早期に発見し、迅速に対応できる体制が欠かせません。
- 相談窓口の設置
産業医やカウンセラーにオンラインで気軽に相談できる窓口を設け、利用を促します。 - ストレスチェックの実施
年に一度のストレスチェックを確実に実施し、高ストレス者には産業医面談を勧奨します。 - 研修の実施
管理職向けに、部下の様子の変化に気づき、適切に対応するための「ラインケア研修」を実施します。また、従業員自身がストレスへの対処法を学ぶ「セルフケア研修」の機会を提供するのも効果的です。
運動不足や身体的負担を軽減する環境整備
在宅でのデスクワークは、運動不足や不適切な姿勢による身体的負担を招きがちです。
- 費用補助制度
デスクやチェア、モニターといった、身体への負担が少ない作業環境を整えるための費用補助制度(在宅勤務手当など)を導入します。 - 運動機会の提供
オンラインで参加できるストレッチセミナーやヨガ教室を開催したり、健康管理アプリを活用してチーム対抗のウォーキングイベントを実施するなど、楽しみながら運動習慣を身につけられる企画が効果的です。
企業が整備すべき在宅勤務のルールと事例
効果的な健康管理を実現するには、その土台となる明確なルールが不可欠です。企業の事例も参考に、自社の実情に合った規定を整備しましょう。
在宅勤務規定に盛り込むべき項目
従業員が安心して働ける環境の基礎として、就業規則や在宅勤務規定を整備します。最低限、以下の項目は明記しましょう。
- 対象者:在宅勤務が可能な従業員の範囲
- 労働時間:始業・終業時刻、休憩時間、業務の途中で私用等により離席する「中抜け」の扱い
- 報告義務:業務の開始・終了報告の方法
- 費用負担:通信費や光熱費などの費用負担に関するルール
- 貸与機器:貸与するPCやスマートフォンの管理方法
- 緊急時の連絡体制:業務中の傷病や災害発生時の連絡方法
参考になる企業の取り組み事例
多くの企業が、健康管理と生産性向上を両立させるために独自の工夫を凝らしています。
- 在宅勤務手当の支給
全社員に月額の在宅勤務手当を支給し、快適な作業環境の構築を金銭的に支援しています。 - コミュニケーションの仕組み化
業務時間内の雑談タイムを推奨し、コミュニケーションを活性化させています。 - 健康イベントの開催
健康管理アプリを全社導入し、チーム対抗で歩数を競うイベントを開催して運動不足の解消を促す事例もあります。 - 定期的な健康チェック
産業医とのオンライン面談を定期的に実施し、心身の健康状態を会社としてチェックする体制を構築した事例もあります。
在宅勤務のルール作りの注意点
在宅勤務のルールを策定する際は、以下の点に注意が必要です。
- 目的の共有
ルールの目的が、あくまで従業員の健康と生産性の維持にあることを明確に伝え、従業員の理解と協力を得ることが大切です。 - 従業員の意見聴取
一方的に企業が内容を決定するのではなく、実際にテレワークを行う従業員の意見を聴取し、実態に即した実効性のあるルールを目指します。 - 定期的な見直し
働き方や社会情勢の変化に対応するため、一度作成したルールを定期的に見直し、必要に応じて改定する柔軟な姿勢が求められます。
2025年4月施行|テレワーク関連の法改正
テレワークに関する法整備も進んでいます。特に注目すべきは、2025年4月1日から施行された改正育児・介護休業法です。
この改正により、3歳未満の子を養育する従業員や、家族の介護を行う従業員から申し出があった場合、企業はテレワークを導入するよう努めることが努力義務となりました。これは、仕事と育児・介護の両立を支援するための措置であり、企業は対象となる従業員がテレワークを選択できるような体制整備をこれまで以上に真剣に検討する必要があります。
今後も、多様な働き方に対応するための法整備が進むことが予想されます。企業は常に最新情報を注視し、法令を遵守した労務管理を行うことが不可欠です。
テレワークにおける健康管理を徹底しましょう
テレワークにおける健康管理は、単なる福利厚生の一環ではなく、企業の持続的な成長を支える重要な経営基盤です。
適切な労働時間管理、コミュニケーションの活性化、心身のケア、そして明確なルール作りとセキュリティ対策は、企業が果たすべき社会的責任であると同時に、従業員のエンゲージメントと生産性を高めるための未来への投資と言えます。
厚生労働省のガイドラインや法改正の動向を正しく理解し、従業員一人ひとりの声に真摯に耳を傾けながら、自社に最適な健康管理体制を構築・改善し続けること。それが、これからの時代を勝ち抜く企業に求められる姿勢です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
退職届の効力はいつ発生する?2週間前までの提出ルールや無視された時の対処法も解説
退職届を提出しようと考える時、「本当にこれで辞められるのだろうか」「いつから法的な効力が発生するのか」といった不安がよぎるものです。特に、会社から強く引き止められたり、就業規則を盾…
詳しくみる役職とは?一覧を用いて順番、肩書きの意味を解説!
役職とは、会社の組織における立場や職務、責任の重さを表す重要なものです。役職の名称は会社によって異なりますが、名刺などに肩書があることで、相手の立場や職務を予想することができます。…
詳しくみる退職勧奨されたらどうする?知らないと損する5つの交渉条件
「突然退職勧奨されたけど、どうすればよいだろう」「退職勧奨は拒否できる?」 このような悩みを抱える方もいるのではないでしょうか。 退職勧奨は、さまざまな理由で行われ、前提知識がない…
詳しくみる辞令の書き方を徹底解説!すぐに使えるシーン別テンプレート集
企業の重要な人事命令である「辞令」。いざ作成するとなると、書き方の基本ルールや記載すべき項目、法的な効力など、気になる点が多いのではないでしょうか。とくに人事異動や役職の変更は、従…
詳しくみる育休退職は問題ない?給付金はどうなる?伝えるタイミングも解説
育児休業中に退職を考えている人にとって、給付金や社会保険料などの手続きは重要です。また、退職を会社に伝えるタイミングに悩む方も多いのではないでしょうか。 本記事では、育休中の退職に…
詳しくみる均衡待遇とは?均等待遇との違いや判断方法、違法した場合のリスクなど解説
働き方の多様化が加速する現代において、あらゆる従業員が納得して能力を発揮できる職場環境の整備は、企業の持続的な成長に不可欠です。その根幹をなす同一労働同一賃金の原則を正しく運用する…
詳しくみる

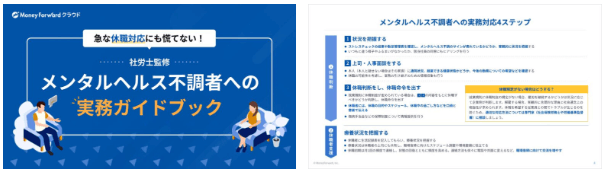
-e1763463724121.jpg)