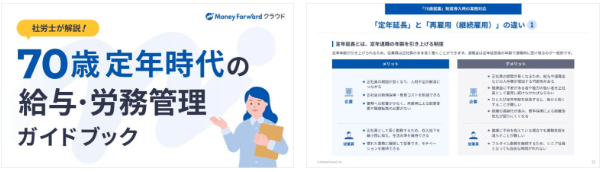- 更新日 : 2025年12月24日
高齢者を雇用した際の手当や給付金、助成金まとめ
高齢者を雇用・再雇用した企業には、「高年齢雇用継続給付」や「65歳超雇用推進助成金」などの制度があります。これらは、賃金が下がった際の補填や、65歳以降の継続雇用に伴う支援として活用することが可能です。手続きや支給条件を理解し、適切に申請することで、シニア人材の活用と企業の人件費の負担軽減につながります。この記事では、最新の制度内容と活用方法をわかりやすく解説します。
目次
高齢者を雇用した際の手当とは?
高齢者を雇用した場合は、国の雇用保険制度や助成制度に基づいて、給付金・補助金といった様々な手当が支給されます。これらの制度は、高齢者が定年後も安心して働き続けられるようにすることと、企業が年齢に関係なく人材を確保できるようにすることが主な目的です。
手当には、賃金が下がった際に本人に支払われる「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」、企業に対して支給される「65歳超雇用推進助成金」などがあります。それぞれ対象年齢や条件が異なりますが、60歳以上の雇用を促進する仕組みとして活用されています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
主な高齢者の雇用手当の種類
高齢者の雇用手当の一つとして、雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付があります。これは、60歳を過ぎても働き続ける方が、賃金が下がった際にその減少分を補うことを目的としています。
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
ただし、この制度は2025年度以降され、2030年4月に廃止される予定です。したがって、利用時には最新の支給率や制度変更に注意が必要です。
高年齢雇用継続基本給付金(継続雇用向け)
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時点で雇用保険に5年以上加入し、同じ会社で働き続ける方が対象です。60歳時点と比較して、賃金が75%未満に下がった場合に支給されます。賃金低下を補填し、60歳以降も働き続けられるよう支援します。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること。
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。
- 60歳以降の賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下していること。
- 各月の賃金が支給限度額(2025年7月現在:約376,750円)以下であること。
- その他、失業給付を受給していないこと、週20時間以上の勤務などの条件があります。
支給額
支給額は、60歳到達時賃金月額と各月の賃金の低下率で決まります。2025年4月1日以降に60歳に達した方は、支給率の上限が15%から10%に引き下げられます。賃金が60歳到達時賃金月額の64%以下に低下した場合は最大10%が支給され、それ以上の場合は徐々に減少します。賃金が61%以上75%未満に低下した場合は、低下率に応じた割合で支給されます。ただし、賃金と支給額の合計には上限があります。
申請手続き
原則として、事業主が本人の協力を得て、管轄のハローワークに申請します。初回申請は60歳到達後2ヶ月以内、その後は原則2ヶ月ごとに申請が必要です。
高年齢再就職給付金(再就職者向け)
高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の方が、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給した後、再就職した場合に支給される給付金です。再就職後の賃金が、離職前の賃金と比較して75%未満になった場合に、その減少分を補填します。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること。
- 基本手当の支給残日数がある状態で再就職し、かつ離職後1年以内に再就職したこと。
- 再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること(原則)。
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。
- 再就職後の賃金が、離職前の賃金月額の75%未満に低下していること。
- 各月の賃金が支給限度額(2025年7月現在:376,750円)以下であること。
- その他、他の雇用保険給付を受給していないこと、週20時間以上の勤務などの条件があります。
支給額
支給額は、再就職後の賃金が離職前賃金と比較してどの程度低下したかで決まります。賃金が離職前賃金の61%未満に低下した場合、2025年4月1日以降に再就職した方については、高年齢再就職給付金の支給率の上限が15%から10%に引き下げられます。賃金が61%以上75%未満に低下した場合は、低下率に応じた割合で支給されます。ただし、賃金と支給額の合計には上限があります。
申請手続き
原則として、本人が再就職後1年以内に、管轄のハローワークに申請します。その後は原則2ヶ月ごとに申請が必要です。
参考:高年齢雇用継続給付について|ハローワーク インターネットサービス
60歳以上の雇用に関する手当・助成金
60歳以上の高齢者が働き続けることを企業が支援できる助成金制度を紹介します。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、ハローワークなどの紹介で、高齢者、障害者、シングルマザーなど、就職が難しいとされる方を雇用する企業に支給されます。
支給要件
この助成金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介で、対象となる高齢者を雇い入れること。
- 雇用保険の一般被保険者として雇い入れること。
- 継続して雇用することが確実であると認められること(原則として1年以上の雇用が見込まれること)。
支給額
支給額は、対象となる労働者の年齢や企業の規模、雇用形態によって異なります。
- 高年齢者(60歳以上65歳未満)を常用労働者として雇い入れた場合:
- 中小企業以外: 50万円(短時間労働者の場合30万円)
- 中小企業: 60万円(短時間労働者の場合40万円)
- 高年齢者(65歳以上)を常用労働者として雇い入れた場合:
- 中小企業以外: 40万円(短時間労働者の場合20万円)
- 中小企業: 50万円(短時間労働者の場合30万円)
支給額は、雇用期間に応じて分割して支払われます。パートやアルバイトといった短時間労働者でも、雇用保険の適用要件を満たし、継続雇用が見込まれる場合は対象となります。
申請手続き
申請は、対象となる高齢者を雇い入れた日の翌日から2ヶ月以内に、管轄のハローワークに提出します。詳しい手続きや必要な書類は、ハローワークで確認できます。
参考:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省
65歳以上の雇用に関する手当・助成金
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、企業が定年年齢を引き上げたり、定年を廃止したり、65歳以降も希望する従業員全員を雇用する制度を導入したりすることを支援します。これにより、高齢者が長く働き続けられる職場環境を促進します。
支給要件
以下のいずれかの制度を導入し、実際に適用を受ける高年齢者がいることが条件です。
- 65歳以上への定年年齢の引き上げ。
- 定年制度そのものの廃止。
- 希望する従業員全員を対象とした65歳以上の継続雇用制度の導入。
支給額
支給額は、導入する制度の種類や、制度の対象となる高齢者の人数によって変わります。具体的な金額は、厚生労働省のウェブサイトや独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下、JEED)のウェブサイトで確認が必要です。
申請手続き
申請は、制度導入後、JEEDに提出します。事前に計画書を提出し、認定を受ける必要があります。
参考:65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)|厚生労働省
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、高齢者が働きやすい環境を整備するため、人事評価制度や賃金制度の見直しなど、雇用管理の改善に取り組む企業を支援します。
支給要件
以下のいずれかの措置を実施し、高年齢者の雇用管理改善が認められる場合に支給されます。
- 高齢者に適用される人事評価制度や賃金制度の導入または改善。
- 高齢者の能力開発体制や健康管理体制の整備。
- 高齢者の職場環境の改善。
支給額
支給額は、実施する措置の内容や費用の額に応じて異なります。具体的な支給額は、JEEDのウェブサイトで確認できます。
申請手続き
申請は、措置実施前に計画書を提出し、認定を受ける必要があります。その後、措置の実施後に支給申請を行います。申請窓口はJEEDです。
参考:65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)|厚生労働省
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換に取り組む企業を支援します。
支給要件
以下の要件を満たす必要があります。
- 50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させること。
- 転換後も継続して雇用することが確実であると認められること。
支給額
支給額は、転換した労働者の人数に応じて決まります。具体的な支給額は、JEEDのウェブサイトで確認できます。
申請手続き
申請は、JEEDに提出します。
参考:65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)|厚生労働省
終了した手当・助成金
下記の助成金制度は終了しました。なお、現在利用可能な助成金制度についても、今後内容の変更や廃止となる可能性があります。申請の際は、最新の情報を厚生労働省や各地域のハローワークで必ずご確認ください。
- 高年齢労働者処遇改善促進助成金→令和7年3月31日で廃止
- 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)→令和4年度末で廃止
参考:高年齢労働者処遇改善促進助成金|厚生労働省
参考:特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)|厚生労働省
高齢者の雇用に関する手当の今後
高齢者の雇用に関する手当や助成金制度は、社会の変化に合わせて見直しが進んでいます。高年齢雇用継続給付は、2025年度以降、段階的に支給率が縮小され、将来的には廃止される方向で検討されています。これは、60歳以降も働くことが一般的になったことや、企業の定年延長が進んでいるためです。
今後は、賃金補填よりも、企業による高齢者の働きやすい環境整備や、キャリア形成支援に重点が置かれるでしょう。例えば、「65歳超雇用推進助成金」のような、定年年齢の引き上げや雇用管理改善を支援する制度は、引き続き重要視されると考えられます。
企業には、高齢者雇用に関する最新情報を確認し、自社の状況に合った制度を活用していくことが求められます。
高齢者の雇用に手当を活用しシニア人材を戦力に
高齢者を雇用することで、豊富な経験や安定した働きぶりを職場に取り入れることが可能です。高齢者雇用手当を活用すれば、そうした人材の確保とあわせて、賃金補填や継続雇用にかかる費用の一部を軽減できます。高年齢雇用継続給付金や65歳超雇用推進助成金は、条件に応じて適用でき、企業の経営面にもプラスになります。制度変更もあるため、最新情報の確認と早めの対応がポイントです。
関連:【テンプレート付き】再雇用契約書とは?作り方や手続きの業務を解説!
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
高年齢雇用継続基本給付金は65歳以上になるとどうなる?代わりの給付金はある?
少子高齢化が進む中、企業にとって高齢者の活用は重要な課題となっています。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も引き続き働く意欲のある60歳から65歳未満の雇用保険被保険者を対象で…
詳しくみる入社前健康診断の義務とは?実施しないリスクや費用について解説
新しい従業員を迎えるにあたって、健康診断の義務や費用、どこで受けてもらうべきかなど、不安を感じていませんか? 本記事では、雇入時の健康診断について知っておくべき情報をご紹介します。…
詳しくみる会社の定期健康診断は義務!受けないとどうなる?対象者や項目、罰則などを徹底解説
会社の定期健康診断は、労働安全衛生法によって事業者に課された重要な義務です。しかし、「どこまでの範囲が義務?」「パートも対象になるの?」「もし受けなかったらどうなる?」といった具体…
詳しくみるコワーキングスペースとは?ドロップイン料金・経費・東京での選び方を解説
近年、リモートワークの広がりにより、都内をはじめコワーキングスペースが増えています。コワーキングスペースは、仕事や勉強などの作業を想定してデザインされており、個人事業主やフリーラン…
詳しくみるビジネスで使える「アイスブレイク」とは?効果や活用例を解説!
ビジネスにおいて、コミュケーションを円滑にするための手法はいろいろありますが、ビジネスシーンで手軽に取り入れることができるものに「アイスブレイク」があります。今回は、アイスブレイク…
詳しくみる中小企業でも義務化のパワハラ防止法とは?防止対策や具体例、事例を解説【始末書テンプレつき】
パワハラとは力関係によって起こる嫌がらせ行為を指します。職場においては優位に立つ者が言葉や態度、行動で、立場の弱い者の就業を邪魔することがパワハラに該当し、身体的な攻撃、精神的な攻…
詳しくみる