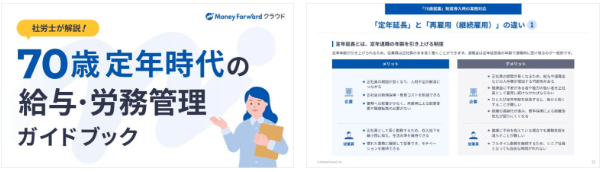- 更新日 : 2025年10月31日
高年齢雇用継続基本給付金のデメリットとは?2025年改正や年金併用、企業の対応を解説
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の再雇用や再就職時に賃金が減少した場合、その差額を補填する制度です。しかし、制度の複雑さや年金との関係、2025年の支給率変更など、注意すべき点もあります。この記事では、高年齢雇用継続基本給付金のデメリットや制度変更点を中心に、申請時の注意点や今後の展望について詳しく解説します。
目次
高年齢雇用継続基本給付金とは
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の再雇用や再就職で賃金が下がった場合に支給される、雇用保険の給付金です。賃金が60歳時点と比べて75%未満に減少した場合、その差に対して一定の給付率を乗じた額を支給する仕組みで、対象者の生活安定と就業継続を支える制度です。
この制度には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も失業保険(基本手当)等を受け取らずに、同じ企業で継続して雇用されている場合に受け取ることができる給付金です。
受給するためには、以下が条件となります。
- 60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満であること
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
支給期間は、原則として60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、各月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが必要です。
高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は、60歳以降に一度会社を退職し、失業保険(基本手当)を受け取った後に再就職した場合に受け取ることができる給付金です。
受給するためには、以下が条件となります。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
- 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
- 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと
支給期間は、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数によって異なり、200日以上の場合は最長2年間、100日以上200日未満の場合は最長1年間です。
【2025年改正】高年齢雇用継続基本給付金の変更点
2025年4月1日から、高年齢雇用継続基本給付金の変更がありました。主なポイントは以下の通りです。
- 支給率の上限が引き下げ:従来の最大15%から、10%に変更されました。
- 改正の適用対象:2025年4月1日以降に60歳を迎える方が対象となり、それ以前に60歳になっていた方は従来の条件(最大15%)が引き続き適用されます。
- 最大支給率の条件変更:これまで最大の支給率(15%)は、賃金が60歳到達時の61%以下に下がった場合に適用されていましたが、改正後は、64%以下に下がった場合に最大支給率(10%)が適用されるようになりました。
例えば、60歳到達時の賃金が月額30万円で、再雇用後の賃金が月額20万円(60%に低下)になった場合、給付金は以下のように算出されます。
- 改正前の給付金額(2025年3月までに60歳になった方)
⇒20万円× 15% = 月額3万円 - 改正後の給付金額(2025年4月以降に60歳になった方)
⇒20万円× 10% = 月額2万円
給付額は2か月ごとに申請し、過去2か月間に支払われた賃金の実績に基づいて算出されます。したがって、勤務状況や労働時間の変動によっても、給付額が変動することがあります。
将来的には廃止の可能性も
政府は「70歳までの就業機会確保」を企業に求めており、高年齢者雇用の考え方が変わりつつあります。そのなかで、60歳〜65歳を対象とした現在の給付制度は、限定的だという見方が広がっています。
そのため、支給対象者や制度の範囲自体も段階的に見直される可能性があります。65歳以上も対象に含めるべきという声や、逆に廃止の議論もあるため、制度の将来像は流動的です。
2025年の改正はその第一段階と考えられており、今後も数年単位で変更が続く可能性があります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
高年齢雇用継続基本給付金のメリット
高年齢雇用継続基本給付金は、シニア層の働き続ける意欲を支える有益な制度です。以下に、具体的なメリットを3つの観点から解説します。
減少した賃金が補填され生活が安定する
60歳以降の再雇用では、賃金が大きく下がる場合があります。高年齢雇用継続基本給付金は、その賃金減少を補う目的で支給されるため、生活水準を急激に下げずに済みます。
例えば、60歳時の賃金が30万円だった方が再雇用で20万円となった場合、一定の条件を満たせば、毎月上限2万円(20万円 × 上限10%)の給付金を受け取ることができます(2025年4月以降の上限)。
この経済的なサポートは、日々の生活費はもちろん、住宅ローンなどの継続的な支出を支える上で、心強い存在となります。
年金との併用が可能
高年齢雇用継続基本給付金は、原則として年金と併用可能です。しかし、老齢厚生年金(在職老齢年金や特別支給の老齢厚生年金)を受給しながら働く場合、賃金と年金の合計額に応じて年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
給付金の受給により賃金が増加すると、年金の支給停止額も変動する可能性がある点に注意が必要です。
企業側も人材を確保しやすくなる
企業にとっても、給付金の存在は定年後の従業員を雇用し続けるための後押しになります。特に人手不足の業界では、経験豊富なシニア人材を確保することが業務の安定に直結します。
給付金により、企業側が高齢者に支払う賃金が相対的に軽くなり、雇用継続が現実的になるため、「高齢者雇用=コスト増」とはなりにくくなります。これにより、定年後の再雇用制度を整備する企業も増加傾向にあります。
高年齢雇用継続基本給付金のデメリット
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の就業を支援する制度ですが、活用には注意点もあるため、事前の確認が必要です。2025年4月に制度改正が施行され、給付金が減少しました。
年金が減額・一部停止につながる可能性がある
高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の老齢厚生年金は、同時に受け取ることで「在職老齢年金」の調整が入ります。つまり、給付金と賃金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる可能性があります。
このため、「給付金を受けたことで年金が減った」というケースもあり、事前に試算を行うことが重要です。
他の給付金と併用できない
高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢再就職給付金や再就職手当 、 育児休業給付金、介護休業給付金 と同時に受け取ることができません。これらの給付金は、それぞれ異なる目的で設けられているため、併給調整が行われています。
受給要件を満たす必要がある
高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには、複数の要件を満たす必要があります。
60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること、雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上あること、60歳以降の賃金が60歳時点の賃金と比較して75%未満であること、支給対象月の賃金額が上限額(2024年8月時点で376,750円)未満であること、計算された給付金の額が下限額(2024年8月時点で2,295円)以上であることなどです。
賞与は計算対象外
高年齢雇用継続基本給付金の支給額を計算する際、原則として賞与は含まれません。比較されるのは、60歳到達前の6ヶ月間の平均賃金(賞与を除く)と、再雇用後の毎月の賃金(賞与を除く)です。
給付金の支給額が減少した
前述のとおり、2025年4月から給付率の上限が従来の15%から10%へ引き下げられました。この変更により、受給者の実質的な補填額は減少します。
例えば、月給20万円の人が上限の15%で3万円を受け取っていた場合、今後は2万円が上限となります。これは月1万円、年間12万円の減収にあたるため、継続雇用のメリットを感じにくくなる可能性も考えられるでしょう。
申請手続きが煩雑で負担がかかる
高年齢雇用継続基本給付金の申請には多くの書類が必要です。例えば「雇用契約書」「賃金台帳」「出勤簿」「雇用保険被保険者資格喪失届」「申請書」「事業主証明書類」などがあります。
申請は原則として本人が事前に事業主に申請の意向を伝え、事業主が手続きを行います。事業所側の協力が得られないと、手続きが進まない場合もあります。
初回申請後は、2か月ごとに定期的な申請が必要です。申請対象月が増えるごとに必要書類も更新されるため、企業側の業務負担も大きくなります。
申請期限を過ぎると給付が受けられないなど、慎重な対応が必要です。
高年齢雇用継続基本給付金のデメリットに備える企業の対応
高年齢雇用継続基本給付金の活用には、企業側の理解と対応が不可欠です。主な対策を3つの視点から解説します。
従業員への情報提供
高年齢雇用継続基本給付金は、年金制度や他の給付金制度と密接に関連しており、制度の誤解がトラブルや不満の原因となりかねません。
企業は、以下のような情報提供を積極的に行う必要があります。
- 在職老齢年金との関係を説明し、年金の一部停止リスクを事前に周知
- 高年齢再就職給付金や育児休業給付金などとの併給制限を理解させ、適切な制度選択を支援
- 「60歳到達時賃金の75%未満」という条件を踏まえた処遇設計に関する説明
- 給付金支給額の減少(2025年改正)の影響についての具体的なシミュレーション提示
60歳を迎える前に制度の概要について個別面談や説明会などでしっかり伝えることで、スムーズな申請と制度活用が可能になります。
継続雇用と賃金設計の見直し
高年齢雇用継続基本給付金の引き下げにより、補填額は限定的になりました。
そのため、賃下げが起きた場合、従業員の手取りは大きく減り、意欲を削ぐ可能性もあります。こうした状況に対応するために、企業には以下のような対応が求められます。
- 職務内容や役割に応じた適正な賃金設計の見直し
- モチベーションを保つための人事評価制度や再任用制度の導入
- 継続雇用の魅力を高める福利厚生・柔軟な勤務形態の検討
企業側は、従業員との対話の中で合理的な再雇用条件を整えることが重要です。
事務作業の効率化
高年齢雇用継続基本給付金の支給申請は、2か月ごとの定期申請が必要です。雇用契約書・賃金台帳・事業主証明書など多くの書類が求められます。
企業が抱える事務負担を軽減し、ミスや遅延を防ぐには次のような対策が有効です。
- 申請スケジュールの管理と担当者の明確化
- 社内で申請フローを文書化し、チェックリストで運用
- クラウド型勤怠・給与管理ソフトの導入により、データ収集・書類作成を効率化
- 本人から事業主への申請意思表明を円滑にするための社内連絡体制づくり
正確かつ継続的な運用には、システム活用と人の支援を両立させることが不可欠です。
高年齢雇用継続基本給付金と老齢厚生年金の支給停止の関係
60歳以上65歳未満の方が、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合、賃金や高年齢雇用継続基本給付金の額に応じて、年金の一部が支給停止となることがあります。これは、在職老齢年金制度と高年齢雇用継続給付の調整によるものです。
在職老齢年金制度による支給停止
在職老齢年金制度では、年金の基本月額と総報酬月額相当額(月給と賞与の合計を月額換算した額)に応じて、年金の一部または全部が支給停止されます。
具体的な基準額は年齢や年度によって異なりますが、例えば2025年4月からは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が51万円を超える場合に支給停止となる金額が発生します。
高年齢雇用継続給付による支給停止
高年齢雇用継続基本給付金を受け取ると、老齢厚生年金の一部が追加で支給停止となる場合があります。支給停止額は、原則として標準報酬月額の4%に相当する額が上限です 。ただし、2025年3月31日以前に60歳に到達した方や再就職した方は、最大で標準報酬月額の6%となる場合があります。例えば、標準報酬月額が20万円の場合、高年齢雇用継続給付による年金の支給停止額は最大で8,000円となります 。
このように、60歳以降も働きながら年金を受け取る場合は、在職老齢年金制度による支給停止と、高年齢雇用継続給付による支給停止の両方を考慮する必要があります 。
高年齢雇用継続基本給付金と年金受給の具体例
以下に、具体的なケースを示します。
事例:60歳時の賃金が35万円、60歳以降の賃金が20万円に減少した場合
- 年金月額:10万円
- 高年齢雇用継続基本給付金:20万円 × 10%(支給率)=2万円
- 年金の支給停止額:20万円 × 4%(支給停止率)=8,000円
- 年金の受給額:10万円 − 8,000円 = 9万2,000円
- 総収入:賃金20万円 + 給付金2万円 + 年金9万2,000円 = 31万2,000円
高年齢雇用継続基本給付金を受給することで、老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合があります。支給停止額は、賃金や給付金の額に応じて変動します。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請が認められた場合、その後に申請を行わなかったとしても、支給可能な期間中は老齢厚生年金の一部支給停止が継続されます。ただし、退職や65歳に到達などの条件を満たすと、支給停止が解除されることがあります。
- 支給停止の条件や計算方法は、年度や制度改正により変更される可能性があります。最新の情報は、日本年金機構や厚生労働省の公式サイトで確認することをおすすめします
高年齢雇用継続基本給付金のデメリットも理解し制度を上手に活用しよう
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の収入減を補う有効な制度ですが、年金の一部支給停止や2025年からの給付率が引き下げたなど、注意点もあります。制度の変更を踏まえ、受給条件や申請手続き、今後の代替制度について正しく理解し、早めに備えることが大切です。
企業の取り組みや各種助成金制度も視野に入れながら、自分に合った働き方を選び、安心して働き続けられる環境づくりを整えましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
退職後にハローワークでするべき手続きは?失業給付の受給までの流れを解説
退職後、失業給付を受給するには、ハローワークで必要な手続きを済ませることが重要です。ハローワークに足を運んだら「求職の申し込み」を行い、必要書類を提出することから始めましょう。指示…
詳しくみる労働契約法第10条とは?就業規則や不利益変更、違反例をわかりやすく解説
就業規則の変更を考えているものの、労働者の同意が得られない、または労働者に不利益になる内容を盛り込みたいといった悩みは、多くの人事・労務担当者や経営者が抱える問題です。 労働契約法…
詳しくみる就業規則への育児休業の記載例|2025年の育児介護休業法改正に対応したひな形つき
育児・介護休業法は、社会情勢の変化に対応するため、ほぼ毎年改正が重ねられています。特に、男性の育児休業取得を後押しする制度の創設や、2025年施行の新たな両立支援策など、企業が対応…
詳しくみる外国人労働者の受け入れ制度の種類とは?雇用までの流れもあわせて解説
人手不足により、外国人労働者の受け入れを検討している企業もいるでしょう。 令和6年10月時点では、外国人労働者が過去最多の230万人を超え、今後もますます外国人労働者が増加し、雇用…
詳しくみる労働安全衛生法の概要、2025年の改正をわかりやすく解説
労働安全衛生法(安衛法)は、職場で働くすべての人の安全と健康を守るための重要な法律です。しかし、その内容は多岐にわたり、専門用語も多いため、「自社にどのような義務があるのか」「最近…
詳しくみる副業解禁に向けて!就業規則見直しのポイントをわかりやすく解説
近年、人手不足や働き方改革推進の影響で、副業を禁止するのではなく解禁していく動きが広がっています。 副業の解禁には注意点もありますが、従業員が他社で培った経験を取り入れたりといった…
詳しくみる