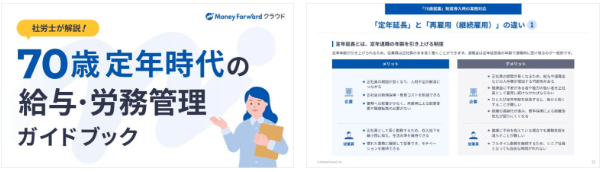- 更新日 : 2025年7月11日
【2025年改正】高齢者雇用安定法とは?企業の対応や義務をわかりやすく解説
少子高齢化が進む中、企業にとって高年齢者の活用は重要な課題となっています。「高年齢者雇用安定法」では、2025年4月施行の改正により65歳までの雇用確保が全企業に義務付けられます。この記事では、改正内容と必要な企業の実務対応をわかりやすく解説します。
目次
高年齢者雇用安定法とは
高年齢者雇用安定法は、1971年9月に「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定されました。その主な目的は、高年齢者の雇用を安定させ、再就職を促進することで、彼らが長年培ってきた技能や経験を活かせるようにすることです。制定以来、社会の高齢化や労働市場の変化に対応するため、幾度かの改正が行われてきました。
高年齢者雇用安定法では、2004年6月の改正によって、65歳までの定年引上げ、65歳までの継続雇用制度の導入、定年廃止のいずれかを講ずることを義務付け、経過措置が設けられていました。2025年の改正では、経過措置がなくなり、希望者全員に対して雇用確保措置を講じることが義務づけられました。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
【2025年4月】高年齢者雇用安定法改正により義務化された内容
2025年4月の高年齢者雇用安定法の改正の最も大きなポイントは、労使協定により制度適用対象者の基準を定めていた場合は、その基準を適用できる年齢を段階的に引き上げることができるという経過措置がなくなり、希望者全員に対して雇用確保措置を講じることが義務化されたことです。
定年を65歳以上に引き上げ
定年年齢を65歳以上に引き上げることは、就業規則などにおいて企業の定年を明確に変更する措置です。定年を65歳以上に引き上げた場合、定年年齢に達するまで雇用が保障されます。
再雇用契約の締結や対象者の選定といった個別対応が不要になる点はメリットですが、人件費や役職の見直し、評価制度の再構築といった運用面での体制整備が欠かせません。
65歳までの継続雇用制度の導入
60歳(定年)に達した従業員が引き続き働くことを希望する場合、企業は再雇用制度や雇用延長制度などを通じて、65歳までの雇用を確保します。
改正前は、労使協定により制度適用対象者の基準を定めていた場合は、その基準を適用できる年齢を段階的に引き上げることができましたが、2025年4月の改正以降は、希望する全従業員を対象とすることが義務となりました。これは、個々の従業員の就労意欲を尊重し、働く機会の平等性を高めることを目的とした措置です。
定年制の廃止
定年制を廃止するという選択肢も、引き続き企業に認められています。年齢による退職の区切りがなくなることで、意欲や能力のある高年齢者が年齢に関係なく働き続けることが可能になります。
一方で、無期限雇用が前提となるため、評価制度・業務配分・健康管理・退職基準の明確化など、企業側の運用体制がより重要になります。
高年齢雇用継続給付の引き下げ
今回の法改正で、雇用保険法に基づく「高年齢雇用継続給付」の支給水準が縮小されています。
これまで高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳時点と比べて75%未満に減少した場合に支給され、賃金の低下率が61%以下という場合は最大15%の給付率が適用されていました。
2025年4月1日以降に60歳に達した方については、最大の給付率が10%に引き下げられ、この10%は賃金が64%を下回った場合に適用されます。
この制度は、60歳から65歳の間の継続雇用を金銭的に支援するもので、年金受給までのつなぎとしての役割を果たしていましたが、今後は支援の規模が縮小され、将来的には制度の廃止も検討されている点に注意が必要です。
高年齢者雇用安定法の改正で企業に求められる対応
高年齢者雇用安定法の改正で、企業は様々な対応を求められます。
就業規則・労働条件の見直し
経過措置がなくなり、希望者全員に対して雇用確保措置を講じることが義務化されました。「定年年齢の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかを選択し、その内容を就業規則に明記しなければなりません。
就業規則の記載例
① 定年を65歳に引き上げる場合
「第〇条 従業員の定年は満65歳とし、満65歳に達した日の属する月の末日をもって退職とする。」
② 65歳までの継続雇用制度を導入する場合
「第〇条 従業員の定年は満60歳とする。ただし、定年後も引き続き雇用されることを希望する者は、満65歳まで嘱託社員として再雇用する。」
③ 定年制を廃止する場合
「第〇条 定年制は設けない。ただし、雇用契約の内容に応じて個別に雇用期間を定めることがある。」
就業規則を変更した場合は、労働者代表の意見書を添付のうえ労働基準監督署に届け出る必要があります。また、全従業員に対して変更内容を丁寧に周知・説明することも必要です。
必要に応じて、継続雇用となる従業員の職務内容、労働時間、勤務地などの労働条件についても、見直しを行う必要があります。 これらの変更は、従業員の意向を尊重しつつ、企業の業務効率や生産性を維持できるような内容に仕上げる必要があります。
賃金制度の見直し
企業は高年齢者の賃金制度についても検討を行う必要があります。特に、高年齢雇用継続給付の給付率が引き下げられるため、従業員の収入減を考慮し、必要に応じて賃金水準を調整することが求められます。
継続雇用となる従業員の賃金は、同一労働同一賃金にのっとり、その技能、経験、職務内容などを適切に評価し、現役従業員との間で不合理な待遇差が生じさせないことが原則です。
年齢や勤続年数だけでなく、役割や成果に応じた賃金体系への見直しも有効な手段の一つです。また、高年齢者の場合は、賃金と年金のバランスも考慮に入れる必要があります。
従業員のモチベーションを維持するためには、能力や貢献に応じた昇給や賞与制度を設けることも重要です。賃金制度の見直しは、従業員の生活安定だけでなく、企業の競争力強化にも繋がります。
社会保険料の取り扱い
高年齢者を雇用する際には、社会保険料の取り扱いについても注意が必要です。再雇用により労働時間や賃金が変更になった場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険の適用や保険料が変動する可能性があります。
再雇用により賃金が大幅に減少した場合、「同日得喪」の手続きを行うことで、再雇用された月から新しい賃金に基づいた社会保険料を計算することができます。 これは、従業員の負担軽減に繋がります。
企業は、こうした制度の変更点を理解したうえで、個々の従業員の年齢・就業条件・契約内容に応じて、必要な手続きを適切に行うことが求められます。
継続雇用の意思確認
定年を迎える従業員に対して、定年前後の継続雇用の意思確認を行います。一般的には、定年の数ヶ月前を目安に、本人と面談を実施し、継続雇用を希望するかどうかの意思を確認します。
その際には、継続雇用の条件(職務内容・勤務時間・勤務地・賃金水準・雇用形態)を丁寧に説明します。
継続雇用を希望する従業員には、「継続雇用希望申出書」などの書面を提出してもらうことが望ましいとされています。 労働条件が変更になる場合は、新たな雇用契約書を作成し、従業員と合意することが必要です。 これらの手続きは、余裕をもって従業員の定年退職日までに行うようにしましょう。
高齢者のための人材配置と支援体制
高年齢者が能力を発揮し、健康で意欲的に働き続けるためには、人材配置と支援体制の見直しが欠かせません。特に定年後の継続雇用においては、従来と同じ働き方を一律に求めるのではなく、本人の状況に応じた柔軟な対応が求められます。
例えば、労働時間や勤務形態について、短時間勤務やフレックスタイム制などを導入することで、高年齢者の多様なニーズに対応できます。 また、新しい技術や業務に対応するための研修やOJTによる再教育の機会を提供することも重要です。特にITスキルの習得支援などは、実務に即した研修が有効です。
経験豊富な従業員が若手社員の指導役として関わる「メンター制度」などを導入すれば、技能継承や世代間の橋渡しとしても大きな効果が期待できます。
また、高年齢者が安心して働ける環境を整えるために、職場のバリアフリー化、空調や照明の整備、定期健康診断の実施とフォローアップなどが求められます。企業全体として、高年齢者の就労を前提とした職場づくりを推進することが、今後の人材確保と企業の持続的成長に直結します。
高年齢者の雇用に関する手続き
高年齢者を雇用する際には、雇用保険や健康保険の手続きについても理解しておく必要があります。
雇用保険の加入条件と高年齢求職者給付金
65歳以上であっても、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合には、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
また、65歳以上の雇用保険被保険者が離職し、再就職を希望する場合には、「高年齢求職者給付金」という一時金を受け取れる可能性があります。この給付金を受け取るためには、離職前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間があることなど、一定の要件を満たすことが必要です。
給付金の額は、雇用保険の加入期間によって異なります。
雇用保険の加入手続きや高年齢求職者給付金の申請は、原則として管轄のハローワークで行います。
高年齢者の健康保険の適用
高年齢者の医療保険制度は、年齢によって区分されています。65歳から74歳までの方は「前期高齢者医療制度」、75歳以上の方または65歳から74歳で一定の障害(例:寝たきりなど)のある方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。
75歳になると、原則として後期高齢者医療制度に自動的に移行し、勤務先の健康保険からは脱退する形となります。 再雇用された高年齢者も、労働時間などの要件を満たせば、引き続き雇用先の健康保険に加入することができます。
社会保険料の企業負担と従業員負担
社会保険料(健康保険、厚生年金保険、雇用保険など)は、企業と従業員がそれぞれ負担します。保険料の計算は、従業員の給与額をもとに行われるため、再雇用後に給与が変更となった場合には、保険料額も再計算されます。
企業には、65歳以上の従業員も含めて、社会保険の加入・脱退手続きや保険料の納付を適切に行う義務があります。なお、厚生年金保険に関しては、原則として70歳未満の従業員が加入対象です。70歳を超えた場合には、厚生年金の資格喪失届を提出します。
これらの手続きを怠ると、従業員の給付金受給に支障が生じたり、企業が追加徴収を受けたりする可能性もあるため、制度内容を十分に理解し、確実な運用を行うことが求められます。
高年齢者雇用に関連する助成金
高年齢者の雇用を促進するため、国や自治体は助成金制度を用意しています。これらの制度は、企業が制度整備や環境改善に取り組む際の費用負担を軽減し、継続的な雇用の実現を後押しする目的で運用されています。
65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金は、65歳以上の高年齢者の雇用を促進することを目的とした助成金です。この助成金には、以下の3つのコースがあります。
65歳超継続雇用促進コース
企業が65歳以上までの雇用を確保するための制度を導入・整備した場合に助成されます。具体的には、定年を65歳以上に引き上げたり、定年制そのものを廃止したりするほか、定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入などが対象です。企業がこれらの措置を制度として明文化し実施することで、支給の対象となります。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者が安心して働き続けられる職場環境の整備を目的とした支援です。対象となるのは、高年齢者専用の人事評価制度や、加齢に配慮した賃金体系、能力に応じたキャリア形成制度の導入などです。これらの制度は、年齢に関係なく適正に評価される仕組みを整えるものであり、雇用管理の質的改善が求められます。
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上で定年年齢に満たしていない有期契約労働者を、無期雇用へと転換した場合に助成が行われます。雇用の安定性を高めることで、より長期的な戦力として高年齢者を活用していくことを目的としています。対象者の年齢や契約条件、転換の実施時期などにより支給要件が異なるため、詳細な確認が必要です。
いずれのコースも、「計画書」の提出と認定を受け、その後に具体的な措置を実施したうえで、最終的に「支給申請」を行うという流れとなります。
申請窓口は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部です。支給額や要件はコースごとに異なるため、申請前に制度内容の確認を十分に行うことが重要です。
その他の高年齢者雇用支援策
高年齢者の雇用を支援する様々な助成金制度の一例があります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金は、60歳以上の高年齢者など、就職困難な方を雇用した場合に支給されます。対象となるのは、ハローワークなどの紹介により高年齢者(または他の就職困難者)を雇用した場合です。
支給対象者は、雇用時に雇用保険の一般被保険者として採用され、かつ継続して一定期間(通常6か月または1年)雇用されたことが条件となります。
参考:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省
エイジフレンドリー補助金
エイジフレンドリー補助金は、高年齢者が安全・快適に働ける職場環境を整備することを目的とした制度です。労働災害を予防し、高年齢者の就労を継続的に支援する内容に対して補助が行われます。
例えば、転倒防止のための床材変更、階段の手すり設置、腰痛防止の補助器具の導入など、安全性向上に資する設備の購入・改修費用が対象です。補助率は1/2以内、補助上限額は100万円(年度ごとに異なる場合あり)とされており、比較的小規模な事業所にも利用しやすい制度です。補助金申請受付期間を設けている制度のため、関連情報で最新情報を確認することをおすすめします。
これらの助成金を活用することで、企業は高年齢者の雇用促進にかかる費用負担を軽減することができます。
高年齢者雇用安定法は65歳までの雇用確保が義務
2025年4月施行の高年齢者雇用安定法改正により、経過措置が廃止され、65歳までの「雇用確保措置」(定年延長・継続雇用制度・定年廃止のいずれか)の実施が全企業に義務化されました。企業は定年制度の見直しや賃金制度の再構築に対応し、就業規則の整備や助成金の活用を通じて、高年齢者の安定的な雇用環境を整えることが求められます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
公務員の退職手続きの流れや注意点は?退職後に必要な手続きも解説
公務員の退職は民間企業と比べて手続きが複雑で、提出書類も多岐にわたります。退職金や年金、健康保険など、退職後の生活に関わる重要な手続きも必要となるため、計画的に準備を進めることが大…
詳しくみる事故発生状況報告書の書き方は?記載例・無料テンプレートつき
事故発生状況報告書は、交通事故の詳細を保険会社や関係機関に正確に伝えるための重要な文書です。適切な記載方法を知ることで、円滑な保険金請求や事故処理が可能になります。本記事では、事故…
詳しくみる仕事で一人に負担をかけるとパワハラ?適切に割り振るポイントも解説
仕事を一人に負担させることは、時にはパワハラにつながる可能性があります。過度な負担は心身の健康に悪影響を及ぼし、休めない状況になるため、注意が必要です。 本記事では、仕事の偏りがパ…
詳しくみる外国人労働者の国別ではどこが多い?多い国の特徴や理由について解説
日本で受け入れられている外国人労働者数は、年々増加傾向にあります。 多くの外国人労働者は、国別でみると大半がアジア圏内であり、今後もアジア圏内のからの外国人労働者が増えるでしょう。…
詳しくみる【テンプレート付】退職辞令とは?様式や書き方を解説!
退職辞令は、従業員に退職を命じる際に発する辞令です。法律は退職に際して退職辞令を出すことを規定していないため、出さなくても問題はありません。フォーマットも定められたものを使う必要は…
詳しくみる外国人労働者を派遣社員として雇用できる?メリットや注意点も解説
外国人労働者を派遣社員として雇用することは可能です。適切に派遣を活用すれば人手不足の解消やコスト削減につながりますが、法的リスクや契約内容の確認が重要です。 本記事では、外国人労働…
詳しくみる