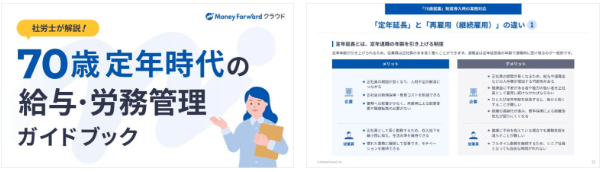- 更新日 : 2025年12月24日
再雇用で役職をそのまま継続することは可能?給与や業務内容の留意点を解説
定年後に再雇用する際、役職をそのまま維持すべきか迷う企業は少なくありません。経験や貢献をどう活かすかに加え、組織運営や処遇のバランスも考慮が必要です。この記事では、再雇用時の役職継続に関して、給与や業務内容、制度との関係など、企業が整理しておきたいポイントを解説します。
目次
再雇用で役職をそのまま継続できるのか?
再雇用後に役職をそのまま継続することは、法的には可能です。労働基準法や高年齢者雇用安定法に反するものではなく、企業と本人が合意していれば役職を維持することに制限はありません。
ただし、実際には多くの企業で、定年を機に役職を外す運用が行われています。これは、管理職手当の見直しや人件費の調整、組織の若返り、後任育成の促進などを目的としたものです。
役職を維持する場合には、再雇用後の業務内容や責任範囲、指揮命令系統、給与水準などについて明確にし、企業と社員の間で納得のいく合意を交わすことが重要です。また、管理職の継続が組織にとって合理的であるかを含め、総合的に検討する必要があります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
再雇用の役職をそのまま継続するか検討する考え方
再雇用で役職をそのまま継続するかどうかは、本人のスキルや能力だけでなく、組織の構造や人材バランスも踏まえて総合的に判断することが求められます。
組織全体の役割を基準に考える
再雇用後も同じ役職を続ける場合、そのポジションが引き続き組織内で必要か、業務の中で実際に機能するかを見極める必要があります。「以前管理職だったから」という理由だけで役職を任すと、組織の中での立場が曖昧になり、周囲との調整が難しくなることがあります。
特に後任との関係性やチーム内のバランスを考えることも重要な視点です。
若手登用とのバランスをとる
再雇用社員が役職を継続した場合、若手社員の昇格機会が後ろ倒しになるケースがあります。再雇用社員も持つ知見は大切ですが、それが若手の意欲や成長の妨げになっていないかは慎重に確認する必要があります。
また、権限の一部移譲や、若手に新たな役割を与えるなど、バランスを取る工夫が必要です。
健康状態や働き方にも配慮する
年齢を重ねることで、健康や体力、働き方に変化が出るのは自然なことです。役職に伴う業務負担や勤務時間に対して、本人の現在の状況と合っているかどうかも判断材料になります。
フルタイム勤務や高いプレッシャーが難しい場合は、肩書きや責任範囲の見直しも含めて柔軟に検討しましょう。
評価と実績に基づく判断を行う
役職の継続は、過去の肩書きではなく、現在の業務能力と実績に基づいて判断することが前提です。再雇用後の人事評価や業務レビューを実施せずに役職を維持すると、不公平感や評価制度の形骸化を招く恐れがあります。
定期的な評価を行い、基準に照らして妥当かどうかを確認する仕組みを整えることが重要です。
組織体制との整合性を保つ
役職を継続する再雇用者が、同じ職位に複数の社員が並ぶことになったり、責任範囲が重複したりする可能性もあります。これにより、指揮命令系統が曖昧になり、業務上の混乱を招くこともあります。
再雇用後の役割や責任、チームとの関係性をあらかじめ整理し、組織内で混乱が起きないよう調整することが求められます。
再雇用の役職を継続した場合の給与設定
再雇用社員が役職を継続する場合、給与の決め方は企業にとって特にデリケートなテーマです。処遇の納得感が得られないと、社員のモチベーション低下や法的リスクにつながる可能性もあります。
給与水準の決め方は業務内容と責任の程度で判断
再雇用後の給与は、原則として就業規則や賃金規程に従って設定します。多くの企業では、定年前より給与を引き下げる運用を取っていますが、その根拠を明確にすることが必要です。
たとえば、定年前と同じ「部長」という肩書きであっても、再雇用後の業務が限定的であれば、役職手当や基本給を調整するのが一般的です。目安として、定年前の給与の6〜7割程度を基準とする企業もあるようですが、社内制度や業務実態に応じて設定されます。
重要なのは、責任の範囲・勤務時間・成果への期待などを具体的に反映した金額であるかどうかと、そしてその理由を本人に丁寧に説明することです。
合理性のない大幅な減額は違法とされることも
給与設定にあたっては、「パートタイム・有期雇用労働法第8条等に基づく「同一労働同一賃金」の考え方を無視することはできません。再雇用後も業務内容や責任が定年前と変わらないのに、詳しい説明もなく給与を下げて設定することは、不合理と判断される可能性があります。
ただし、再雇用にあたって業務の一部を軽減し、管理職としての裁量や責任を縮小するケースでは、その分の給与調整は認められます。たとえば、全社的な経営判断から外れ、特定のプロジェクトの実務に専念する形で役職を維持する場合などが該当します。
給与設定は、社内制度・評価の一貫性・法令順守の3点を押さえることが重要です。再雇用後も役職を継続する場合は、「業務内容に応じた処遇」を原則とし、本人にわかりやすく説明できる形で設計することが、信頼と納得を得るためのポイントとなります。
再雇用の役職を継続した場合の責任や業務内容
再雇用後に役職を継続する場合、責任や業務内容をあいまいにしたままでは、現場の混乱や本人との認識のずれが起きやすくなります。再雇用契約を結ぶ時点で、役職者として何を期待するのかを明らかにしておくことが必要です。
期待する役割は明確に設定する
役職を継続するからといって、定年前と同じ責任や業務をそのまま求めるわけではありません。再雇用後は、役割を絞った形で業務にあたってもらうのが一般的です。
例えば、定年前は部長として部門全体を統括していた社員に対し、再雇用後は技術指導や若手育成、プロジェクトアドバイザーとしての立場を任せるといった形が見られます。現場の第一線に立たせるのではなく、支援・助言的な役割に移行するケースも増えています。
このように、どの範囲に責任を持ち、どこまでの意思決定を任せるのかを明文化しておくことで、組織内の混乱を避けられます。
業務量と勤務条件は柔軟に調整する
再雇用社員は年齢を重ねているため、健康状態や働くスタイルに応じた業務設計が求められます。役職を維持している場合でも、定年前と同じ業務量をこなすことが難しいケースは少なくありません。
週3〜4日の勤務や時短勤務、担当業務の範囲を限定するなど、業務量を調整することが現実的です。体力的な負担を軽減しつつ、経験を活かせる業務に集中できる環境を整えることが、継続的な雇用とパフォーマンス維持につながります。
役職定年制度との関係
役職定年制度は、多くの企業で55歳や60歳を区切りに、管理職から一度役職を外れる仕組みとして導入されています。目的は、若手にチャンスを与えたり、組織を一新することにあります。
この制度がある企業で再雇用後に役職をそのまま続ける場合、制度とのバランスをどう取るかがポイントです。例えば、役職定年で部長を退いた方が、再雇用でまた部長に戻ると、制度の趣旨と食い違う印象を与えてしまうかもしれません。
その場合は、役職名を変えたり、責任範囲を調整したりすることで、スムーズな運用ができます。「技術アドバイザー」や「専門職」としての活用も、経験を無理なく活かせる方法です。制度に沿いつつ、再雇用者の力を活かす工夫が大切です。
再雇用時の役職継続に関する留意点
再雇用後も役職を継続することは、本人の経験やスキルを活かすという点で企業にとって有益ですが、一方で運用を誤ると組織内に不公平感や混乱を生む可能性もあります。制度面・契約面・コミュニケーション面の3点から、事前の備えが欠かせません。
コミュニケーションは早めに、具体的に
再雇用の面談時には、役職の継続だけでなく、給与、業務内容、勤務日数、責任範囲などについて、できる限り具体的にすり合わせておくことが大切です。
特に給与が下がる場合や、職務範囲が変更になる場合は、社員が納得できるよう丁寧な説明が必要です。「以前と同じ役職だから同じ内容」と思い込まず、変更点をきちんと伝えることで、誤解やトラブルを防げます。
合意内容は雇用契約書で明示する
再雇用時の条件は、必ず書面で合意し、雇用契約書に記載しましょう。以下のような項目を盛り込むことが望まれます。
- 役職名とその定義(例:実務上の指揮命令権の有無)
- 担当業務の範囲と内容
- 勤務形態(週の勤務日数、勤務時間)
- 給与・役職手当の額と内訳
- 契約期間と更新の条件
就業規則にも、「再雇用後の役職者の取り扱い」に関する方針があれば、より整合性のある運用が可能です。制度化が難しい場合でも、個別契約に基づいた明確な記載があれば、労使トラブルのリスクを大きく減らせます。
社内への説明と理解促進も必要
再雇用社員が役職を継続する場合、他の社員、とくに若手にとっては「なぜあの人だけ?」という疑問が生まれることもあります。
そのため、再雇用された社員の知識や経験が組織にどのように活かされるのかを明文化し、チームへの説明や共有の機会を設けることが望まれます。協力体制をつくるには、納得感のある説明が重要です。
制度は定期的に見直す
役職継続の取り扱いを含め、再雇用制度や役職定年制度は、数年おきに見直すことが必要です。年齢層の構成や法改正、社員の働き方の変化に応じて、現場に合った柔軟な制度へとアップデートしていく視点が求められます。
たとえば、「役職継続は原則認めないが、専門職としての登用は可能」といったルールを設けておくことで、制度と実務のバランスを取りやすくなります。
再雇用時に役職を継続しない場合の対応
定年後の再雇用で役職を外す判断は、組織の若返りや人件費の見直しを進める上で有効です。ただし、本人の納得と社内の理解を得るためには、雇用形態、伝え方、給与の設定を丁寧に整えることが大切です。
雇用形態は一般職や専門職への転換が多い
役職を継続しない場合、雇用形態は嘱託社員や契約社員として、一般職や専門職に切り替えるケースが多く見られます。「シニアスタッフ」「シニアアドバイザー」など、新しい職位名を用いることで、業務への期待は示しつつも、組織上の位置づけを再定義できます。
管理職から外れることで、指揮命令権はなくなりますが、豊富な経験を生かして現場の支援や技術指導に専念してもらうなど、役割を明確にすることが大切です。
事前の面談では丁寧に伝える
再雇用の打診や契約前の面談では、「なぜ役職を外れるのか」について丁寧に説明する必要があります。理由は抽象的にせず、役職定年制度の運用、組織再編、若手登用の推進、など、納得しやすい背景を示すことが望まれます。
また、「役職を離れても経験を必要としている」というメッセージをきちんと伝えることで、本人の承認欲求や貢献意欲を尊重することができます。
書面では、雇用契約書に「役職なし」「非管理職」と明記し、担当業務と職務範囲を具体的に示すことで、誤解や混乱を防ぎます。
給与は業務内容に応じて合理的に設定する
役職を外れる場合、給与も定年前に比べて減額されるのが一般的ですが、業務内容や責任範囲と整合性が取れていれば問題ありません。例えば、マネジメント業務を外れ、専門業務やアドバイザー業務に特化する場合、役職手当は削除しつつ、経験値に見合う基本給を設定する方法もあります。
減額の際は、本人に具体的な基準や計算根拠を伝えることが重要です。突然の大幅減額や理由が明らかでない設定は、不信感やトラブルの原因になります。
再雇用で役職をそのまま継続するかは慎重に検討を
再雇用で役職をそのまま継続するかどうかは、組織の方向性や働き方の実態に合わせて柔軟に考えることが大切です。継続する場合は、業務内容や責任を明確にし、納得のいく給与設定が求められます。継続しない場合でも、丁寧な説明と適切な役割の設計によって、再雇用を前向きな選択肢として位置づけられます。契約書や就業規則の整備、制度の見直しも含め、本人と組織双方が安心して合意できる体制づくりが求められます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
外国人労働者の労働時間に制限はある?雇用する際に確認すべきことを解説
外国人労働者の労働時間には、日本人と同様に「1日8時間・週40時間」の上限があり、留学生は「週28時間以内」の制限が設けられています。 違反すると事業主には不法就労助長罪が適用され…
詳しくみるリクルーターとは?役割やメリット・デメリット、制度の導入方法など解説
近年、少子高齢化に伴う労働力不足により、企業間の採用競争は激化しています。従来のような「求人票を出して応募を待つ」手法だけでは、優秀な人材の確保が困難な「超・売り手市場」となってい…
詳しくみるサーバントリーダーとはどのような存在か?支配型との違いや組織への導入メリットを徹底解説
Pointサーバントリーダーとは? サーバントリーダーは、部下の成長支援を通じて組織成果を最大化します。 奉仕と信頼が影響力の源/li> 自律性と心理的安全性向上 VUCA時代に適…
詳しくみる労働条件通知書と雇用契約書の違いとは?記載事項や兼用についても解説
労働条件通知書は労働条件を明示するための書類、雇用契約書は契約を結ぶための書類であり、両者には明確な違いがあります。 ただ「どのようなところが違うのか具体的に知りたい」「記載する内…
詳しくみるフィードバック面談の効果的な方法は?シートの活用から逆質問への対応まで徹底解説
フィードバック面談は、従業員の成長を支え、組織全体のパフォーマンス向上につなげるために欠かせない取り組みです。しかし、その方法を誤ると、かえって従業員のモチベーションを低下させるこ…
詳しくみる【テンプレ付】上申書とは?嘆願書との違いや書き方について解説
警察など官公庁の手続きで、上申書の提出が必要になることがあります。一般的にはあまり認知されていないため、いざ提出するとなると困惑することもあるでしょう。 今回は上申書の基礎知識や嘆…
詳しくみる