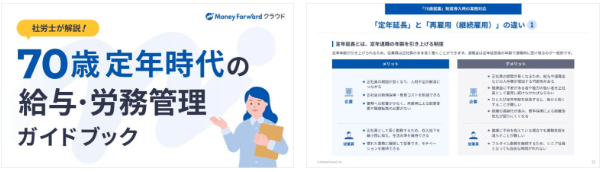- 更新日 : 2025年12月24日
継続雇用制度と再雇用との違いとは?選ぶメリット・デメリットを解説
継続雇用制度は、定年を迎えた従業員が希望すれば65歳まで働き続けられるようにする制度です。「高年齢者雇用安定法」に基づき、企業に導入が義務付けられています。少子高齢化が進む中、意欲と能力のある人材を活かすことは、企業にとっても重要な課題です。この制度には「再雇用」と「勤務延長」の2つの方法があり、雇用形態や待遇はそれぞれ異なります。この記事では、継続雇用制度の目的や仕組み、再雇用との違い、導入時のポイントをわかりやすく解説します。
目次
継続雇用制度と再雇用との違い
継続雇用制度は法律で定められた枠組みの総称であり、その中に再雇用制度が含まれます。
継続雇用制度に再雇用が含まれる
継続雇用制度とは、60歳などの定年を迎えた従業員が、希望すれば65歳まで働き続けられるようにするための制度です。高年齢者雇用安定法第9条により、定年を65歳未満に定めている企業は、65歳までの雇用確保措置を実施する義務があります。
この制度は、高齢者の雇用機会を守ることを目的とし、企業には以下のいずれかの方法で「65歳までの雇用確保措置」を講じる義務が求められます。
- 定年を廃止する
年齢に関係なく定年を設けない制度です。本人の能力や意欲に応じて、年齢制限なく勤務が可能になります。 - 定年年齢を65歳以上に引き上げる
例えば定年を60歳から65歳に延長するなど、定年年齢そのものを見直す方法です。契約形態や処遇は原則として正社員のまま継続されます。 - 継続雇用制度を導入する(再雇用と勤務延長が含まれる)
60歳で定年退職とし、その後、再雇用契約または勤務延長契約等により引き続き雇用する方法です。
このいずれかを導入していない企業は、法律違反となる可能性があります。
再雇用は7割近く採用されている
一般的には、多くの企業が再雇用制度を採用する傾向にあります。
令和6年(2024年)6月1日時点の厚生労働省の調査によれば、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの中小企業では99.9%で大企業では100.0%であり、その内訳は以下のとおりです。
- 継続雇用制度の導入:67.4%
- 定年の引き上げ:28.7%
- 定年の廃止:3.9%
このデータから、継続雇用制度(再雇用制度)を導入している企業は67.4%であることがわかります。
参考:令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します|厚生労働省
なお、2021年4月からは70歳までの就業機会確保も企業の努力義務となりました。
これは定年後のさらなる雇用延長や、フリーランス契約・業務委託などを含む柔軟な働き方も対象にしています。
70歳までの高年齢者就業確保措置をすでに実施している企業は、全体の31.9%にとどまっており、今後の広がりが期待されています。
再雇用は契約期間や勤務条件を柔軟に設定しやすいため、企業側にとっても調整しやすい仕組みです。一方、勤務延長は雇用関係を維持したまま働き続けることができるため、業務の連続性や組織の安定を図りやすい点が特徴といえます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
継続雇用における再雇用と勤務延長との違い
継続雇用制度には「再雇用」と「勤務延長」があり、主な違いを項目ごとに解説します。
給与の違い
再雇用では、定年前に比べて給与水準が下がることが一般的です。新たに締結する契約に基づいて報酬が決まるため、定年前の50〜70%程度に設定されるケースが見られます。職務内容や責任の範囲が変わることもあり、それに応じて給与も調整されます。
勤務延長では、定年前と同じ給与水準を維持する企業が多く、生活水準が大きく変わることは少ない傾向です。給与体系が継続されることで、従業員は安定した収入を見込むことができます。
雇用形態の違い
再雇用は、一度定年退職として扱われた後に再び雇用契約を結ぶ制度です。そのため、正社員から契約社員、嘱託社員、またはパートなどに変更されるのが一般的です。
勤務延長は退職を伴わずに雇用契約が続くため、定年前と同じ正社員としての雇用形態が維持されます。役職や権限も継続しやすいのが特徴です。
労働条件の違い
再雇用では、新たな契約に基づき労働条件が設定されます。勤務日数や労働時間の短縮、残業の制限、福利厚生の縮小など、正社員時代と異なる条件が提示されることがあります。契約時に内容を明確にし、納得の上で締結することが必要です。
勤務延長の場合は、原則として定年前の労働条件が継続されます。業務内容に応じた調整があることもありますが、労働時間、休日、福利厚生などの変更は最小限にとどまる傾向です。
役職の違い
再雇用では、多くの場合、定年前に携わっていた役職を退き、新しいポジションで再スタートします。管理職から一般職や専門職に変わることもあり、組織内での位置づけが変化します。
勤務延長では、定年前と同じ役職で業務を続けることが可能なケースが多いため、役割や責任が変わらないまま働き続けられる場合もあります。
手続きの違い
再雇用は、新たな雇用契約を結び直すことが必要です。契約書の作成、労働条件通知、社会保険の加入・変更など、通常の採用に近い手続きが求められます。
勤務延長では、既存の雇用契約の期間を延長する形になるため、特別な手続きは不要です。就業規則に基づいて自動的に適用されるケースもあります。
継続雇用における再雇用と勤務延長の比較表
| 項目 | 再雇用 | 勤務延長 |
|---|---|---|
| 給与 | 定年前より低くなる(50~70%など) | 定年前と同水準で維持されることが多い |
| 雇用形態 | 嘱託社員、契約社員、パート等が一般的 | 正社員のまま継続 |
| 労働条件 | 新たな契約に基づいて設定(短時間勤務など) | 原則、定年前と同じ |
| 役職 | 一般職や専門職など別の役割で雇用される | 維持されることが多い |
| 勤続年数 | 一度リセットされ、再契約時から再カウントされる | 加算が継続される |
| 手続き | 新たな雇用契約締結、社会保険などの手続きが必要 | 雇用延長に伴う簡易な社内手続きが中心 |
継続雇用制度で再雇用を選ぶメリット
再雇用は、継続雇用制度のなかで多くの企業が採用している方法です。具体的には、以下のようなメリットがあります。
1. 柔軟な働き方を選べる
再雇用では、勤務時間や勤務日数を短縮できる契約が一般的です。本人の希望に応じて「週3日勤務」「時短勤務」などの設定が可能で、家庭や健康と両立した働き方を実現できます。
2. 年金受給までの収入を確保できる
年金の支給開始年齢に達するまでの間、再雇用で働くことで収入を補うことができます。特に、65歳未満で退職する場合には、大きな生活支援となります。
3. 契約内容を再調整できる
企業にとっても、業務内容や報酬を柔軟に設定できる再雇用は、コストと人材配置のバランスを取りやすい制度です。1年ごとの契約更新が多く、状況に応じて継続や終了の判断ができます。
4. 定年後も経験を活かして働ける
ベテラン人材として再雇用されることで、長年の経験や知識を後輩育成や技術継承に活かすことが可能です。企業側も即戦力として期待でき、教育コストが抑えられます。
継続雇用制度で再雇用を選ぶデメリットや課題
一方で、再雇用には課題もあり、従業員と企業の双方に配慮が求められます。
1. 給与が大きく下がるケースがある
再雇用契約では、定年前に比べて給与が50%〜70%程度の水準になるといわれています。職責や勤務時間が変わるためとはいえ、本人にとっては生活レベルの見直しを迫られることがあります。
2. 雇用形態が変更される
再雇用では正社員から契約社員・嘱託社員に変わるため、雇用の安定性や福利厚生の面で差が生じます。労働条件の変更については、契約前にしっかり説明する必要があります。
3. 勤続年数がリセットされる
一度退職の形を取るため、勤続年数がリセットされることが一般的です。再雇用後は新たなスタートとなるため、退職金の加算や社内表彰制度に影響する可能性があります。
4. 役職が外れるケースが多い
再雇用では、定年前の役職を離れ、現場の実務を担う立場に変更されるケースが多くあります。これにより、本人のモチベーションが下がることや、業務の再調整が必要になることもあります。
5. 「再雇用されない」というリスク
再雇用には選定基準が設けられていることがあり、勤務態度・健康状態・出勤状況などにより、希望しても再雇用されない場合があります。基準の明確化と説明が求められます。
継続雇用制度を導入する際のポイント
継続雇用制度を導入する際には、社内制度の整備だけでなく、従業員の理解を得てもらう仕組みづくりが求められます。トラブルを避け、円滑に運用するための視点を押さえておきましょう。
対象者の基準は明文化しておく
再雇用や勤務延長の対象者を選定する際には、就業規則や社内規定でその基準を明記することが必要です。勤務成績、健康状態、出勤状況など、客観的な評価項目を設けておくことで、再雇用の可否に関するトラブルを未然に防げます。
労働条件の変更内容は事前に明示する
再雇用契約では、定年前とは労働条件が変わることが一般的です。給与水準、勤務時間、休日、役職の有無、福利厚生など、変更内容は書面で明確に示し、本人が十分に理解・納得したうえで契約することが求められます。
契約期間と更新の有無を明確にする
多くの再雇用契約は1年ごとの有期契約ですが、期間や更新の可能性を明示しましょう。また、勤務延長の場合も、延長可能な年齢上限(例:65歳、70歳など)を定めておくとトラブルを避けやすくなります。
制度導入前に従業員説明会や通知を行う
制度の導入や変更時には、対象となる従業員や全社向けに説明会や通知文書を通じて周知を行うことが重要です。「知らなかった」「説明を受けていない」といった誤解を防ぐため、口頭だけでなく文書化して説明履歴を残すようにしましょう。
高年齢者雇用確保措置としての整合性を保つ
継続雇用制度は「高年齢者雇用確保措置」の一環として、65歳までの雇用を企業に義務づける制度です。形式だけの導入ではなく、実際に働き続けやすい制度設計になっているか、社内体制との整合性を確認する必要があります。
制度の見直しは定期的に行う
法改正や社会環境の変化、高齢者の就労ニーズの変化に対応するためにも、継続雇用制度の見直しは定期的に行います。導入後も制度が形骸化しないよう、実際の運用状況を定期的に点検し、必要に応じて内容の更新を検討します。
Q&A:継続雇用制度に関するよくある疑問
Q1:継続雇用制度で、再雇用されないことはありますか?
継続雇用制度は、原則として希望者全員が対象ですが、企業が定める客観的で合理的な基準に該当しない場合は、再雇用されないこともあります。例えば、過去の勤務態度に問題があった場合や、健康上の理由で業務遂行が困難と判断された場合などがこれに該当します。ただし、基準は明確に就業規則に定める必要があり、恣意的な判断は許されません。
Q2:継続雇用制度で、再雇用されないことはありますか?
はい、あります。継続雇用は原則として希望者全員が対象ですが、勤務態度や健康状態などが企業の定める基準に満たない場合は、再雇用されないことがあります。ただし、その基準は就業規則などに明確に示されていなければなりません。
Q3:1年ごとの契約更新は、何歳まで可能ですか?
法律では65歳までの継続雇用が義務付けられており、70歳までの雇用は努力義務とされています。多くの企業では1年ごとの更新で65歳または70歳まで継続していますが、企業ごとに上限を設けている場合もあるため、就業規則の確認が必要です。
Q4:退職金や年金は、再雇用と勤務延長で違いますか?
はい、異なります。再雇用は定年で一度退職扱いとなるため、その時点で退職金が支給されます。勤務延長では退職扱いにならず、退職金は実際に退職した時に支給されます。年金も、在職中の給与により一部または全額が支給停止となる場合があります。
継続雇用制度は企業と従業員のこれからを支える仕組み
継続雇用制度には、再雇用と勤務延長という2つの方式があり、給与や雇用形態、役職、手続きに違いがあります。再雇用は柔軟な働き方に向いており、勤務延長は雇用の安定性を保ちやすいという特徴があります。
制度を効果的に活用するためには、就業規則の明確化、従業員への丁寧な説明、そして制度内容の定期的な見直しが必要です。企業の運用方針と従業員の希望をすり合わせながら、納得感のある形で導入することで、双方にとって働きやすい環境を築くことができます。
関連:【テンプレート付き】再雇用契約書とは?作り方や手続きの業務を解説!
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
「休職するなら退職しろ・休職したら終わり」はパワハラ?ルールを解説
従業員が何らかの理由で休職を申請する際に、上司から「休職するなら退職しろ」や「休職したら終わり」と言われた場合は、パワハラになる可能性があります。 本記事では、休職を申請した際の上…
詳しくみる仕事が遅いと言われるのはパワハラ?パワハラに該当するケースや対応方法を解説
部下や後輩がいると「仕事が遅い」と言ってしまうという方もいるかもしれません。これの言動は実は要注意であって、パワハラに該当する恐れがあります。 本記事では「仕事が遅い」と言うのがパ…
詳しくみる離職状況証明書とは?正式な名称と取得方法をわかりやすく解説
退職後の手続きで「離職状況証明書」を求められて、どうすればよいかお困りではありませんか? 実は、公的な書類として「離職状況証明書」という名称のものは存在しません。 この言葉は、ご自…
詳しくみるテレワークでの健康管理の方法は?厚生労働省の指針やルール作りの事例、法改正まで解説
テレワークは、通勤時間の削減や柔軟な働き方を実現するというメリットがある一方で、従業員の心身に不調をきたすという新たな健康問題も浮上しています。企業には、従業員が働く場所を問わず、…
詳しくみるブルーカラーとは?ホワイトカラーとの違いや仕事内容
ブルーカラーは、工場や建設現場などで働く労働者を指します。かつて、業場で働く従業員が青い襟のついた作業着を着用していたことから、肉体労働者をブルーカラーと呼ぶようになりました。決し…
詳しくみる労働者派遣法とは?改正の歴史や禁止事項、違反した場合の罰則などを解説!
労働者派遣法とは、派遣労働者を保護することなどを目的に定められた法律。 1986年の制定依頼、規制の緩和や強化など、当時の社会的背景に応じて改正が行われてきた。 守るべきルールも多…
詳しくみる