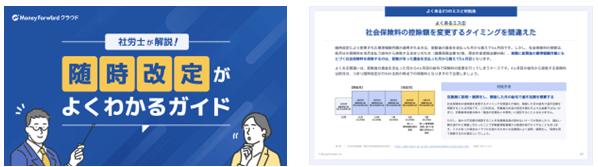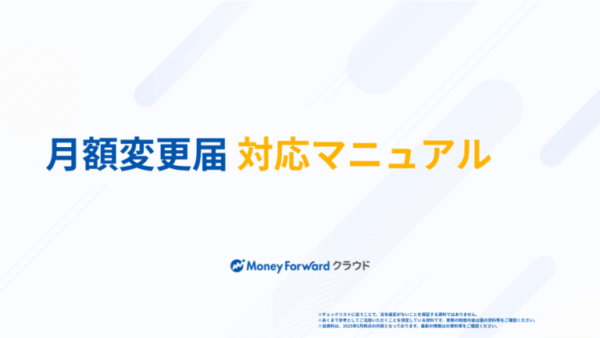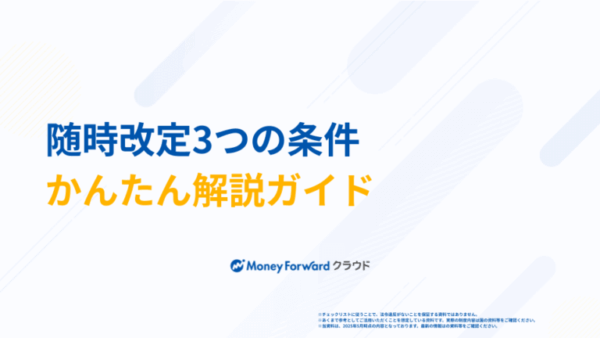- 更新日 : 2025年12月8日
社会保険の定時決定・随時改定とは?概要や適用条件、重なる場合の対応を解説
定時決定と随時改定は、従業員の給与にもとづいて標準報酬月額を見直すための制度です。しかし、制度の違いや適用条件を正しく理解していないと、手続きの遅れや誤りにつながり、従業員の保険料負担や企業の信用に影響を与えます。
本記事では、両者の違いや適用条件、手続きが重なった場合にどちらを優先すべきかについて、解説します。
目次
標準報酬月額に関係する定時決定と随時改定の違いは?
社会保険料は、従業員の給与に応じて変動します。その基準となるのが、標準報酬月額です。
標準報酬月額を決定・変更するために行われるのが定時決定と随時改定です。ここでは、標準報酬月額の概要や、定時決定と随時改定の違いについて解説します。
以下の記事では、社会保険料の変更に伴う手続きについて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。
社会保険料の算出に関係する標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を算出するための基準となる報酬額のことです。原則として、毎年4月〜6月に支払われた給与の平均額をもとに、等級表に当てはめて決定されます。
健康保険は1等級58,000円~50等級1,390,000円、厚生年金保険は1等級88,000円~32等級650,000円までの範囲で区分されています。給与が高くなるほど高い等級に分類され、それに応じて保険料も高くなる仕組みです。
標準報酬月額は、従業員本人と企業の双方が負担する保険料の金額に直結するため、適正な設定が大切です。
以下の記事では、標準報酬月額について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
標準報酬月額の対象範囲
標準報酬月額の報酬になるもの・報酬にならないものは、下記のとおりです。
| 項目 | 金銭(通貨)で支給されるもの | 現物で支給されるもの |
|---|---|---|
| 報酬になるもの | ・基本給(月給・週給・日給等) ・能率給 ・奨励給 ・役付手当 ・職階手当 ・特別勤務手当 ・勤務地手当 ・物価手当 ・日直手当 ・宿直手当 ・家族手当 ・扶養手当 ・休職手当 ・通勤手当 ・住宅手当 ・別居手当 ・早出残業手当 ・継続支給する見舞金 ・年4回以上の賞与 | ・通勤定期券 ・回数券 ・食事 ・食券 ・社宅 ・寮 ・被服(勤務服でないもの) ・自社製品 |
| 報酬にならないもの | ・大入袋 ・見舞金 ・解雇予告手当 ・退職手当 ・出張旅費 ・交際費 ・慶弔費 ・傷病手当金、 ・労災保険の休業補償給付 ・年3回以下の賞与 | ・制服 ・作業着(業務に要するもの) ・見舞品 ・食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める額により算定した額の2/3以上の場合) |
出典:日本年金機構の算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)
これらの区分は、標準報酬月額の算定に大きく関わるため、報酬に該当するか正しく判断することがポイントです。
現物支給される通勤定期券や社宅などは、一定の基準を満たす場合に報酬とみなされます。そのため、金額の把握や社内ルールの整備が必要です。
また、年4回以上支給される賞与は報酬に含まれる一方で、年3回以下であれば標準賞与額として扱われます。報酬・非報酬の判断を誤ると、標準報酬月額が不適切に決定され、保険料にも影響が出るため注意しましょう。
標準報酬月額の決定方法
標準報酬月額は、対象者の4・5・6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額をもとに、標準報酬月額表の等級に当てはめて決定されます。この期間、各月の支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)であることが条件です。
また、パートやアルバイトなどの短時間就労者であっても、週の労働時間および労働日数が常勤社員のおおむね4分の3以上であれば、通常の被保険者と同様に定時決定の対象となります。
短時間就労者の標準報酬月額の決定方法は、下記のとおりです。
【短時間就労者の場合】
| 支払基礎日数(4~6月) | 決定方法 |
|---|---|
| 17日以上の月が1ヶ月以上 | 該当する月の報酬平均額で決定 |
| すべて17日未満だが15日以上の月がある場合 | 15日以上の月の報酬平均額で決定 |
| 3ヶ月間すべて15日未満 | 従前の標準報酬月額を継続 |
【特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合】
| 支払基礎日数(4~6月) | 決定方法 |
|---|---|
| 11日以上の月が1~2ヶ月 | 11日以上の月の報酬平均額で決定 |
| 3ヶ月間すべて11日未満 | 従前の標準報酬月額を継続 |
特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は、下記3つの条件すべてを満たす方が対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生でないこと
なお、特定適用事業所とは、短時間労働者を含まない厚生年金保険の被保険者が1年間のうち6月間以上で50人を超えることが見込まれる事業所をいいます。
標準報酬月額は勤務状況や雇用形態に応じて異なる算定方法が設けられています。支払基礎日数の把握と正確な報酬集計が、適切な社会保険料の算出につながるでしょう。
定時決定とは、年に1回標準報酬月額を見直すために行う手続きのこと
定時決定とは、毎年1回、社会保険料の基準となる標準報酬月額を見直す手続きのことです。9月から翌年8月まで使用される標準報酬月額を決定するために、事業主は被保険者報酬月額算定基礎届(算定基礎届)を提出する必要があります。
対象となるのは、4・5・6月の3ヶ月間に報酬の支払いがある従業員で、その報酬の平均額をもとに標準報酬月額が決定されます。厚生労働大臣が届出内容を確認し、毎年1回標準報酬月額を決定する仕組みです。
定時決定は社会保険料の算出に直結するため、ミスなく正確に行うことが求められます。
以下の記事では、定時決定について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
随時改定とは、標準報酬月額を変更するための手続きのこと
随時改定とは、従業員の給与が大きく変動した際に、定時決定を待たずに標準報酬月額を変更するための手続きのことを指します。毎年行われる定時決定を待たずに、給与の大幅な変動があった際に標準報酬月額を変更するのが特徴です。
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料を計算するための基準となる金額のことです。給与は一定の範囲ごとに「等級」に分類され、その等級に応じた標準報酬月額が決定されます。
しかし、昇給・降給・手当の増減などで給与が2等級以上変動した場合、随時改定の対象となります。3ヶ月間の平均報酬を再計算し、月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)の提出が必要です。
適正な保険料負担を実現するためにも、随時改定の条件と手続き方法を把握しておきましょう。
参考:
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
随時改定がよくわかるガイド
月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。
この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。
月額変更届 対応マニュアル
従業員の報酬が変動した際、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。
本資料は、「月額変更届」に関する対応マニュアルです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きの実務にお役立てください。
随時改定3つの条件 かんたん解説ガイド
社会保険料の標準報酬月額を見直す「随時改定」は、実務上、正確な理解が求められます。
本資料は、「随時改定」の対象となる「3つの条件」について、かんたんに解説したガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きにおける実務の参考としてご活用ください。
定時決定と随時改定の適用条件・適用時期
定時決定と随時改定は、それぞれ異なるタイミングや条件で標準報酬月額に影響を与える制度です。ここでは、それぞれの制度の適用時期や対象者、除外されるケースについて詳しく解説します。
定時決定が適用される時期
定時決定は、毎年7月1日現在で在籍しているすべての被保険者および70歳以上被用者が対象です。正社員だけでなく、一定の労働条件を満たすアルバイトやパートも含まれます。育児休業・介護休業中や、病気・けがにより休職している場合でも、被保険者であれば原則として算定基礎届を提出する必要があります。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、提出は不要です。
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
これらを事前に確認しておくことで、提出対象者の特定ミスを防げます。
随時改定が適用される条件
随時改定は、従業員の給与に大きな変動があった際に行われる標準報酬月額の見直し手続きです。下記3つの条件をすべて満たす場合に、月額変更届を提出して随時改定を行う必要があります。
- 昇給または降給などにより、固定的賃金に変動があったこと
- 固定的賃金の変動月から3ヶ月間に支給された報酬の平均額にもとづき、標準報酬月額を算定した場合に2等級以上の変動があったこと
- 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であること
これらの条件をすべて満たすことで、随時改定の対象となります。
以下の記事では、随時改定の条件について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
随時改定の対象にならないケース
随時改定には適用されないケースもあります。
1つ目は、休職中に固定的賃金の変更があった場合です。給与体系が変わっても、実際に勤務していない期間中の変動は、通常勤務にもとづくものではないため対象外となります。
ただし、休職中でも減額なしで給与が支給されていれば、対象となる場合もあるので注意しましょう。
2つ目は、賃金変動の要因が非固定的賃金による場合です。たとえば、固定給は上がったものの、残業手当の減少によって結果的に報酬平均が下がった場合は、随時改定の対象外となります。
また、賞与の支給や単発的な手当の増減などの一時的な報酬変動も、随時改定の対象にはなりません。固定的賃金の継続的な変動であるかが、判断ポイントです。
誤って不要な届出をしないように、賃金項目ごとの性質を正しく理解しておきましょう。
随時改定はいつ社会保険料に反映される?
随時改定が適用されると、変動後の固定的賃金が支払われた月から起算して、4ヶ月目に標準報酬月額が変更される仕組みです。
実際の社会保険料は、反映月の翌月に納付されるため、給与から天引きされるタイミングは企業の給与体系によって異なります。
給与が翌月払いの企業では、変動後の賃金が支払われた月を含め5ヶ月目に、改定後の保険料が給与から差し引かれます。一方、当月払いの場合は、4ヶ月目に反映されるのが一般的です。
当月払いと翌月払いで、反映されるタイミングが異なるため、自社の給与締め・支払い日を把握しておく必要があります。
定時決定と随時改定が重なる場合は、どちらが優先される?
定時決定は、毎年4月・5月・6月の給与をもとに標準報酬月額を決定する制度です。一方、随時改定は期間の定めがないため、同じ4〜6月の間に随時改定の要件を満たすこともあるでしょう。
手続きが重なる場合、7月・8月・9月に随時改定の対象となる従業員については、随時改定で決定された標準報酬月額が優先されます。算定基礎届を提出済みであっても、新たに決定された標準報酬月額が最終的に適用されるため、適切な処理が必要です。
参考:日本年金機構|算定基礎届と月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか
定時決定・随時改定の手続きを行う際の注意点
定時決定や随時改定の手続きを正しく行うためには、事前準備だけでなく、運用面でもいくつかの注意点があります。ここでは、よくあるミスや適切な提出方法、罰則リスクについて詳しく解説します。
よくあるミスと対策を把握する
定時決定や随時改定の手続きでは、給与計算の誤りや提出漏れ、適用条件の誤認などが発生しやすい傾向があります。
4月〜6月の給与データの集計ミスは、標準報酬月額の不適切な決定につながり、従業員の保険料に直接影響します。このようなミスを防ぐためには、チェックリストの活用や書類・データの事前確認が必須です。
社内でのダブルチェック体制の整備も効果的です。企業に適している対策を行い、ありがちなミスを防ぎましょう。
企業に適した提出方法を選ぶ
定時決定・随時改定の手続きは、下記の方法で行えます。
- 電子申請
- 郵送
- 窓口提出
電子申請は業務効率が高く、処理も迅速なため、多くの企業にとって便利です。一方、デジタル環境が整っていない場合や、書類確認が必要な企業では、郵送や窓口提出の方が適しています。
企業の業務フローや体制にあわせて、スムーズに運用できる方法を選びましょう。
手続きを怠ると罰則の対象になる可能性がある
社会保険の手続きは、企業にとって法的義務であり、定時決定・随時改定ともに正しく行う必要があります。手続きを怠ったり、提出を忘れたりすると、法律にもとづいた罰則が科される場合もあるため注意が必要です。
ここでは、それぞれの手続きにおけるリスクと具体的な対応策について解説します。
定時決定に関するリスクと対応策
定時決定に必要な算定基礎届は、期限内に提出する義務があります。提出を怠った場合は、年金事務所から催告状が届くことがあります。
そのあとも対応しないままでいると、法律にもとづき6ヶ月以下の懲役または50万円の罰金が科される可能性があるため、注意しましょう。さらに、長期間未提出のままだと、年金事務所の立ち入り調査が行われることもあります。
このような事態は、企業と従業員に大きなリスクとなるでしょう。提出漏れが判明した際は、速やかに算定基礎届を提出しましょう。
随時改定に関するリスクと対応策
随時改定に必要な月額変更届を提出しなかった場合は、健康保険法や厚生年金保険法により罰則が規定されています。届出義務を怠ると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただし、月額変更届には明確な提出期限がないため、遅れてもすぐに提出すれば、罰則が適用されるケースは少ないでしょう。
とはいえ、届出を放置したままにしておくと、年金事務所などの行政機関から指摘を受け、あらためて提出を求められる可能性があります。固定的賃金の変更があったら、速やかに随時改定の要否を確認し、10日程度を目安に手続きの準備を進めましょう。
定時決定と随時改定の手続きをスムーズに進めるポイント
定時決定や随時改定の手続きは、期日を守り、正確に行う必要があります。ここでは、手続きをスムーズに進めるポイントを解説します。
事前に必要書類・データを準備しておく
定時決定や随時改定の手続きをスムーズに行うためには、事前に必要書類やデータを揃えておきましょう。
定時決定では、算定基礎届を作成するために、4月〜6月分の給与データを正確に集計する必要があります。一方、随時改定では、昇給・降給の履歴や手当の変更内容など、固定的賃金の変動を即座に把握できる体制を整えておくことが大切です。
変動を見逃さないように心がけることが、正確な手続きにつながります。
提出期限を守るためにスケジュール管理を徹底する
定時決定は、毎年7月10日(地域や管轄により異なる)までに手続きを完了する必要があります。また、随時改定は、給与の変動があった月から3ヶ月目の月末までに月額変更届を提出します。
期限をすぎると業務に支障をきたすため、社内でスケジュールを作成し、担当者や確認フローを明確にしましょう。電子申請の場合は、システムトラブルへの備えとして、余裕をもった申請スケジュールを組むことが望ましいです。
定時決定と随時改定は同時に手続きできる
定時決定と随時改定は、それぞれ異なる基準で標準報酬月額を決定するため、基本的には別々の手続きとして扱われます。しかし、算定基礎届を提出後に随時改定の要件を満たした場合は、定時決定で決定された内容をもとに、随時改定を追加で行う必要があります。
7月に月額変更届を提出する場合は、6月分の給与支払い後、速やかに提出しなければなりません。この際、月額変更届は算定基礎届と同時、またはそれより先に提出する必要があります。
なお、電子申請またはCD等の電子媒体で、2つの手続きを同時に行う際は、別々にファイルを作成する必要があります。
定時決定と随時改定の手続きを同時に進めることで、社会保険料の算定が正確になり、業務の効率化にもつながるでしょう。
参考:
関東ITソフトウェア健康保険組合|令和6年度算定基礎届等の提出方法について
定時決定と随時改定の違いと適用条件を理解し、適切に手続きを進めよう
定時決定と随時改定は、標準報酬月額を見直すための大切な制度です。定時決定は、毎年1回必要な手続きであり、随時改定は給与に大きな変動があった際に行うものです。
それぞれ適用条件や時期、提出書類が異なるため、制度の違いを正しく理解しておく必要があります。とくに、手続きが重複する7~9月は注意が必要です。
適切な判断とスケジュール管理を徹底し、ミスや提出漏れを防ぎましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
厚生年金における経過的加算とは?計算方法などわかりやすく解説!
長く加入するほど将来もらえる年金額が増えていくのが厚生年金保険ですが、50歳以上の方にハガキで届く「ねんきん定期便」に載っている経過的加算額を見て、経過的加算の意味がわからず疑問を…
詳しくみる社会保険料の対象・対象外になる手当一覧!適用促進手当も解説
給与計算時に支給する多くの手当は社会保険料の算定対象ですが、慶弔見舞金や実費弁償的な出張費など、一部は対象外です。この違いは、その手当が「労働の対償」と見なされるかどうかで決まりま…
詳しくみる労災の遺族年金とは?受給条件・金額・手続きをわかりやすく解説
勤務中の事故や通勤途中の災害によって、突然大切な家族を失ってしまうことは誰にとっても想像したくない出来事です。しかし、そんなときに遺されたご遺族の生活を支える仕組みとして、「労災保…
詳しくみる厚生年金の44年特例とは?特例の対象者にメリット・デメリットはある?
会社員が加入する厚生年金保険には、44年特例という優遇措置があります。 年金制度自体が非常に複雑であるため、44年特例もあまり知られていないのが実情です。 本稿では、44年特例の優…
詳しくみる雇用保険適用事業所番号とは?必要なケースや取得・確認方法を解説
雇用保険適用事業所番号とは、雇用保険に加入している企業に対して割り当てられる番号です。ハローワークで雇用保険に関連する手続きを行う際に雇用保険適用事業所番号が必要になります。 従業…
詳しくみる労働保険への加入方法
労働保険(労災保険と雇用保険)への加入方法を知っていますか?ここでは、労働保険に加入するため手続き、労働保険の加入に必要な各種届出、申告書の主な内容について解説します。 労働保険へ…
詳しくみる