- 更新日 : 2025年11月19日
仕事を与えないのはパワハラ?仕事の割り振りの注意点も解説
管理職は部下に対し適切な仕事を配分しなければなりません。仕事を与えすぎて長時間労働を強要するのはパワハラに該当する恐れがありますが、逆に仕事を与えないという行為もパワハラとみなされる可能性があります。
この記事ではパワハラに該当するケースとしないケースや、仕事を割り振る際の注意点についてご説明します。
目次
仕事を与えないことはパワハラになる?
そもそもパワハラとは職場での優位性を背景として、業務の適正な範囲を超えて労働者に対して精神的・身体的苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為を指します。暴言や暴力、過酷な労働の押しつけはパワハラとみなされる場合がありますが、仕事を与えないという行為もパワハラとみなされるケースがあります。
厚生労働省ではパワハラは主に「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」という6類型に分類していて、仕事を与えない行為は「過小な要求」に該当する恐れがあります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
パワハラの判断基準と実務対応
従業員からパワハラの相談を受けた際、適切な調査方法や判断基準がわからず、対応に苦慮している企業は少なくありません。
本資料では実際の裁判例も交えながら、パワハラの判断方法と対応手順を弁護士が解説します。
ハラスメント調査報告書(ワード)
本資料は、「ハラスメント調査報告書」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご利用いただけます。
ぜひ貴社のハラスメント調査における報告書作成の実務にご活用ください。
パワハラのNGワード&言い換えまとめ
職場におけるパワーハラスメント防止対策は進んでいますでしょうか?本資料は、「パワハラのNGワード」と、その「言い換え」についてまとめた資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社のハラスメント対策やコミュニケーションの参考としてご活用ください。
仕事を与えないことがパワハラに該当するケース
仕事を与えない行為がパワハラに該当するかどうかはケースバイケースです。以下のような状況に当てはまる場合は、パワハラとみなされる恐れがあります。
特定の労働者にだけ仕事の割り振りをしない
職場に同等の知識やスキルを持ったメンバーが複数いる中で、特定の人にだけ仕事を割り振らないというケースはパワハラ扱いになる可能性があります。また、部署異動をさせて仕事を全く割り振らないというケースもパワハラです。
本来の業務とは無関係の業務ばかり割り振る
自分の担当する業務とは関係ない業務をメインに割り振り、本来すべき業務を全くさせないという行為もパワハラに該当します。例えば、営業職なのに倉庫の掃除を必要以上に強要する、事務職なのに毎日草むしりのみをやらせるといった例が挙げられています。
自宅や別室など仕事がない場所で勤務させる
他のメンバーが同じ職場に出勤して働いているのに、一人だけ在宅勤務や仕事がない場所・できない場所に行かせる、いわゆる「追い出し部屋」と呼ばれるような別室での勤務を命じて仕事を与えないような行為もパワハラとみなされる可能性があります。特にこのケースではパワハラ類型の「過小な要求」に加え、「人間関係からの切り離し」にも該当するでしょう。
仕事を与えないことがパワハラに該当しないケース
仕事を与えないことがパワハラに該当する可能性は大いにありますが、一方で事情があって仕事を割り振れないケースもあるでしょう。ここからはパワハラに該当しないケースについて考えていきましょう。
職種に就いたいたばかりでスキル不足のため、割り振る仕事量が少ない
入社して日が浅い、あるいは異動してきたばかりで、その人に必要なスキルや知識が不足していると、どうしても割り振れる業務も限られてしまいます。この場合、仕事を与えないという状況もある程度やむを得ません。ただし、必要なスキルや知識が身につくよう指導をする、その人ができる範囲の業務を割り振る、徐々に仕事を増やしていくなどの対応が重要です。
本人の病気や怪我により、本来の業務が遂行できない
特に工場や建設現場などの作業を伴う業務や、営業やドライバーなどの外出が多い仕事は、病気や怪我によって本来の業務ができなくなってしまうケースも想定され、この場合はパワハラには該当しません。しかし、補助的な業務に就かせる、身体的な負担が少ない部署や内勤部署に移動させるといった配慮が必要となります。
仕事を与えないパワハラが認定された裁判例
裁判にて仕事を与えない行為がパワハラとして認定された判例はいくつもあります。有名なのは「JR東日本(本荘保線区)事件」です。
1988(昭和63)年5月に国鉄労働組合のマークが入ったベルトを装着していた保線作業員に対して、上司である保線区長がそれを就業規則違反としてベルトを外すよう求めました。その後、就業規則全文の書き写しと感想文の作成、就業規則の読み上げを繰り返し命じたということで、作業員は腹痛を発症し入院しました。
当該作業員は業務訓練に関する業務命令権の裁量の範囲を超えており、人格権を侵害されたとして会社と保線区長を被告として損害賠償を求めて提訴。秋田地裁、秋田高裁は原告である作業員の主張を支持し、被告は最高裁に上告したものの、棄却されて平成8年2月23日に損害賠償命令が確定しました。
また、ある銀行では会社の経営方針に協力しなかったとして、勤続33年の課長に対してこれまで契約社員が担当していた総務課の受付に配置転換を命じ、当該課長が銀行に対して慰謝料を請求。1995(平成7)年12月4日、東京地裁は受付業務が33年間に及んで課長職にまで昇進した原告にはふさわしい職務ではないとして、当該配置転換は裁量権の範囲を逸脱した行為であり人格権の侵害にあたるとして、当該銀行に対して慰謝料の支払いを命じました。
仕事を与えないパワハラがもたらすリスク
部下に仕事を与えないというパワハラ行為をすることで、以下のようなさまざまなリスクを会社にもたらします。
離職による人材流出
それなりに経験があり、業務に必要なスキルや知識を持っている人材に対して仕事を与えないことで、「自分は必要とされていないのではないか」「他の人は仕事をしているのに自分だけやることがない」という精神的苦痛を与えて、それが心身の不調につながり休職や離職といった事態にもなりかねません。
また、「この職場にいる意味がない」「転職して知識やスキルを磨いたほうがいい」と考え、離職につながってしまう恐れがあります。
従業員のモチベーション低下
仕事を与えないというパワハラを行うことで、本人以外の従業員のモチベーションの低下を招くこともあります。「明日は我が身」ではありませんが、会社の方針に従わない、上司の機嫌を損ねると今度は自分が仕事を干されてしまうのではないかと考えてしまいます。
会社への不信感や不安感を抱き、職場全体の生産性が低下する、優秀な人材が離職してしまうといった事態が発生する恐れもあります。
訴訟などによる社会的信用低下
先ほどのように、仕事を与えない、あるいは不当な人事異動を命ずることで、当事者から訴訟される恐れもあります。そうなれば裁判に対応するための手間やコストがかかり、敗訴すれば損害賠償や慰謝料、治療費などの支払いもしなければなりません。
訴訟され、その事実が世間に知れ渡ると、社会的信用が大きく失墜します。特に大手企業や有名企業では、訴訟されたことが大々的に報道されることもあるでしょう。
また、訴訟まではいかなくとも口コミサイトやSNSでパワハラ行為があったことが書き込まれた場合、非難が集中するいわゆる「炎上」と呼ばれる事態が発生し、やはり大きな損失につながりかねません。
管理職が心がけたい「仕事を与えない」以外の対応とは?
仕事を与えないのがパワハラに該当するか否かは、本人がどう捉えるかにもよります。仕事ができない、遅い、やる気がないなどの理由で、仕事を割り振りたくてもできずに悩まれている管理者の方もいらっしゃるかもしれません。最後に、管理職が心がけたい対応方法について考えてみましょう。
コミュニケーションをしっかりと取る
まずは部下の様子をしっかりと見て積極的にコミュニケーションを取りましょう。例えば、部下が手持ち無沙汰な様子である場合は、業務量が少ない可能性があります。このまま放置しておくと、パワハラだと捉えられかねません。
また、日頃から業務量は適正か、仕事をするうえで問題が発生していないか、どのような仕事がしたいのか、将来どうなりたいのかを話し合うことで、今後の指導や育成の方針が見えてきて、適切な業務の割り振りや人員配置にもつながります。
メンター制を導入する
部下とのコミュニケーションは大切ですが、管理職が全員の面倒を見るのもなかなか難しいです。特に新入社員や若手社員のモチベーションやスキルが低いと感じたら、先輩社員や中堅社員をメンターとしてつけることも検討してみましょう。
管理職よりも立場が近いメンターが指導をしたり管理職の代わりにコミュニケーションを取ったりすることで、状況が改善する可能性もあります。
配置転換を検討する
人にはどうしても向き・不向きがあります。指導をしてもモチベーションが上がらない、スキルや知識が身につかないということであれば、そもそも割り振っている業務がその人に合っていないのかもしれません。本人の希望や素質に合わせたポジションに転換することで、大きな成果が得られる可能性があります。
仕事を与えないのはパワハラに該当するリスクも十分にある
仕事を与えないという行為は場合によってはパワハラに認定される恐れもあります。特に特定の人にだけ仕事を与えない、本来の業務とは異なる業務ばかりをさせる、仕事がないような場所で勤務させるといった行為はパワハラ扱いとみなされるでしょう。
一方で、会社の事情や本人の状況によっては仕事を割り振りたくても任せられないケースもあり得ます。できる範囲で割り振る、しっかりとコミュニケーションを取りつつ指導をする、適正な部署に配置転換するなどの手段を検討してみましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
オワハラとは?チェックリストや対処法を解説!
オワハラとは、「就活終われハラスメント」の略称のことで、ハラスメントの一種と捉えられています。就活をしている学生などに対して、企業が内定を出す代わりや内定後に他の企業への就活を終わ…
詳しくみるブルーカラーとは?ホワイトカラーとの違いや仕事内容
ブルーカラーは、工場や建設現場などで働く労働者を指します。かつて、業場で働く従業員が青い襟のついた作業着を着用していたことから、肉体労働者をブルーカラーと呼ぶようになりました。決し…
詳しくみる退職勧奨通知書とは?書き方やひな形、違法リスクを回避するポイントを解説
退職勧奨通知書は、従業員に退職を提案する際の条件や内容を明示し、合意形成を円滑に進めるための重要な文書です。法的に必須ではないものの、実務では「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、…
詳しくみる外国人労働者に対する税金はどうなる?免除されるケースや3つの注意点について解説
人手不足が深刻化している企業では、日本人労働者だけでなく、外国人労働者の雇用も行っているケースが増えています。しかし、外国人労働者の場合は税金に関わるルールが異なるため、どのように…
詳しくみる退職勧奨はパワハラになる?該当する事例と3つの対処法
「退職勧奨をしなければならないが、パワハラにならないだろうか」「パワハラにならないための対策を知りたい」 このように悩む方もいるのではないでしょうか。 退職勧奨自体は違法ではありま…
詳しくみる高校生のバイトを雇用するには親の承諾書が必要?無料テンプレートも
高校生をアルバイトとして雇用する際には、様々な書類が必要です。当記事では、高校生を雇用する際に必要となる書類の中でも、承諾書に焦点を当てて解説します。承諾書が必要な理由や、承諾書の…
詳しくみる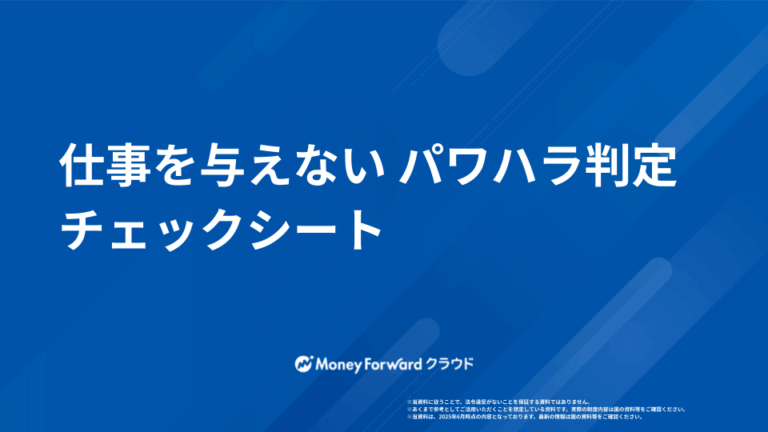


-e1762259162141.png)
