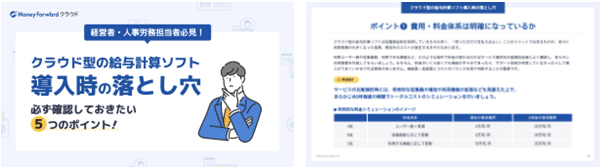- 更新日 : 2024年8月21日
HRTechとは?人事とテクノロジーの活用、企業事例、導入方法を解説
HRTechとは「Human Resources」と「Technology」を掛け合わせた略語で、AIやビッグデータなどの最先端の技術を駆使し、人事労務の業務に変革をもたらす技術やサービスのことです。本記事ではHRTechの概要やメリット、企業事例などをわかりやすく解説します。
目次
HRTech(HRテック)とは?
HRTech(HRテック)とは、AI(人工知能)やビッグデータなどの最先端の技術を駆使し、人事労務部門業務に変革をもたらす技術やサービスなどを指します。HR(Human Resource:人事)とテクノロジーを掛け合わせた略語です。
デジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、注目を集めている分野の1つです。
人事とテクノロジーの融合
HRTechは、人事とテクノロジーを融合させることで、データを蓄積・分析できるようになり、人事労務部門における業務の課題を可視化することが可能になります。その結果、人材不足や残業超過などの問題を解決できるようになると考えられます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック
人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。
40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。
クラウド型の給与計算ソフト導入時の落とし穴
給与計算ソフトの導入では、自社に適したものを選ばなければ、業務がかえって煩雑になったり、期待した成果が得られなかったりすることがあります。
この資料では、導入時に必ず確認しておきたい5つのポイントを解説します。
従業員情報の一元管理を実現する方法
従業員情報の収集や転記、複数システムの情報更新など「従業員情報の管理」が複雑になっていませんか?
この資料では、従業員情報の管理でよくあるお悩みとマネーフォワード クラウド人事管理を活用した業務改善方法を紹介します。
HRTechのメリット
HRTechの主なメリットとして挙げられるのは、以下の3点です。
- 業務の効率化
- 業務品質の向上
- 人事部門領域の可能性の拡大
HRTechを導入することによって、業務の効率化が叶うでしょう。人事労務部門における、人材採用や人事評価、教育、労務管理などは非常に手間がかかる業務といえます。具体的には、人事情報に関する書類のデジタル化や、Web上での社会保険の手続きの処理、勤怠管理の自動化などが可能になり、業務効率化につながります。
また、これまで書類チェックが必要であった業務において、書類のデータ化によって記載ミスや漏れを自動でチェックしてもらえるため見落としが減り、業務品質が向上するでしょう。
さらに、HRTechの導入によって、既存業務の品質向上にとどまらず、新しい業務ができるようになる可能性があります。たとえば、勤怠データと人事評価上位者の情報を分析し、優秀な従業員の特性を抽出するといった活用方法などが生まれる可能性があります。
HRTechの領域・サービス
HRTechが関わる領域・サービスは、以下のとおりです。
- 労務管理
- 給与計算
- 勤怠管理
- 人事評価・人材マネジメント
- 採用管理
それぞれの内容を解説します。
労務管理
労務管理システムとは、労働時間の管理や労働保険・社会保険の各種手続きなどを支援するシステムです。具体的には、以下のような項目が該当します。
- 社会保険の手続き
- 有給休暇をはじめとした各種休暇申請
- 労働時間の管理
- 安全衛生管理にかかる業務
HRTechの導入は、人件費や残業代などのコストカットに寄与します。業務の自動化により、労務管理の業務負荷が軽減され、注力すべき業務に人的リソースを回したり、残業代を削減できたりするでしょう。
給与計算
給与計算システムとは、従業員の給与に関わるすべての業務を一括管理できるシステムです。主に以下の機能を利用できます。
- 自動給与計算
- 勤怠管理システムとの連携
- 振込口座登録
勤怠管理システムと連携できるシステムも多く、従業員が打刻した勤怠データに基づき、自動的に給与計算まで実施します。その場合、ほとんど操作不要となり、給与計算に要していた作業を大幅に削減できます。
勤怠管理
勤怠管理システムとは、打刻や勤務時間といったデータを収集・管理し、勤怠管理業務を効率化するためのシステムです。勤怠データを自動で集計できたり、従業員が社外から打刻を行うことが可能になったりします。給与計算システムと連携できるシステムも多くみられます。
人事評価・人材マネジメント
人事評価システムとは、従業員の経歴・実績・給与・等級といったデータを管理し、人事評価を適切かつ効率的に実施するためのシステムです。HRTechの導入によって、評価者の主観が入りがちだった人事評価を是正できるでしょう。
そのほか、個人の仕事に対する姿勢や資格、スキルなどの情報をデータベース化し管理することで、適材適所の人員配置が期待できます。
採用管理
採用管理システムとは、採用活動におけるあらゆる情報を一元管理し、業務を効率化するシステムです。人手不足が続く状況であるため、採用業務の重要性が増すとともに、より煩雑化しており、業務の効率化が求められます。HRTechの主なサービスとして、履歴書や職務経歴書などの書類や面接時のデータなどの一元管理が挙げられ、導入によって速やかに情報確認を行えるようになるでしょう。
HRTechに関わるテクノロジー
HRTechに関連する主なテクノロジーや技術は、以下のとおりです。
- AI(人工知能)
- ビッグデータ
- SaaS
- RPA
それぞれの概要を解説します。
AI(人工知能)
AIとは、日本語では「人工知能」を意味する言葉で、「Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)」の略語です。一般的には、人間の言葉の理解や認識、推論などの知的行動をコンピューターに行わせる技術を指します。
たとえば人材配置であれば、現状はまだAIの分析データをもとにして、人間によって行っている状況です。しかし、将来的には最終的な人材配置まで、すべてAIに任せられるようになると考えられます。
ビッグデータ
ビッグデータとは、これまで使用されてきたデータベース管理システムでは記録や分析が難しい、巨大なデータ群のことです。ビッグデータは、人材配置や退職予測などの分析において、AIと並び欠かせない存在です。AIは高度な処理ができる一方で、根拠となるデータがなければ分析や予測はできません。
たとえば、退職予測では、過去に退職した従業員の退職理由や営業成績の推移などが、ビッグデータに該当します。
SaaS
SaaSとは、インターネットを介して提供されるソフトウェアのことで、「Software as a Service」の略語です。
SaaSは、インターネットがあれば、外出先や自宅からでも社内と同じアプリケーションやソフトウェアを利用可能にします。また、基本的にデバイス単位ではなくユーザー単位でのライセンスのため、1つのアカウントからさまざまなデバイスにログインできるようになることもメリットです。
それにより、人事部門内における情報共有の円滑化や、アンケート機能で従業員の満足度の把握ができるようになり、働きやすい職場環境作りに役立ちます。
RPA
RPAとは、コンピューター上での作業を人に代わって自動で行ってくれるソフトウェアのことで、「ロボティクス・プロセス・オートメーション」の略語です。
人事部門では、給与計算などの多くの事務作業が発生します。RPAの活用によって、これらの事務作業の一部をほぼ完ぺきにこなせるようになっています。
HRTechの製品・企業事例
ここからはHRTechの製品と、HRTechを活用している企業の事例をご紹介します。
会計・人事労務・契約Saas|マネーフォワード クラウド
「マネーフォワードクラウド」は、経理・人事労務などバックオフィスのあらゆる課題解決をサポートする製品です。
「マネーフォワードクラウド人事管理」なら、入退社・異動時の手続きにおいて、Web上で依頼から収集までを完結し、ペーパーレス化を実現します。また、「マネーフォワード クラウド勤怠」は、出退勤打刻から働き方改革対応まで、勤怠管理のすべてが簡単に行えるようになります。勤怠管理を効率化したり、残業や休暇の申請、承認がWebで完結したりする点がメリットです。
AI・ビッグデータ活用|日立製作所
世界を代表する電機メーカーである日立製作所がHRTechを導入したのは、価値観の近いタイプを採用してしまう傾向があり、それによって企業の成長の鈍化が懸念されたためです。
そこでHRTechを活用し、対応診断を導入しました。それまでとは異なるタイプの人材を積極的に採用したことで、人材タイプの偏りが解消され、創造性が高く顧客と一緒に価値を生み出せるタイプの人材を計画的に採用できるようになりました。
SaaSの活用|電通デジタルアンカー
インターネット広告代理店である電通デジタルアンカーでは、それまで使用していたシステムの都合上、情報管理はスプレッドシートで行い、社会保険関連の電子申請のみに活用していました。しかし、クラウド上ですべてを完結できる「マネーフォワード クラウド勤怠・給与」の導入によって、人事情報の管理や手続き申請に費やしていた工数も時間も削減でき、業務負荷は導入以前の3分の1程度にまで軽減できました。
参考:クラウド上の人事情報管理とペーパーレスの労務契約で業務負荷は3分の1に軽減!|マネーフォワード クラウド
HRTechの導入方法
HRTechサービスは、基本的に以下のようなステップで導入します。
- 業務の棚卸
- テクノロジーで代替できる業務の仕分け
- 目的に合うHRTechサービスの検討
- 導入プロジェクトの立ち上げ
具体的なHRTechサービスを選定する際は、数社のトライアルを行い、比較検討するとよいでしょう。本格導入の前に、必ず使用感を試してみることが大切です。
サービスの選定を終えたら、導入プロジェクトを立ち上げましょう。導入にあたっては、どのような業務を具体的にどのようにシステムに置き換えるかなど、詳細な要件定義が欠かせません。そのため、人事労務の担当者だけでなく、IT担当やシステム販売業者にもプロジェクトに関わってもらう必要があります。
HRTechを導入・運営する際の注意点
人事労務部門がHRTechサービスを導入する際は、事前に以下のような注意点を押さえておきましょう。
- 個人情報の取扱いに注意する
- 中長期的な視点で取り組む
- 最終判断はシステムではなく人が行う
それぞれの内容を解説します。
個人情報の取扱いに注意する
労務管理や人事評価にHRTechを活用する際、個人情報に関するデータを収集・管理する必要があり、その取扱いに注意しなければなりません。個人情報の漏洩を防ぐため、新たにHRTechサービスを導入する場合は、安全性が担保されているかどうかを必ずチェックしましょう。
中長期的な視点で取り組む
HRTechの推進は、中長期的な視点で取り組むことが求められます。一気に業務フローを変更しようとすると、社内に混乱が生じる可能性があります。まずは従業員に対して、HRTechを導入する目的を丁寧に説明し社内全体で共有することが重要です。短期間での変革を求めず段階的に進めていくことで、従業員の理解や協力を得られ、成果が出やすくなるでしょう。
最終判断はシステムではなく人が行う
HRTechサービスを利用する場合でも、最終判断はシステムではなく人が行うことが大切です。たとえばAIを活用するケースで、AIが出力した情報を鵜呑みにし、採用や人事考課における重要な判断に用いることは避けましょう。求職者や従業員から不信感を抱かれてしまう可能性があります。最終判断は、必ず人が行いましょう。
HRTechを導入して人事労務部門の業務効率化を進めよう
HRTechとは、AIやビッグデータなどの最先端の技術を駆使し、人事労務部門の業務に変革をもたらす技術やサービスのことです。人事とテクノロジーを融合させることで、人事労務部門の業務の効率化や業務品質の向上、人事部門領域の可能性の拡大が期待されます。人事労務部門の業務効率化を目指し、RTechの導入を検討しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
LGBTとは?Qとの関係や意味をわかりやすく解説【まとめテンプレート付き】
LGBTとは、「レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー」の頭文字をとった言葉ですが、性的マイノリティの人々を表す言葉として使われることもあります。 ここでは、LGB…
詳しくみるコワーキングスペースとは?ドロップイン料金・経費・東京での選び方を解説
近年、リモートワークの広がりにより、都内をはじめコワーキングスペースが増えています。コワーキングスペースは、仕事や勉強などの作業を想定してデザインされており、個人事業主やフリーラン…
詳しくみる安全管理者の役割とは?仕事内容、資格の取り方から巡視頻度までわかりやすく解説
安全管理者という言葉を聞いたことはあっても、具体的な仕事内容や、どのような場合に選任が必要なのか、どうすればなれるのか、正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。 この記事…
詳しくみる外国人雇用管理主任者の概要とは?合格率や取得するメリットを解説
外国人雇用管理主任者は、外国人労働者の雇用管理に関する専門知識を身につけ、企業や団体に対する総合的なサポートを提供できる資格です。資格の取得により、外国人雇用に関する法令や労務管理…
詳しくみる職場で無視されたらパワハラ?該当事例や対処法を解説
職場での無視は、特定の人物を組織内のコミュニケーションから排除するものであり、身体的・精神的な苦痛を与える可能性があります。このため、パワハラの3要素を満たすとみなされるとともに、…
詳しくみる転職して1年未満だと育休は取れない?伝え方や給付金について解説
転職して1年未満でも、2022年4月の法改正により原則として育児休業の取得が可能です。ただし、労使協定が存在する場合や、雇用形態によって制約を受けることもあります。 この記事では、…
詳しくみる