- 更新日 : 2025年12月24日
時間外手当とは?残業手当との違いやケース別計算方法を解説
時間外手当とは、法定労働時間を超えて働いたときに支給する手当です。労働時間が所定労働時間を超過したときに支給する残業手当とは異なり、常に1.25倍以上の割増賃金が適用されます。時間外手当が該当するケースや計算方法、時間外手当が基本給に含まれるケースや手当が支払われないときの対処法もまとめました。
目次
時間外手当とは?
時間外手当とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働いたときに支給する手当です。法定労働時間の基準は、以下をご覧ください。
- 1日8時間
- 1週間40時間
上記を超えて働くときは、時間外手当の支給対象です。時間外手当として、通常の賃金の1.25倍以上の割増賃金を支払います。
参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
時間外手当が発生する条件
時間外手当が発生するのは、法定労働時間を超えて働いたときです。所定労働時間を超えて働いても、法定労働時間を超えていないときは時間外手当が発生しないときもあります。ここで、法定労働時間と所定労働時間の違いについて確認しておきましょう。
| 法定労働時間 | 労働基準法で定められた1日8時間、1週間40時間の労働時間ルール |
| 所定労働時間 | 各企業で定めた就業規則に基づく労働時間ルール(9時~17時など) |
所定労働時間が1日8時間未満のときは、残業をしても法定労働時間を超えないことがあります。
たとえば、就業規則では9時~17時(1時間の休憩を含む)と労働時間が定められているとしましょう。所定労働時間は元々7時間(8時間の拘束時間-1時間の休憩時間)です。残業を1時間して18時まで働いた場合は、所定労働時間を1時間超えますが、トータルの労働時間は8時間のため、法定時間は超えません。
そのため、残業手当は発生するものの時間外手当は発生しないことになります。詳しくは「時間外手当と残業手当」で解説します。
アルバイトやパートも時間外手当はもらえる
時間外手当は、正社員だけでなくすべての労働者に対して支給する手当です。アルバイトやパートが1日8時間・1週間40時間を超えて働いた場合も、通常賃金の1.25倍以上の時間外手当を支給します。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント
給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。
この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。
給与規程(ワード)
こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
時間外手当と残業手当との違い
時間外手当は、労働者が法定労働時間を超過して労働したときの手当です。一方、残業手当とは所定労働時間を超過して労働したときの手当です。
残業には、次の2つの種類があります。
| 法定外残業 | 法定労働時間を超えて働くこと |
| 法定内残業 | 法定労働時間を超えてはいないものの、所定労働時間を超えて働くこと |
時間外手当は法定労働時間を超えて働いたときの手当のため、法定外残業をしたときに適用される割増賃金とも言い換えられます。
一方、残業手当は所定労働時間さえ超過すれば支給される手当、つまり、法定内残業・法定外残業のどちらの場合でも適用される手当です。残業が法定内残業の場合は、通常賃金の1.25倍以上である必要がないため、通常賃金と同額のこともあります。
たとえば、所定労働時間が9時~17時(休憩1時間含む。労働時間は7時間)の場合に、2時間残業をして19時まで働いたとしましょう。17時~18時の残業については法定内残業のため、残業手当の対象ですが割増賃金とはならない可能性があります。一方、18時~19時の残業は法定外残業のため、通常賃金の125%以上の割増賃金が適用されます。
なお、法定外残業には上限があり、原則として月45時間・年360時間以内です。臨時的かつ特別な事情がない場合は、上限を超えることはできません。
臨時的かつ特別な事情がある場合でも、時間外労働は年720時間以下かつ、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6ヶ月の平均が80時間以内になるように調整することが必要です。
時間外手当の計算方法
時間外手当の計算方法について紹介する前に、割増賃金のルールを解説します。労働基準法で定められた基準は以下をご覧ください。
| 割増賃金が発生するケース | 割増賃金の基準 |
|---|---|
| 法定外残業 | 通常賃金の1.25倍以上 |
| 深夜勤務(22時~5時) | 通常賃金の1.25倍以上 |
| 法定休日の労働 | 通常賃金の1.35倍以上 |
| 法定休日に8時間以上働く | 通常賃金の1.35倍以上 |
| 法定休日に深夜勤務をする | 通常賃金の1.6倍以上 |
| 法定外残業が深夜におよぶ | 通常賃金の1.5倍以上 |
| 1ヶ月の法定外残業が60時間を超える | 通常賃金の1.5倍以上 |
なお、各割増賃金は、少なくとも上記の基準を満たして支払うことがルールです。とくに上限は定められていないため、企業によっては上記の基準を超える時間外手当を支給することもあります。
労働時間が1日8時間以内のケース
所定労働時間が1日8時間以内の場合は、労働時間が1日8時間に達するまでは法定内残業、8時間を超えた分は法定外残業と考えます。
たとえば、所定労働時間が9時~17時(休憩1時間、労働7時間)の場合において、23時まで残業したときは以下のように手当を計算します。
18時~22時:通常賃金×1.25以上×4時間
22時~23時:通常賃金×1.50以上×1時間
時間外手当が基本給に含まれる場合は?
基本給に時間外手当が含まれる場合があります。主なケースは以下をご覧ください。
- 固定残業代制度
- みなし労働時間制度
固定残業代制度とは、残業の有無にかかわらず一定時間の残業を見込んで、一定の残業手当を基本給に組み込む制度のことです。時間外労働や休日労働がない場合でも、常に残業手当を含んだ給与が支払われますが、残業をした場合でも給与は変わりません。
みなし労働時間制度は、実際に働いた時間ではなく事前に決めた時間を働いたとする制度です。雇用者側が労働者の労働時間を管理することが難しいときに用いられることがあります。
なお、いずれの制度を導入している場合でも、労働時間が法定労働時間を超えている場合は時間外労働にあたります。就業規則で定めている所定労働時間を超えているときや休日・深夜に働いているときも、適切に評価し、給与に反映することが必要です。
基本給に残業代を組み込む場合は、以下のような計算式で固定残業代を計算します。
固定残業代 = 給与総額 ÷ {月平均所定労働時間 + (固定残業の対象時間 × 割増率)} × 固定残業の対象時間 × 割増率
たとえば、給与総額45万円(月平均所定労働時間180時間)、固定残業時間30時間の場合で考えてみましょう。
450,000÷{180+(30×1.25)}×30×1.25=77,587円(円未満を切り上げ)
上記式により求めた77,587円が固定残業代となり、所定労働時間労働に対する賃金は372,413円です。そして、両者を合算した額である450,000円が給与総額となります。
なお、このケースでは固定残業時間が30時間となっていますが、この時間を超えた分についても追加の残業代の支払いが必要となります。
時間外手当が出ない場合の対処法
時間外手当が正しく支給されていないと思われるときは、次の点を確認してみましょう。
- タイムカードの記録
- オフィスへの入出館記録
- 業務日誌
いずれも労働時間や労働時間帯を確認し、企業側と話し合うときの証拠として役立ちます。時間外手当が正しく支給されていないことが判明したときは、まずは企業側と話し合ってみましょう。話し合っても解決しないときは、労働組合や労働基準監督署、労務関係を専門とする弁護士などに相談してください。
時間外勤務申請書のテンプレート(無料)
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
時間外手当の基準を確認しておこう
時間外手当は、法定労働時間を超えて働くときに支給する手当です。労働基準法では、通常賃金の1.25倍以上を支払うことと決められています。
みなし残業や固定残業の制度を導入している場合も、時間外手当が発生することもあるため、労働者各自の労働時間を正確に把握することが大切です。また、休日や深夜の労働は割増賃金のルールが異なるため、正しく理解し、給与計算に反映するようにしてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
賞与支払届は電子申請できる!e-Govでの手続きの流れやメリットをわかりやすく解説
賞与支払届を提出する際には、電子申請を活用することで業務効率が向上します。 紙での申請に比べて郵送の手間や時間が省けるだけでなく、ミスの防止やコスト削減にもつながります。 しかし、…
詳しくみる【2025年最新】給与計算の法改正一覧|実務で対応すべきポイントを解説
2025年から2026年にかけて、給与計算業務は複数の法改正への対応が必要です。特に、2025年4月から順次施行される育児・介護休業法の改正は、従業員の働き方に直接影響し、給与計算…
詳しくみる給料ファクタリングとは?仕組みや安全性、違法な事例・選び方を解説
給料ファクタリングとは、労働者がまだ受け取っていない給与を「給与債権」として売却し、給与支給日よりも前に現金化するサービスです。給料ファクタリングを騙る違法業者も多く、金融庁では注…
詳しくみる給与計算における端数処理の方法
給与計算では、1円未満の端数が発生します。また、給与計算のもととなる労働時間を集計する際、1分単位の扱いに戸惑うかもしれません。ここでは、給与計算の端数処理について解説します。 割…
詳しくみる年末調整と住民税の関係
住民税とは、自分の住む地域を維持していくための費用を住民自身が負担するというシステムの下、設定された税金です。所得に応じて課される税のため、基本的なしくみは所得税と同じです。 市町…
詳しくみる茨城県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
茨城県は工業が発展しており、特に自動車や電子部品の製造が盛んです。また、農業や観光業も重要な産業として位置づけられており、多様なビジネスが展開されています。こうした多岐にわたる業種…
詳しくみる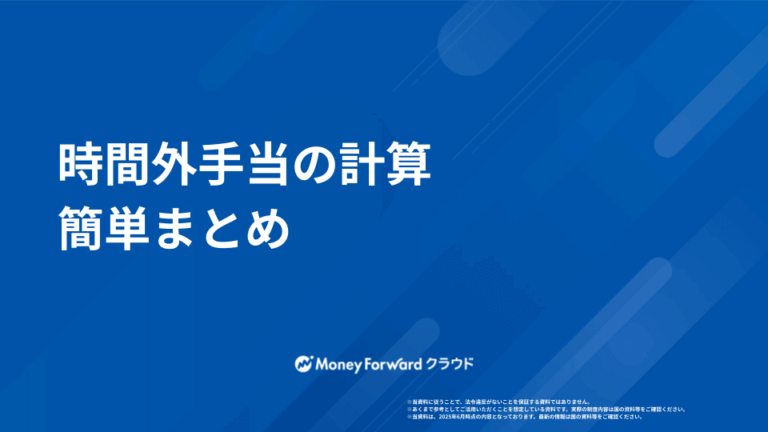

-e1762740828456.png)

